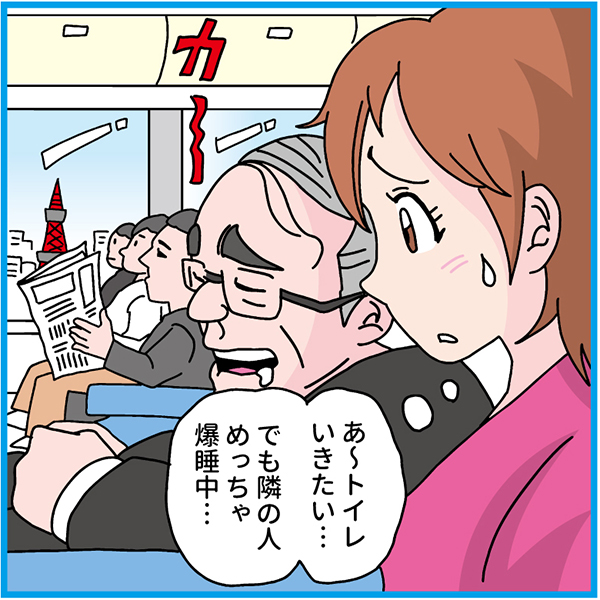新進気鋭のクリエイターたちが隅田川沿いの下町「蔵前」を目指す理由
蔵前は「東京のブルックリン」 渋谷・表参道・青山など、東京のおしゃれスポットはほとんどウエストサイド(西側)にあります。しかし現在、東京のイーストサイド(東側)にもおしゃれなエリアが現れています。そのひとつが、ちまたで「東京のブルックリン」(ニューヨーク)と称されている、蔵前(台東区)です。 隅田川に隣接する蔵前(画像:清水麻帆) ブルックリンと蔵前が似ているのは、風景です。それは、生活の中で感じられる自然や醸成された文化といえるでしょう。 例えば川。蔵前には隅田川、ブルックリンにはイーストリバーがあります。ここは人びとの憩いの場になっています。 隅田川の川岸からはスカイツリー、イーストリバーからは対岸のマンハッタンが見渡せます。またどちらのエリアも昔は工場地帯で、古い倉庫や建物が立ち並んでいるところです。これらの建物はリノベーションされ、こだわりのあるショップが入居。趣のある雰囲気を醸し出しています。 サンフランシスコ発のチョコ専門店も 蔵前にはカフェ、雑貨、食事所(レストラン)など、多種多様でユニークなお店が混在しています。 「SOL’S COFFEE」(台東区蔵前3)は自家焙煎(ばいせん)のコーヒーを提供する人気店で、フルーティーな香りの本格的なコーヒーを飲むことができます。 「SOL'S COFFEE」の外観(画像:清水麻帆) ほかにも玄米専門のショップ兼食事所「結わえる」(蔵前2)や自分だけのノートが作れるお店「カキモリ」(三筋)などがあります。 サンフランシスコの有名なチョコレート専門店「ダンデライオン・チョコレート」(蔵前4)は海外初の店舗を構えたのが蔵前。こうした特徴のあるショップが多く立地することで、まちの風景や雰囲気をおしゃれなかいわいへと変貌させているのです。 歴史あるモノづくりのまち・蔵前歴史あるモノづくりのまち・蔵前 おしゃれなエリアに変貌した蔵前ですが、もともとは「モノづくりのまち」です。その歴史を簡単に振り返ってみましょう。 蔵前という名前は、江戸時代に幕府のお米蔵があったことに由来しています。そのことからも、当時は米問屋のまちでした。明治以降になると政府関連の施設が立地し始め、その流れのなかで東京職工学校が1881(明治14)年、作られました。 1909(明治42)年9月に測図された蔵前周辺の地図。東京職工学校の後身である東京高等工業学校(現・東京工業大学)の記載が見える(画像:時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕) 東京職工学校は現在の東京工業大学で、関東大震災で被災するまで蔵前にあったのです。蔵前にモノづくりの人材を育成する高等教育機関があったことがモノづくりのまちとして発展していく礎を作ったといえます。 周辺にはおもちゃ大手の本社も立ち並ぶ 蔵前は、現在も歴史あるモノづくりのまちとして存続しています。 浅草橋周辺には、繊維製品やひな人形・ぬいぐるみ・文具の問屋街があります。蔵前3丁目付近には、おもちゃ工具材料の問屋街があり、おもちゃ大手のバンダイ(台東区駒形)やエポック社(同)の本社が立地しています。 バンダイの外観(画像:清水麻帆) 他にも神仏具から革製品など、さまざまな製造と卸の会社が蔵前周辺に集積しています。ではなぜモノづくりのまちである蔵前が、イーストサイドの東京を代表するおしゃれなエリアになったのでしょうか。 なぜ注目されるようになったのか 理由のひとつは、自由でクリエーティブな文化が醸成されているためです。 その背景には、新旧のアーティスト気質を持ったクリエイターや職人たちがこのエリアに集まり、歴史ある蔵前のモノづくりを継承していることが挙げられます。 結わえるの外観(画像:清水麻帆) 彼らが蔵前に新しい風を吹き込み、まちの一員として歴史や文化そして風景を作っています。それがさらに新たな人を呼び込み、まちにさらなる活気を生み、地域の歴史や文化を受け継ぎながら、伝統と新しさを交差させ、まちをアップデートしているのが蔵前なのです。 受け継がれてきたモノづくりの魂受け継がれてきたモノづくりの魂 そもそも、クリエイターたちはなぜ蔵前を選んだのでしょうか。 そのひとつとして、都心に近いにもかかわらず地価が安く、リノベーションされた古い建築物が存在していることが挙げられます。これが新たなクリエイターを引きつける要因のひとつになっています。 しかし、理由はそれだけではありません。地元の人たちから受け継がれてきたモノづくりを絶やさないよう、地域で一体となって若手を支援してきたことが大きな影響を及ぼしています。 その活動のひとつがモノづくりをまち全体で支援している「台東区デザイナーズビレッジ」の存在や「モノマチ」の開催です。 2019年に開催された「第11回モノマチ」の様子(画像:台東モノづくりのマチづくり協会)「モノマチ」とは職人やクリエイター、さまざまなショップが参加する、まちとモノづくりのPRイベントです。ここでの出会いから縁が生まれ、蔵前に出店する人も多くいます。こうした地域から生まれたつながりが、彼らを蔵前に引き寄せているのです。 鍵は「開放的な風土」「水平的なネットワーク」 もうひとつの理由は、蔵前に新たな人びとを受け入れる「寛容性」があったことです。 一般的な古い商店街は、新規出店が難しいところも少なくありません。その点、蔵前は新たなチャレンジを可能にする場所としての潜在的可能性があります。 「古いモノや人」が「新しいモノや人」を受け入れた結果、ほかにはないユニークな店が集まり、新旧入り交じった地域に作り替えられたことで、自由な雰囲気を醸し出しています。 前述の「モノマチ」だけではなく、蔵前のカフェやバーは、雑談や新たなつながりが生まれる場所となり得ます。そうした場所からさらに新たなアイデアが生まれ、本当の意味でのクリエーティブな空間になっていくのです。 チョコレート専門店「ダンデライオン・チョコレート」の内観(画像:清水麻帆) クリエーティブな空間形成に関連する研究においても、地域経済学者のアナリー・サクセニアンは、「開放的な風土」や「水平的なネットワーク」が「アイデアの発見」や「自由なコミュニケーションを促す」とし、それが地域の発展につながると分析しています(1995年)。 新たなことを生み出すことのできる空間は、人や景色が紡ぎだす地域文化の一部として歴史とともに再構築され、まちの新たなイメージとなっていくのです。まさにそうした風土や文化が、現在の蔵前を作っているのでしょう。 新旧の風や文化的な香りを感じながら川沿いのまち・蔵前をゆっくりと散策してみてはいかがでしょうか。
- 未分類