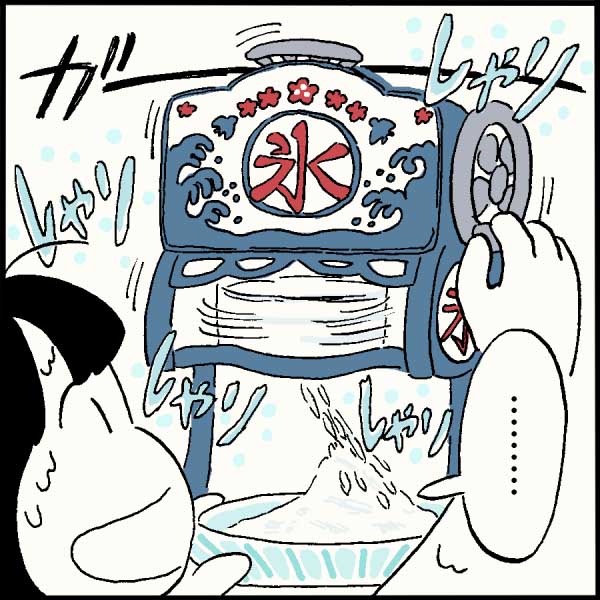静岡県で発掘された神津島産の旧石器
東京都の島しょ部である伊豆諸島は、
・大島
・利島
・新島
・式根島
・神津島
・三宅島
・御蔵島
・八丈島
・青ヶ島
の9島から成り、現在は船や飛行機で比較的簡単に訪問できます。とはいえ、長きにわたって本土から遠い離島だったのもまた事実。美しい海に囲まれた常春の島・八丈島もかつては流刑地で、「鳥も通わぬ」と言われるほどだったのです。
そんな伊豆諸島ですが、有史以前から多くの人の営みがありました。
これまでの研究で、すでに旧石器時代から人類が到達していたことが明らかになっています。その証拠として、神津島産の旧石器が本土の各地で発見されています。
これまでに発見された最古のものは、静岡県沼津市の井出丸山遺跡から。この遺跡は約3万7000年前のものと推測されており、出土した黒曜石は分析の結果、神津島産であると判明しています。黒曜石はそのほかにも、関東地方を中心に広い地域で発見されています。
本土と伊豆諸島を行き来した人たちがいた?
同じく静岡県の河津町にある見高段間(みたかだんま)遺跡は縄文時代中期の遺跡で、約19kgの黒曜石が発見されています。これは、神津島から巨大な原石を切り出し、運びやすい大きさに加工してから流通していったことを示しています。
 神津島(画像:海上保安庁)
神津島(画像:海上保安庁)
このことから、旧石器時代から縄文時代までの長きにわたって、石器の良質な材料を求めて本土と伊豆諸島を行き来していた人たちがいたのではないかと考えられています。
しかし、小舟を使って本土から伊豆諸島へ航海するのはとても困難です。そのような点から、日本人の源流とされる、黒潮の流れに乗って南方から移住してきた人たちによって伝承された航海術を彼らが使ったとも考えられるのです。
神津島産の石器は本土で発見されているものの、現時点で、伊豆諸島での旧石器時代の人類の営みは発見されていません。もっとも、現時点では発見されていないだけで、伊豆諸島に旧石器時代には人が住んでなかったと言い切ることはできません。
伊豆諸島は縄文時代、「宝の島」だった
その後の縄文時代になると、各地に定住する人たちが現れ、それを示す遺跡も発見されています。人が増えた理由は定かではありませんが、旧石器時代に続き、縄文時代にも黒潮の流れに乗って移住してきた人たちがいたという説もあります。
この説を裏付けるものとして、八丈島の湯浜遺跡があります。
 八丈島(画像:海上保安庁)
八丈島(画像:海上保安庁)
湯浜遺跡では多くの石器が発見されているのですが、神津島産の黒曜石がある一方、石器の加工方法などには南方文化が残っています。このことからも、伊豆諸島では縄文時代の早い時期から、本土に住んでいた人たちが南下し、黒潮の流れに乗った新たな移住者も加わり、新たな社会が生まれていったのではないかとされてます。
伊豆諸島は縄文時代、貴重な物資を生み出す宝の島でした。
中でも珍しいのが、オオツタノハという巻き貝の一種を使った貝輪です。縄文人は動物の骨や貝などを使って髪飾りや耳飾りなどの装身具をつくっており、その中にオオツタノハを使ったものがありました。出土例は北海道から愛知県まで200点ほど。200点もあると多いように聞こえますが、ひとつの遺跡から1、2個出土するかどうかですから、現代のダイヤモンドやエメラルドよりもさらに希少価値のあるものだったと考えられます。
巻き貝の生息地は国内でも限られていて、伊豆諸島南部(三宅島、御蔵島、八丈島)や大隅諸島にしかみられません。しかも貝が取れるのは荒海に面した断崖です。縄文の人たちは、この貴重な貝を求めて海を渡って貝の採集を行っていたのです。
伊豆大島の下高洞(しもたかぼら)遺跡では、約1mの厚さの貝や遺物を含む地層が発見されています。
この遺跡では30点のオオツタノハ製貝輪が発見されていますが、多くは破片だったり、輪が途中で欠けたりしたものです。これは、下高洞遺跡が伊豆諸島各地で採取されたオオツタノハを使って貝輪を製作する拠点であったことを示しています。
実は離島でも孤島でもない?
縄文時代に加工が行われたことを示す遺跡は下高洞遺跡だけですが、弥生時代の遺跡である三宅島のココマ遺跡でも40点のオオツタノハが発見されています。
 三宅島(画像:海上保安庁)
三宅島(画像:海上保安庁)
こちらも破片が主であり、これまでの発見事例をみると、時代とともに加工者たちも採取地の近くに移動していったことがわかります。
貝が運ばれた場所として、神奈川県三浦半島の海蝕洞穴(かいしょくどうけつ)遺跡があり、漁労具や装飾品などが発見されています。
ようは海沿いの洞窟を物置などに使ってきた結果の遺跡なのですが、よほど便利だったのか、縄文時代から中世までの遺物が見つかっています。ここでも、オオツタノハの貝輪が見つかっています。
ほかの遺跡と違うのは、研磨処理をしていない未完成品が見つかっていることです。このことから、伊豆諸島で採取されたオオツタノハは、いったん加工してから運ばれていたこともわかっています。
縄文時代、日本列島にはいくつもの交易ルートが存在していました。伊豆諸島はその中でも重要な産地だったのです。こんな歴史を知ると改めて「離島」「孤島」という認識は、正しくないことがわかります。