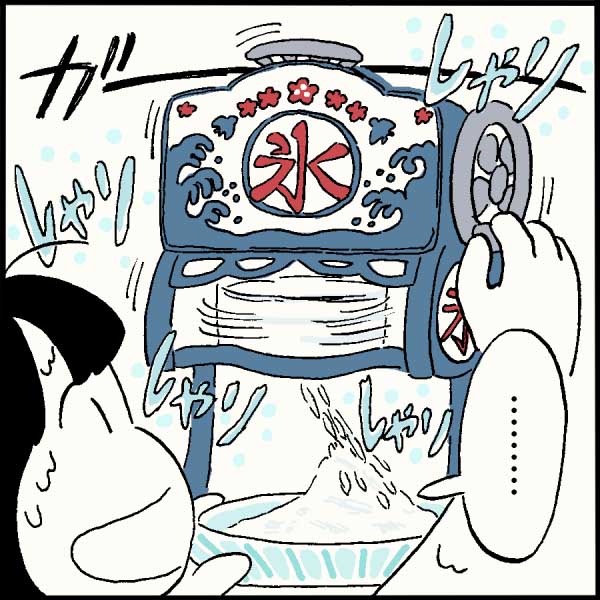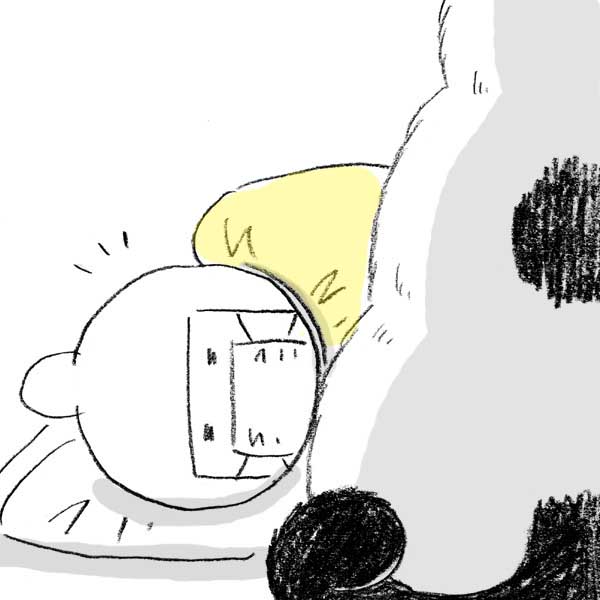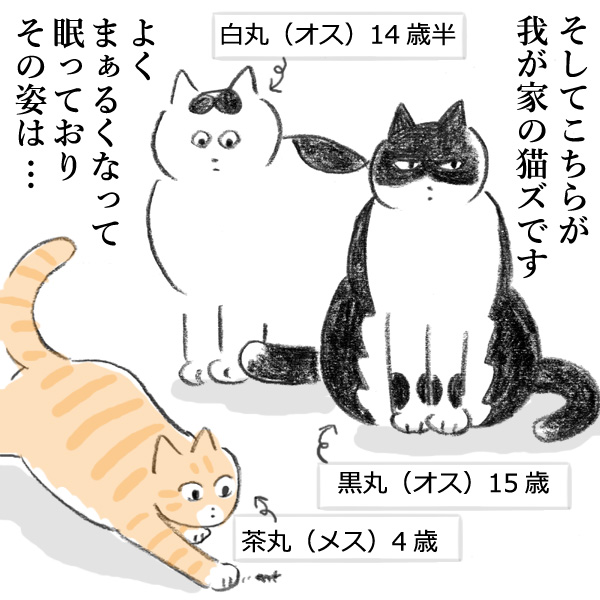政治的中心都市が置かれた府中市
東京都の中心は23区で、皇居のある千代田区か、都庁のある新宿区が特に際立っています。しかしこのエリアが中心となったのは、徳川家康(1543~1616年)が江戸の町を建設してから。それ以前はもっと西、多摩地域中部に位置する、現在の府中市あたりにありました。
東京都の旧国名(律令制により設けられた国)は武蔵国(むさしのくに)です。時代によって領域は変動しますが、武蔵国は東京都のほか、埼玉県と神奈川県北東部(横浜市・川崎市)をカバーしていました。
そんな武蔵国の国府(政治的中心都市)が置かれたのが、現在の府中市です。
奈良時代から平安時代にかけて、国府には朝廷から派遣された国司(地方官)が政務をつかさどっていました。しかし国府は平安時代以降に廃絶され、現代ではどこにあったか判明していない地域も多いのです。
同じように武蔵国府も、平安時代の辞書『和名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)』に「多麻郡に在り」と書かれているだけで、具体的な位置はわかっていませんでした。
府中という地名は、同地に武蔵国の総社(複数の神社の祭神を1か所にまとめた神社)の大國魂神社(府中市宮町)があるため、伝承により名付けられましたが、肝心の国府の場所がはっきりしていませんでした。
ところが1975(昭和50)年以降に行われた発掘調査によって、国衙(こくが。国司が政務にあたった役所)が発見され、位置が判明。その後も発掘調査は続けられて、住居だけでも、これまでに4000軒あまりが発掘されています。
発掘の成果は大國魂神社の境内にあるふるさと府中歴史館に保存されているほか、遺跡の多くも整備され、見学できるようになっています。
賑わいの中心から外れていた武蔵国
そもそも、なぜ現在の府中市が国府を設置する場所として選ばれたのでしょうか。
 かつて武蔵国の国府が置かれた府中市(画像:(C)Google)
かつて武蔵国の国府が置かれた府中市(画像:(C)Google)
武蔵国に国府が設置されたのは7世紀末から8世紀前半、奈良時代の初め頃と考えられています。この時代の都と関東地方を繋ぐ幹線道路は東山道でした。
東山道は畿内(きない。京都に近い山城・大和・河内・和泉・摂津の5か国)から毛野国(けぬのくに。現在の群馬県と栃木県南部)を通って陸奥国(現在の福島県、宮城県、岩手県、青森県)へ至ります。
武蔵国はこの幹線から外れていたため、国府に向けて武蔵路という支線が設けられていました。国府は当時の賑わいの中心から外れた地域にあったのです。
この大きな理由は、さまざまな「しがらみ」を避けるためと考えられます。
『日本書紀』の安閑(あんかん)天皇元年(西暦534年と推定)に、武蔵国造の乱という事件の記述があります。国造(くにのみやつこ)とは、大化の改新(645年)以前における世襲制の地方官です。
武蔵国造の乱は、武蔵国造の笠原直使主(かさはらのあたいおみ)と小杵(おき)が争い、小杵が上毛野国造の上毛野小熊(かみつけののおくま)と組んで使主を殺そうとしたため、朝廷が小杵を誅殺し、使主を武蔵国造としたというものです。
このとき、横渟(よこぬ)・橘花(たちばな)・多氷(たひ)・倉樔(くらす)の4つの屯倉(みやけ。大和朝廷の直轄領)が設置されたとされています。
このことから、武蔵国南部には国府の設置以前から中央の拠点があったことがわかります。なお、多氷は「多末」を間違って書いたのがそのまま伝わったものとされています。
さらに武蔵国南部では、府中市の武蔵府中熊野神社古墳などのいくつかの古墳を除けば、目立った古墳は見当たりません。対して北部は、埼玉県行田市の埼玉古墳群のような巨大古墳がみられます。
ここからわかるのは、有力者とそのしがらみが多そうな北部を避けて、朝廷の拠点が長らく存在していた南部に国府が置かれたということです。
多摩川の近さと土地の標高
さらに南部でも現在の府中市が選ばれた理由は、交通の便がよく、かつ災害の危険性も少ないことがあげられます。
武蔵国府の中心地は東京競馬場(府中市日吉)の北西あたりで、国土地理院の地形図を見ると、市の中心部はもちろんのこと、多摩川流域の低地からは一段高い台地になっていることがわかります。
 府中市日吉にある東京競馬場周辺の地形図(画像:国土地理院)
府中市日吉にある東京競馬場周辺の地形図(画像:国土地理院)
つまり、多摩川の水運を使った物流ルートに接した場所にあり、かつ土地の標高も高くて水害の危険が低い土地を選んで国府が置かれているのです。
多摩川の南にある多摩丘陵では、その斜面を利用して須恵器(すえき。古墳時代の後半からつくられた陶質の土器)や瓦を生産する登り窯の跡が数多く発掘されており、物流も便利かつ、生産拠点にも近い最善の場所として選ばれたのが、この土地だったのです。
武蔵国府は数多くの発掘調査で全体像が明らかになりましたが、謎もまだ残っています。国府がこの場所に置かれたこともあってか、武蔵国は相模国(現在の神奈川県の一部)や下総国(現在の千葉県北部と茨城県の一部)とも活発に往来するようになり、771(宝亀2)年には行政区分が東山道から東海道へと変更されています。
そうであれば、多摩川の南側には多摩丘陵を貫いて相模国府と繋ぐ道も整備されたのではないかと考えられますが、こちらはまだ発見されていません。府中市一帯にはまだまだ謎が眠っているのです。