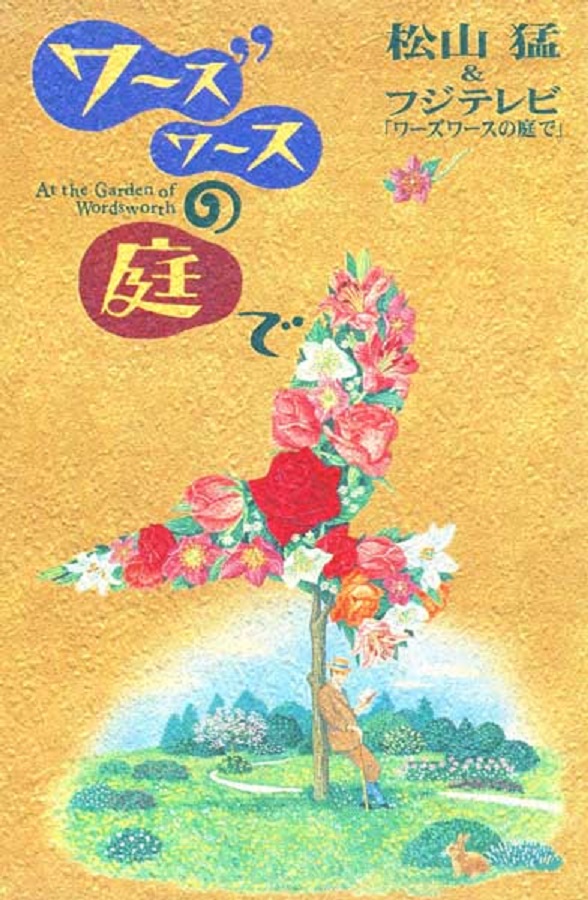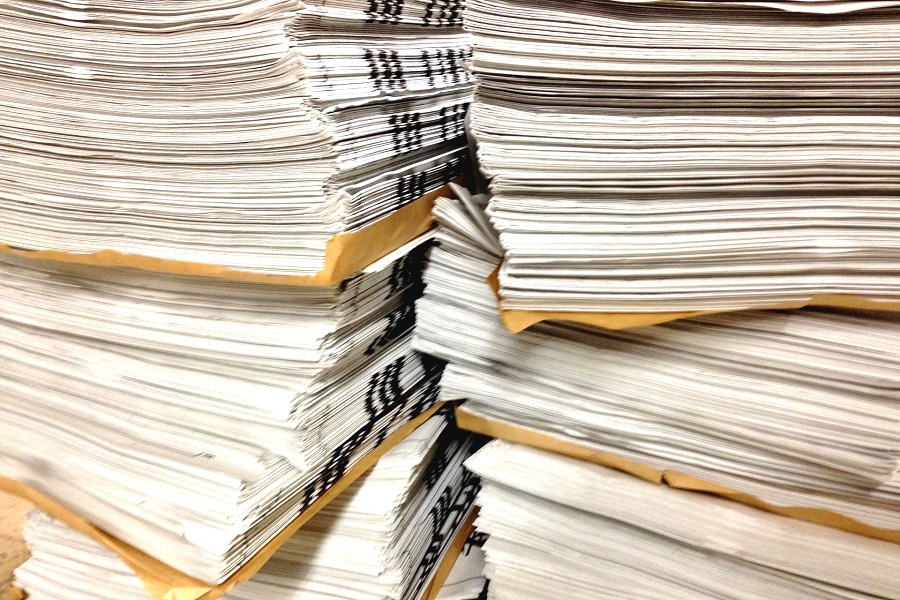自分の知識とこだわりを武器にする! 90年代初期のフジテレビに、現代人の生き方を先読みした番組があった
昨今はオタクやマニアなどの言葉が肯定的に語られますが、約30年前に「自分のこだわりや美学」を追求したテレビ番組がありました。20世紀研究家の星野正子さんが解説します。バブル崩壊後に変わった価値観 田舎で文化系のオシャレな生活は絶対にできない、東京に行けばできるはず――。現在とは異なり、テレビが主流メディアだった時代、東京に憧れる人たちは、テレビ番組を通じて都会生活を夢見ていました。 しかし1990年代前半のバブル崩壊後、そんな考えは一転。 「あくせくお金ばかりを追いかけるのではなく、内面の充実した生活をしたほうがいいのでは」 と考える人たちが徐々に増えました。 そんななか、この流れを敏感にキャッチしたテレビ番組『ワーズワースの庭で』(フジテレビ系列)が1993(平成5)年4月、始まりました。 書籍になった『ワーズワースの庭で』(画像:扶桑社) 竹中直人(もしくは清水ミチコ)さんがオープニングでその日のテーマを話した後、 「ようこそワーズワースの庭へ」 の言葉とともに、番組はスタート。歌舞伎役者の坂東八十助(5代目)さんとアナウンサーの河野景子さんが、ゲストとともにビデオを見ながら語り合う放送スタイルを採っていました。 記念すべき第1回は、ゲストに女優・浅野ゆう子さんを迎えた紅茶の回。45分間の番組内容は濃く、 ・初めて茶をヨーロッパに伝えた17世紀のオランダ船 ・茶に関する広告や書物 ・茶で一代の富を築いたトーマス・リプトン などのトリビアとともに、イギリス人と紅茶の楽しみ方を語るというマニアックなものでした。 放送時間は金曜日23時。家に帰って週末をどう過ごそうかと考えている時間に、しゃれた雰囲気で、押しつけがましくなく語られる番組は当時とても珍しい存在でした。 なぜなら、高度成長期からバブル景気まで長らく続いていた「お金第一の風潮」「上昇志向」とはうってかわって、精神的に豊かなライフスタイルとそれに必要な知識を、番組が提示していたからです。 番組ではそのほかにも、 ・南仏・プロヴァンスで暮らす ・和食器のある食卓 ・川奈ホテル物語 などさまざまなテーマが扱われましたが、特に人々の印象に残ったのは、歌舞伎を扱った回でした。 かつて歌舞伎座でお見合いがかつて歌舞伎座でお見合いが この回は、会社をサボって昼から歌舞伎座(中央区銀座)で歌舞伎を楽しんでいるサラリーマンが登場したり、歌舞伎座でのお見合いが紹介されたりしました。 中央区銀座にある歌舞伎座(画像:(C)Google) 歌舞伎座でのお見合いは、まず午前中に東西の桟敷席に分かれて座り、遠くからお互いの姿をチェック。その上で昼食をともにして、午後はふたりで……という流れでした。 歌舞伎座のウェブサイトを調べてみても、 「江戸の昔から、芝居見物をかねて、芝居小屋でお見合いなどがよく行われたようですが、歌舞伎座でもかつては、男女が東西の桟敷席に分かれて対面し、お見合いをすることがあったようで」 と、かつてそうしたものが本当にあったと書いてあります。現代でも再現してみたら面白いのではないでしょうか。 歌舞伎自体、地方ではなかなか見る機会がありませんが、それを平日の昼間から楽しんでいる東京人はすごいと、憧れを募らせた人も大勢いたことでしょう。 テレビ番組の在り方を変えた? ゆったりとした流れでひとつのテーマを構成していく番組のスタイルは、それまでの視聴率重視の、常ににぎやかで、常に視聴者をハラハラさせようとしていたテレビ番組に転換をもたらすものでした。 ザ・フォーク・クルセダーズのデビュー曲『帰って来たヨッパライ』(1967年)の作詞で知られる作詞家・松山猛さんは、この番組を 「浮世の尻馬に乗らない」 「テレビ番組の在り方を、すでに変えたのかも知れない」 と絶賛しています(『週刊文春』1993年7月29日号)。 ゴールデン☆ベスト ザ・フォーク・クルセダーズ(画像:ユニバーサル ミュージックジャパン) また松山さんは 「適当に見ているうちに、けっこう番組のプレゼンテーションにひたり切っている人も多いのではないか」 とも記しています。よっぽど番組にハマッたのか、その後、松山さんは番組レギュラーになっています。 この指摘はまさにその通りで、今では当たり前の存在になった、いわゆる「大人の週末」的な生活を好む人々は1990年代後半には増加しています。 大人の週末とは「こだわる必要のない、どうでもいいことに時間とお金を割くこと」を意味します。つまり他人から見たら「なんでわざわざそんなことまで……」というものに、自分しか理解できない美学を持つわけです。 美学の加減が難しいという問題もありましたが、こうしたスタイルは次第に定着していったのです。 数々の「神回」があった数々の「神回」があった 番組は1994(平成6)年4月から日曜日22時30分へ移動し、ナレーションを中心に各回のゲストが進行していく形になります。ここから、番組はさらにディープに。 例えば焼き魚の回では、単なる焼き方の伝授だけではなく、都会のマンションで近所に迷惑をかけずに魚を焼く方法という、都会暮らしならではの問題解決方法まで広げています。 またチャーハンの回では、卵を後から入れるレシピについて、素人のやり方だと提示しています。この回のリポーターは女優・藤田朋子さんで、料理人タレント・金萬福さんに鍋の使い方をひたすら教えられていました。 チャーハン(画像:写真AC) 番組はゲストのチョイスもさえていて、北フランス美食めぐりの回では藤井フミヤさん、麻布の回では宮沢りえさん、銭湯の回では片岡鶴太郎さん、細川ふみえさんを招いています。また美輪明宏さんを招いた回も話題になりました。 『ワーズワースの庭で』は、まさに21世紀に展開する新しい価値観を提示した番組でした。残念ながら、現在に至るまで再放送はされていません。
- ライフ