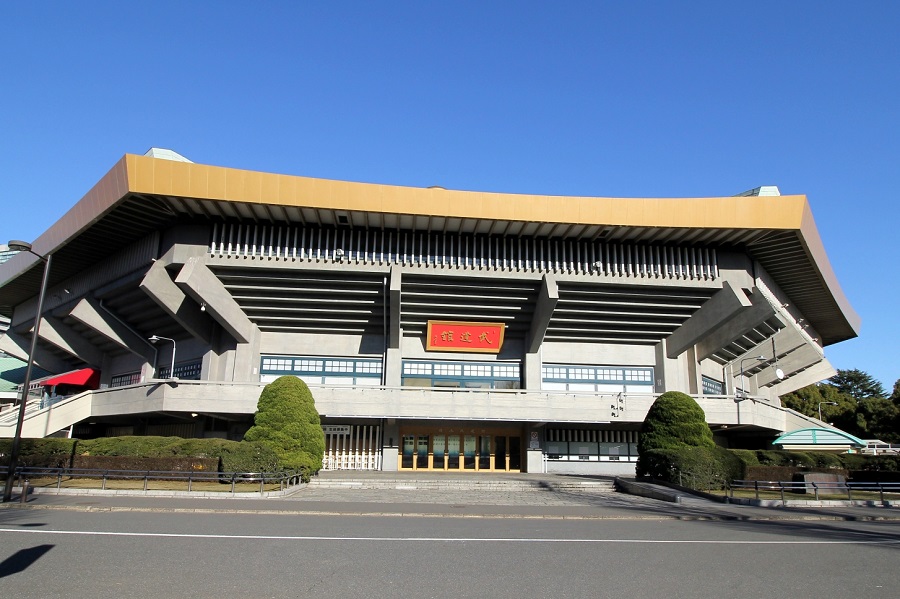子どもを怒ってばかりで「自己嫌悪」な母親へ送りたい、一通のこころの処方箋
子どもを怒りたくないのに怒ってしまう 北海道札幌市で2019年6月5日(水)、2歳の女の子が母親らに虐待を受けて死亡するという痛ましい事件が発生しました。また、12日(水)には、新潟県長岡市で、育児に疲れた母親が生後3か月の長女を床に落として殺害するという事件も起きています。 育児は思い通りにいかないことも多い(画像:Pixabay) 背景はさまざまですが、悲しいことに、親による行き過ぎたしつけや暴力によって子どもが被害を受ける事件が後を絶ちません。 厚生労働省が2018年8月に発表した「平成29年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数」によると、2017年度に18歳未満の子どもが保護者から虐待を受けたとして児童相談所が対応した件数は13万3778件で、東京都は約1割にあたる1万3707件でした。 日常的な暴力やネグレクトまではいかなくても、ついつい子どもを怒り過ぎてハッと我に返る……というのは、ほとんどの親が経験していることではないでしょうか。 育児中は不安や焦りにかられることが多く、また子どもの世話は思い通りにいかないことも多いもの。手っ取り早く「怒る」という手段をとり、段々と怒ることに「慣れ」が出てしまうということもあります。 先日札幌市で2歳の女の子の虐待事件が起こり、新潟県長岡市では「授乳で眠れない」と悩んでいたという母親が3か月の長女を床に落とすという事件が起きたばかりです。子どもを怒り過ぎてしまう自分に悩んだら、どうやって怒りを止めると良いのでしょうか。 「子どもは可愛いのに、気付けば怒ってばかり……」というママも少なくないですよね。小学生から未就園児の3人の子を抱える筆者も、「怒ってしまった」と反省する日々です。 「第二次感情」といわれる怒りの感情。子どもに怒る機会を減らすには、「第一次感情」の解決にヒントがあったのです。 「第一次感情」にフタをするのは理想の母親像「第一次感情」にフタをするのは理想の母親像 第一次感情とは、自分が本当に感じている感情のことで、第二次感情とは、第一次感情によって発生する感情のことです。 「怒りは第二次感情」といわれます。よく考えれば、怒りたくなる場面で以下のような「第一次感情」が隠れていたことに気付きました。 ・肉体的な疲労…夜間授乳、夜泣き、看病等による寝不足。一日中抱っこへの対応や子連れ外出の疲労。 ・精神的な疲労…初めての育児に慣れない。産前と産後の生活のギャップに慣れない。リラックスする時間がなく、心に余裕がない。 ・自分に戻る機会がない…赤ちゃん中心の生活で、物理的にも精神的にも自分の時間がない ・孤独感…ちょっとした話をしたり、相談したり、ねぎらい合える相手がいない。密室育児で社会との関わりを感じられない。単純に寂しい。 ・緊張感…小さな子の命を守る責任感。寝返り期~3歳までは1日中目が離せず気が張り詰めっぱなし。 ・不安や焦り…発達、成長、病気などの不安や焦り。自分できちんと育児できるかという不安。 ・世間体…「母親として完璧にしなければ」という気負い。 ・理想や期待とのギャップ…自分に対しては、家事や仕事が思うように進まないなど。子どもに対しては、何十回同じことを教えても分からないなど。夫に対しては、育児に協力的でないなど。 上記のような「第一次感情」を感じてしまう自分を、「母親として失格」と思い、そのことに怯え、フタをしてしまう。そうして出てきた「怒りという第二次感情」で発散してしまうのではないか。そう考えると、思い当たることもありました。 たとえば筆者も先日、「学校に行きたくない」と言う子どもに怒ってしまったことがありました。まだ前日の夜は「学校に行きたくないんだね」「まだ慣れなくて緊張するんだね」と子どもの気持ちに共感したり、「何かあったの?」と聞く余裕があり、話を聞いていました。 しかし登校前は忙しく、自分も仕事の予定が詰まっている状態。「今日は仕事をしなければならない」という気負い、「登校時間まであと10分」という焦り、「親としてきちんと学校に行かせねば」という世間体への意識が混ざり、怒ってしまったのです。冷静に考えれば、これから行きたくないところへ行くというのに、親に怒られるのでは子どもは余計辛いでしょう。 日本では母親が神格化されがちですが、母親だってひとりの人間。まずはそのことを受け止め、「第一次感情」と向き合うことが大切だと気付いたのです。 「これ以上はできない」ことを、家族に分かってもらう「これ以上はできない」ことを、家族に分かってもらう 今では怒りそうになったら、「第一次感情は何か?」と考えるようにしています。 そうして「素直に悲しみ、泣き、愚痴る」ことが大切。怒る前に「今日は寝不足で疲れた」「子どもが熱を出していて不安で余裕がない」と、第一次感情を発散してしまうのです。 母親が弱音を吐いてはダメなんてことはありません。むしろ母親を神格化し、我慢を強いることが、怒りを生んでしまうのです。 母親だって人間。無理な我慢はしない(画像:Pixabay) 同時に大切なのが、「第一次感情を引き起こす環境の改善」。特に大切だと思ったのは、以下の4点です。 ・話し相手作り(育児の不安や愚痴を発散したり、労り合える相手) ・無理をしない(夜泣き、イヤイヤ期、看病など乳幼児期はイレギュラーなことが起こりやすいため) ・家事を減らす、なくす工夫 ・家族の理解と協力 特に大切なのは、最後の「家族の理解と協力」。話をしたくても、無理を止めたくても、家事を減らしたくても、家族の理解がないと後ろめたく思うママも少なくありません。 理解が得られないなら、「分かってもらう勇気」を持ちましょう。限界がくる3歩手前で無理を止め、「これ以上はできない」と線引きをすることは、円満な家庭運営に必要です。一時的に嫌な空気になったり、話し合いも必要になりますが、無理を続けるよりはいいでしょう。 「等身大の自分」で育児する 第一次感情と向き合い続けると、「自分は何が得意で苦手か、何が好きで嫌いか、どのような状況に不安を感じ、体力はどれくらいで、どんなことでリフレッシュできるか。心の余裕を保つためには何を減らすべきか」と、どんどん等身大の自分やキャパシティーが明らかになります。 等身大の自分が分かるほど、「無理をしない家事と育児」ができるようになり、怒る回数も減らせるでしょう。人間ですから、全く怒らないのとも、また違います。ほどよい育児ができるよう、まずは第一次感情を掘り起こしてみてくださいね。
- ライフ