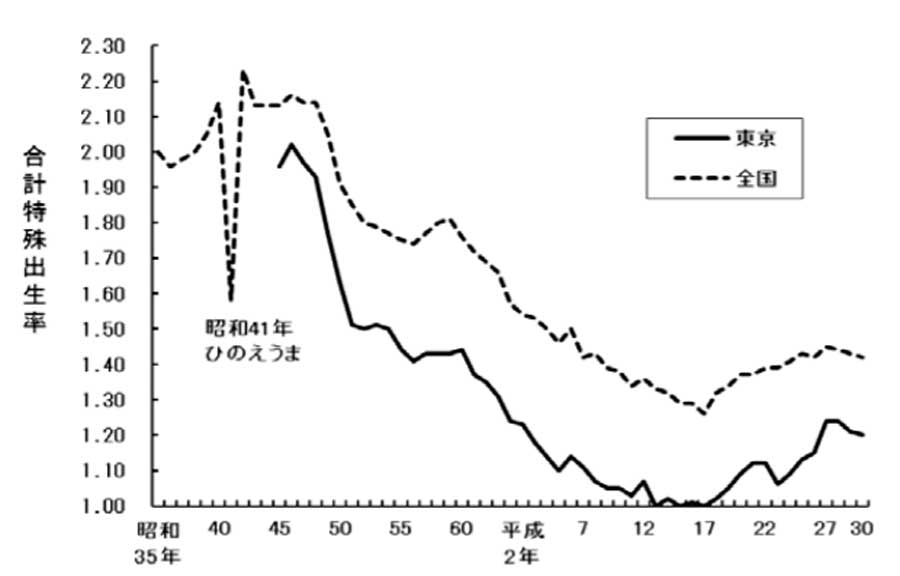おしゃれなのに機能的、深まる秋に「シャツワンピ」が効く4つの理由
1.ダーク系ストライプなら「ほそ見え」効果あり 秋に活躍する「シャツワンピース」。カジュアルなイメージが強いかもしれませんが、最近はキレイめにも甘めにも着られるアイテムが続々と登場しています。 1枚でコーディネートが決まるシャツワンピは、前を開いて着られるのが大きな特長。ワンピースとしてだけでなく羽織りものやコート代わりにもできるから、着回し力の高い優秀アイテムなんです。 ブラックなカラーが大人っぽい雰囲気を引き立てる(画像:フェリシモ) たとえば秋らしさを感じさせるトラッド調ストライプのロングシャツワンピ。黒を基調にしたストライプはハンサムな存在感があって、上品かつ大人っぽい雰囲気を演出してくれます。 濃い色味のストライプは「Iライン効果」で体全体をほっそり見せてくれるから、体型が気になるという人にもおススメです。 少し暑さを感じる日中にも、袖を折り返して様になるのもシャツワンピの特長。重ね着をすればもちろん晩秋まで着回せる、活躍シーズンの長い優秀アイテムです。 2.丸襟としぼり袖で、甘さとかわいらしさを注入 カジュアルやハンサムといったシャツワンピのイメージを覆す、甘めのアイテムも人気上昇中。たとえば襟元はいつものスクエアタイプではなくラウンドタイプを選ぶだけで、グッとかわいらしくピュアな印象が引き立ちます。キュッとしぼった袖も、かわいらしさを底上げしてくれるディテールのひとつ。 丸襟のシャツワンピは清楚ながら、かわいらしい印象(画像:三越伊勢丹ホールディングス) かわいい系を着たいなら、色は断然ホワイトがおススメ。コーディネート全体を明るく底上げして清潔感をかもし出してくれる色なので、1枚持っておくと重宝すること間違いなしです。 3.ワンピにもコートにも着られるのは「ベージュ」3.ワンピにもコートにも着られるのは「ベージュ」 シャツワンピにも、シャツコートにもなるのがベージュのアイテム。ボタンを留めてワンピースとして着れば、上品な大人の着こなしに。 ベージュのシャツワンピはサラッと羽織ってコート代わりにも(画像:DoCLASSE) さらに、前を開けて羽織れば軽めのコートに早変わり。着回しの利くベージュは、インする服を選びません。上品にもナチュラルにもコーディネートできて、秋だけでなく春にも活躍してくれるアイテムです。 4.コートライクに着たいならグレンチェックも要チェック グレンチェックのドレスシャツコートも見逃せません。前を閉めてフロントでリボンをキュッと絞れば、余裕のある落ち着いた大人の印象に。逆にリボンをほどいて前を開ければ、カジュアルで親しみやすい印象に早変わりします。 シャツワンピはダボっと重くなりがちなイメージがありますが、背中にタックが付いているデザインならXラインのメリハリをきちんと表現してくれます。 大人っぽくも、カジュアルにも。いろんな表情を見せてくれるグレンチェック(画像:フェリシモ) 着回し力の高いシャツワンピのうれしいところは、1枚で圧倒的な存在感を発揮して一気におしゃれ度を上げてくれるところ。コロコロ表情を変える「着ていて楽しい服」は、間違いなく女性の味方です。重ね着がますます楽しくなるこの季節、まずは1枚、手に取ってみませんか?
- ライフ