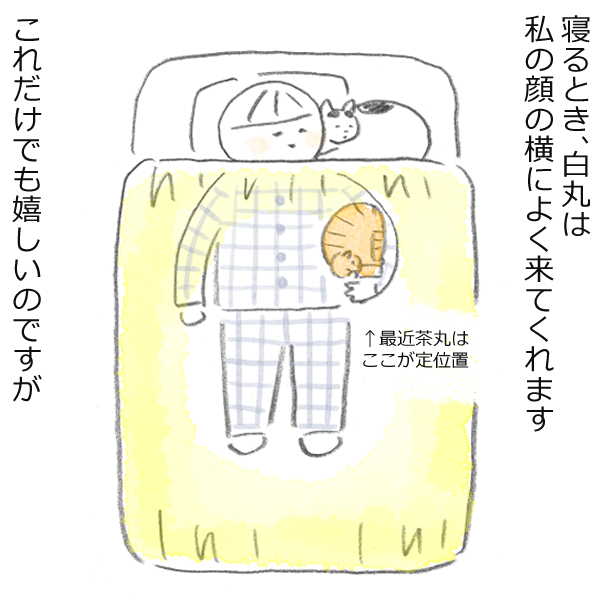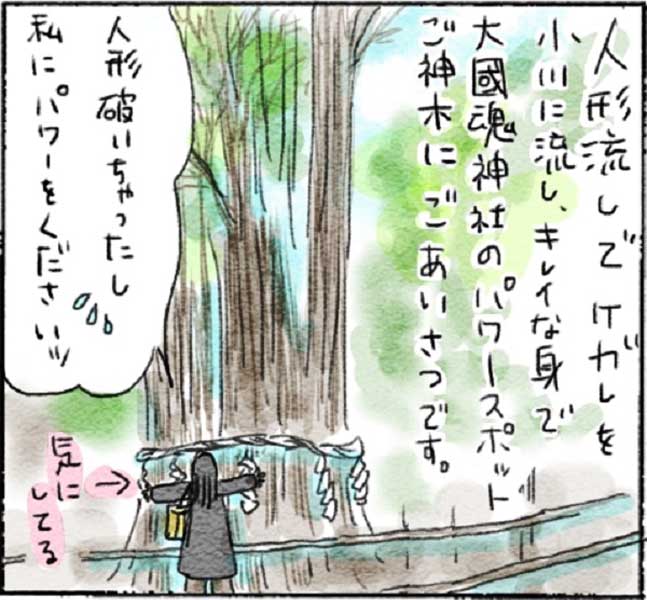東京都に「ジュラシックパーク」があった? 知られざる熱帯自然林の正体とは
島の百科事典にも載っていない 知っているつもりの場所でも現地へ赴けば、必ず新たな発見があるのが旅の醍醐味でしょう。十数回は訪れている八丈島ですが、先日初めて会った島人が誘ってくれました。 「ヘゴの森へ、行ったことがありますか」 ジュラシック・パークを彷彿(ほうふつ)とさせるような森が、八丈島にあるというのです。ずいぶん歩いている島ですが、そんな場所は行ったことはもちろん、聞いたこともありません。島の百科事典『シマダス』にも載っていないので、すぐに飛びつきました。 「ぜひ、歩いてみたいです。連れて行ってください」 「ヘゴの森」を歩く(画像:斎藤潤) 大人の背丈をはるかに超えて成長し、幹はまるで木のように太く硬くなるシダがあります。 熱帯・亜熱帯性のヘゴと呼ばれる木性のシダで、南西諸島では森などでごく当たり前に見かける植物。それでも、日ごろ見慣れていない人間にすれば、植物園の温室でしか見かけないような、エキゾチック極まりない植物でしょう。 その自生北限地帯が、八丈島にある。それは知っていましたが、南西諸島と異なり、さすがに八丈島でもヘゴは珍しい。そんな貴重なヘゴの森があったのは、島の南半分を占める三原山の南麓でした。入り口には、特に案内板もありません。 ヘビのような模様のフルーツがヘビのような模様のフルーツが「ヘゴの森は、私有地なんですよ」 だから、オーナーに許可を得たガイドの同行が必要です。勝手に入ると、不法侵入になるので、要注意。 「オーナーが、自分の森にあったヘゴを増やして、ジュラシックパークのような世界を作り上げたんです。オーナーの神様も祀(まつ)られている場所なので、失礼のないよう注意してください」 といっても、そんなに改まったことではありません。ゴミを捨てたり、植物を勝手に採ったりしてはいけないということ。無礼なふるまいをすれば、神様に祟(たた)られる。素晴らしい森の環境を、謙虚に楽しめばいいのです。 変哲もない林道をぶらぶら歩いていくと、葉の長さが1mほどのシダ、ハチジョウカグマが道端の斜面から垂れ下がっていました。少しずつ南国らしくなってきたぞ。 やがて、2mほどの大きな葉をつけたリュウビンタイ(これもシダの1種)も現れました。近くの杉の立ち木には、モンステラが絡んでいます。鉢植えなどでもよく見かける観葉植物で、ヘビを思わせる鱗(うろこ)模様の実は怪しげ。 モンステラの実と葉(画像:斎藤潤) とても食べられそうにないですが、実はフルーティーでおいしい。カブツ(八丈のダイダイ)らしき実も、なっていました。 恐竜がいるのではと思う深い森恐竜がいるのではと思う深い森 この辺になると、お待ちかねのヘゴが次々と登場。おお、すごい。たくさんある。どれも見上げるばかりで、高さ4、5mはありそう。一挙に、ジュラシックパークへ突入です。この辺りは、「ヘゴ谷の路・ジュラの森」と呼ばれているらしい。 これだけヘゴが密生していれば、映画ゴジラのロケ地になった奄美大島の金作原原生林と比べても、遜色(そんしょく)はありません。いや、数ではまさっているかもしれない。ヘゴの葉で覆われた空を見上げては、恐竜がのぞき込んでいないかと妄想しながら、ついついシャッターを押してしまいます。 道端のドーナッツ状の盛り上がりは、炭焼き窯の跡だといいます。中に入るすき間は、窯の口らしい。土で作られた窯は、多様な植物に覆われ、まるで天然の植木鉢のよう。自然の力が強く、人間の手を離れると人工物も、たちまち自然に帰って行くのです。 杉などの針葉樹とヘゴが混じりあっている森も珍しく、他ではほとんど目にすることはないのではないでしょうか。 しばらくすると、不思議なフォルムの緑色をした花が咲いていました。 シマテンナンショウ(画像:斎藤潤) 三宅島、御蔵島、八丈島に分布する、シマテンナンショウ。コンニャクの仲間で、島ではへんごと呼ばれ、球茎(地中の芋のような部分)はゆでてモチのようについて、つるんと飲み込んで食べていたといいます。再び咲いていたよく似た花は、ハチジョウテンナンソウ。御蔵島と八丈島にだけ生えている珍しい植物です。 行程2km、90分 ジュラの森散策行程2km、90分 ジュラの森散策 ちなみに、巨大なワラビそっくりのヘゴの芽も、食べることができます。沖縄の西表島ではバラピ(ワラビの転訛)と呼ばれ、祭りの行事食などに使われているとのこと。 食感は、山芋そっくりで、さっくりとろりとして粘り気があり、おいしい。デンプンをたっぷりと貯えたヘゴの幹の芯も食べられますが、こちらは筋っぽいダイコンのようで、あまりいただけません。 緩やかな山道を登り切ると、ぽっかり開けた空間に出ました。彼方には、緩やかな斜面に囲まれた三原山がそびえていました。 上から見たヘゴの森(画像:斎藤潤) その辺りから「シイの尾根路・照葉樹の森」と呼ばれる地域でした。根元から一斉に噴き出すように枝が生える株立ちが目立ちます。炭焼きが盛んだった時代の名残りだそう。 その先、いろいろと珍しい植物に出合いましたが、それについては書いてくれるな、直接見に来てほしいと言われたので、あえて伏せておくことにします。 おおよその行程は、約2km。標高差はわずか70mで、所要時間は90分ほど。八丈島観光レクリエーション研究会が、「ヘゴの森ツアー」を実施しています。
- 未分類