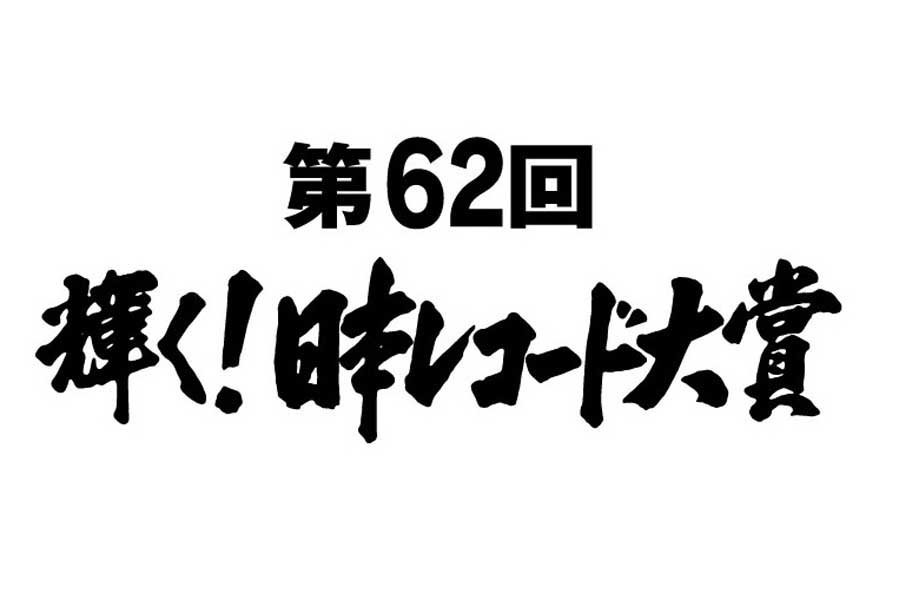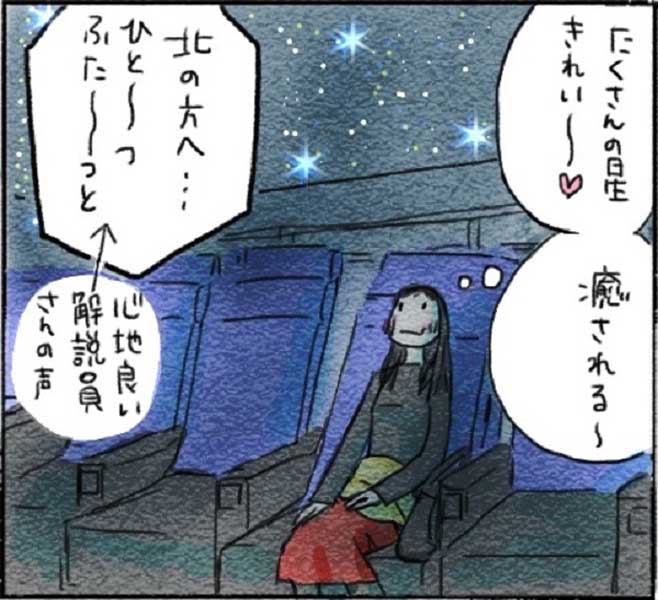日本郵便サイトにひっそり掲載 「お手紙文例集」がエモいと話題! 「デートの誘い方」にSNSから「いい文面」「惚れちゃう」の声
あっと驚く衝撃の場面、感心させられる発見や豆知識、思わず涙を誘う感動の出来事……。SNS上では毎日、新鮮な話題がいくつも発信されています。そのなかから「東京」に関連するものを厳選してご紹介します。手紙を書かない今の時代に 最後に手紙を書いたのはいつですか。 パソコン、携帯電話、スマートフォンが普及して以降、あらたまって誰かにペンを執る機会はめっきり少なくなりました。自宅の郵便受けに届くのは企業からのDMや宅配チラシ。ポストを開けて投函物を確認するのが楽しみだったのは、すでにひと昔の感覚なのかもしれません。 令和の時代に手紙を書くなら……? 日本郵便サイトの文例集が話題に(画像:写真AC) しかし手紙には手紙ならばこその情緒や良さがある。そんなことを再確認させてくれるつぶやきが今、ツイッター上で静かな反響を呼んでいます。 2021年8月17日(火)、東京都内の大学3年生、三浦くもり(@miurakumori)さんが投稿した日本郵便にまつわるつぶやきです。 奥ゆかしく、つつましい誘い文句「日本郵政、デートの誘い方まで面倒みてくれるらしい」 というひと言とともに三浦さんが投稿したのは、日本郵政グループ(千代田区大手町2)の日本郵便ウェブサイト「お手紙文例集」の中から「デートの誘い」のページを引用した画像。 その文面がじつに奥ゆかしく、つつましくて“手紙的”なのです。 「突然お手紙を差し上げる失礼を許してください。 実は、○月○日夜○時から、○○○○ホールで開かれるコンサートのチケットが2枚、手に入りました。バッハのオルガン曲です。」 「先日の昼休みに君が、『音楽が大好きなの』と話していたのを思い出したので……。 会社ではなかなかプライベートなお誘いはしにくく面と向かうと照れくさくて言い出しにくいので、手紙に書きました。御一緒できれば本当にうれしいです。」 「御都合はいかがでしょうか。よいお返事をお待ちしています。」―― 明治・大正時代みたいな文面?明治・大正時代みたいな文面? ツイートのリプライ(返信)欄には、 「これは……惚れる」 「いい文面だなあ」 「今度試してみよう」 といった感想から、 「こういう時代に生まれたかった」 「今の若い女性って手紙もらったことないんじゃない?」 「明治大正って感じで良いと思ってしまった。実際令和でこれやったらおもしろい」 と内容にツッコミを入れるものまで、さまざまな声が寄せられました。 手紙の良さは「相手を考える」こと 都内の大学に通う三浦さん。就職活動を控えて「ビジネスマナーとして手紙の書き方を確認しておこうと思い、日本郵政のサイトを見ていた」ところ、偶然にこのページを発見したのだそうです。 「お堅いイメージのある企業の遊び心を垣間見たようで、くすっと笑ってしまいました」 自身も普段、手紙を書く機会は決して多くはないといいますが、 「友人の誕生日には毎年プレゼントに手紙を添えています。手紙は、便せんや切手、筆記具などを相手のことを考えながら選ぶ時間がとても楽しいと思います。同じ内容の文章がメールやSNSで送られてくるよりも、手紙だと自分専用の作品のようでうれしくなります」。 デートの承諾、お断りの文例も!デートの承諾、お断りの文例も! ちなみに、日本郵便のサイトには「デートの誘い」に続く「デートの誘いの承諾」「デートの断り」の文例集も記載されています。 承諾バージョンは、 「思いがけないお誘いに心躍る思いです。もちろん、ぜひ御一緒させてください。」 と快諾とともに率直な喜びを伝え、 「音楽を聴くのは大好きなのですが、正直に言うと就職してからクラシックのコンサートに足を運ぶのは初めて。それも、私にとっては思い入れの深いバッハのオルガン曲だなんて……。どんなにすてきでしょうね。」 と、浮き立つ思いを情感たっぷりに伝える文面です。一方、断りバージョンは、 「実はちょうどその日、学生時代の友人たちと食事の約束をしていたのです。○年ぶりに仲良しが全員集まるので、今さら断るわけにはいかなくて……。」 「まずは、取り急ぎお返事まで。」 と、断りの理由を添えて相手の落胆に配慮する行間が印象的です。 千代田区丸の内にある東京中央郵便局(画像:写真AC) それだけにとどまらず同ページ内には、「デートのお礼」「再会の申し込み」「プロポーズ」「プロポーズの承諾」「プロポーズの断り」……と、文例集というよりひとつの小説を読んでいるような気持ちにさせられるシリーズがずらり。 たとえばプロポーズの手紙は、 「君といっしょにいる時間はいつもあっと言う間で、この○年間はとても充実していました。僕としては、この時間を一生に延長したいと思っています。つまり、結婚して欲しいのです。」 プロポーズ、断る場合には……?プロポーズ、断る場合には……? それに対する承諾の手紙は、 「喜んで○○さんの申し出をお受けします。『結婚しよう』という○○さんのプロポーズをずっと待っていました。」 一方、断りの手紙は、 「もうあと数年は仕事に専念していきたいのです。○○さんならおそらく結婚後も仕事を続けるのは大賛成だとおっしゃってくださるでしょう。でも、たとえば○○さんに転勤辞令が出たときにどうするか、見極めがつくまでは、安易に結婚するわけにはいかないのです。」…… 思いを伝えて、思いが返ってくる。手紙とはまさに小説のようなひとつの物語ということが、文例集からは伝わってくるようです。 思いを伝えて、思いが返ってくる。手紙とはひとつの物語(画像:写真AC) 三浦さんは日頃、自作の短歌を作品投稿サイトnoteなどにアップしています。 <西川と戸山と野田が来てないね小田急線が遅延してるね> <さん付けのまま秋になり小道具の係と言われ頷いている> 上記2首は女子高生だった頃の記憶をもとに読んだ連作の一部。 三浦さんのみずみずしい感性が、ツイッターを通して手紙の楽しみを再び思い起こさせてくれました。
- ライフ