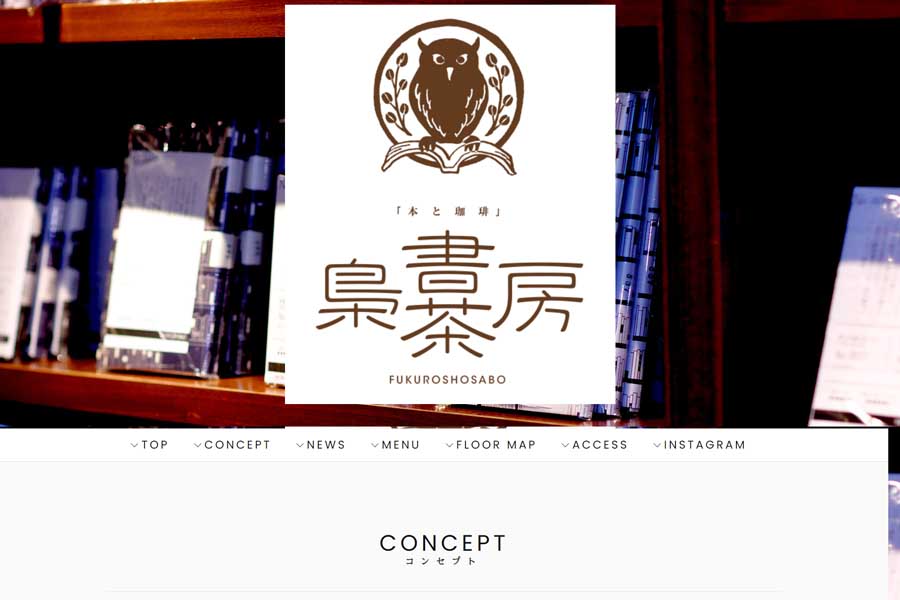福を呼ぶまち歩き「東京七福神めぐり」―龍のいる神社やさんぽが楽しいエリアはどこ?【2024】
正月の松の内に行うと、大きな福がもたらされるといわれている「七福神めぐり」。東京にもエリアごとにさまざまな七福神が隠れています。 今回は写真家の石津祐介さんが、東京でオススメの「七福神巡り」を、街の特徴とともに9種類ご紹介します。 正月の松の内に行うと、大きな福がもたらされるといわれている七福神めぐり。七福神とは、大黒天、毘沙門天、恵比寿天、寿老人、福禄寿、弁財天、布袋尊の七つの神様で、この七柱が祀られている社寺を全てお参りするのが「七福神めぐり」です。 七福神を参拝すると「七つの災難が除かれ七つの幸福が授かる」とされ、室町時代末期頃に始まり、江戸時代になると庶民の間で流行したといいます。 おめでたい七福神の福を新年に呼び込む、東京でオススメの七福神めぐりをご紹介します。 東京ドーム横にある小石川七福神の福禄寿(画像:石津祐介)【その他の画像】>> 【江東区】深川七福神/下町グルメやカフェが豊富 深川七福神めぐりは、門前仲町駅から森下駅までの間にある寺社をめぐるコースです。下町の雰囲気が残り、見どころも多く商店街やカフェに立ち寄りながら、名物の深川めしを堪能するのもオススメです。 ・深川神明宮 (寿老人) ・深川稲荷神社(布袋尊) ・龍光院(毘沙門天) ・円珠院(大黒天) ・心行寺(福禄寿) ・冬木弁天堂(弁財天) ・富岡八幡宮(恵比須) ■深川七福神 http://www.fukagawa7.net/ 「深川の八幡様」として親しまれている富岡八幡宮(画像:石津祐介)【台東区・荒川区・北区】谷中七福神/江戸最古の七福神 江戸最古の七福神めぐりといわれている谷中七福神。田端駅から上野駅までのコースには歴史的な建造物も多く、谷中銀座商店街での食べ歩きも楽しめます。 ・東覚寺(福禄寿) ・青雲寺(恵比寿) ・修性院(布袋尊) ・長安寺(寿老人) ・天王寺(毘沙門天) ・護国院(大黒天) ・不忍池弁天堂(弁財天) 上野公園の不忍池にある辯天堂(画像:石津祐介)【台東区・荒川区】浅草名所(などころ)七福神/9カ所あるのは理由がある 七福神ですが、九つの社寺をめぐるのが浅草名所七福神。「九は数のきわみ、一は変じて七、七変じて九と為す。九は鳩でありあつまる意味をもち、また、天地の至数、易では陽を表す」という古事に由来します。浅草エリアをはじめ、見どころの多いコースです。 ・浅草寺(大黒天) ・浅草神社(恵比寿) ・待乳山聖天(毘沙門天) ・今戸神社(福禄寿) ・橋場不動院(布袋尊) ・石浜神社(寿老人) ・吉原神社(弁財天) ・鷲神社(寿老人) ・矢先稲荷神社(福禄寿) ■浅草名所七福神 2024年正月期間受付時間: 【1月1日】0:00~18:00まで ※吉原神社は1月1日2:00~8:00までは千束稲荷神社にて対応 【1月2・3日】9:00~18:00 【1月4~7日】9:00~17:00 【1月8日~】9:00~16:00 http://www.asakusa7.jp/ 三社祭で有名な浅草神社(画像:石津祐介)【文京区】小石川七福神/こんにゃく閻魔の源覚寺や滝沢馬琴の眠る深光寺も 小石川七福神は平成7年に始まった比較的新しい七福神で、茗荷谷駅と後楽園駅の間にあります。小石川後楽園の散策や東京ドームシティなど見どころも多くあります。 ・東京ドーム(福禄寿) ・源覚寺(毘沙門天) ・福聚院(大黒天) ・真珠院(布袋尊) ・宗慶寺(寿老人) ・極楽水(弁財天・女) ・徳雲寺(弁財天・男) ・深光寺(恵比寿) 滝沢馬琴のお墓やキリシタン灯籠のある深光寺の恵比寿様(画像:石津祐介)【新宿区】新宿山手七福神/東京の坂を味わうコース 新宿から飯田橋にかけて7つの社寺を巡るコースです。昭和初期に始まったといわれ、新宿の繁華街から神楽坂の路地など、東京の古今を味わえます。 ・太宗寺(布袋尊) ・稲荷鬼王神社(恵比寿) ・厳嶋神社(弁財天) ・法善寺(寿老人) ・永福寺(福禄寿) ・経王寺(大黒天) ・善国寺(毘沙門天) ■新宿観光振興協会 新宿山手七福神 https://www.kanko-shinjuku.jp/course/-/article_2809.html 新宿御苑近くの太宗寺にある不動堂(画像:石津祐介)【目黒区・港区】元祖山手七福神/巡る順番でご利益が変わる 元祖山手七福神は目黒駅と白金台駅を起点として、アップダウンの多い目黒や高級住宅街として有名な白金を巡ります。巡る順番でご利益に違いがあり、港区の覚林寺から巡ると無病息災や長寿祈願、逆に目黒区の瀧泉寺から巡ると商売繁盛のご利益があるといわれています。 ・蟠竜寺(岩屋弁財天) ・瀧泉寺(恵比寿) ・大円寺(大黒天) ・妙圓寺(福禄寿・寿老人) ・瑞聖寺(布袋尊) ・覚林寺(毘沙門天) 福禄寿と寿老人を祀る妙圓寺(画像:石津祐介)【港区】港七福神/ショッピングのついでのお参りも 七福神に加え宝船を含めた8カ所をめぐるのが特徴の港七福神。参拝途中に、麻布十番商店街の食べ歩きや六本木ヒルズ、東京ミッドタウン、東京タワーなど観光名所に立ち寄れるのも楽しみの一つです。 ・宝珠院(弁才天) ・熊野神社(恵比寿) ・十番稲荷神社(宝船) ・大法寺(大黒天) ・麻布氷川神社(毘沙門天) ・櫻田神社(壽老神) ・天祖神社(福禄寿) ・久國神社(布袋尊) ■港七福神 受付期間:毎年元日から成人の日(2024年1月8日)まで 受付時間:9:00~17:00 ※最終日の集印開始受付は14:00まで https://www.minatoshichifukujin.org/ アニメ『セーラームーン』に登場する「火川神社」のモデル、麻布氷川神社(画像:石津祐介)【中央区】日本橋七福神/小網神社には龍の彫刻も 日本橋七福神めぐりは、7つ全てが神社となっているのが特徴です。人形町通りや甘酒横丁など、老舗の名店が連なる下町情緒あふれた通りを散策するのもオススメです。 ・松島神社(大黒天) ・末廣神社(毘沙門天) ・笠間稲荷神社(寿老人) ・椙森神社(恵比寿) ・小綱神社(福禄寿) ・茶の木神社(布袋尊) ・水天宮(弁財天) ■日本橋七福神めぐり公式サイト https://www.nihonbashi-shichifukujin.gr.jp/ 「中央辨財天」と呼ばれる水天宮の弁財天(画像:石津祐介)【品川区】東海七福神/レンガ造の虚空蔵横丁など旧宿場町の風情を 北品川から大森までの旧東海道を歩く東海七福神。レンガ造の虚空蔵横丁や旧東海道品川宿の街道松など見どころも多くあります。 ・品川神社(大黒天) ・養願寺(布袋尊) ・一心寺(寿老人) ・荏原神社(恵比寿) ・品川寺(毘沙門天) ・天祖諏訪神社(福禄寿) ・磐井神社(弁財天) ■しながわ観光協会 東海七福神 https://shinagawa-kanko.or.jp/recommended_route/toukaishichifukujin/ 東京十社の一つ、品川神社(画像:石津祐介) 七福神めぐりの御朱印や授与品の頒布時間などは、社寺の諸事情により変更または中止となる場合がありますので、参拝の際は最新の情報をご確認ください。
- スポット
- 人形町・小伝馬町
- 六本木・乃木坂・西麻布
- 品川
- 大森駅
- 後楽園駅
- 日本橋・京橋
- 浅草
- 田端駅
- 目黒・白金・五反田
- 門前仲町駅
- 飯田橋駅