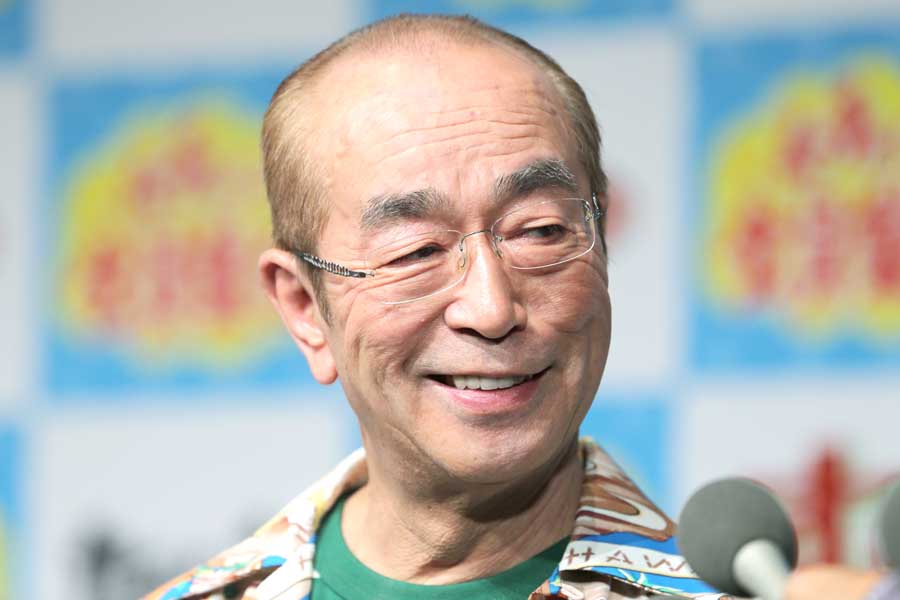新型コロナで一斉休校 = 「地元野菜」をお得に食べるチャンス? 未曽有のピンチを生産者応援に転じる術があった
新型コロナウイルスの影響で全国の小中高校が一斉休校となるなか、2020年3月13日、東京都内の区立学校の給食で使われる予定だった地場産コマツナが新宿のJA施設で販売されました。採れたて、新鮮な東京コマツナ 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、2020年3月2日(月)から一斉に臨時休校の措置が取られている全国の小中高校。 学校給食で使われる予定だった野菜を各地の直売所などで販売する動きが広がるなか、JR新宿駅近くの「JA東京アグリパーク」(渋谷区代々木)でも13日(金)、足立区などの区立小中学校の給食用として栽培されたコマツナが店頭販売されました。 収穫してすぐに販売されたコマツナ。新鮮そのもの(2020年3月13日、遠藤綾乃撮影) 販売されたのは、足立区・葛飾区・江戸川区の生産者らでつくるJA東京スマイル農業協同組合(葛飾区白鳥)のコマツナ計200袋。1袋約500gと、スーパーなど市場に出回るものより2倍程度大きく、税込み100円という価格は市販品と比べてずいぶんお値打ちです。 「応援販売!!」と大きなポスターが掲げられた売り場は、前日の夕方から当日朝までに収穫された新鮮なコマツナを求める人たちで販売開始早々からにぎわいました。 廃棄するなんて、もったいない廃棄するなんて、もったいない 友人とともに訪れた近くに住む40代の女性は、「学校給食用に育てられたお野菜なら品質は間違いないはず。食べないで廃棄するなんてもったいないですし」。 夫とともに新宿で用事を済ませに来たという大田区在住の70代女性は、「たまたま通りかかっただけですが、コマツナが安く買えてありがたかったです。(生産者が)一生懸命作った野菜ですから、少しでも手助けになればと思いました」。 普段行くスーパーでは、もっと小さいサイズのコマツナが138円くらいするとのことで、「これはお得ですね。今日の夕食用に、油揚げと一緒に煮るなりしておいしくいただきます」。 給食用のコマツナを買い求める人たちでにぎわったJA東京アグリパーク(2020年3月13日、遠藤綾乃撮影) また、仕事の昼休みを利用して来店したという別の女性は「ここ(JA東京アグリパーク)で売ってる野菜はハズレがないんです。おいしいし新鮮だから、いつも買っていっていますよ」と話していました。 都内に農産物直売所は58か所都内に農産物直売所は58か所 JA東京スマイル営農指導課の齋藤真史課長は、 「2019年10月の台風15号、19号のときのように、ハウス栽培品が駄目になって出荷できないといった例は過去にありますが、『(野菜の)出来はいいのに出荷できない』というのは記憶にありません。こんな事態ではありますが、コマツナは今が一番おいしい時期ですから、多くの方に手に取っていただきたいです」 とコメント。普段は東京産のコマツナを食べない人にも、味を知ってもらう機会になればとの考えを示しました。 給食用のコマツナを買い求める人たちでにぎわったJA東京アグリパーク(2020年3月13日、遠藤綾乃撮影) 東京都内には58か所の農産物直売所があり、給食用だった野菜は随時、各所で販売されているとのこと。 日頃は地場産の野菜をわざわざ選んで食べる機会がないという人も、こんな時期だからこそ地元の味を試してみるというのはいかがでしょうか。
- ライフ