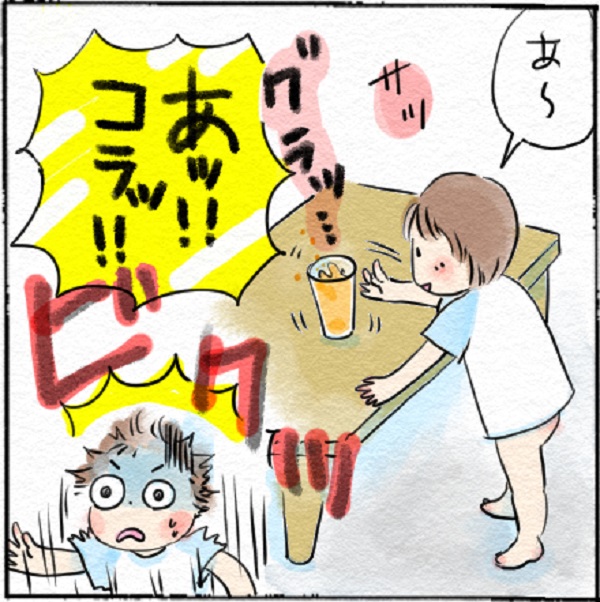不気味系からカワイイ系まで……コロナ禍で「変わったマスク」が次々誕生した日本のド根性魂とは
どうせ付けるなら変わったマスク? 2020年8月、上野や御徒町駅にほど近い総合ディスカウントストア「多慶屋(たけや)」(台東区台東)が導入したスマイルマスクが大きな話題を呼びました。 新型コロナウイルスが猛威を振るった2020年。いまだ事態は収束せず、東京では連日150人以上の感染者が報告されています。 感染予防の観点から、オフィスや映画館、ライブ会場など、マスクの着用が事実上“義務付け”られている状況です。街を見渡しても、8~9割ほどの人が屋外でもマスクを着用している姿が見られます。 これまでの日常では、マスクを着用している人を頻繁に見かけることはありませんでした。着用するとしても、インフルエンザが流行し始める秋口から寒い時期にかけてのみだったでしょう。 しかし、2020年は3月頃から必要となり、マスクの売り切れが続出。一時期はマスクを求める人たちの行列をドラッグストアなどで見かけることもありました。 これを受け、政府は全世帯にガーゼ製の布マスク、いわゆる「アベノマスク」を2枚ずつ配布。 また各メーカーは夏でも涼しくマスクを着用できるように冷感マスクやメッシュ素材のマスク、あるいは口に直接触れないフェースシールドを開発するなど、2020年はマスクにまつわるニュースが後を絶ちません。 そんな中、新たなアイデアで世間をにぎわせたのが多慶屋のスマイルマスクです。 ビートたけし氏まで着用した話題作ビートたけし氏まで着用した話題作 これは8月10日(月・祝)から10月31日(土)までの期間に店内で実施される「スマイルキャンペーン」の一環として開発されたもの。表面に笑った口元のリアルな写真がプリントされている、奇抜な布マスクがインパクトを与えました。 着用している従業員の写真を見るとかなり自然で、一見本当に笑っているように見えます。 リアル過ぎて、ぱっと見では印刷と気がつかない? 多慶屋のスマイルマスク(画像:多慶屋) 一方で、白いマスクの上からリアルな口元が見えるというユニークさに「逆に不自然」「怖い」という否定的な意見も。一体なぜ、多慶屋はスマイルマスクの開発に着手したのでしょうか。 担当者は以前、こんなことをインタビューで語っています。 「プロジェクトメンバーの発案がきっかけです。コロナ禍でマスクをつけるのが当たり前になっているなか、接客の際に笑顔の口元が隠れてしまう、なんとか笑顔を届けることはできないか? とずっと思っていました」(2020年8月23日付、FNNプライムオンライン) 最初は布マスクに手書きで笑顔を描こうとしましたが、衛生的観念から断念したとのこと。 「それならば、笑った口元の写真を印刷しよう!」と思い立ち、プロジェクトメンバーの口元を撮影。その写真を外部委託で転写プリントし、スマイルマスクが完成したのです。 いつも来店してくれるお客さまのために笑顔を届けたい、という従業員の配慮から生まれたスマイルマスク。思わぬ反響を受け、多慶屋は「多慶屋 オリジナルマスク スマイルマスク」と称して男女2種類の商品を販売することを決定しました。 すると、予約販売の時点で即完売に。以外にも、医療・介護施設関係者からの購入予約が多かったといいます。 8月22日(土)に放送された報道番組「新・情報7daysニュースキャスター」(TBSテレビ系)のオープニングでは、MCのビートたけしさんもスマイルマスクを着用して登場しました。 マスクを付けたままでも笑顔を表現マスクを付けたままでも笑顔を表現 多慶屋のスマイルマスクのように「笑顔を届けたい」という思いから開発された商品がほかにも存在するのかInstagramで調べたところ、いろいろなマスクが見つかりました。 例えば、福岡青年会議所が発案した「スマイルマスク運動」の一環で配布された、ニコちゃんマークのシールを貼ったマスク。 マスク着用を嫌がる子どもや、マスクで表情が隠された大人に不安を感じる子どもたちのために、制作されたのことです。 笑っているように見える多慶屋のスマイルマスクとは異なりますが、ニコちゃんマークがあるだけでほっこりとした気分になります。 また、ミュージシャンの松任谷由実さんがファンクラブ会員に配布したマスクには、「YOU DON’T HAVE TO WORRY」(=心配しないで)という英字プリントが施されています。 松任谷由実さんがファンクラブ会員に送ったマスク。笑っている口元のよう(画像:めろん、@pinkmeronpan) よく見ると、カーブを描くようにプリントされた英字が笑顔の口元に見えますよね。このフレーズは松任谷さんの名曲「守ってあげたい」のサビにも使われています。 もうひとつ、最後に紹介するのは、バンド・サザンオールスターズが6月22日(月)に開催した特別ライブ「Keep Smilin’~皆さん、ありがとうございます!!」のグッズとして販売した「Keep Smilin’マスク」。 着用するだけでスマイルになれるイラストが描かれています。リアルな多慶屋のスマイルマスクに対して、こちらはキュート。かわいいものが大好きな子どもも喜びそうです。 奇抜なマスク、込められた思いとは奇抜なマスク、込められた思いとは それにしても、こういった類似の商品を見ていると、ますます多慶屋のスマイルマスクが奇抜に思えてきます。 リアルな写真をプリントせずとも、笑顔に見える商品を作ることもできたはず。そこをあえて実写にした理由が、多慶屋の公式YouTubeチャンネル「TAKEYAチャンネル」に投稿されたスマイルマスクの宣伝CMには表れていました。 動画にはスマイルマスクを付けた女性従業員が、ファッション雑誌の撮影さながら扇風機の風を浴びて髪をなびかせる姿とともに「笑ってくれたら嬉(うれ)しい~」という文字が映されているのです。 「笑ってくれたら嬉しい~」。コミカルなようでいて、切実にも取れる思いが込められたスマイルマスク(画像:多慶屋) つまり多慶屋は、スマイルマスクを付けることで来店客に対してただ笑顔の表情を見せるだけでなく、見た人が思わず吹き出してしまうような商品を作りたかったのでしょう。 そして私たち客側も、そこに込められた思いを無意識のうちに受け取っていたのかもしれません。だからこそこのマスクは、人々を魅了したのでしょう。 コロナ禍の今、自由に行動できないストレスから世の中の雰囲気が以前よりも張り詰めています。 それでもなくとも感染のリスクにおびえながら過ごしているのに、無機質なマスク姿の人ばかりが並ぶと、子どもはもちろん、怖く感じる大人もいるのでは? ニュースを見てしかめ面ばかりしている私たちに、ひと時でも笑顔になってほしい――多慶屋スマイルマスクには、そんな願いが込められているような気がしました。
- ライフ