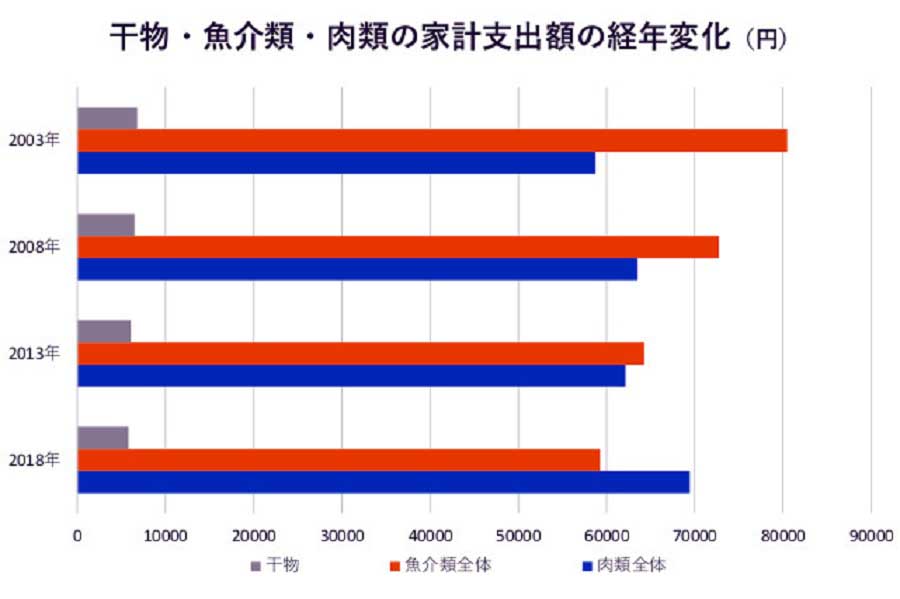英語のせいで中学受験失敗も? 加熱する英語教育で窮地に立つ都内の小学生たち
幼児期から英語教育に走る家庭が多い首都圏の現状について、教育ジャーナリストの中山まち子さんが解説します。外国語教室の開校は堅調に伸びている 2020年度から本格的にスタートする小学校の英語科目化に備え、英語教育の関心が高まってきています。また、首都圏の私立中学では受験科目に英語を加える学校が年々増えています。早い時期から英語に触れさせようと考え、英会話教室に子どもを通わせる家庭の数も同様です。 中学受験を考えている場合、従来の教科の勉強も重要です。そのため、「英語は先手を打ちたい」と幼児期から英語教育に走る家庭が多いと考えられます。今回は、ますます高まる東京での英語教育の現状を解説します。 子どもの英語教育のイメージ(画像:写真AC) 経済産業省の「特定サービス産業動態統計調査」によると、2014(平成26)年7月期の全国の外国語会話教室は3751校で、総務省の「平成26年経済センサス 基礎調査」では1144校が東京に開校しています。3割以上の教室が東京にあり、一極集中していることが明らかです。 「特定サービス産業動態統計調査」の速報値を見ると、2019年の1月から9月までに新規開設した教室は、8月を除いたすべての月で前年同月比を上回っています。 首都圏の入試で英語を入試科目としていた中学は、2015年度に30校を超える程度でしたが、2019年度は125校にまで急増。こうした背景もあり、外国語教育へのニーズに応えての開校が続いているのです。 小学生以下の英検受験者数も右肩上がり 少子化にもかかわらず実用英語技能検定(英検)も、小学生以下の受験者数が年々増加しています。2014年度の受験者数は33万2790人でしたが、2018年度は41万4502人に増えており、英語教育の低年齢化が進んでいることがわかります。2020年度から始まる大学入学共通テストでの本格的な導入は見送られましたが、入試での英検利用を認めている大学は存在しています。 「小さい頃から英検に慣れさせておこう」「英検で2級以上を取得させよう」と考える親が増えるのは自然な流れです。英語は小学校で習う他の4教科と異なり語学であるため、使用機会を増やせば上達するスピードも速く、試験に年齢に関係なく合格することができます。ただし、親が前のめりする危険性も十分に秘めているのです。 日本国内だけで英語力をキープするにはお金もかかる日本国内だけで英語力をキープするにはお金もかかる 両親ともに日本人の場合、インターナショナルスクールに通っていない限り、普段の生活で英語と触れ合う機会は限られます。週1~2回の英会話教室だけでは、英語力の向上は望めません。家庭で英語を毎日鍛えるためには、洋書や映像教材やオンラインレッスンが必要ですが、金銭的な負担は馬鹿になりません。 子どもの英語教育のイメージ(画像:写真AC) 東京では都心を中心に中学受験が当たり前で、そのための通塾が加わると教育費は急に跳ね上がります。受験用の塾に通わせたいけれど、英語力が落ちるのは避けたいと悩んでいると、「二兎を追う者は一兎をも得ず」状態になってしまいます。 逆に「英語を入試科目にしている中学が増えている」と焦り、塾と英会話教室両方に通わせるなど、子どもに無理強いすると、どちらも中途半端になります。小学6年生の年明けにどれだけの英語力をつけさせるかを、両親は子どもが乳幼児期のころから考える必要があります。 通塾が本格化する前に英検3~4級程度の力があれば、他の科目の勉強に支障をきたさないなど、逆算しておかなければなりません。英語への関心がかつてないほど高まっている現在、親が今まで以上に冷静になって子どもに最善な教育を検討することが求められているのです。
- ライフ