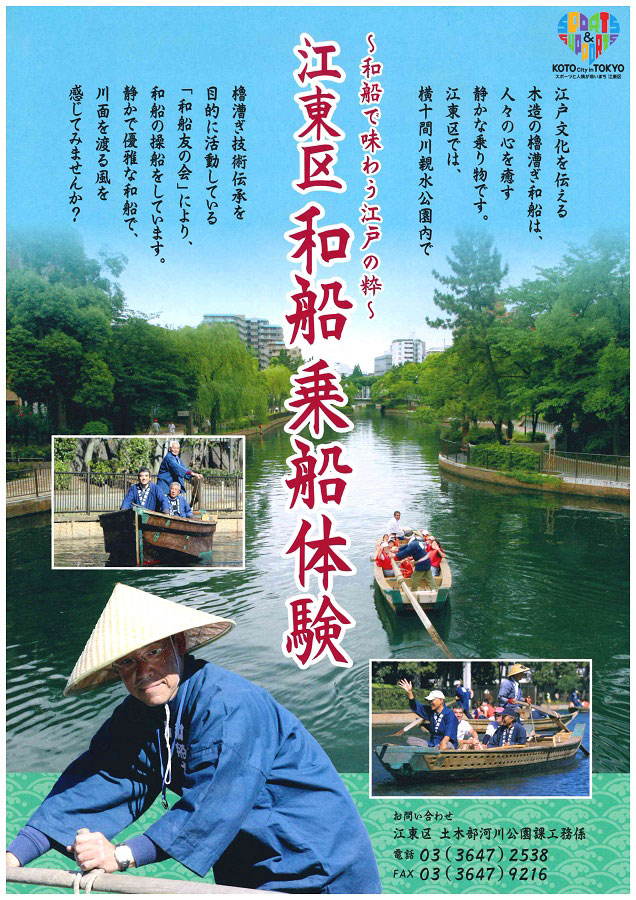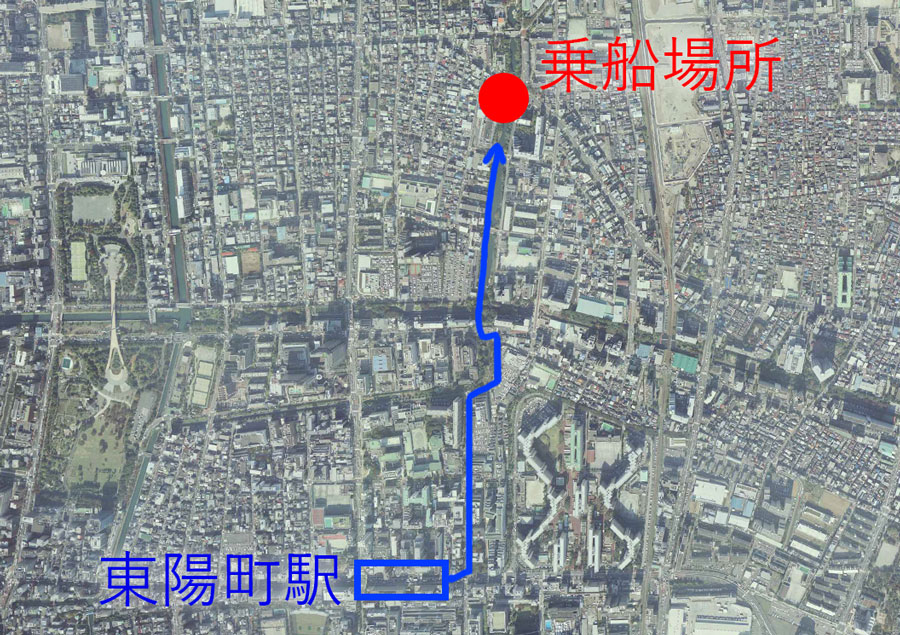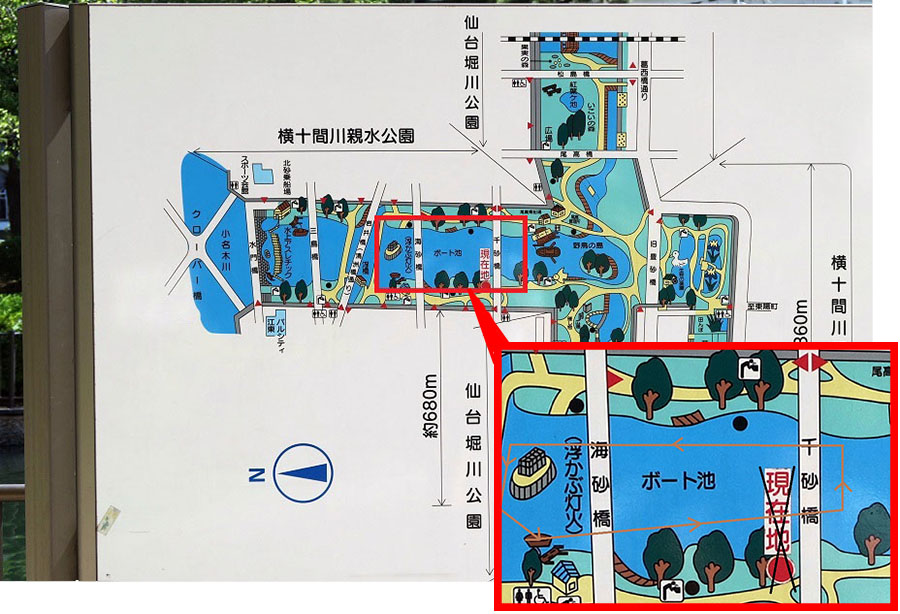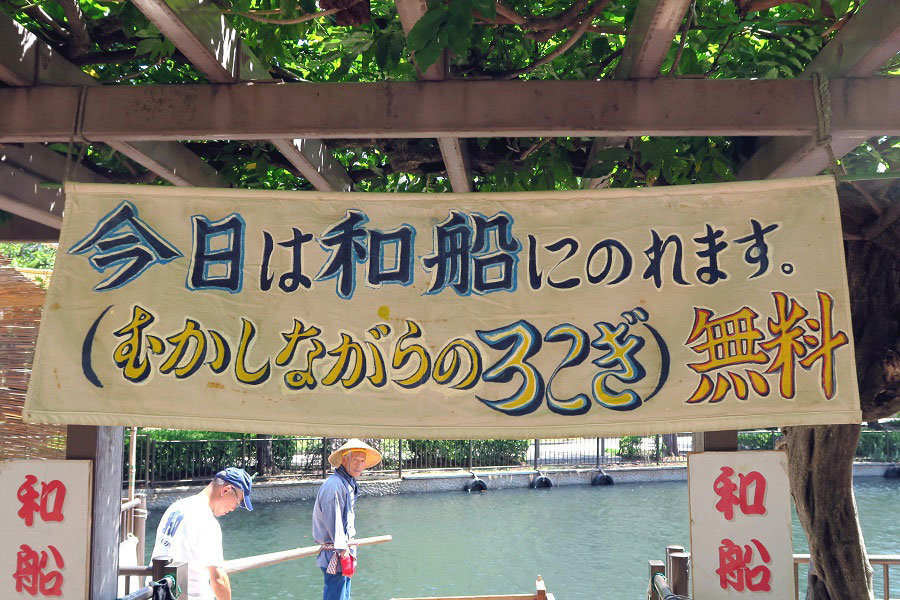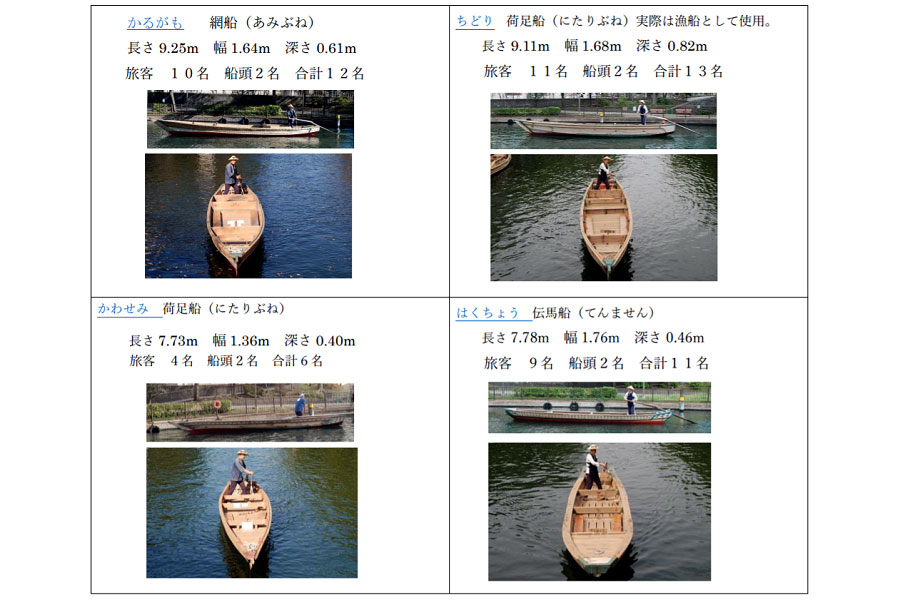ランチやディナー、バイキングも。30年の時を重ねた東京湾クルーズの現在地【両国・日の出・天王洲】
90年代頃に始まった東京湾クルーズ。ロマンティックな東京の夜景を求める恋人たちの聖地ともされてきました。クルージングの種類は水上バスで周遊するものからランチやディナー付きのプランまでさまざま。今回はエデュケーショナルライターの日野京子さんが、東京湾クルーズの現在地をご紹介します。 海に面している東京ですが、海の見えるエリアは限られています。「東京で生活をしているけど海を感じることはほとんどない」という人も多いはず。 東京には複数のクルーズ船運航会社があり、それぞれ趣の異なる内容で優雅なクルーズの時間を提供しています。運航開始はベイエリアが現在のような観光スポットになってからと思いきや、バブル経済で沸いた1990年頃と30年以上の歴史を持ちます。 今回は、東京の美しい夜景を堪能できる東京湾クルーズの世界をご紹介していきます。 恋人たちの夜を彩ってきた東京の美しい風景(画像:photoAC)●【両国・浅草エリア発】東京水辺ライン 1991年から運航をスタートした公益財団法人「東京都公園協会」が運航している「東京水辺ライン」は、水上バス運航の他、ゆっくり隅田川からベイエリアを巡る周遊プラン、ナイトクルージングが人気です。 東京屈指の観光スポットである浅草からお台場への水上バスに乗ると、隅田川を下り、勝どき橋やレインボーブリッジを通り抜け、東京湾に出て、海上から東京の風景を楽しむことができます。 屋根の上にも出られる水上バス(イメージ画像:photoAC) 完全予約制の「いちにち ゆらり旅」は、朝9:00に両国リバーサイド発着場を出発し、最長9時間かけて隅田川から岩淵、荒川、東京湾、臨海部と周遊します。ベイエリアの一日の風景をたっぷり堪能することができます。 一方、主に土曜日18:30~運航する「ナイトクルーズ 2大タワー周遊便」は、スカイツリーや東京タワー、レインボーブリッジを眺める90分のクルージング。ライトアップされた橋の下を通り抜けるなど、陸上とは一味違う東京の夜景を一望できるのが魅力です。こちらもネット予約制です。 夕暮れ時の海から東京タワーを眺める(画像:photoAC)●【浜松町・日の出】東京湾シンフォニークルーズ 観光バスで有名な「はとバス」のグループ会社の一つである株式会社シーライン東京が運航する「東京ベイ・クルージングレストラン シンフォニー」は、1989年から運航を開始したベイエリアでも最古参のレストラン・クルージング船です。 日の出桟橋から出港するクルージングは、東京湾を眺めながらランチやディナーを楽しめるだけでなく乗船のみでもOKというシンプルなショートプランも用意されており、幅広い客層から受け入れられています。 フレンチ・イタリアン・和食・バイキング・飲み放題など種類豊富なプランあり(画像:photoAC) クルージングプランは、ランチクルーズ、アフタヌーンクルーズ、サンセットクルーズ、ディナークルーズの4つの時間帯に分かれ、各クルーズとも複数の料理コースが用意されているのが特徴的。 50分のショートコースであるアフタヌーンクルーズを除くと、他のクルージングは2時間以上と東京湾をバックに、ゆっくりと食事を楽しみながら至福の時を過ごせます。 東京湾シンフォニークルーズの航路は東京ゲートブリッジをくぐり東京ディズニーランド方面に周航するオリジナル航路。上空から見るとハートの形になっているため「恋人の聖地サテライト」に選定されている(イメージ画像:photoAC)●【天王洲】ザ・クルーズクラブ東京 1990年から運航しているザ・クルーズクラブ東京の「レディ・クリスタル」は、気品あふれるクルーズシップ。専用のクラブハウスにはバーやレストラン、ラウンジがあり、ヨーロッパのリゾート地をほうふつとさせます。 ベーシックプランは土日祝限定の「ランチクルーズ」「アフタヌーンクルーズ」、平日も運航しているのは「ナイトクルーズ」と「ディナークルーズ」になります。ディナークルーズでは、ゆっくりと高層ビルやお台場、大井ふ頭の夜の風景を見ながら船内でフレンチのコース料理を堪能できます。 フリードリンクが付いた乗船のみの「ナイトクルーズ」は、平日21:15~、土日祝は20:30~と東京湾のクルーズ船の中で最も遅い時間帯に出航します。仕事が終わってからナイトクルーズをし、闇夜に輝く東京の夜景を目に焼き付けてみるのもいいですね。 美しい船でフリーフロードリンクが楽しめる「ナイトクルーズ」は陸地でのディナーの後で訪れることもできる運航時間(画像:photoAC)移り変わるベイエリアに思いをはせて 東京湾のクルーズ船はバブル期から歴史が始まり、30年以上の歴史を持つベイエリアの観光の顔の一つにもなっています。 しかし、当時の湾岸エリアにはランドマークタワーであるレインボーブリッジやフジテレビもなく、現在のようなきらびやかな夜景とはほど遠い状況でした。 湾岸エリアの開発とともに変わりゆくベイエリアの風景と共に歴史を歩むクルーズ船に乗り、時の流れを感じてみるのもいいですね。 開発とともに変わりゆくベイエリアの風景を見守ってきた桟橋(画像:photoAC)■東京水辺ライン 住所:東京都墨田区横網1-2-13 ヒューリック両国リバーセンター2F TEL:03-5608-8869(営業時間9:00~17:00 月曜日を除く) 運行時間: ・「いちにちゆらり旅」9:00~18:00(最長9時間。乗船地により時間・料金が異なる) ・ナイトクルーズ「2大タワー周遊便」18:30~20:00(土日祝のみ) アクセス:JR総武線 両国駅より徒歩3分 都営大江戸線 両国駅より徒歩6分 ※最新情報は公式サイトをご確認ください ■東京湾シンフォニークルーズ 住所:東京都港区海岸2-7-104(シーライン東京 日の出ふ頭営業所) TEL:03-3798-8101(予約センター10:00~18:00) 運行時間: ・ランチクルーズ11:50~14:00 ・アフタヌーンクルーズ15:00~15:50 ・サンセットクルーズ16:20~18:20 ・ディナークルーズ19:00~21:30 アクセス:ゆりかもめ 日の出駅より徒歩1分 JR山手線 浜松町駅より徒歩約12分 都営大江戸線 大門駅より徒歩約15分 ※最新情報は公式サイトをご確認ください ■ザ・クルーズクラブ東京 住所:東京都品川区東品川2-3-16 シーフォートスクエア1F TEL: 03-3450-4300 (受付時間10:00〜18:00) 運行時間: 【平日】 ・ディナークルーズ18:30~20:30 ・ナイトクルーズ(フリードリンク付き)21:15~22:15 【土日祝】 ・ランチクルーズ12:00〜13:40 ・アフタヌーンクルーズ(1ドリンク付)14:15〜15:00 ・ディナークルーズ17:30~19:30 ・ナイトクルーズ(フリードリンク付)20:30~21:30 アクセス:東京モノレール 天王洲アイル駅より徒歩2分 りんかい線 天王洲アイル駅より徒歩5分 ※その他プラン・最新情報は公式サイトをご確認ください
- 両国駅
- 乗り物
- 大門駅
- 天王洲アイル駅
- 日の出駅
- 浜松町駅
- 竹芝駅