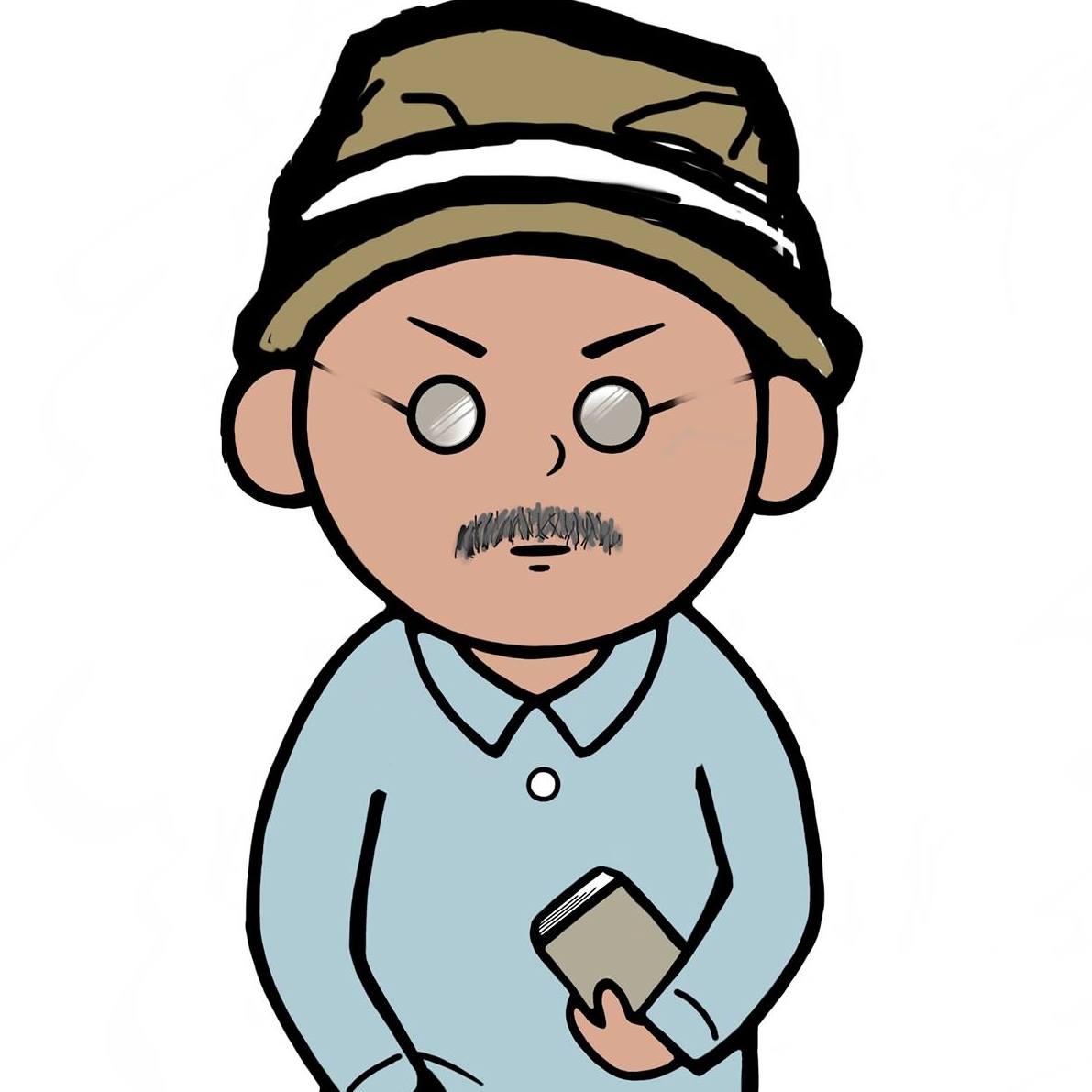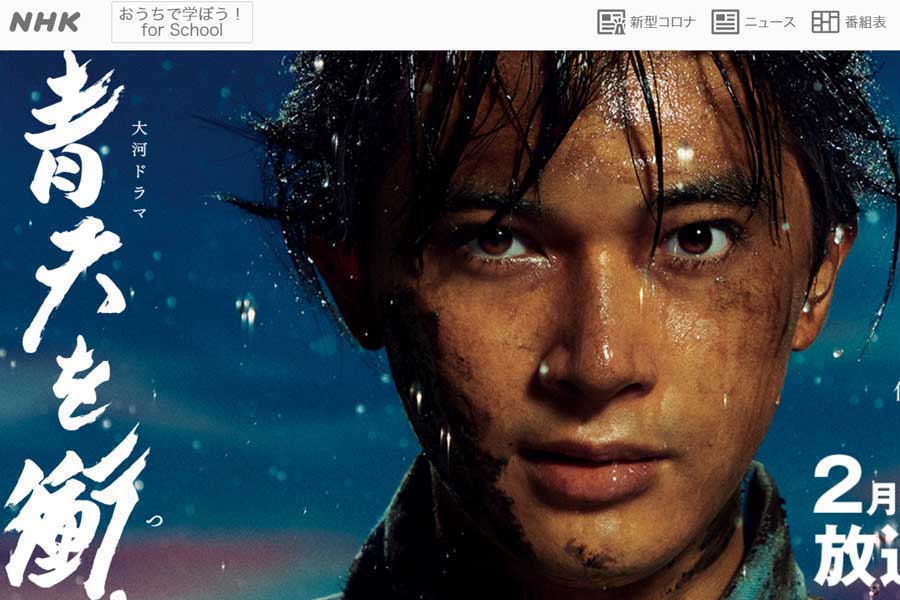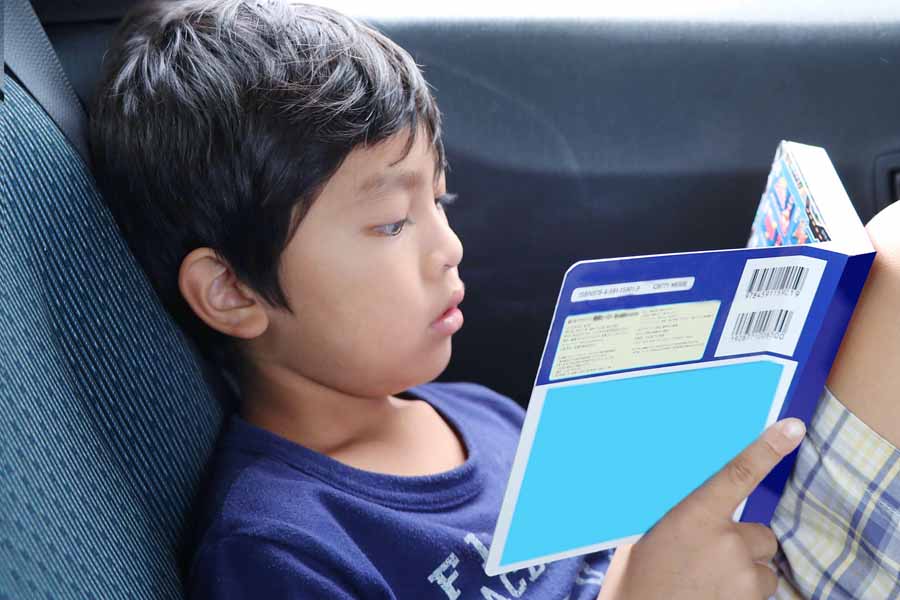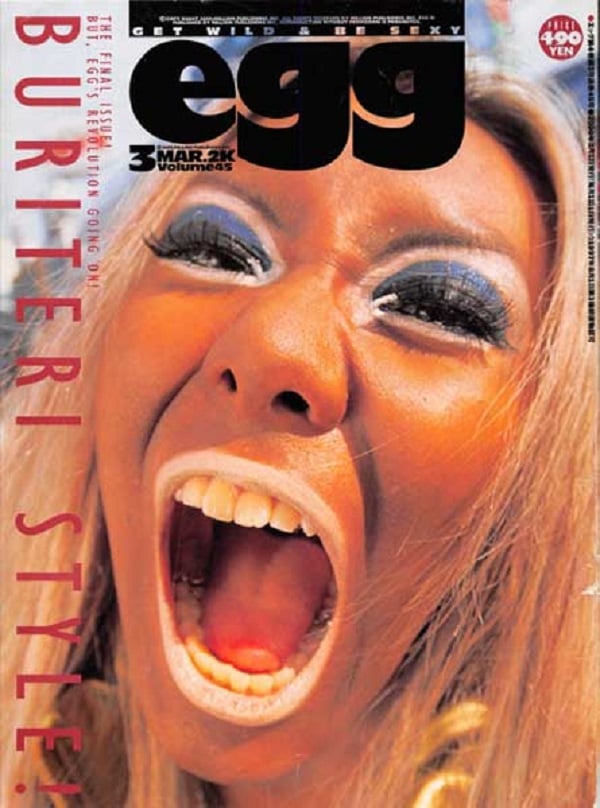難関私大のAO入試「ラッキー合格」はもはや無理? あまりにレベルの高い早慶の要求事項とは
受験方式が多様化するなか、「AO入試にラッキー合格できる」「推薦入試だから勉強しなくても大丈夫」という時代は終わりを迎えつつあります。その実情について、教育ジャーナリストの中山まち子さんが解説します。私大で主流になりつつあるAOと推薦 いまだ「大学入試 = 学力試験」というイメージは根強いですが、私立大学ではすでに過去のものとなっています。 文部科学省が2021年3月に公表した「令和2年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要」によると、2020年度の私立大学入学者のうち、なんと 「56.5%」 もの数がAO入試(学力試験を課さず、小論文や面接によって学生の合否を決める選抜制度)や推薦入試を使って入学していることが分かりました。 ちなみに2020年度からAO入試は「総合型選抜」、指定校推薦は「学校推薦型選抜」と、その名を変えています。そんな総合型選抜の願書受付解禁日は8月1日で、受付が集中するのは9月から10月まで。受験シーズンは初秋からすでに始まっており、「大学入試 = 冬」という構図も崩れ始めています。 コロナ化の影響で部活動の大会が中止となった2020年とは異なり、本年度はインターハイも行われたため、部活動での実績は格好のPR材料になります。また、都内の有名私立大学は難化傾向にあるため、総合型選抜や学校推薦型選抜を活用しない手はありません。 もはやラッキー合格はできない? しかし問題もあります。AO・推薦入試で入学した学生と、学力試験で入学した学生との間に明確な学力差があるのです。 新宿区戸塚町にある早稲田大学(画像:写真AC) この問題の是正のため、文部科学省は2020年度の「大学入学者選抜実施要項」から、AO・推薦どちらの入試でも、受験生に大学入学共通テスト(旧センター試験)、または小論文、プレゼンテーション、口頭試問、実技、各教科・科目に係るテスト、資格・検定試験の成績等を課して、学力を測ることを各大学に求めるようになったのです。 そのため、 「AO入試にラッキー合格できる」 「推薦入試だから勉強しなくても大丈夫」 とも一概に言えなくなっています。特に都内の難関私立大学では、このような一般的なイメージとは異なるほど、入試内容も条件もハードルが高くなっています。 AO入試の先駆者である慶応の取り組みAO入試の先駆者である慶応の取り組み 都内の難関私立大学の双璧をなす早稲田大学(新宿区戸塚町)と慶応義塾大学(港区三田)は、学力試験以外でも独自の入試を行っています。 港区三田にある慶応義塾大学(画像:写真AC) 日本初のAO入試を行った慶応義塾大学の総合政策学部と環境情報学部では、出願はオンラインのみとなっており、 ・志望理由や入学後の学習計画、自己アピールが記載されているPDFファイル ・3分間のプレゼンテーションビデオ を提出しなければなりません。 書類選(1次選考)をパスしなければ2次選考に進めず、一般的な私立大学の総合型選抜よりも厳格です。 1次選考は免除されることもありますが、その条件は ・日本数学オリンピック(国際数学オリンピックに派遣する学生の選考会)予選Aランク者 ・福澤諭吉記念全国高等学校弁論大会 最優秀賞受賞者 など、ハードルはまったく低くありません。 しかし、学力入試が主流だった日本の大学入試に新たな道を作ったパイオニア学部とあって、2021年度入試(夏秋AO入試)では150人の募集人員に対し、 ・総合政策学部:1332人 ・環境情報学部:1216人 が志願しました。最終合格者は両学部ともに120人程度で、突破するのは困難です。 理工学部でも同様に行っていますが、募集人員は若干名。こちらも二段階選抜を実施しています。出願資格は、 ・評定4.1以上 ・国際数学、物理、化学オリンピックなどの世界規模のコンテストへの出場 など、出願できる受験生は限られています。ちなみに2021年度は7人が出願し、合格者は3人でした。 合格者ゼロ・志願者ゼロの入試もある早稲田合格者ゼロ・志願者ゼロの入試もある早稲田 早稲田大学でも一部の入試を除くと二段階選抜が主流となっています。慶応義塾大学と同じように、入試は各学部の独自基準で行われますが、複数学部が合同で行うものもあります。 法学部を含む6学部(商学部・文化構想学部・文学部・人間科学部・スポーツ学部)で行われる新思考入試は9月中旬に出願がスタート。最終合格が発表されるのが翌年の2月中旬と長期間に及びます。なお新思考入試とは 「すべての都道府県からの受け入れを目標とし、入学後は所属学部の学びに加え「地域への貢献」をテーマとした全学共通の活動を行うことで、当入試出願に至った志を入学後の学びにつなげる「高大接続」型の入試制度」(早稲田大学のウェブサイトより) です。 書類審査(1次選考)を突破し、11月に大学で行われる2次選考をパスしても、その後、各学部が定める大学入学共通テストの科目を受験し、そこで合否判定が行われます。 2021年度入試では、6学部ともに募集人員が「若干名」ということもあり、志願者は文化構想学部の102人が最多でした。なお文学部と人間科学部では最終合格者ゼロと、かなり厳しい判断を下しています。 受験生のイメージ(画像:写真AC) このほかにも、先進理工学部の特別選抜入学試験では応募資格要件として、 ・日本数学オリンピック予選合格(Aランク) ・日本学生科学賞入賞 など、七つの要件のうちひとつでもクリアしていないと出願できません。そのため、2021年度は志願者ゼロという衝撃的な結果となっています。 早慶の壁はAOでも高い早慶の壁はAOでも高い 両校ともに理系学部の独自入試は要件が高いこともあり、志願者は多くはありません。その背景には、両大学を狙える学生は難関国立大学を本命視していることも少なからず影響しているでしょう。 受験生のイメージ(画像:写真AC) 早慶ともに二段階選抜を導入しており、書類選考通過はとてもハードルが高くなっています。早稲田大学の新思考入試のように、合格者ゼロという結果もあり得ます。 大学入試は学力試験、総合型選抜、学校推薦型選抜の3本柱の時代に突入しています。これまでの常識は通用せず、受験生にとっては楽な状況ではありません。
- ライフ