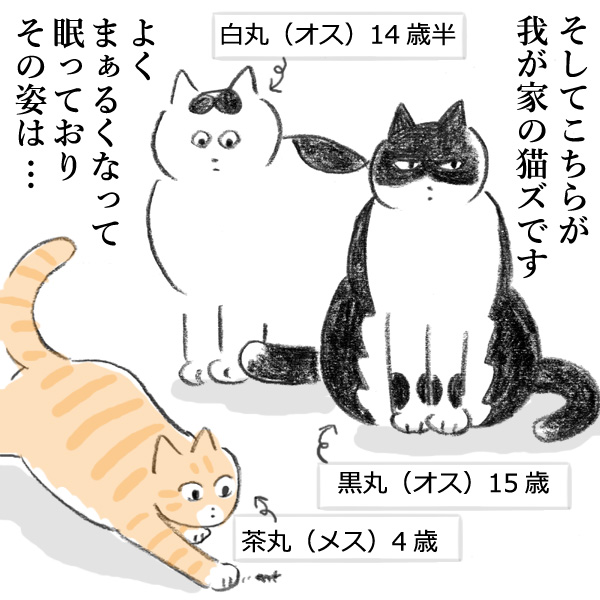とんねるず『やぶさかでない』――成増から成りあがった石橋貴明のロックアンセム 板橋区【連載】ベストヒット23区(12)
特異なイメージに乏しい区だが……「ベストヒット23区」を追っていくこの連載も、今回で早くも12区目の折り返しの回。そんな記念すべき(?)回に、板橋区はぴったりだと思うのです。 下町(代表:足立区)と山の手(世田谷区)という縦軸、メジャー(千代田区)とマイナー(北区。失礼)という横軸を組み合わせたポジショニングマップがあるとすれば、板橋区は、ほぼ中央に位置しそうな感じ。 この連載も、マップの中央にある板橋区で折り返して、再度、マップの四隅を攻めていくのがいいと思っているのですが。 逆に言えば、特異なイメージに乏しいのが板橋区なのです。それでも、私 = 「ベストヒット23区ライター」の手にかかると、板橋区の地図からメロディーが聞こえてきます。今回は区の北東にある東武東上線の駅名から聞こえてきました。 とんねるず・石橋貴明の出身地だった「成増」=「なります」――。 成増駅北口の様子(画像:写真AC) 1985(昭和60)年に発売された、とんねるずのファーストアルバム『成増』。正式名称は『成増/とんねるず1番』と威勢がいい。レコード会社はビクター。 『成増』というアルバムタイトルは、石橋貴明の出身地から取られています。そう、石橋氏は板橋区成増の出身なのです。私はこのアルバムをLPで持っているのですが、針を落として、いきなり聞こえてくる、若きとんねるずふたりのタンカにしびれます。 幼少期に苦労していた石橋幼少期に苦労していた石橋――「ダビングすんじゃねえよ!」 1985年頃は、まだレンタルレコード店がにぎわっていて、レコードを買わずに借りて、カセットテープにダビングして聴く若者が多かったのですが、それを制する一言です。 手元にあった1988年発売の本 = 『とんねるず 大志』(ニッポン放送出版)によれば、石橋貴明は、かなり苦労した生い立ちだったようです。 お父さんは、板橋区小豆沢(あずさわ)で大きな工場を営んでいて、つまりはお坊ちゃんだったのですが、小1のころ、その会社 = 「石橋化成」が倒産し、成増の六畳一間風呂無しアパートに、家族で引っ越したといいます。 風呂無しアパートのイメージ(画像:写真AC) 大阪のテレビ好き少年だった私が、とんねるずの前身である「貴明&憲武」を初めて見たのは日本テレビ系『TVジョッキー』。「とんねるず」と改名して、同じく日本テレビ系『お笑いスター誕生』で10週勝ち抜き、グランプリを獲得した頃には、その、いかにも東京のテレビ好き少年ふたり組のとりこになってしまいました。 B&Bやおぼん・こぼん、ギャグ・シンセサイザー(懐かしい)など、先にグランプリを獲得したコンビと比べて、あきらかにセミプロなのに、グランプリまでたどり着いてしまう。あの頃の石橋貴明のパワーは、少年時代の屈折の反動だったのかも知れません。 先の『とんねるず 大志』には、他にも、なかなかに興味深いエピソードがいろいろと書かれています。最高なのは「とんねるず」の命名エピソード。名付け親は、日本テレビの歴史、いや「日本のテレビの歴史」を代表する重鎮にして顔役、泣く子も黙る井原高忠(いはら・たかただ)。 とんねるずの名前の由来とんねるずの名前の由来――「貴明君のTと憲武君のNからとりました。ひとつは“とんまとのろま”。もうひとつは“とんねるず”。さあ、どっちがいいでザーマスか」 いやぁ、「とんまとのろま」が選ばれていたら、それこそ「日本のテレビの歴史」はどう変わったのだろうと妄想します。 もうひとつ、とんねるずが秋元康と運命の初対面をしたときに、秋元が「キミたち、つかこうへい好きでしょう?」というシーンも最高です(ふたりとも「つかこうへいのつの字すら知らな」かったというオチがつくのですが)。 とんねるずのファーストアルバム『成増』から1曲選ぶとすれば、やはり『一気!』ということになります。 1984(昭和59)年12月の発売。11万枚のスマッシュヒット。ですが、今回は時代を少しずらして、1986年5月発売の『やぶさかでない』を「ベストヒット板橋区」に認定したいと思います。 1985年3月に発売された、とんねるずのファーストアルバム『成増』(画像:ビクターエンタテインメント) レコード会社はキャニオン(現ポニーキャニオン)。アルバム『成増』やシングル『一気!』『雨の西麻布』などがビクターで、この『やぶさかでない』からキャニオンに移籍しました。 この移籍によって、「とんねるず × 秋元康 × ポニーキャニオン」という黄金トライアングルが完成、1992年『ガラガラヘビがやってくる』の140万枚というメガヒットにつながっていくのですが。 板橋から全国区に成りあがった石橋板橋から全国区に成りあがった石橋 そういうムーブメントの導火線がこの『やぶさかでない』。このタイトルからして若き秋元康の面目躍如。軽妙なロックンロールに乗って、若きとんねるずが、パロディー精神あふれた秋元ワールド全開の歌詞をほえまくります。 とんねるずが主演したTBS系ドラマ『お坊っチャマにはわかるまい!』の主題歌。このドラマタイトルが、「お坊っチャマ」からつまずいて、板橋区の六畳一間から成りあがって来た石橋貴明のあり方を、見事に象徴しています。 結成40周年を迎えるお笑いコンビ・とんねるず(画像:AWA) ビクターからキャニオンに移り、木梨憲武と秋元康の手を借りながら、いよいよ全国区に成りあがっていく石橋貴明のロックンロール・アンセムが、この『やぶさかでない』に成増、いや、なります。
- 未分類