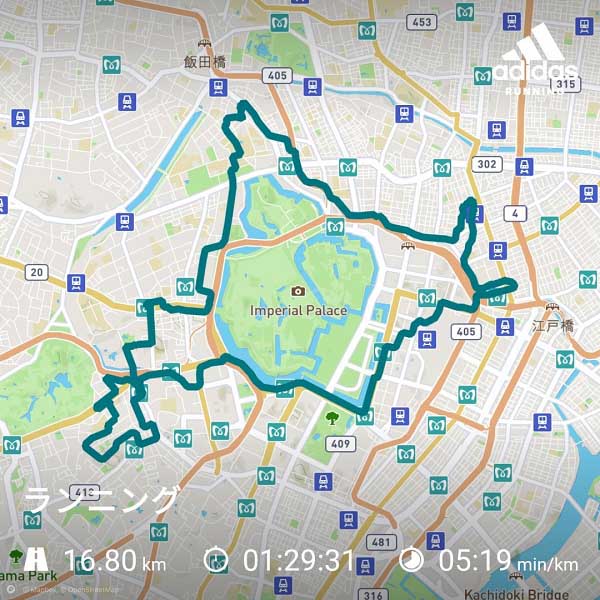牛丼チェーンから浮かび上がる「地域性」――下町の吉野家、山の手の松屋、ハマのすき家
多様な業態を持つ「松屋」 筆者(増淵敏之。法政大学大学院教授)の自宅近所に最近、牛丼大手の松屋フーズホールディングス(武蔵野市中町)が運営するすし店「すし松」と中華料理店「松軒中華食堂」が同時に開店しました。 とんかつ店「松乃家」と「松屋」はすでにあるため、同社の拠点地区になったような趣があります。もはや牛丼のみではない、多様な業態を持つ飲食店になりました。長きに渡ってお世話になってきた愛好者としては、少々複雑な心境です。 牛丼のイメージ(画像:写真AC) 牛丼でまず頭に浮かぶのは吉野家です。吉野家は1899(明治32)年に日本橋で創業。その後、1926(大正15)年に築地へ移転し、この場所が1号店となっていましたが。しかし、2018年に築地市場の豊洲移転に伴い閉鎖されました。近年ではメニューの多様化が進んでいるものの、いまだ牛丼主体のイメージが強いです。 しかし、吉野家はあくまでも吉野家ホールディングス(中央区日本橋箱崎町)の子会社。同ホールディングスでは「京樽」「海鮮三崎港」「すし三崎丸」の京樽、「はなまるうどん」のはなまる、「ステーキのどん」「フォルクス」のアークミールなどを傘下に収めています。2017年2月期の売り上げは連結で1886億2300円。下町を本拠地にした外食大手企業といえます。 さて松屋はというと1961(昭和36)年に東京都練馬区羽沢の住宅地に中華飯店「松屋」を開店、この店は1969(昭和44)年に閉店していますが、それに先立つ1968年に江古田に牛丼(松屋では牛めしと呼ぶ)、焼肉定食店としての「松屋」を開店させています。これが「松屋」の 1号店です。この店は現在も営業を行っており、吉野家に比べると牛丼以外のカレーライスや定食ものなどの比率が高いといわれています。 吉野家は1号店も本社も下町吉野家は1号店も本社も下町 その理由は、1号店が開店した江古田に日本大学芸術学部や武蔵大学、武蔵野音楽大学があり、昼間は学生で賑わうためです。またベッドタウンでもあることから、夜は独身サラリーマンが帰宅するという地域特性を考慮した結果といわれています。学生には牛丼、サラリーマン向けにはカレーライスや定食が必要と考えたのでしょう。それで現在のメニュー、牛丼、カレーライス、定食という3本柱での構成になったとのこと。 松屋 江古田店の外観(画像:(C)Google) 松屋 江古田店(練馬区栄町)に行くと店内にしっかり「1号店」の張り紙や開店時の写真などが掲示されています。一見、何の変哲もない松屋の既存店という風情ですが、感慨深いところもあります。松屋はここから始まったわけです。現在、松屋フーズも松屋フーズホールディングスとなり、2018年3月期では連結売り上げは930億608万円になっており、こちらも外食大手と呼べる規模でしょう。 かつて松屋が江古田店のみのとき、創業者が吉野家のファンでスタッフと顔見知りになった際、肉などの食材卸を共有していた時期があるとのこと。その頃は吉野家も築地店のみで、そこから牛丼の時代が到来したのです。不思議な縁を持つ吉野家と松屋ですが、それぞれに独自の味を追求してきたからこそ、現在があるのではないでしょうか。 松屋は2006(平成18)年、それまで本社を構えていた練馬区下石神井から武蔵野市中町に移転、三鷹駅前に本拠地を移しました。吉野家が牛丼以外の業態をM&A(合併・買収)で拡張していったのに対し、松屋はM&Aにあまり積極的ではなく、直営という形で業態を広げています。 吉野家は1号店も本社も下町にあり、松屋は同じく山の手にあります。かつて評論家の川本三郎が『東京おもひで草』(1997年)で、以下のように述べています。 「東京は、下町と山の手というまったく違ったふたつの場所によって作られている。それはパリにもニューヨークにもなかった東京の特色だ。ふたつの場所の対立によって、都市としての深み、陰影を増していく」 下町は江戸時代以降の老舗も数多く点在し、山の手は下町に比べると新興の名店が多いということになるのでしょうか。吉野家は牛丼に拘り続ける老舗といったイメージがしますし、松屋は新興ならではのフレキシビリティに富んだイメージがするのです。「地域性」と言ったらよいでしょうか。 ゼンショーホールディングスは「枠外」ゼンショーホールディングスは「枠外」 更に新興のすき家はゼンショーホールディングス(港区港南)が経営していますが、すでに47都道府県全てに店舗があり、日本国内店舗数最多の1930店舗(2019年6月現在)を展開しています。売りは牛丼とカレーライスです。 ゼンショーホールディングスの売り上げは、2018年3月期の連結で5791億800万円と圧倒的。現在の本社は港区港南にありますが、創業時は横浜市鶴見区でした。弁当屋からのスタート、1982(昭和57)年のことでした。同年、同区内にある生麦駅前にすき家1号店が開店。本社はその後、横浜市神奈川区、西区へと移転します。 同社は「なか卯」「ココス」「ジョリーパスタ」「はま寿司」「華屋与兵衛」を傘下に収めるなど、M&Aを積極的です。海外展開に関しても吉野家、松屋に比べて積極展開の姿勢を維持しています。 すき家は下町や山の手ではなく、横浜のイメージでしょう。1980年以降の新興企業ならではのダイナミズムを体現しているように思います。古い慣習に縛られない自由な展開とでもいいましょうか。下町vs山の手の二項対立から外れた、「枠外」の企業といえます。 このように牛丼チェーンから見える地域性を考えながら、各店に赴くのも面白いかもしれません。
- ライフ