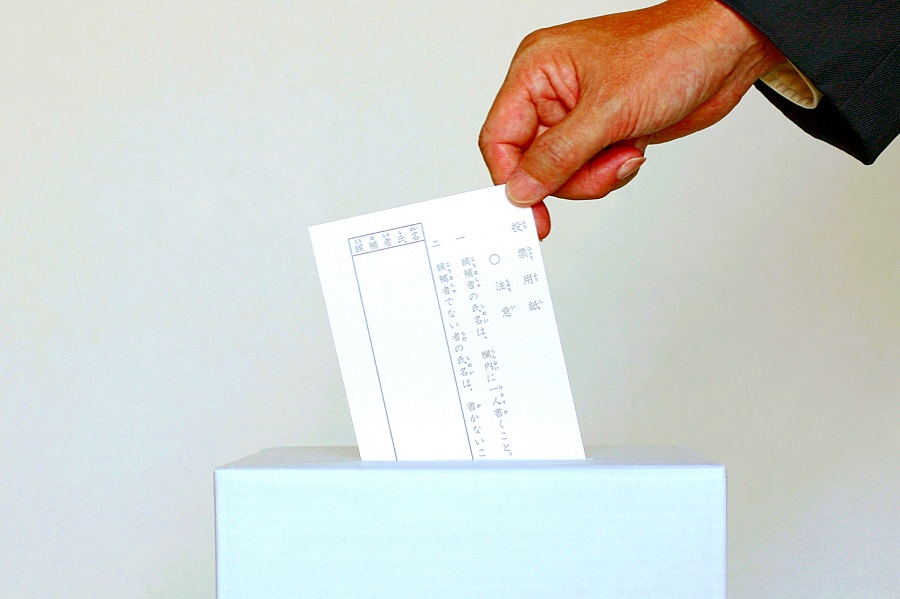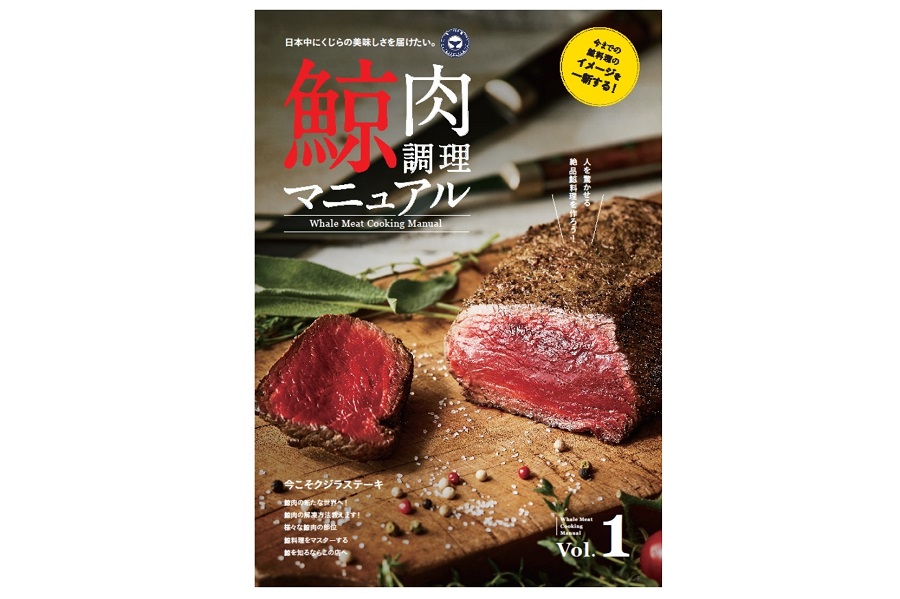慶応にあって、早稲田と上智にない「医学部」 いったいなぜ?
早稲田、慶応、上智の間に横たわる決定的な差 早稲田大学(新宿区戸塚町)と慶応義塾大学(港区三田)、そして上智大学(千代田区紀尾井町)は難関の私立総合大学として、広く知られています。 しかしこれらの大学は、「医学部の有無」という点で大きな違いがあります。医学部があるのは慶応義塾大学のみ。設立は1917(大正6)年と、100年以上の歴史があります。 新宿区信濃町にある慶応義塾大学医学部・医学研究科の外観(画像:(C)Google) なぜ、早稲田大学と上智大学には医学部がないのでしょうか。今回は、慶応義塾大学に医学部がある背景と医学部設置の難しさを探っていきます。 日本の近代医学の発展とともに歩んだ歴史 慶応義塾大学の創立者は福澤諭吉で、緒方洪庵(こうあん)の私塾で学んでいました。緒方洪庵は蘭(らん)学者であり、また医師でした。師が医師だったことを踏まえると、福澤は医学の知識に触れる機会があったと考えられます。 実際に1873(明治6)年、福澤は自身が開いた蘭学塾・慶応義塾に一度、慶応義塾医学所を開設しましたが、財政難で1880年に閉鎖しています。慶応義塾はその後、1890(明治23)年、文学・理財・法律の三科で大学部が開設されました。 医学からいったん距離を置いた福澤ですが、ドイツ留学から帰国した医学者・北里柴三郎を受け入れる機関がないことを知り、北里のために私財を投げうち、1892(明治25)年に私立伝染病研究所(現在の東京大学医科学研究所の前身)を設立しました。 同研究所は1914(大正3)年、時の政府によって内務省管轄から文部省へと移行。それとともに、東京帝国大学に合併されることになり、これを不服とした北里柴三郎たちは職を辞することになりました。当時の内閣総理大臣が大隈重信(早稲田大学の創設者)だったのは、何とも言えない縁を感じます。 そして慶応義塾の大学部に医学科新設の声が上がります。1916年に認可が下り、翌1917年に医学科が新設。福澤への恩返しとばかりに、北里柴三郎が初代医学部長に就任しました。1920年に慶応義塾は大学令によって旧制大学となり、文学部・経済学部・法学部とともに医学部が設置されました。 1909(明治42)年に測図された、現在の慶応義塾大学病院がある場所。かつては陸軍用地だった(画像:時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕) このように、慶応義塾大学医学部は日本の近代医学の歩みと重なり、非常に歴史ある学部なのです。 1970年代にあった医学部ラッシュ1970年代にあった医学部ラッシュ 一方、早稲田大学(1902年に大学部と専門部を新設し、東京専門学校から改称)では1906(明治39)年、大隈重信が会長を務めてい東亜同仁会(アジア地域の医療と伝染病予防に貢献する民間組織)が大学敷地内に東京同仁医薬学校を立ち上げたものの、こちらも慶応義塾医学所と同様、経営難で閉校しています。 時はたち、1970年代は医師不足や大学進学率の上昇により、医学部の新設が相次ぎました。しかし早稲田大学は、医学部設置までに至りませんでした。 早稲田大学の外観(画像:写真AC) 1970年代は首都圏や大都市圏だけでなく、地方各地でも医学部設立のラッシュはありましたが、1979(昭和54)年の琉球大学(沖縄県西原町)以降は長きにわたって新設は行われていません。しかし近年、状況は変化しています。 2010年代に入り、東日本大震災で地域医療が壊滅的になった東北の復興支援も兼ねて、東北薬科大学(現・東北医科薬科大学。宮城県仙台市)は2016年4月、医学部を新設。また2017年には、国際医療福祉大学(栃木県大田原市)が成田キャンパスに医学部を新設しました。 医学部新設のハードルは極めて高いことに変わりありませんが、両大学は薬科や医療系に特化した大学だったことから、新設という難題をクリアするに至ったと考えられます。そのことからも、これらのような専門学部がない大学が医学部を作るのは、極めて困難な道だと言えます。 聖マリアンナ医科大学と提携する上智大 上智大学は、神学部など文系学部を主体とした大学としてスタート。そのため、理工学部の開設も1962(昭和37)年と、医学部と距離をおいた運営を行ってきました。 上智大学の外観(画像:(C)Google) しかし2010年代に入り、医療系学科を合併したり医科大学と提携したりするなど活発な動きをみせています。2011年、カトリック系の聖母大学(2014年閉校)などを運営する学校法人聖母学園を吸収合併し、総合人間科学部に看護学科を開設しています。 また、2014年には聖マリアンナ医科大学(川崎市)と大学間交流の包括協定を締結するなど、医学部とのつながりを強化しています。一連の流れから、上智大学も医学部新設に興味を示しているのは明らかです。 東京都内での施設増幅や付属病院の敷地取得は難しい東京都内での施設増幅や付属病院の敷地取得は難しい しかし、総合大学が医学部を新設するのは国からの認可もさることながら、学生を教える力量のある教職員をそろえたり、施設を整備したりする必要があります。安易に「新設したい」と声を上げても、実現するのは不可能に近いのです。 上智大学の看護学科の学生は聖マリアンナ医科大学の講義を受けたり、同大学の付属病院で実習したりするなど、現段階でできる最大限のことは交流なのでしょう。 聖マリアンナ医科大学の外観(画像:(C)Google) また昨今、地方と都心との医療格差も叫ばれているため、上智大学や早稲田大学は都内に施設や付属病院を作るのが難しくなっています。医学部を新設するのであれば、地方に作って「地域のために医療貢献する」という大義名分を打ち出すことが必要です。 どちらも本部は都心にありますが、充実した施設や付属病院には広大な敷地が必要です。学生が集まり、地域経済が潤い、土地の確保に悩まないで済む場所を念頭に置かないと、医学部新設の悲願はかなえられないのです。
- ライフ