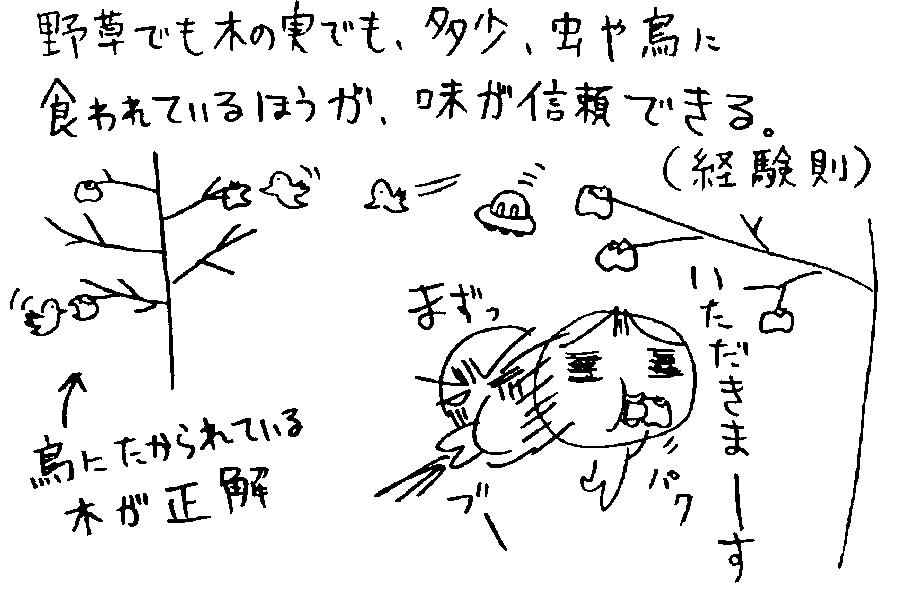瑛人や「きゅんです」…… 2020年に無名アーティストが次々ヒットを飛ばした理由
音楽ヒットは「東京発」からSNS発へ 2020年は、音楽のヒットの出どころが大きく変わった1年でした。 アーティストの所属事務所やレコード会社による公式プロモーション、あるいは渋谷や新宿にあるCDショップによる店頭セールスなど、あくまで東京を中心とする“中央集権”体制が常識だった音楽シーンのヒット構造。 しかし近年SNSによる影響力が徐々に高まり、いよいよ決定的となったのが2020年だったと言えるでしょう。 楽曲「香水」が大ヒット。公式YouTubeチャンネルで「ビデオブログ(Vlog)」を配信するなど、ネット上での発信も多い瑛人(画像:AlphaBoat合同会社) 瑛人、yama、りりあ。、ひらめ、オレンジスパイニクラブなどの名前を目に(あるいは耳に)したことがある人も多いのではないでしょうか。上に挙げた名前は、2020年TikTokを通じて楽曲をヒットさせたアーティストです。 TikTokとは、15秒の動画を音楽とともに投稿できるサービス。2016年にリリースされたあと、2018年に中高生を中心に盛り上がりを見せました。 始めはダンス動画などが多く、ノリのいい音楽が使用されることが多かったですが、2019年頃から異なる潮流も見られました。2020年になると、TikTokで人気を得た楽曲がストリーミングやbillboardのチャート上位にランクインされるほど、TikTokは音楽界にも影響力のあるプラットフォームに変貌を遂げます。 瑛人の「香水」はそれを象徴する最たる例でしょう。 アコギと歌詞が高める「共感度」の強みアコギと歌詞が高める「共感度」の強み 2019年4月にリリースされた「香水」は、そのおよそ1年後からTikTokでの使用や動画サイトでの「歌ってみた」コンテンツが増加しました。2020年5月にはbillboard JAPAN Hot 100で34位にランクイン。翌週には5位まで浮上し、TikTokユーザーだけでなく多くの人々に浸透しました。 「香水」のサビは15秒きっかりでTikTokの動画の長さと相性がよく、そのコンパクトさは人気になった理由のひとつと考えられています。また、アコースティックギターと歌といったシンプルな編成は、TikTokから人気になる楽曲の多くに見られる特徴でもあります。 「香水」やひらめの「ポケットからきゅんです!」など、アコースティック編成の楽曲は弾き語りカバーもしやすく、歌ってみた動画にしやすいためさらに人気が拡大しました。 「TikTok CREATOR'S LAB. 2020 -REFLECTIONS-」で、TikTok流行語2020大賞が「#きゅんです」に決定。写真中央が受賞した、ひらめ(画像:SANGPIL PARK、Bytedance) TikTokで多く利用されることにより人気になった楽曲は、歌詞にも共通点があります。 「香水」は元恋人との再開を歌う曲で、多感な若者を中心に共鳴しやすいでしょう。りりあ。の「浮気されたけどまだ好きって曲。」では心情の説明が細かくされている半面、特定の人物像が描かれないため、聴き手が自由に自分ごととして解釈しやすくなっています。 誰もが自分の出来事としてカバーしたり、感情移入したりすることができるのです。 アーティストではなく曲単位で売れる理由アーティストではなく曲単位で売れる理由 歌詞を自分のものとして消化できることは、楽曲が主にならないゆえに、ユーザー自身が楽曲を使用して数十秒の動画を作成するTikTokと非常に相性がよいでしょう。 LINEやインスタといったSNSの名前などが歌詞に使われていることも、より身近に感じる要因です。TikTokで見つけた楽曲を自分の動画のBGMに使うという、TikTokユーザーの行動の特性上からも、親しみやすい楽曲であることがTikTokからのヒットの傾向だと言えるでしょう。 このような特徴を備えているなどTikTokに最適化された楽曲は、無名の歌手の旧譜でも一瞬にして注目を浴びることができる時代なのです。 TikTokでの楽曲のヒットは、基本的にアーティストではなく曲単位で生まれます。 若い世代を中心に欠かせないプラットフォームに成長したTikTok(画像:Bytedance) アーティストの思考や方向性よりも、楽曲の雰囲気や内容にリスナーが即時的に飛びつくことで素早い広がりを見せ、プラットフォームを越えた人気を獲得しているのです。 楽曲単位で人気を獲得できるTikTokは、さまざまなアーティストの楽曲が混在するプレイリストの存在感が大きい音楽ストリーミングと相性がいいとも言えるでしょう。 楽曲が動画に使用され、その動画がバズること、また影響力のあるプレイリストに組み込まれることなどがきっかけでヒットになるということは、リスナーが楽曲に及ぼす影響が大きくなっているということでもあります。 コロナ禍で強固に結びついた音楽と映像コロナ禍で強固に結びついた音楽と映像 プレイリストを作るのはアーティストの公式プロモーションの一環ではないことも多いですし、TikTokなどで利用されるのもアーティストからすると全くの偶然であることが多々あるからです。リスナーはもはや、単なる受け手ではないのです。 音楽のヒットに直接的な影響力を持つようになったリスナー。2020年はその象徴的な年とも言える(画像:写真AC) 2020年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で音楽ライブが配信に移行する風潮があったなど、音楽と映像の結びつきがより強固になる動きがあった年となりました。 楽曲の作者ではないユーザーが作る動画と音楽の結びつきがこれからどのようなヒットを生みだし、どんな化学反応を見せるのか。あるいは、楽曲そのものの意味の重要性はユーザーによる消費に阻害されないのか。 いずれにせよ、しばらくTikTokや動画プラットフォームの存在感は大きくなり続けるでしょう。その動向に2021年も目が離せません。
- ライフ