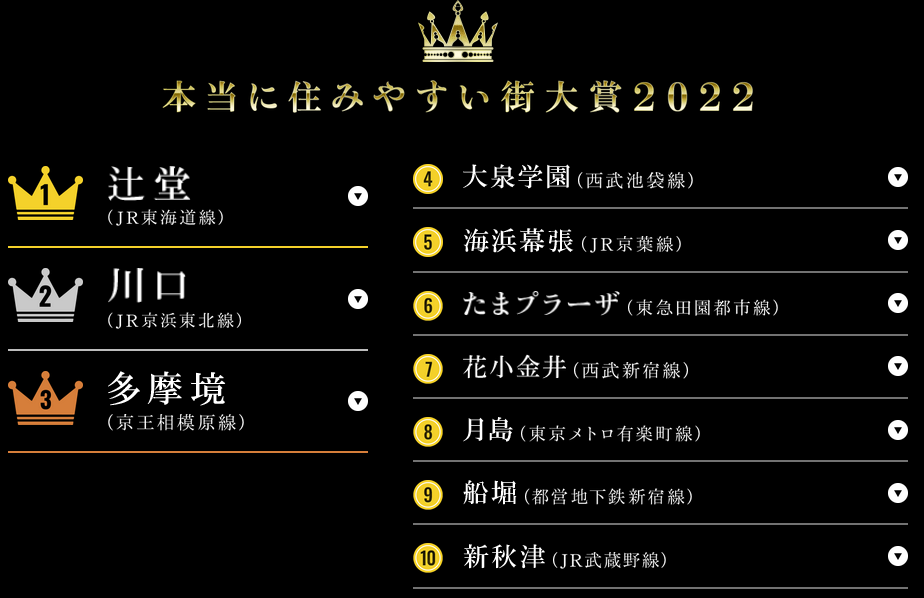景色と一体になる穴場カフェも!梅の花咲く公園さんぽ【お花見(2)】
春には大勢の花見客でにぎわう桜の名所。桜開花前の2月頃に、梅の花が見事に咲き誇り、実は穴場スポットだった! という場所があります。見事な桜も楽しみですが、人混みに流されることなく自分のペースでお花見できるって、ぜいたくですよね。今回は公園をおさんぽしながら春の東京を満喫できる、すてきなスポットをご紹介します。青空のもと「梅見ウォーキング」でリフレッシュ! 立春の頃、春を告げる梅の開花を目にすると、春が近づいているとうれしくなりますよね。少し先の桜の開花も待ち遠しいものですが、にぎやかな桜のシーズンとは違い、梅のシーズンは落ち着いてお花見ができます。 都内には多くの桜の名所がありますが、実は桜の前に梅も楽しめる箇所も多いことをご存じでしたか? この記事では、桜の名所としては知られているものの、梅の名所としてはあまり知られていない穴場スポットを2ヵ所ご紹介。どちらも美しく整備されているので「梅見ウォーキング」にぴったり! スカイツリーと梅のコラボを楽しんだり、青空に映える紅梅の梅の写真を撮ったりして、リフレッシュしてみてはいかがでしょうか? スカイツリー×梅の構図は現代の浮世絵のよう。東京を象徴している感たっぷりです(イメージ画像:photoAC) 8代将軍・徳川吉宗が造った桜の名所「隅田公園」。浅草駅からも近く、隅田川の両岸約1kmにわたって桜並木が続く桜の名所です。実はこの「隅田公園」には「梅めぐり散歩道」という梅の名所もあります。すでに開花が始まっており、これからの季節、紅白の梅やしだれ梅などを楽しむことができます。 場所は、浅草駅から待乳山聖天や今戸神社方面に7分ほど歩いた言問橋付近に位置しています。 メジロと梅のツーショット写真が撮れるかも(イメージ画像:photoAC) 梅の木には種類がわかるように名前と写真付きのラベルが設置されているので、ちょっと梅に詳しくなれそう。整備された散歩道からはスカイツリーがよく見えます。東京ならではの風景を独り占めにしているようで、なんだかぜいたくな気分に。 「梅めぐり散歩道」の見ごろは2月上旬~下旬頃。すでに開花し始めています。言問橋の手前には大きな窓が開放的なリバーサイドカフェ「Cafe W.E(カフェ ウィ)」も。あんこバターやハンバーグなど種類豊富なホットサンドやピザなどのお食事メニュー、ホットケーキにパフェといったスイーツ、アルコール類までメニューが豊富です。 花見ついでに浅草の甘味処で和スイーツをいただくもよし、そのまま今戸神社の福猫に会いに行くもよし。仕事帰りにちょっと立ち寄ってみるのも気分転換によさそうですね。 隅田公園は犬の同伴もOK!(画像:photoAC)>>関連記事:「昼休みに水辺でまったり」は効果アリ。居心地が良くなる隅田川、将来はこう変わる 東京都世田谷区にある都内屈指の広さを誇る砧公園。こちらも桜の名所として人気があります。砧公園内には2ヵ所の梅林があり、早咲きの梅は2月の中旬頃から咲きはじめます。澄み切った凛とした空気の中、けなげに咲く花とほのかな香りに癒やされます。 丸い花びらが可憐な梅の花。ちなみに白梅の方が香りが強いのだそう(イメージ画像:photoAC) 1960年代まではゴルフ場だったという砧公園。バードサンクチュアリなどの自然スポットやサイクリングコース、園内を流れる多摩川の支流、谷戸川にかかる吊り橋など、都内にいることを忘れてしまいそうな風景です。 アスレチック広場近くの梅林とファミリーパーク内の梅林は離れた位置にあるので、公園内をゆったりと散策しながら向かうと良いでしょう。 休憩するなら、公園の一角にある世田谷美術館のカフェ「SeTaBi Café (セタビカフェ)」でコーヒーブレイク。デザートガレットや期間限定のソフトクリームが人気です。 3月下旬~4月に行われる桜まつりの頃には、広大な敷地が多くの人でにぎわう(画像:photoAC)梅の花から元気をもらおう! 寒波再来のニュースなどを聞くと気持ちが落ち込むこともありますが、厳寒のなか梅が開花している様子を見ると、なんだか元気や勇気がわいてきます。家から一歩踏み出して「梅見ウォーキング」に出かけませんか? ストレッチして歩き始めると、身体も気持ちもポカポカあたたかくなってきますよ。人混みに邪魔されない今の季節のお花見ウォーキング、おすすめです。 小さな梅の花の強さとたおやかさを愛でて、この冬の時期を乗り切りましょう! なまった身体を戻すにもウォーキングは最適!(イメージ画像:photoAC)■隅田公園「梅めぐり散歩道」 住所:東京都台東区浅草7 TEL:03-3625-5495(隅田公園) アクセス:東武伊勢崎線・東京メトロ銀座線・都営浅草線 浅草駅より徒歩約7分 ■Cafe W.E 住所:東京都台東区花川戸1-1-30 隅田公園内 TEL:03-5830-3687 営業時間:9:00~20:00(L.O 20:00) アクセス:東武伊勢崎線・東京メトロ銀座線・都営浅草線 浅草駅より徒歩5分 ■砧公園 住所:東京都世田谷区砧公園1-1 TEL:03-3700-0414(砧公園サービスセンター) アクセス:東急田園都市線 用賀駅から徒歩20分 小田急線 千歳船橋駅より東急バス・田園調布駅行き約10分「砧公園緑地入口」下車すぐ 小田急線 成城学園前駅より東急バス・二子玉川駅行き約10分「区立総合運動場」下車すぐ ■SeTaBi Café 住所:東京都世田谷区砧公園1-2 世田谷美術館地下1F TEL:03‐3416‐2250 営業時間:10:00~18:00(L.O 17:30) 定休日:月曜 アクセス:東急田園都市線 用賀駅 より徒歩17分 美術館行きバス 「美術館」停留所下車徒歩3分
- ライフ
- 浅草駅(東武・都営・メトロ)
- 用賀駅