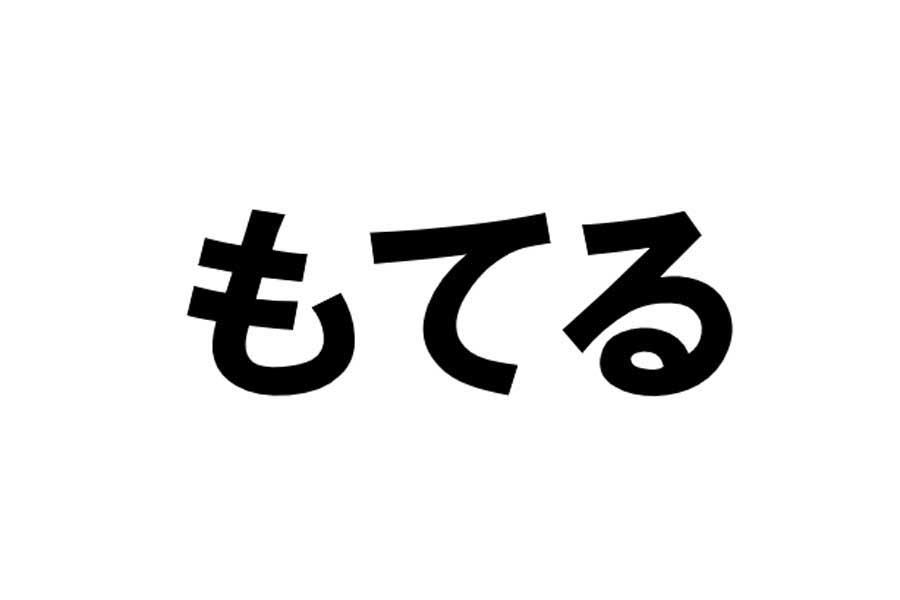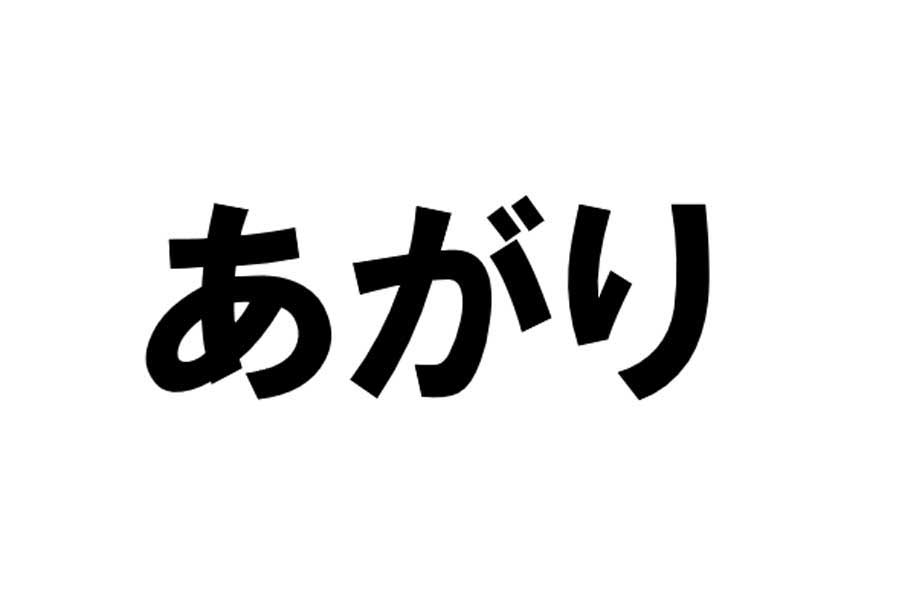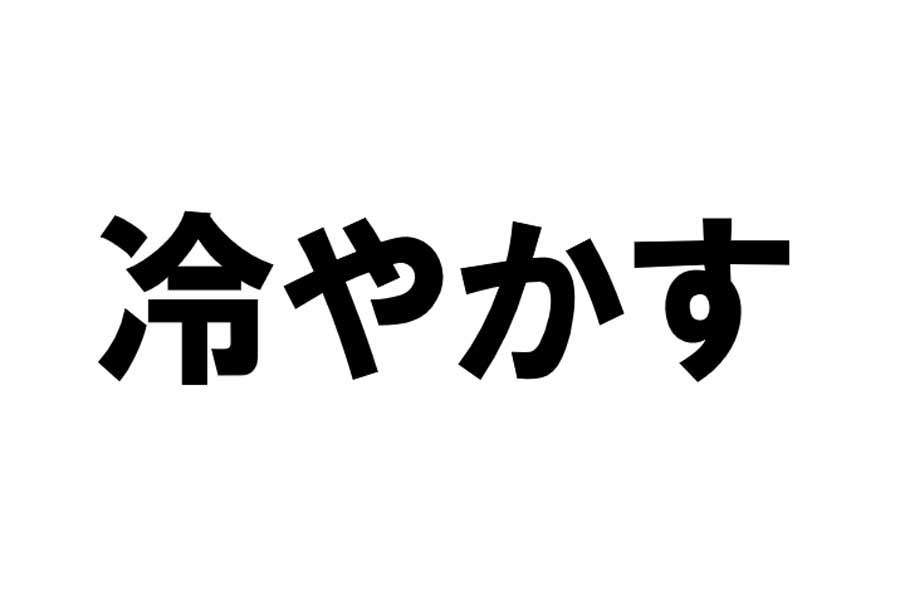浅草に5000円の「カワイイ巨大寿司」登場、SNS映え間違いなし? インバウンドに照準か
浅草駅から徒歩1分の飲食店ビルに2019年11月19日(火)、ニュータイプの和食料理店がオープンします。「SNS映え」と「体験型」を柱に据える同店のターゲットはずばり、「kawaii(かわいい)」が大好きな外国人観光客と日本人女性です。浅草系と原宿系のミックスカルチャー? 今や外食産業でも欠かせないキーワードとして定着した「SNS映え」と「体験型消費」。これに「日本食」を掛け合わせたニュータイプの和食店が2019年11月19日(火)、台東区雷門の浅草駅前にオープンします。 目玉はウニやキャビアや金箔を豪快にのっけた巨大高級手まり寿司(直径10cm)や、カラフルポップな12種のおばんざいプレート(手巻き寿司またはだし茶漬け付き)。まるで浅草的な和風要素と原宿系カルチャーを融合させたようなメニュー展開は、「kawaii(かわいい)」もの好きの外国人観光客と日本人女性の支持を集めそう……? 直径10cmのウニ金箔キャビア手まり寿司。果たして一人前なのか、シェアして食べる者なのか(2019年11月18日、遠藤綾乃撮影) 店の名前は「体験型Dining 和色-WASHOKU-」。 直径10cmのウニ金箔キャビア手まり寿司は、ディナータイム限定で5000円(税抜。事前予約が必要)。また、ランチタイム向けのおばんざいプレートは、管理栄養士が監修した12種が品良く盛り付けられて、手巻き寿司かだし茶漬けが付いて2000円です。 おばんざいは生ホタテやマグロ、ひじき、煮穴子など和食王道の顔ぶれを並べつつ、かたやアボカドのような変わりダネ食材も投入。従来の日本食といえば醤油ベースの味付けで茶色が目立ちがちですが、こちらは赤・橙・黄・黄緑・赤紫と目に鮮やかな色合いも魅力的。 セットで付いてくるお茶漬け出汁とご飯におばんざいの具をのせて食べても美味。ともすれば敷居が高くなりがちな日本食のお作法を超えて、自由に楽しく食べてもらいたいというのが同店の狙いだそうです。 日本的なる体験コンテンツをこれでもかと投入日本的なる体験コンテンツをこれでもかと投入 ほかにも、ランチ営業とディナー営業の合間――朝9~11時と15~17時には、オリジナルの手まり寿司を作れる料理体験イベントも開くそう(こちらも要予約)。 体験型コンテンツは食だけにとどまらず、着物の着付けを体験できたり、人力車を予約して東京スカイツリーまで走らせたり、江戸切子を作ってみたり……と、とにかくあらん限りの「日本っぽいアクティビティ」をこれでもか、とかき集めたようなコンセプトの同店です。 「体験型」が売りの同店。手まり寿司づくりも体験できる(2019年11月18日、遠藤綾乃撮影) 先述した通り、主なターゲットにする客層は外国人観光客と日本人女性を半々ずつ。同店を運営するワールド(中央区八重洲)の代表取締役・坂めぐみさんは、 「インスタグラムにアップされている『#kawaii』というハッシュタグ付きの投稿は、今や4000万件以上。投稿は日本人に限らず、海外からの観光ツアーに『kawaiiを探しに原宿へ』といったプログラムが盛り込まれるほどです。海外旅行先では特に、モノを買う・食べるだけよりも貴重な体験をすることに重きが置かれる時代。少々値が張るとしても、忘れられない思い出をつくれるコンテンツが選ばれると考えています」 と同店のコンセプトに込めた思いを語ります。オープン前日の18日に開かれたメディア向け先行試食会には、中国の有名ユーチューバーを抱えるパートナー企業なども招き、海外への発信に力を入れる狙いが垣間見えました。 浅草駅から1分という便利さ、窓の外に広がる墨田川とアサヒビール(墨田区吾妻橋)の金色オブジェ、そしてスカイツリー。確かに外国人観光客に人気の出そうな立地です。そして「新しい日本食の魅力」が外国人に見いだされることで、「#kawaii」というハッシュタグを通じて日本人女性へも関心が逆輸入されるかもしれません。 まあ、とはいえ手まり寿司5000円(税込)はいくら巨大とはいえやはり「観光地価格」。その代わりにSNS映えは確実で、味も新鮮なウニが甘くて申し分ありませんでした。費用対効果を確かめに、同店へ足を運んでみるのもよいかもしれませんね。
- おでかけ
- 和食
- 浅草