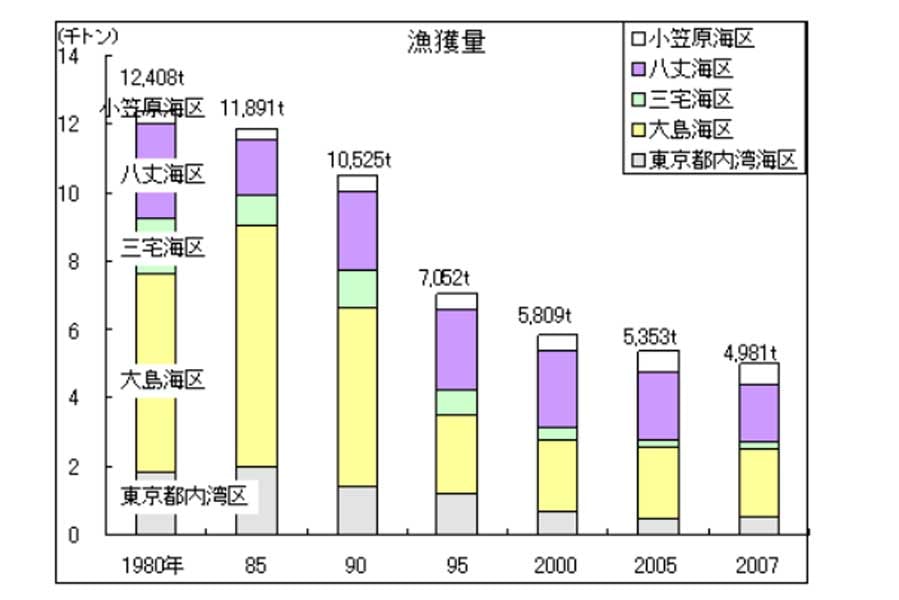一体いかなる覇権争いが……『半沢直樹』をしのぐ、リアル「都市銀行」大合併の系譜
現実世界にはどんなドラマがあったのか 2020年9月27日(日)夜に最終回を迎える話題のテレビドラマ『半沢直樹』(TBSテレビ系)は、架空の銀行「東京中央銀行」が主な舞台。 ドラマ内で「東京中央銀行」は、半沢(堺雅人)、大和田(香川照之)らが属していた「産業中央銀行」と、頭取の中野渡(北大路欣也)、常務の紀本(段田安則)らが属していた「東京第一銀行」という、ふたつの都市銀行が合併して生まれた日本屈指の大銀行という設定です。 ひるがえって、現実世界で「日本三大銀行」とされているのは三菱UFJ銀行(千代田区丸の内2)、三井住友銀行(同区丸の内1)、みずほ銀行(同区大手町)です。 遂に最終回を迎えるテレビドラマ『半沢直樹』の番組ウェブサイト(画像:TBSテレビ) 40代以上の人なら、昔の日本にはもっと多くの都市銀行が存在したことをご記憶でしょう。それらが駅前や繁華街に並んでいたのは、もはや懐かしい風景になってしまいました。 都市銀行が少数に集約されたのは、『半沢直樹』の世界同様に合併が行われたからです。では、多数あった都市銀行はどのようにまとまっていったのでしょうか? ピーク時には15もあった日本の都市銀行 いわゆる「都市銀行」は、1968(昭和43)年に「普通銀行のうち、6大都市またはそれに準ずる都市を本拠として、全国的にまたは数地方にまたがる広域的営業基盤を持つ銀行」と公的に定義されたものです。 1969年の時点で、次の15銀行がこれに該当しました。 大人にとっては懐かしい名前がズラリ大人にとっては懐かしい名前がズラリ1.第一銀行 2.三井銀行 3.富士銀行 4.三菱銀行 5.協和銀行 6.日本勧業銀行 7.三和銀行 8.住友銀行 9.大和銀行 10.東海銀行 11.北海道拓殖銀行 12.神戸銀行 13.東京銀行 14.太陽銀行 15.埼玉銀行 これらの中で最初の合併があったのは1971(昭和46)年のこと。 新1万円札に肖像が描かれる渋沢栄一が創設した銀行が前身の「第一銀行」と、宝くじ販売業務を受託していた「日本勧業銀行」が合併し、「第一勧業銀行」が誕生。 続いて1973年、兵庫県を拠点とした「神戸銀行」と、以前は相互銀行だった「太陽銀行」の合併し「太陽神戸銀行」となります。 以後、この13行体制時代は20年近く続きました。 3大銀行はいかにして生まれたのか ここからは、現在の3大銀行の生まれる過程を、大まかに整理していきます(法人格の変遷については割愛)。 さまざまな合併を重ねて今に至る日本の都市銀行(画像:三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行)●三菱UFJ銀行 この銀行は、かつての「三菱銀行」、「東京銀行」、「三和銀行」、「東海銀行」が2段階の再編を経て成り立ったものです。 まず、1996(平成8)年に旧三菱財閥の流れをくむ「三菱銀行」と、日本唯一の外国為替銀行だった「東京銀行」が合併し、「東京三菱銀行」となります。 一方、2002年に、大阪に本店があった「三和銀行」が、中京圏を拠点とする「東海銀行」と合併し「UFJ銀行」が誕生。 そして2006年に「東京三菱銀行」と「UFJ銀行」が合併し、「三菱東京UFJ銀行」となり、勢力を拡大させるのです。 ただしこの行名は長過ぎたためか、2018年に「三菱UFJ銀行」に改称されています。 赤、緑、青に塗り分けられた日本の都市銀行赤、緑、青に塗り分けられた日本の都市銀行●三井住友銀行 ふたつの旧財閥系銀行がタッグを組んだような名称ですが、実際は「住友銀行」、「三井銀行」、「太陽銀行」、「神戸銀行」が段階的に結集していったものです。 バブル崩壊前の1990(平成2)年に旧三井財閥系の「三井銀行」と「太陽神戸銀行」が合併し、「太陽神戸三井銀行」として一気に規模を大きくします。 また、同銀行は1992年に「さくら銀行」と改称。ソフトな印象の行名は当時としては珍しいものでした。 やがて「さくら銀行」はバブル崩壊の影響を著しく被りますが、2001(平成13)年に財務面が盤石だった旧住友財閥系の「住友銀行」との合併に活路を見出します。 このとき、「三井」のブランドを復活させ、「三井住友銀行」という、ふたつの旧財閥名を並列させた行名となるのです。 ●みずほ銀行 この銀行は原則的に、2002(平成14)年に「第一勧業銀行」と、旧安田財閥系の「富士銀行」、さらに長期信用銀行だった(都市銀行ではない)「日本興業銀行」が合体した姿です。 同行が宝くじの販売業務を行っているのは、旧「日本勧業銀行」、「第一勧業銀行」から引き継がれたものです。 経営破綻した銀行と3大以外の都市銀行経営破綻した銀行と3大以外の都市銀行 では当初の13都市銀行のうち、残る4行はどうなったのでしょう? まず、「北海道拓殖銀行」は、1997(平成9)年に経営破綻しています。 『半沢直樹』の世界でも、「大同銀行」なる銀行が経営破綻に追い込まれたという設定がありますが、現実世界でもそうしたことがあったのです。 江東区豊洲にある、大銀行の看板がズラリと並ぶ一角(画像:(C)Google) そして、他の3行は、現在の3大銀行以外の都市銀行「りそな銀行」、「埼玉りそな銀行」の前身です。 まず、1991年に「協和銀行」と「埼玉銀行」が合併し「協和埼玉銀行」に(翌年「あさひ銀行」と改称)。 さらに、「大和銀行」と2003年に合併し「りそな銀行」となるのですが、これと前後して旧「あさひ銀行」の主に埼玉県内店舗を継承する銀行として「埼玉りそな銀行」が生まれています。 ※ ※ ※ 以上、ざっくりと流れをまとめました。 こうした銀行再編の裏では、『半沢直樹』に描かれたような……あるいはそれ以上に苛烈な覇権争い、生存競争が行われていたのは間違いないのでしょう。
- ライフ