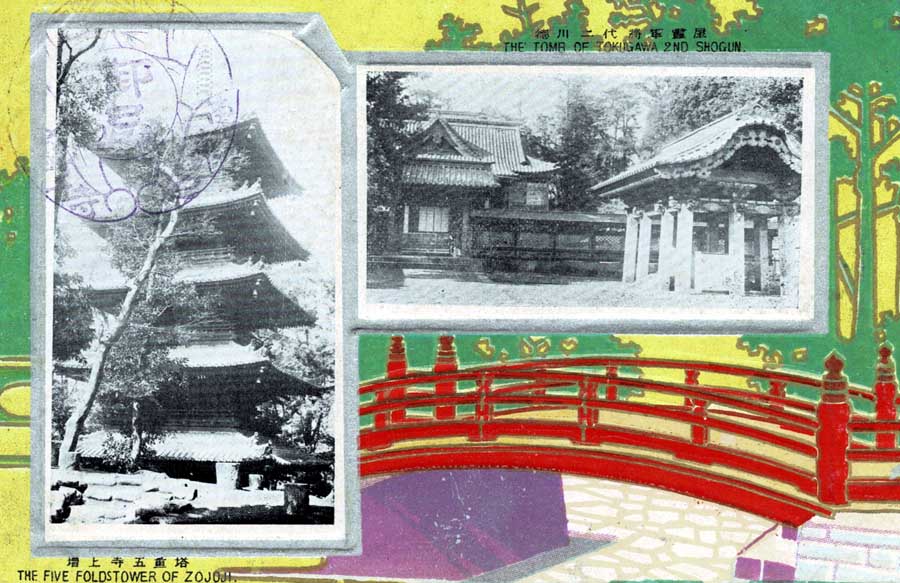大人だって食べたい! 誰でも注文OKな「お子さまランチ」 魅惑の東京都内5選
もう立派な大人の年齢だけど、なぜか無性に食べたくなるメニュー。それが「お子さまランチ」。子ども以外の注文はダメ、というレストランもありますが、なかには大人も注文OKな店も。久しぶりに食べてみたくなりませんか?ときどき無性に食べたくなりませんか? 2021年夏に実写映画が公開されて、ますます注目を集めている人気漫画『東京卍リベンジャーズ』(和久井健、少年マガジン)。 アニメ版でも描かれた、主人公が属する巨大暴走族グループ『東京卍會(とうきょうまんじかい)』の総長・マイキー(佐野万次郎)と副総長・ドラケン(龍宮寺堅)のとあるワンシーン。 旗の立っていないお子さまランチに「旗が立っていねぇじゃん!」と文句を言うマイキー。そこへドラケンが「ほらマイキー、旗だぞ」と旗を刺し、「わー!」とマイキーが目を輝かせます。 「マイキーとドラケンの関係があつい!」「マイキーかわいい!」とファンの中では人気の高いシーンです。 大人になっても魅力的……! 「お子さまランチ」が食べられる東京都内のお店5選(画像:写真AC) この作品のファンも、そうでない人にとっても、お子さまランチって大人になっても何だか魅力を感じさせられるメニューの代表格です。そこで今回は、大人も食べられるお子さまランチがある、東京都内のお店を紹介します。 ハンバーグやエビフライ、オムライスにケチャップで描かれたニコちゃんマークを、ぜひ童心に返って味わってみてください。 1. 高円寺「Baby King Kitchen」1. 高円寺「Baby King Kitchen」 高円寺にある「Baby King Kitchen」(杉並区高円寺北)は、屋根裏部屋の秘密基地をイメージしたというかわいい店内が心くすぐられる魅力的なお店。 子どもたちの笑顔を想像して手作りしたというスベリ台やブランコなど、とことんこだわった内観が魅力です。 これぞお子さまランチ! という顔ぶれがそろったひと皿(画像:Baby King Kitchen) そんな同店で食べられる「お子さまランチ」は、チキンライスにハンバーグ・エビフライ・ウィンナー・目玉焼き・スパゲティー・ポテト・サラダ・プリンというオールスターがそろう夢のようなメニュー。 さらに、おまけまでついているというのだから驚き! 小さい子ども向けの『小さい君のお子さまランチ』というメニューもあり、親子そろってお子さまメニューを食べられます。 2. 二子玉川ほか「100本のスプーン」「100本のスプーン」は世田谷区の二子玉川、江東区の清澄白河(東京都現代美術館内)、立川市内、江東区豊洲などに店舗を構える人気店です。 「コドモがオトナに憧れて、オトナがコドモゴコロを思い出す」をコンセプトにしており、「オトナと同じものを食べたい」という子どもの願いをかなえるハーフサイズメニューがあったり、赤ちゃんへの離乳食も料理として提供していたり。 みんなの思いをかなえてくれる、まさに”ファミリーレストラン”です。 たくさんのメニューがのった目にも楽しいワンプレート(画像:100本のスプーン) そんな同店で大人のお子さまランチをイメージして作られたプレートが「リトルビックプレート」。オムライスやポテト、エビフライをはじめとした料理が全10品プレートの上に並びます。 思わず、カメラを構えてしまうおしゃれなお子さまランチです。 3. 秋葉原「須田町食堂」3. 秋葉原「須田町食堂」 秋葉原UDX(千代田区外神田)3階に店を構える「須田町食堂」は、前述2軒のようなカフェ系レストランではなく、手づくりとお肉にこだわった老舗の洋食店。ガラス張りの店内は、秋葉原の夜景が見えなんともキレイに映ります。 大人気の「大人のお子さまランチ」は、「サーロインステーキプレート」「大人のお子さまランチ 洋食プレート」「大人のお子さまランチ 須田町プレート」の3種類。 子どもの頃の夢が詰まったひと皿(画像:須田町食堂) 一番人気という「大人のお子さまランチ 洋食プレート」はオムライス・ハンバーグ・海老フライ・ポテトフライ・スパゲッティー・サラダという、童心を思い出す夢のひと皿です。 洋食屋の名に恥じぬ、オリジナルハンバーグとサクサク衣のエビフライが大好評! 4. 上野「レストラン じゅらく」4. 上野「レストラン じゅらく」 全国でホテルやレストラン事業を展開している聚楽(じゅらく、文京区湯島)グループの系列店である「レストラン じゅらく」の上野駅前店(台東区上野)でも「大人のお子さまランチ」が食べられます。 お子さまランチの顔ぶれだけど、ボリュームも十分(画像:レストラン じゅらく) 上野動物園でパンダを見た後に、ぜひ寄り道して食べてみたいお店です。 同店の「大人のお子さまランチ」は、オムライス・ハンバーグ・エビフライ・スパゲティー・サラダという、洋食のオンパレード! 自分へのごほうびにもなりそうな豪華さです。 5. 渋谷そば「ビストロ ビンゴ」 京王井の頭線で渋谷の隣、神泉駅にある「ビストロ ビンゴ」(渋谷区円山町)は、新鮮で安全な瀬戸内地方の魚介を中心とした食材を現地から仕入れ、おしゃれな古民家で楽しめる「和×フレンチ×ワイン」のお店です。 ビストロという名にふさわしく、おしゃれな外観(画像:ビストロ ビンゴ) 同店「大人のお子さまランチ」は個性的でおしゃれ。六穀豚のハンバーグ・六穀豚のトマト煮込み・有頭エビフライ・ローストビーフ・くん製ポテトサラダ・温玉・サラダという、何とも和ビストロ料理店らしいひと皿に仕上がっています。 「ご飯&おみそ汁」または「バケット&スープ」、好きな方を選べるというのもまた魅力的。 ときには童心に返ってときには童心に返って ハンバーグやオムライス、エビフライなど、幼い頃にときめいた、お子さまランチを待つときのワクワク、口へ運ぶときのワクワクがよみがえってくるようでした。 幼い頃のときめきがよみがえってくるよう(画像:写真AC) それぞれのお店ならではのこだわりが感じられて、「大人のお子さまランチツアー!」と題して全てのお店を訪れたくなってしまうほど。 ときには童心に返ってお子さまランチ、あなたもいかがでしょうか。
- グルメ
- 上野・御徒町・湯島
- 秋葉原駅
- 高円寺