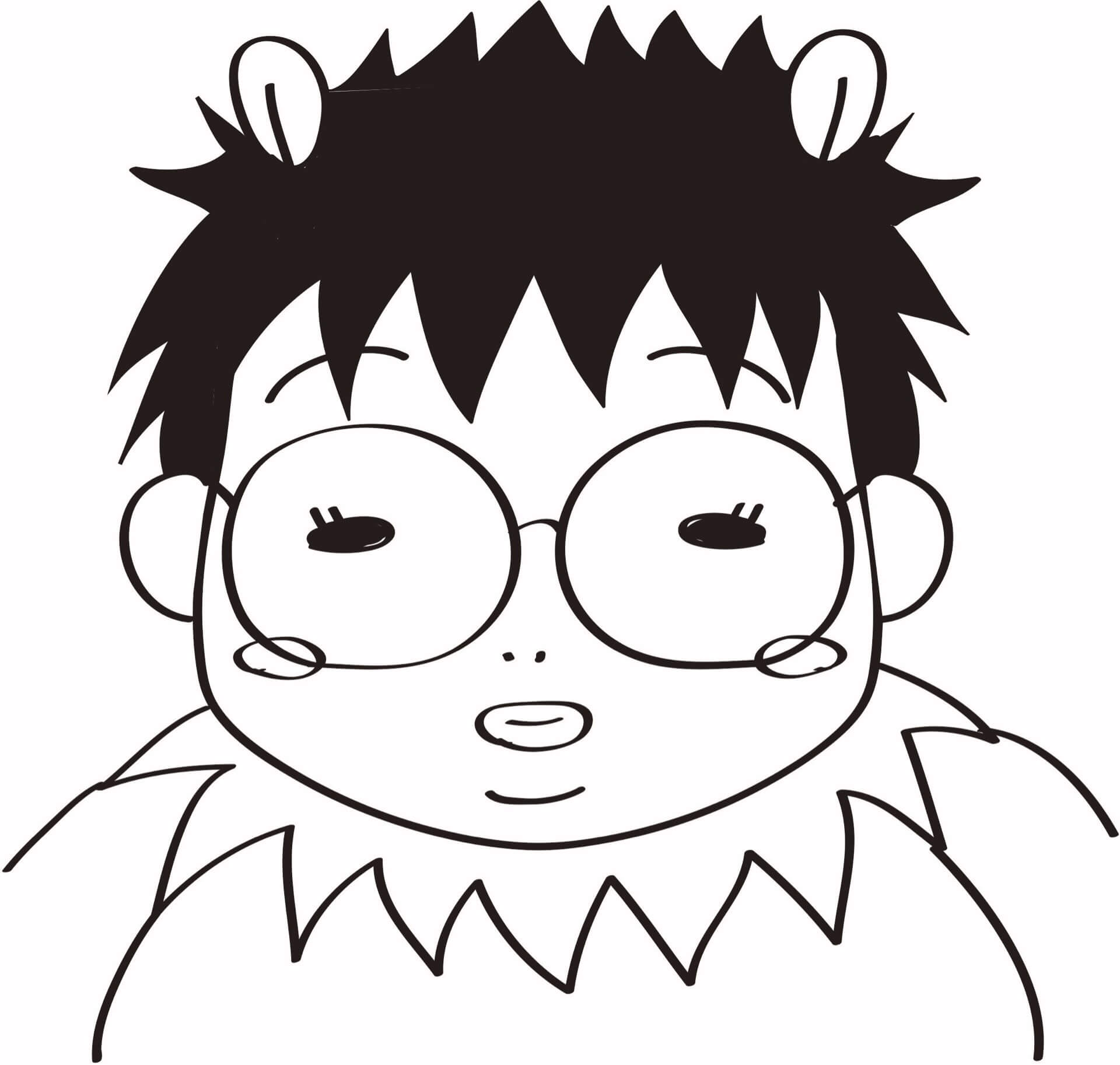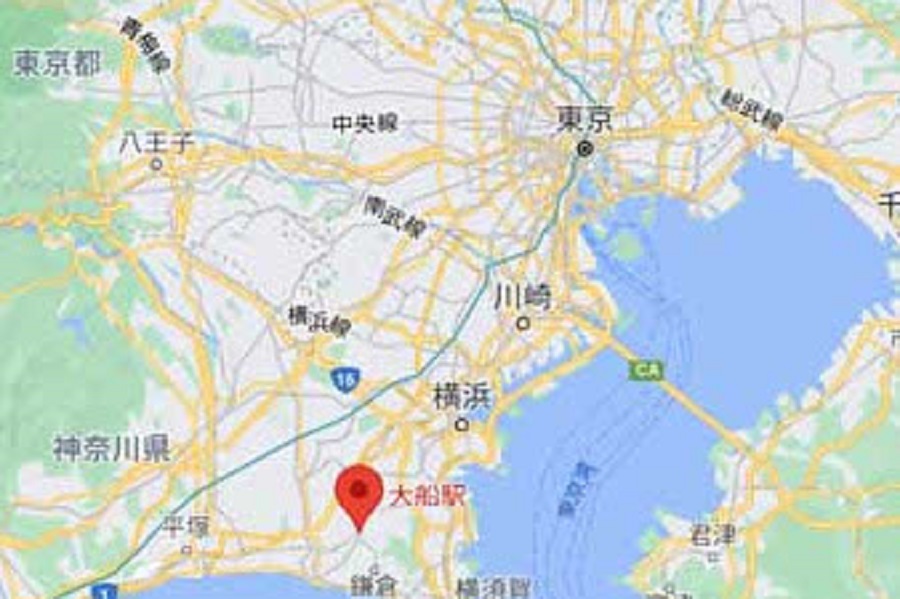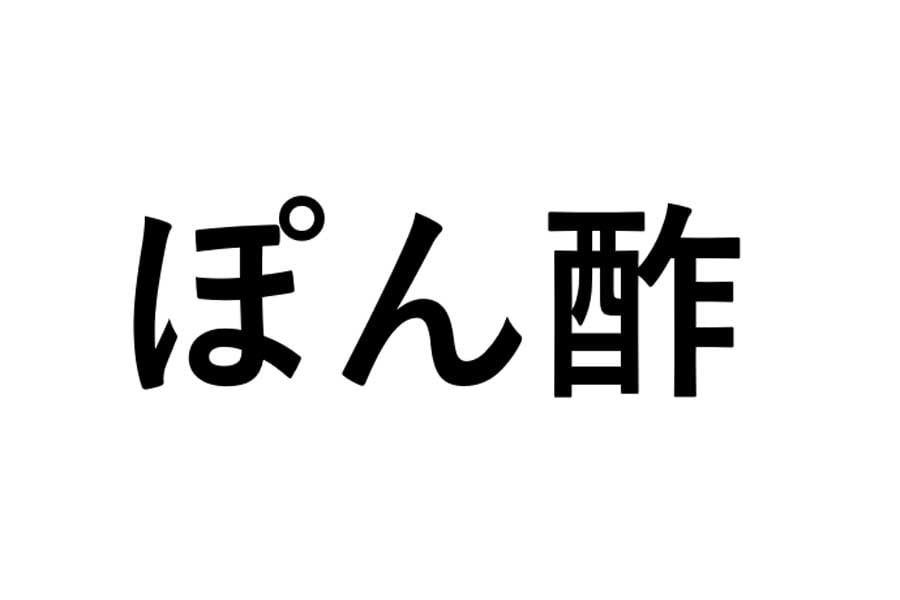4月に名称復活、首都大改め「都立大」へ 変更後の15年間を振り返る
都立大から首都大学東京へ 2020年4月、東京都立大学(以下、都立大)の名称が復活します。 石原慎太郎東京都知事(当時)が2期目に肝いりで行った都立大改革で、長年積み上げてきた都立大の名称を止め、「首都大学東京」(八王子市南大沢)という新たな大学名としました。設置は2005(平成17)年。しかし、その名称もわずか15年の歴史に幕を下ろす形となりました。 首都大学東京の外観(画像:(C)Google) 首都大学東京の知名度は上がらず、復活を求める声が少なからずありましたが、再編など無いまま名称のみが変更することになりました。都立大の名が復活することで、どのような風が吹くのでしょうか。 石原都知事2期目の当選で、学部再編は白紙に バブル崩壊後、各自治体の財政は悪化の一途をたどりました。困難な状況を打破するために、既存の大学の在り方にもメスが入れられることになりました。 1999(平成11)年4月に閣議決定され、翌年から国公立大学の法人化に関する検討会などで議論が重ねられてきました。 首都大学東京のある南大沢の街並み(画像:写真AC) 都立大もこれを受けて大学改造に着手することとなり、東京都立科学技術大学、東京都立保健科学大学、東京都立短期大学の三つの大学との統合再編をする方向に動き出したものの、事態は一変します。 公約に都立大の改造を掲げ、東京都知事の2期目を狙う石原慎太郎氏が都知事選に当選したためです。都立大が進めていた学部再編は、全て白紙に戻りました。 混乱を極めた2005年の船出 さらに2004(平成16)年、再編統合された新大学の名称公募4047件の内、中核となる都立大の名は2604件と最多だったにもかかわらず、公募にはなかった首都大学東京に決定しました。 現場の声を無視した一方的な流れに、現場の教職員から大きな反発の声が上がりました。その結果、それまで都立大を支えていた教授たちが他の大学に移る事態が発生。当初予定していた経済学部の担当教員が不足したため、初年度の2005年4月に経済学系のコースを設けられないなど、混乱を極めた状態での船出となりました。 名称復活の考えを表明した小池都知事名称復活の考えを表明した小池都知事 当初の混乱も落ち着き、都市環境学部といった大都市・東京ならではのユニークな学部が設置されるなど、独自性の高い大学運営は支持されてきました。しかし、首都大学東京の名前は世間一般に定着するに至りませんでした。 2013年度9月から11月までの間に行われた学生へのアンケートでも、改善してほしい点では「大学名・知名度」が43%と断トツ1位となっています。 アンケート調査のイメージ(画像:写真AC) 新しい大学名が浸透していなければ、就職活動などで不利になると不安を覚える学生もいることでしょう。学生からの声があっても、一度決まった大学名を覆すことは容易ではありません。 しかし、2018年7月の都政改革本会議の席上での、小池百合子都知事の一声で事は急変しました。 復活で東京都立大の魅力発信に期待がかかる 2017年の秋に実施されたアンケートでも、改善点の1位が「大学名・知名度」だったこともあり、首都大学東京を知名度の高い東京都立大にし、知名度とブランド力をアップさせる考えを示唆したのです。 小池知事は2018年8月の定例会見で、2020年4月から都立大の名称に変更することを正式発表。名前だけが入れ替わるため、大きな混乱もなくそのときを迎えられると考えられます。 記者会見のイメージ(画像:写真AC) 15年以上経過して振り返ってみると、都立大を巡る混乱はバブル崩壊を機に起きた財政悪化による大学再編が発端になっています。しかし、結果的には全国の公立大の中ではトップクラスの学部数を誇る総合大学となりました。 南大沢キャンパスという優位性南大沢キャンパスという優位性 公立大学は国立大学と異なり、設置されている地域へ文化面や経済面などの貢献が期待されています。東京都立大の名が復活することで、学生や教職員の士気も高まるはずです。 東京都庁の外観(画像:写真AC) 本部のある広大な南大沢キャンパスは、学業に集中するには最適な場所です。首都大学東京を経てさまざまな変化や荒波を経験してきた新生「東京都立大学」は都民やメディア、受験生からの注目を浴びる中、どのような成果を出していくのか、ゆっくり見守っていきたいところです。
- ライフ