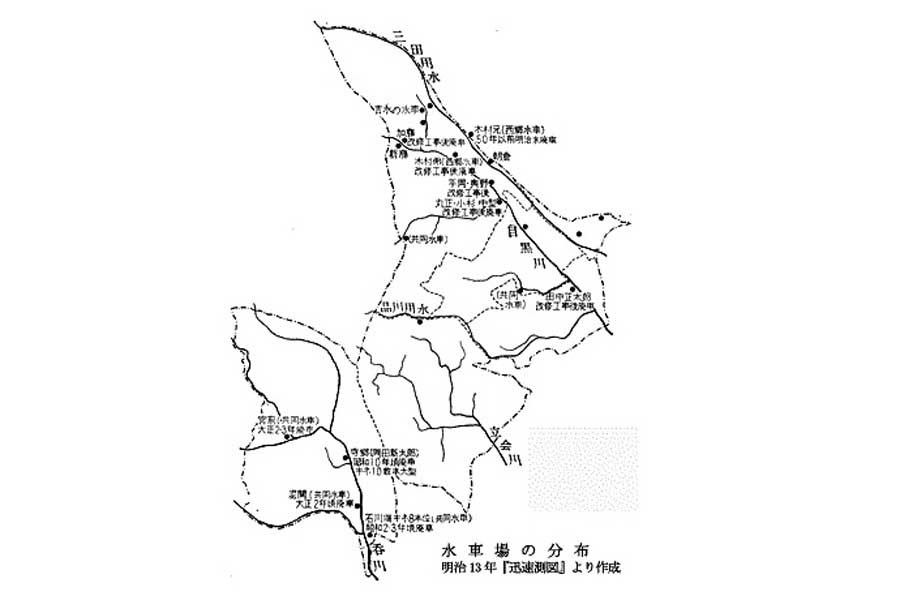入ってみたいけどビビっちゃう……東京のおしゃれなお店あるあるを描いた漫画「勇気を出して……!」
雨の日、突然のピンチ。目の前にはおしゃれなお店…… ナカムラエコさん(ペンネーム)は東京都下で夫と長男、次男の家族4人で暮らすイラストレーターです。毎日のちょっとした幸せを描くナカムラさんのアーバンライフメトロ・オリジナル4コマ漫画、今回のテーマは「東京を楽しむ極意」です。 ナカムラさんの体験を描いた漫画のカット(ナカムラさん制作)――ナカムラさん、今回の作品を作った背景を教えてください。 思い切って行動してみたら良い結果になったので、この経験は今後も生かしたい! と思って描きました。 ――2コマめの気持ち、分かります。東京のおしゃれなお店って、お値段やら敷居やら高そうで、ちょっと気後れしてしまうんですよね。 そうなんです。勇気を出して入ったところで買うものが無い! ってなったとき、今度は手ぶらで出づらいという……(笑)。 ――店内はたくさんの傘があって、目移りしてしまいそうです。どのくらいの種類があったのでしょうか。 スゴイんですよ! 1階から4階まで全て傘で。ホームページには約500種類、1万本とありました。テンションが上がります。 ――「思い切って行く!!」 これは本当に、東京を楽しむ鉄則ですね。 東京はおしゃれなお店が多いですからね~。楽しむためにはビビっちゃダメ!「思い切って行く!!」です。 ――それにしても、もともと持っていた傘は、柄の部分がすっぽ抜けてしまうという不思議な壊れ方をしたのですね。 折りたたみ傘だったんです。連結部分のピンが取れて真っぷたつに分離しちゃって。ピンも飛んで無くなったので再起不能という(涙)。 ――すてきな傘も買えたし、新しいお店に入れたし、けがの功名という感じでしょうか。 そうなんです! ずっと細くてコンパクトな折りたたみ傘が欲しいと思っていたのでちょうど良かったです。たくさんの傘の中から選べてうれしかったです。 ――外出時に傘を無くしてしまいがちな人に、ひと言アドバイスをお願いします。 手から離さない。これが1番です(笑)。 ――漫画の読者にひと言お願いします。 ウオーターフロントはいろいろなタイプの傘があるのでかなり楽しめますよ! 今度は長傘が欲しいな。
- 未分類