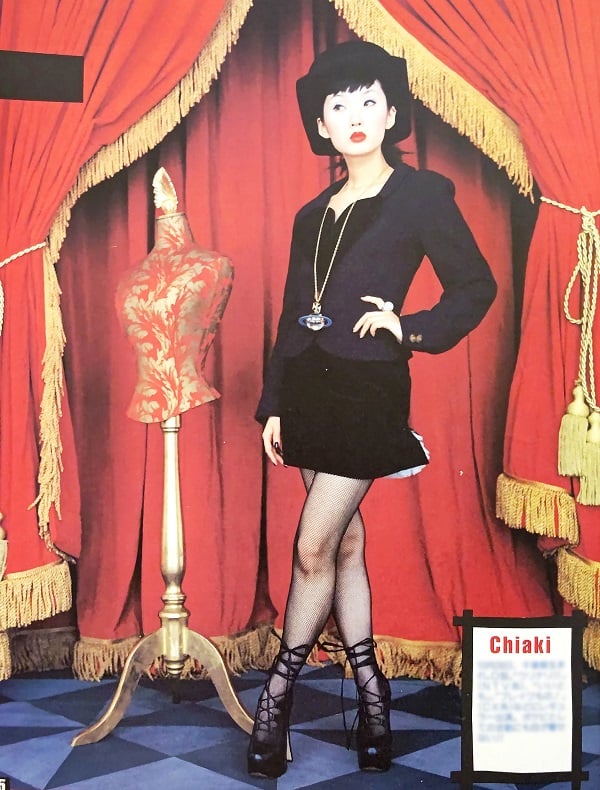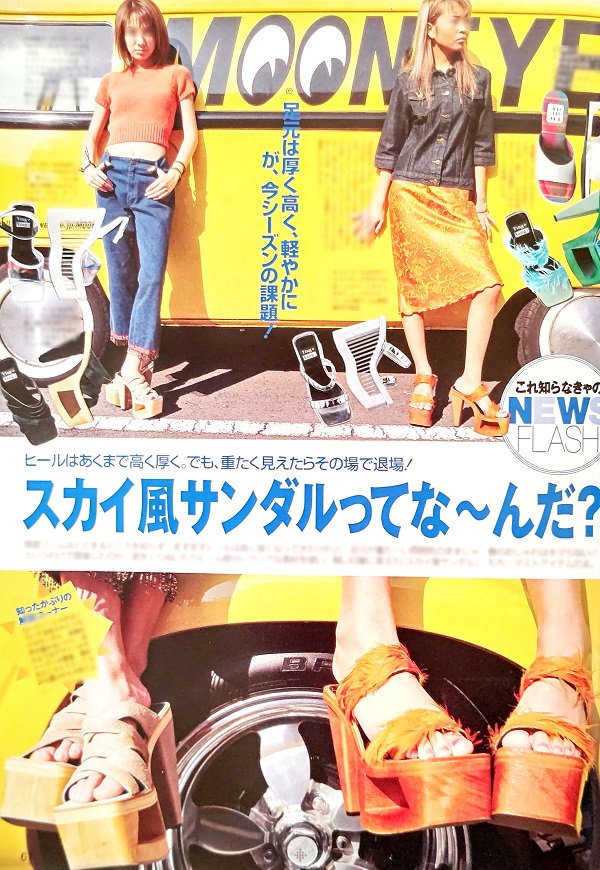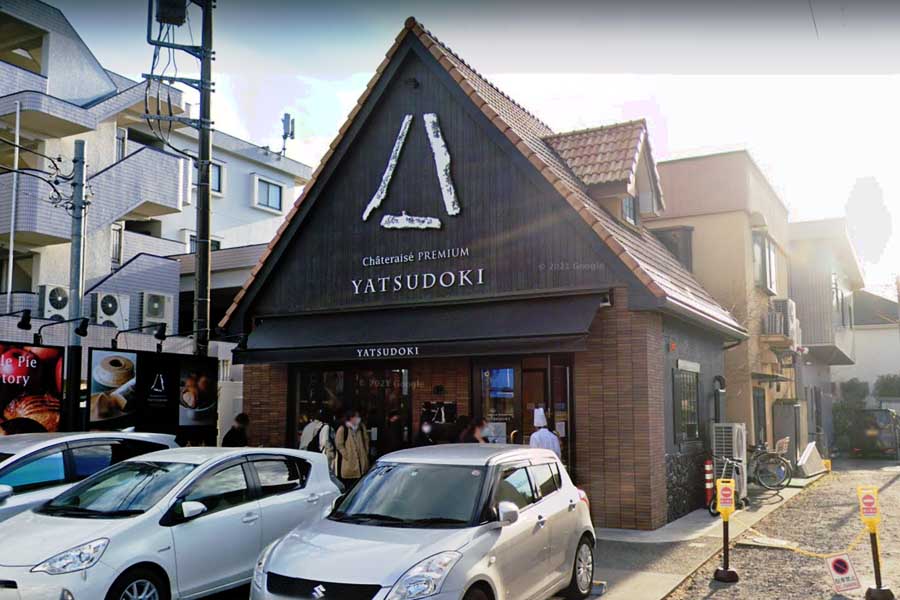サラリーマンの強い味方「立ち食いそば」は早さを売りに高度成長期に急増した
駅そばという、東京の「日常」 コロナ禍で外食産業は危機的な状況を迎え、その影響で都内でも多くの名店や老舗が閉店を余儀なくされています。ただ感染対策は次第に進み、客足も徐々に戻っている店もあるので、これ以上辛い思いはしなくてすみそうです。 さて、東京人にとって「いつもの店」といえば仕事の途中の昼ご飯や、外出先で手早く小腹を満たす店のことでしょう。そんな東京人の強い味方といってまず思い浮かぶのが、駅のホームや構内にある「駅そば」なのではないでしょうか。 駅そば・立ち食いそばのイメージ(画像:写真AC) 朝や昼の混雑する時間帯に多くの人が肩を寄せ合いながらそばをすする光景は、コロナ禍であっても変わらない大都会の「日常」です。 9月13日(日)には、渋谷駅構内で40年にわたって営業してきた「本家しぶそば」が渋谷駅周辺の再開発にともない閉店したニュースは大きな話題となりました。 江戸で生まれた立ち食いそば そんな駅そばや立ち食いそばのルーツは、言うまでもなく江戸時代です。その原型は屋台でそばを売るスタイルで、江戸時代前半に発生した大火災「明暦の大火」(1657年)の後に登場したと言われています。 明暦の大火で焼け尽くされた江戸の町では、多くの職人たちが再建のために働くことになりました。 そのような職人を相手にしたそばの屋台が、現在に伝わるファストフードとしてのそばの原型です。 この頃のそばは現在と異なり、そば粉を餅のようにした「そばがき」でした。 そばがきのイメージ(画像:写真AC) これがやがて麺スタイルの「そば切り」になり、その後の江戸時代中期頃、現在の主流となる、汁につけたタイプへと変化していきました。 スタートは待ち時間相手の商売からスタートは待ち時間相手の商売から 手軽な食事として定着していったそばですが、現在の駅そばや立ち食いそばスタイルの原点となったのは、軽井沢駅(長野県軽井沢町)だといわれています。 現在は、北陸・長野新幹線としなの鉄道の駅となっている軽井沢駅。その始まりは軽井沢駅と碓氷(うすい)峠を挟んだ横川駅間に1893(明治26)年、後の信越本線が開通したことでした。 新幹線の開通で廃止された信越本線のこの区間は、鉄道でも屈指の難所でした。当初はアプト式(列車が滑らないように2本のレールの中央に軌条を取り付けた方式)の鉄道が使われ、後に補助機関車を接続して急勾配を列車が登って行ったのです。 そのため、麓の駅では待ち時間を要することに。そんなときに駅のホームで弁当とともに売られていたのがそばでした。 駅そば・立ち食いそばのイメージ(画像:写真AC) こうして駅の待ち時間に、そばを売るスタイルは全国に広がっていきます。ちなみに当初は注文が入ったら麺をゆでて丼に盛り、列車内の乗客に渡すスタイルが主流でした。なお、駅のホームに現在のようなそば屋が見られるようになったのは、戦後になってからのことのようです。 ちなみに列車の中でそばを食べるスタイルは、使い捨ての容器が普及するとともにごく一般的に見られるようになりましたが、汁が残ったままの容器を座席の下に捨てていく人が多かったため、次第に姿を消していきました。 高度経済成長期との関係性 このように長距離列車の待ち時間の人を相手にしていた駅そばの歴史が変わるのは、1960年代、高度成長期を迎えてからです。 手早く食事を済ませるスタイルは、猛烈に働くことを美徳としていた当時のサラリーマンにマッチしました。そして、人が多く集まる駅周辺に店舗は増えていきます。 駅そば・立ち食いそばののれんのイメージ(画像:写真AC) 現在も続く立ち食いそばのチェーン店の歴史をみると、「梅もと」は1965(昭和40)年に大塚に、「名代富士そば」は1966年に渋谷に、それぞれ1号店をオープンしています。 つまり、立ち食いそばは高度経済成長期の需要にマッチした最新スタイルのファストフードだったのです。 立ち食いそば店からわかる日本人の心情変化立ち食いそば店からわかる日本人の心情変化 こうした業態を可能にした背景には、製麺技術の発展もありました。 今では生麺をゆでることを売りにした店もありますが、当然時間がかかります。もしも店内で生麺をゆでようとすれば設備とその設置スペースが必要になります。そのため、スピード重視の立ち食いそばには向きません。 そこで新たに開発が進んだのが「箱麺」です。製麺所であらかじめゆでたり、蒸したりしたそばを一玉ずつケースに入れた状態で店まで運ぶのです。運んでからすぐに使うのあれば、生麺と遜色のない味を出すことができます。 この箱麺の存在があってこそ、立ち食いそばは限られたスペースでも開店が可能となり、かつ回転率のよい店舗運営ができるというわけです。 高度成長期に人の集まる駅周辺では、多くの店が立ち食いそばに商売替えをしたようです。 駅そば・立ち食いそばのイメージ(画像:写真AC) 再開発で神泉に移転した、渋谷駅近くのガード下にあった「麺 KAWAKEI」も、1960年頃に立ち食いそば屋になる以前は、たばこや駄菓子を売る売店だったそうです。ちなみに同店は、1960年代から24時間営業を行っていた草分け店舗でもあります。 いま、立ち食いそばもスタイルは次第に変わっています。一般的に「立ち食いそば」といわれる店でも、店内に椅子席があるところが増えているのは大きな変化です。これこそが、急ぐことを美徳としなくなった日本人の心情の変化と言えるのではないでしょうか。
- ライフ