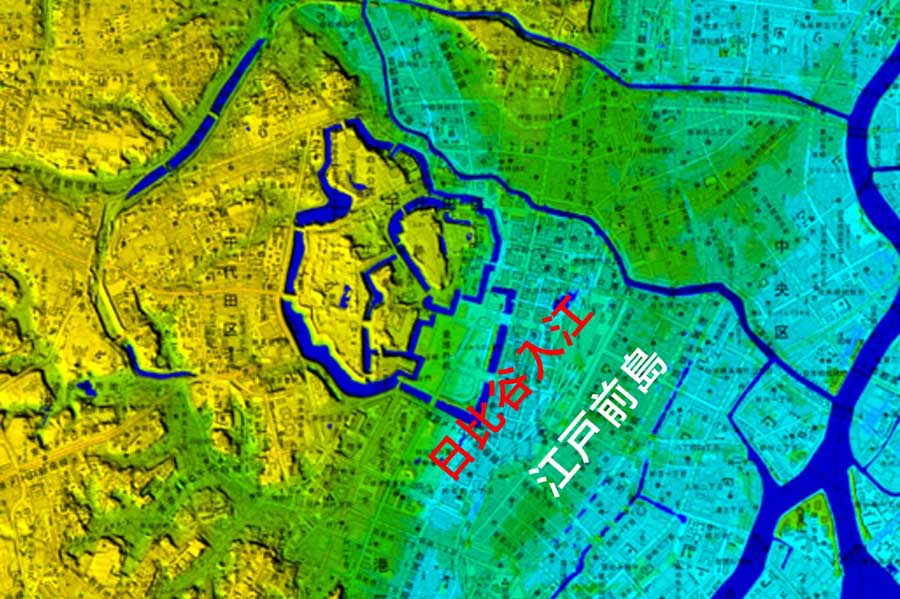今さら聞けない「江戸前寿司」の意味、海鮮丼とちらし寿司の違いとは?
発祥の背景にある「江戸前寿司」のふたつの意味「江戸前寿司」とは何か。外国人にそう聞かれたら、なんと説明しますか? 煮切りを煮る江戸前寿司のイメージ(画像:写真AC)「江戸前」とは、「江戸の前海(東京湾)」を指したとされています。しかし、今は東京湾で揚がる魚は減り、さまざまな地域から寿司種や魚が豊洲(以前は築地)に集まってきて、それを寿司屋が仕入れます。 「江戸前で獲れる魚」、転じて「新鮮な魚を用いた寿司」に変わった。それならば、日本の多くの寿司が「江戸前寿司」と呼べるものになります。 知っているようで知らない、それでいて今さら聞けない「江戸前寿司」の意味。諸説あるなかの通説はどういったものでしょうか。 寿司の起源は魚を塩と米飯で乳酸発酵させた「馴れずし」だったといわれています。これは魚を長期保存する目的の調理法であり、ご飯は捨てて魚だけを食べていました。ご飯を捨てたのは、発酵によってドロドロになるためです。 やがて、この調理法が広まるにつれて、ご飯を捨てるのはもったいないとして、粒が残る程度に発酵を浅くしたご飯をつけたまま魚を食べるようになりました(「なまなれ」と呼ばれる)。それが、寿司の原形と考えられています。 滋賀県近江地方の郷土料理である鮒(ふな)ずし。現存する最古の馴れずしといわれる(画像:AC) しかし、発酵には時間がかかるため、早く食べられるように酢が使われるようになります。これは、時間のかかる馴れずしに対して「早ずし」と呼ばれました。手軽になったことですしに多様性が生まれ、江戸後期、華屋與兵衛(はなやよへい)が考案したとされる「にぎり寿司」が江戸に誕生します。 シャリを型に詰める形成から「手でにぎる」という手法の転換により編み出されたにぎり寿司。それを、当時、江戸で流行していた屋台で供し、瞬く間に江戸名物となっていきました。 しかし、今のように冷蔵庫がなかった時代。魚の宝庫だった江戸の前海で獲れた魚介を、塩や酢で〆る、煮る、漬け込むなどの工夫を凝らして保存し、ネタにして提供しました。これが、江戸前寿司の原点とされています。 その時代背景から、江戸前寿司とは「江戸の前海で獲れる魚(コハダ、赤貝、イカ、エビなど)を使った寿司」という意味と、「保存に適する調理法で、それぞれの魚の旨みを最大限引き出す仕事を施した寿司」のふたつを意味したというのが通説となっています。 江戸前寿司職人が語る「海鮮丼とちらし寿司の違いはネタへの仕事」江戸前寿司職人が語る「海鮮丼とちらし寿司の違いはネタへの仕事」 しかし現代、東京湾で獲れる魚種が減り、輸送や冷蔵・冷凍技術の発達によってネタのバラエティーも増え、江戸前寿司は総じて後者の「魚の旨みを最大限引き出す仕事(加工)を施した寿司」の意味合いが強くなったといえるでしょう。 どの魚にどういった仕事を施し、魚の旨みを最大に味わってもらえる寿司にするかを考えるのが、江戸前寿司職人の仕事力の見せどころ。板前が煮切りを刷毛でサッと塗るなど、そのまま食べる「完成品」として供します。それが、鮮魚の刺身をシャリにのせた寿司を客自身で醤油に浸けて味わう、関西などに多い寿司屋のスタイルと異なる点です。 魚の旨みを最大に引き出すのが江戸前の仕事(画像:写真AC) 江戸前の技は高価なにぎり寿司だけでなく、手頃な「ちらし寿司」で味わう方法もあります。「ちらし寿司」と聞くと海鮮丼のように酢飯の上に何種類もの魚介の刺身が盛られているものを想像する人も少なくないかもしれません。 刺身がたっぷり盛られた海鮮丼(2018年11月、宮崎佳代子撮影) 銀座の江戸前寿司の職人さんに話を聞くと、「海鮮丼はそれはそれで美味しいけれど、江戸前寿司のちらしとは別物です」と言います。「刺身におろすだけなら魚屋さんにもできることで、寿司屋としての仕事を施すために、寿司職人の腕が必要になるんです」と語ります。 実際のところ、酢飯の上に刺身をのせてすし桶に入れたものを「ちらし寿司」としているところもあり、江戸前寿司の店でもちらし寿司については内容やスタイルが異なります。東京の寿司屋のちらし寿司メニューによくあるのが、「ばらちらし」や「吹き寄せちらし」です。 江戸前寿司の店のメニューに見られる「ばらちらし」の一例(写真は「鮨 さゝ木」の「特製ばらちらし」)。内容は寿司屋によって異なる(2018年12月、宮崎佳代子撮影)「ばらちらし」の多くは持ち帰り可能なメニューです。「吹き寄せちらし」はその豪華版。ばらちらしは、時間が経ってからも食べられるよう、魚を醤油に漬ける、煮る、〆るなどの調理が施され、色々な具材が入っています。「そういったネタへの仕事と、シャリと具材のバランスが、江戸前寿司のちらし」と前出の職人さんは言います。手軽に江戸前仕様のちらし寿司を楽しむのは、その店の仕事力を知ることにもつながるのではないでしょうか。
- 未分類