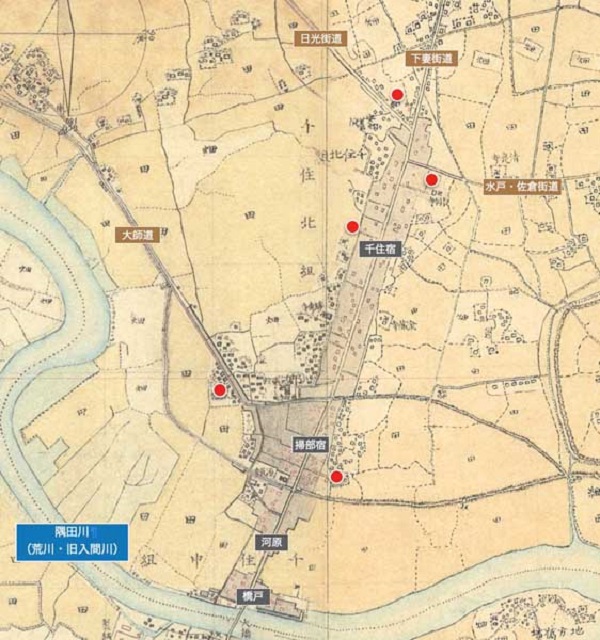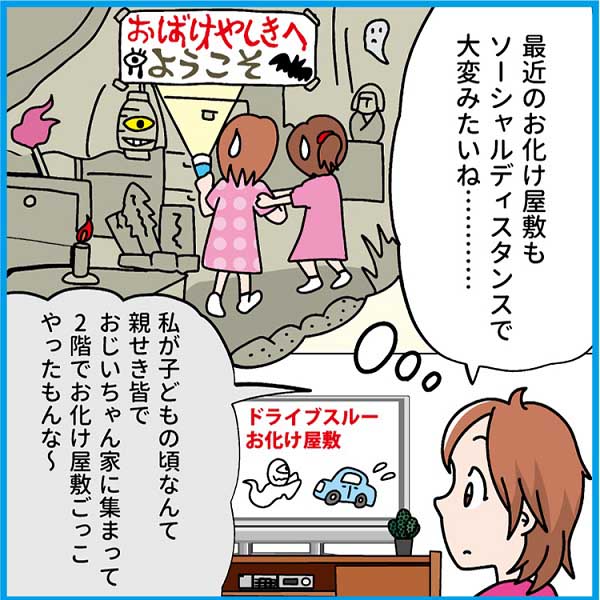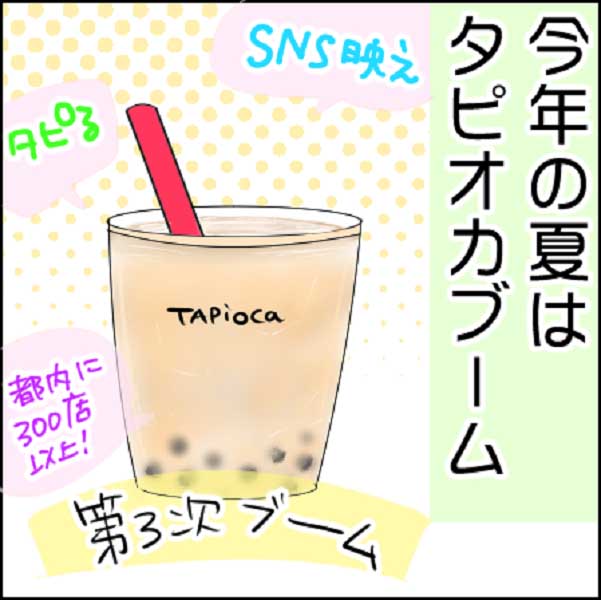今では当たり前、でも50年前は超めずらしかった女性の趣味とは? を描いた漫画「いい日~旅立ち~♪」
50年前、若い女性たちが始めたコト pigurani(ピグラニ)さんは、服飾関係の会社で働くかたわらイラストや漫画を描くイラストレーターです。SNSでは「巡りめくるファッション史」と題した作品を配信中。そんなpiguraniさんが東京の街を彩るファッションと歴史について描く、アーバンライフメトロ・オリジナル4コマ漫画。今回のテーマは「アンノン族」です。 piguraniさんが描いたファッション漫画のカット(piguraniさん制作)――piguraniさん、今回の作品を作った背景を教えてください。 前回に引き続き「族シリーズ」第2弾です。「GoToトラベル」キャンペーンが2020年10月から東京も解禁されたのもあって、「アンノン族」を描いてみました♪ ――今や旅好きの女性はたくさんいますから、時代の変化を感じさせられますね。 そうですね。今だと観光地に行けばカフェとかおしゃれな施設もいっぱいあって、昔に比べてすごくウェルカムな感じになりましたね。 ――当時の女性たちにとって、旅はものすごく新鮮で刺激的なものだったんだろうなと想像すると、何だか胸が熱くなります。 1970(昭和45)年頃の日本は、高度成長期で娯楽が徐々に増えていき(アンアン、ノンノなどのようなファッション雑誌も創刊されるなど)、こうした流行が生まれるくらい女性の社会進出も認められ始めて、大きく国の文化が動いた時代だったんだなぁと思うと感慨深いものですね。 ――piguraniさん自身は旅は好きですか。今一番行きたい場所はどこでしょう。 旅好きですよ! 普段は家で絵ばかり描いていますが、必要に応じて出て行きます(笑)。今一番行きたい場所は、やはり東京です! 東京をテーマにした漫画を描くようになって、あらためて東京のすばらしさを知り、またもっと勉強したいと思いまして、今一度東京のいろいろな場所を訪れてみたいです! GoTo解禁になったしね☆ ――「GoToトラベル」で東京を満喫中の女性たちにひと言お願いします。 長らくGoToできなかった東京を思う存分エンジョイしましょう!♪ ――漫画の読者にひと言お願いします。 コロナ渦で身動きを取りにくい世の中ですが、あなたが必要とするその行動は、きっとアンノン族のように世の中に影響を与えるはずです。それぞれが「必要とする動き」が今求められていると思います! 今回もご清覧ありがとうございました!
- 未分類