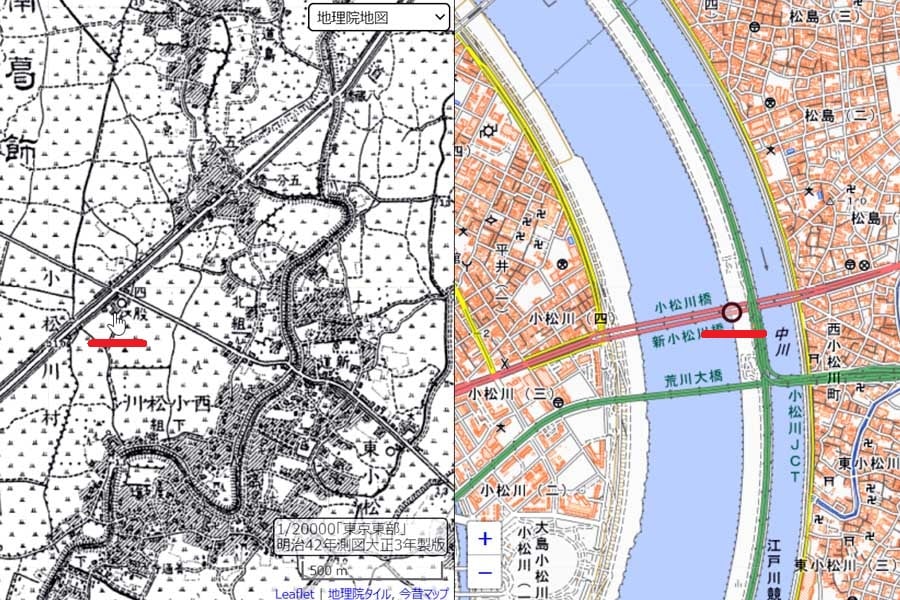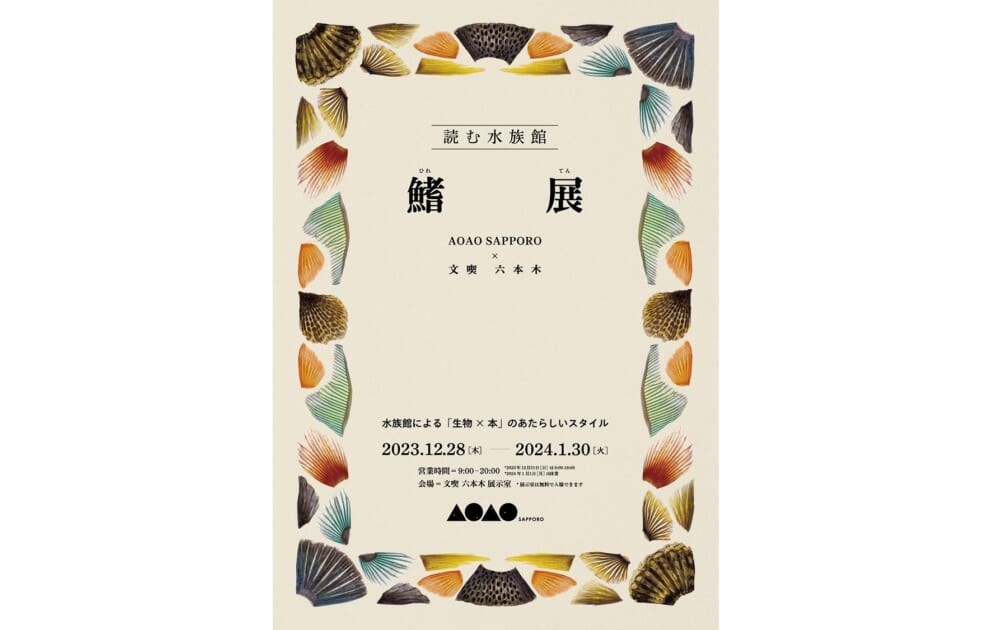「ダサ面白い」と話題の深夜ドラマ『M』 浜崎あゆみ本人は世間の反応に何を思うのか
東京の街を舞台にしたドラマ『M』 平成の歌姫・あゆ、こと浜崎あゆみ。彼女は2000年代初頭、中学生から大学生まで多くの女子にとってカリスマ的存在でした。 1998(平成10)年のデビューから22年がたった2020年現在、東京の街を舞台にしたドラマ『M ~愛すべき人がいて~』(テレビ朝日系)が土曜深夜に放送中です(新型コロナウイルスの影響で、2020年5月27日現在は放送延期)。 放送中のドラマ『M ~愛すべき人がいて~』のメインビジュアル(画像:AWA) 深夜帯ドラマとしてまずまずの注目を集めている理由に挙げられるのは、「なんだかダサい」「全体的に大げさで『大映ドラマ』っぽさがある」「でもそれが妙にクセになる」――。SNS上でも「なんか逆にハマった」「一周回ってあゆが好きになった」ともっぱらです。 平成の歌姫の半生をドラマ化、という設定に対する当初のイメージをある意味で鮮やかに裏切る脚本と演出が「想像のナナメ上を行っていてイイ」という、いかにも現代らしい支持を得ている同作。 「あれほどのスポットライトを浴び、時代の寵児(ちょうじ)と持てはやされた彼女のドラマが、まさか『ダサ面白い』という理由で評判になるとは……」。そんな感慨を抱く人は、あゆの全盛期を知る者であれば、おそらく筆者以外にも数多くいることでしょう。 みんな、あゆに夢中だった 金髪にぱっちりとした大きな二重、透き通った美肌、細いあご、きゃしゃな手足、切なげな歌詞に、切なげな高音の歌声。全盛期を知る者として今あらためて振り返ってみても、当時のあゆは「完璧」でした。 街を歩けばあゆの歌が流れ、女性誌を開けばあゆの特集が目にとどまり、音楽番組には連日あゆが出演。彼女の歌や姿を見かけない日は文字通り1日もありませんでした。 ひとりの「カリスマ」がいた時代ひとりの「カリスマ」がいた時代 たったひとりの「カリスマ」という言葉がすでにやや前時代的になり、代わりに何人もの「インフルエンサー」が存在するようになった令和の現代には信じがたいかもしれませんが、当時はひとつのCDが100万枚も200万枚も売れました。 放送中のドラマ(およびその原作小説)のタイトルにもなっている、あゆの2000(平成12)年のシングル『M』の売り上げは130万枚超、翌2001年のアルバム『A BEST』は400万枚超という驚異的ヒットを記録しています。 130万枚超を売り上げ、ドラマのタイトルにもなっている2000年のシングル『M』(画像:avex trax) 彼女が書く何気ない日常、体験をつづった歌詞は、決して奇抜ではない分リスナー自身の思いを重ね合わせやすく、ゆえに同世代を中心に強固な支持を集めました。「切ない気持ちになる」「共感する」と、歌詞をわざわざノートや通学バッグに書き留める同級生もいたことを覚えています。 「盛者必衰のことわり」 盛者(じょうしゃ)必衰という世のことわりは、音楽シーンにも漏れなく当てはまるどころか、最も盛衰の激しい世界のひとつでもあるのでしょう。 かつて熱狂したファン世代が進学、就活、社会人デビューとせわしない日々に翻弄(ほんろう)されているうちに、気がつけば彼女のポジションは「最前線」ではなくなっていました。 CDなどの売り上げ枚数が少しずつ減少していくのと入れ替わるように2010年代、彼女の話題で取り上げられるのは結婚や離婚、それから体形の変化(「もしかして、あゆ太った?」)やSNSにアップされる画像の加工疑惑などばかりに。 新しい恋人や婚約者の存在が明らかになるたび、ネットでは「話題づくりなんじゃないの?」というやゆが飛び交い、同時代を彩った歌手・安室奈美恵さんの引退が発表されると「引き際って肝心だね」などと比べられました。 ライブツアーを行う2017年の浜崎あゆみ(画像:WOWOW) いくら芸能人であっても「有名税」という都合のよい言葉で誹謗(ひぼう)中傷を看過してはいけない、という問題提起は、くしくも2020年5月、SNSでの検察庁法改正案をめぐるタレントの投稿や恋愛リアリティー番組に出演していた女性の死をきっかけに俎上(そじょう)に載っていますが、中傷とも取れるネットの書き込みを一切振り払うように、あゆはその後も黙々とライブツアーを重ねていきます。 きっぱりと引退することが潔(いさぎよ)いのか。ただひとつのことを、ひたすらに続けていくことが潔いのか――。それは、決して一概に決められるものではないのでしょう。 あゆ自身が伝えたいこととはあゆ自身が伝えたいこととは それからまた何年かが過ぎ、ドラマ『M』が放送されるのを知り、あゆ全盛期をリアルタイムで見てきた者として視聴することにしました。 まずこみ上げてきたのは、言いようのない懐かしさ。 当時、東京の街角で多く見かけた流行のミニスカファッションに(2020年現在、ミニスカートをはいている女性は街でほとんど見掛けません)、キャラが濃く派手で強気な女性たちと、イケイケの男性陣。 時はバブル景気の崩壊から久しく「失われた10年」などと呼ばれた時代でしたが、それでも2020年現在と比べれば、派手さと華美さが何の違和感もなく確かに世間を彩っていたことを、しみじみと思い返した視聴者も少なくないでしょう。 2020年5月27日時点で放送済みなのは1~3話なので、物語はまだ、あゆの歌手デビュー前夜。 「わたし、東京に行く。東京に行って、夢をかなえる」と宣言して福岡から上京するまだ少女のあゆ(演者・安斉かれん)の物語がこれでもかと大げさな演出と極端なせりふ回しにより描かれていて、それに対する視聴者たちの評価は冒頭に紹介した通りです。 放送中のドラマ『M ~愛すべき人がいて~』の1場面(画像:テレビ朝日) それにしても、です。 「あゆはダイヤ」 「俺がお前を選んだんじゃない。神様がお前を選んだんだ」 「俺の作った虹を渡れ!」 「渡る、あゆ、その虹渡る!」 この、真面目に視聴していたら思わず赤面してしまうような、それゆえに、この作品を肯定しようとすれば「ダサい」「でもそれが面白い」という評価しか選び得ないようなせりふが飛び交う展開を眺めつつ、あゆ全盛期を知る人たちはおそらく1度は考えるはずです。 このドラマを、かつての歌姫本人はどのように受け入れているのだろう? あるいは、このドラマが制作されることによって、彼女自身は何を伝えたかったのだろう――? 「完璧」と称された歌姫の告白「完璧」と称された歌姫の告白 あくまで筆者個人の考えですが、これは浜崎あゆみにとって、20年越しの「人間宣言」なのではないかと想像するのです。 「完璧」と持てはやされ、羨望(せんぼう)や嫉妬(しっと)のまなざしを一身に受けても「笑い」の対象になどなろうはずもなかったかつての歌姫が、最盛期を過ぎてもアーティスト活動を続ける自身のスタート地点を、いくばくかの笑いを交えながら泥臭く人間臭く開陳することは、「自分は決して完璧などではなかった」と告白することにも近い何かを感じます。 そして、当時10代の彼女の知られざる苦労、曲折、努力や涙をドラマというフィルターを通して知る視聴者は、この下積み期間の後に待ち受ける、彼女自身も想像し得なかったような壮大なヒットの訪れに思いをはせ、同時にそれに続く衰退の過程をもまた、思わずにはいられません。 ファッション誌『ViVi』2004年2月号の表紙を飾ったあゆ。CD売り上げ枚数という観点では、すでにピークを過ぎつつあった(画像:ULM編集部) 瞬く間に頂点を極め、その後少しずつピークアウトしていく過程からただよう、はかなさや切なさは、彼女自身の楽曲の世界観とも見事に重なるから不思議です。 「君を咲き誇ろう 美しく花開いた その後はただ静かに 散って行くから…」 (『vogue』、2000年4月発売) 『M』の8か月前に発表されたシングル曲の歌詞です。まさに頂点にいたその当時から、彼女はとっくに今後の「覚悟」を決めていたのかもしれません。 あゆのような歌姫はまた生まれるか 彼女が最も輝いた2000年前後は、先述した通り「ひとりのカリスマ」に大勢が熱狂する時代でした。あゆブームの背景に当時の時代性があったということは、あらためて言うまでもありません。 それでは今後、あゆのような「歌姫」は再び誕生するのでしょうか。 2010年代、そして2020年とへるにつれて人々の関心は一極集中から多様化が進み、ひとりひとりの趣味は複雑に細分化されています。 全国民を巻き込むほどの大きなムーブメントを生み出すアーティストは、もう生まれないのかもしれないと、一種の感傷とともに筆者は考えます。 あゆとは時代が見せたはかない夢だったのか、あるいは今後、全く別のタイプの歌姫が現れるのか――。平成とは違った新たな「令和の歌姫」のあり方を期待する一方で、今なお活動を続けることで、はかなさではなく力強さも身につけた、「夢」ではない現実のあゆの姿を、これからも筆者は見届けていたいと考えています。
- ライフ