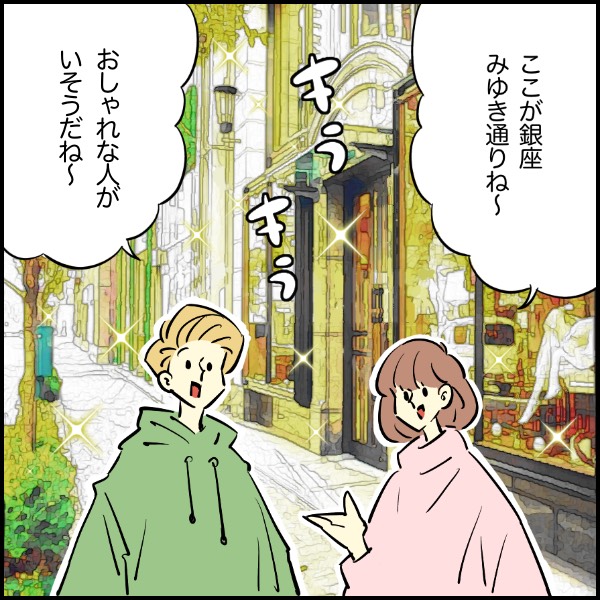世界有数のブランドショップが並ぶ銀座
2020年6月19日(金)から東京都内は休業要請が全面的に解除され、初の週末を迎えた20日には多くの人でにぎわいを見せました。
しかしインバウンド(訪日外国人)がやってこなくては、本当の復活とは言えません。改めて、東京が国際都市であることを思い知らされます。
そんな東京の象徴的な繁華街といえば、世界有数のブランドショップが並ぶ銀座です。
 銀座並木通りの様子(画像:写真AC)
銀座並木通りの様子(画像:写真AC)
一般人にとって、ブランドショップはそうそう足を踏み入れるところではありませんが、そうしたショップのある通りを歩くだけで、どこか心が豊かになるものです。
変化のきっかけは街路灯
そんな銀座といえば、「並木通り」。この通りにブランドの直営店が並ぶようになったのは、今から24年ほど前のことです。
 赤線部分が銀座並木通り(画像:(C)Google)
赤線部分が銀座並木通り(画像:(C)Google)
もともと、並木通りは銀座の中でもバーやクラブ、喫茶店など飲食店の多い通り。1980年代までは現在のようにオシャレな雰囲気は希薄で、「裏路地」という雰囲気がありました。
そんな街の雰囲気が変わったのは、1980年代の始め頃に街路灯が整備されてから。それまではタクシーで「銀座の並木通り」と言っても、スムーズに連れていってもらえませんでした。そこで少しでも通りを目立たせようと、地元の商店会で街路灯を設置したのです。
ブランドショップ進出に適していた道幅
そうして「もっと魅力的な街にしよう」という機運が盛り上がり、まずは足元からオシャレにしようと、歩道の整備が始まります。敷石はブラジルから取り寄せた赤御影石に、並木はプラタナスからリンデンに変わりました。
こうして雰囲気が変わった並木通りに目をつけたのが、海外のブランドでした。
まず1991(平成3)年にカルティエが進出。これが呼び水となり、グッチ、ルイ・ヴィトン、シャネル、セリーヌなどなど世界の名だたるブランドのショップがやってきます。
 銀座並木通りの様子(画像:(C)Google)
銀座並木通りの様子(画像:(C)Google)
それまで夜の方がにぎわっていた並木通りですが、実はショップに適した通りでした。
道路の道幅は適度に広く、歩道と駐車帯を設けても狭くなりません。それでいて、通りの反対側にいくのも横断しやすいのです。加えて、ちょうど地元の不動産は持ち主が世代交代する時期で、売買も円滑に進みました。
不況を追い風にしたブランド消費
何より、バブル経済の後遺症で不動産の価格が下落していたこともブランドショップの進出を容易にさせました。
並木通りにあるカルティエ銀座ビル(中央区銀座5)は、リシュモンジャパンが1997(平成9)年に購入したものです。当時の報道では坪単価は3500万円程度とされており、さすがに銀座という価格ですが、バブルの頃には1億8000万円だったといいますから、かなりお買い得になっていたのです。
 カルティエ銀座ビルの外観(画像:(C)Google)
カルティエ銀座ビルの外観(画像:(C)Google)
次々と進出するブランド直営店の強気な姿勢は、バブル崩壊後の不景気に悩む日本人を驚かせました。
店舗が増加した1997年は、山一証券の自主廃業や経済の苦境ばかりがニュースになっていた時期です。しかしパリ本店と同じ店構えや内装、品ぞろえの旗艦店はにぎわいを見せました。
実のところ、不況は向かい風ではなく追い風になって客を増やしていたのです。日本人がグッチやシャネル、ヴィトンを当たり前のように持つようになったのは、バブル期の円高が背景にあります。その頃の日本人は、そうしたブランド品を買いあさることに必死だったのです。
変化したブランド意識
ところが、不景気によってブランドに対する「意識」が変わります。
例えばヴィトンのバッグは、一生物どころか二世代、三世代にわたって使えるものです。好景気のときは真新しい商品をいくつも買っては使わずにいたのが、本当に良いものを買って長く使うものへと変わったのです。
その結果、本国と変わらない品ぞろえのショップは本当に良いものを見つける場として脚光を浴びたというわけです。
皮製品は新品のままでは恥ずかしく、使い込んで味が出てきてこそ価値があるという常識が浸透したのもこの頃でした。
 銀座並木通りの様子(画像:(C)Google)
銀座並木通りの様子(画像:(C)Google)
こうしてブランドショップが並ぶ並木通りは、イタリアはミラノのブランドショップ通りになぞらえて、「日本のモンテ・ナポレオーネ通り」と呼ばれるようになりました。
それから二十数年。高級ブランドが集まる並木通りは現在、「日本の」ではなく、「アジアのモンテ・ナポレオーネ通り」になっています。