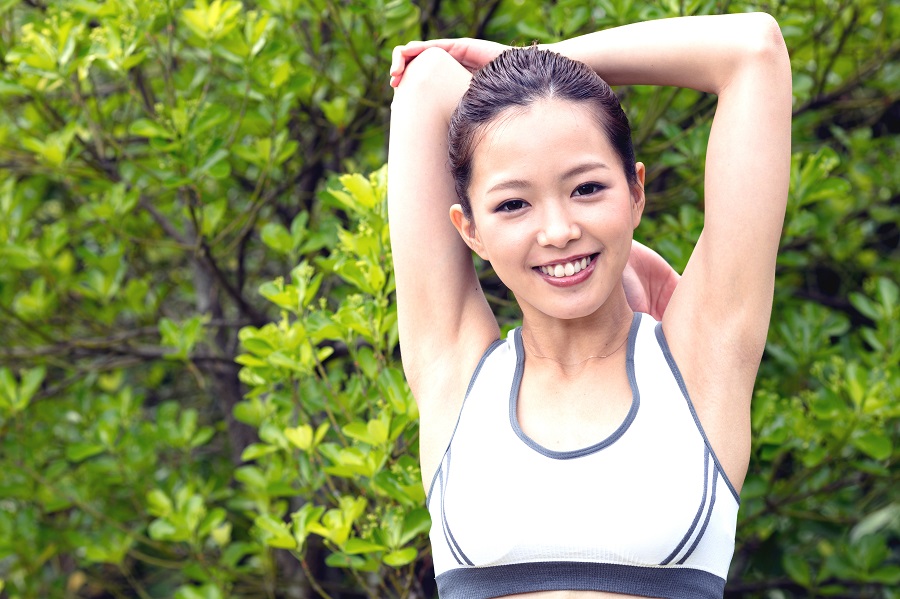1年で「記念日」が1番多い日はいつ? 2番は11月11日でキリタンポの日、チンアナゴの日
月別で最も多いのは11月。理由は? 1年366日、毎年楽しみにしている「記念日」はいくつありますか? 自分や家族の誕生日、結婚記念日、引っ越し記念日、好きなアイドルグループの結成記念日、受験の合格発表があった日……。来し方行く末に思いをはせたり、懐かしい記憶に思い出し笑いをしたりする、ほかの人にはありふれた1日でも、自分にとっては大切な1日です。 1991(平成3)年に発足した日本記念日協会が認定登録している記念日は、2020年3月末時点で2100件超。 企業や団体などからの登録申請を受け、毎週火曜日に行う審査会で認定の可否を決めるため、記念日は毎週のように増え続けているといいます。 逆に、登録要件を満たさなくなって抹消されるものもあるそう。 「チンアナゴの日」は11月11日。日付の理由は分かりますよね(画像:写真AC) 同年11月1日現在、月別で最も記念日が多いのは11月で363件。2番目に多い月は10月の322件。 11月に記念日が多いのは、「いい○○の日」という語呂合わせが使われることが多いからなどの理由とのこと。また「11」は棒の形に見えることから、棒状の細長い棒状の商品などの記念日として登録申請されるケースが多いといいます。 「世の中にはまだまだ『いい○○』や細長いもの、棒状のものがたくさんあるので、これからも11月の記念日は増え続けることでしょうね」と、同協会は説明します。 さて、それでは日別に見たとき366日で最も記念日が多いのは? 前述の流れで行くと、これまた11月11日かなと思いきや、同日は8月8日と並ぶ2番目で、49件とのこと。 1番多い日は「肉だんごの日」など55件1番多い日は「肉だんごの日」など55件 1位は10月10日の55件なのだそうです。 この日にどのような記念日が制定されているのか、日本記念日協会のウェブサイトで確認すると、 ・銭湯の日 1964(昭和39)年の東京オリンピック開幕日にちなみ、スポーツで汗をかいたあとに入浴をすると健康増進につながることから東京都公衆浴場業生活衛生同業組合(千代田区東神田)が1991(平成3)年に制定。銭湯(セントウ=1010)という語呂合わせも由来のひとつ。 1010はセントウ。語呂合わせで「銭湯の日」に(画像:写真AC)・肉だんごの日 日本ハムグループの日本ピュアフード(品川区大崎)が制定。「10」の並びが串と団子を連想させること、鍋がおいしい季節となることが由来。 ・ちくわぶの日 東京近郊でしか食べられていないちくわぶを全国に知ってもらう目的で制定。「10」の形をちくわぶの棒状の形と穴が開いていることに見立てて10月10日に。 ……などなど。全体として「1」と「0」の形に絡めた記念日の制定が多いという印象です。 11月に相次ぐ協会への問い合わせ ところで、11月に入ると「日本記念日協会に認定登録されている記念日が一番多い日は何月何日ですか?」という問い合わせが急増するそう。 実際、同協会のサイトでは2018年に続いて2020年も「11月11日は、1年で『2番目』に記念日登録が多い日」という趣旨のコラムを11月上旬に掲載しており、年間で唯一同じ数字が四つ並ぶこの日が近づくと、多くの人が記念日を意識する傾向があるようです。 さて、その11月11日には一体どのような記念日が登録されているのでしょう。 水族館の人気者から定番料理まで水族館の人気者から定番料理まで・チンアナゴの日 東京スカイツリー(墨田区押上)にあるすみだ水族館が、館の人気者であるチンアナゴをさらにアピールするために制定。水底の砂から体を出している姿が「1」に似ているうえ、群れで暮らす習性があることから1年でも最も「1」が集まるこの日に。 ラーメン、うどん、そば。愛好家が多い麺の記念日も、その形状から11月11日(画像:写真AC)・めんの日 1年を通じて麺類への関心を持ってもらおうと全国製麺協同組合連合会(江東区森下)が制定。毎月11日を「めんの日」としつつ、11月11日は中でもシンボル的な記念日。 ・おりがみの日 日本折紙協会(墨田区本所)が制定。この日付の四つ並ぶ「1」を、正方形の折り紙の1辺と見立てると、全部で4辺を表すことになるため。 細長い棒状のもののオンパレード 以上のような東京に関連する企業・団体の制定以外にも、 ・ポッキー&プリッツの日(江崎グリコ、大阪市) ・きりたんぽの日(かづのきりたんぽ倶楽部、秋田県鹿角市) ・棒ラーメンの日(マルタイ、福岡市) など、とにかく細長い棒状のものに関する記念日が多数、名を連ねています。 11月で最も記念日が少ない日はいつ?11月で最も記念日が少ない日はいつ? 日本記念日協会への記念日登録は、企業・団体だけでなく個人でも行えるそう。 記念日の名称・日付・由来・目的・活動などの必要事項を「記念日登録申請書」に記入し、郵便・宅配便・ファクスのどれかで長野県佐久市にある同協会あて提出するという手順で申請が可能です。 特定の政治活動・宗教活動に関するものや、反社会的な要素がみられるものなどは対象外。認定合格の場合は、書面郵送で結果が通知されます。1件につき15万円の記念日登録料が掛かります。 ※ ※ ※ 誕生日などの記念日は、1年に1回しかないからこそ楽しみが増しますが、毎日何かしらの記念日が制定されているのを知るのもちょっと乙なもの。 ちなみに、年間で最も同協会認定の記念日が多い11月にあって、現在たったひとつしか登録がされていない日があります。それは11月27日。現在認定されているのは「組立家具の日」だけ。 いいフナの日。いいツナの日。いいニナの日。語呂合わせで考えてもいろいろな可能性がありそうです。今後、この日にどのような記念日が追加されていくのか、個人的にウオッチしたいと考えています。
- ライフ