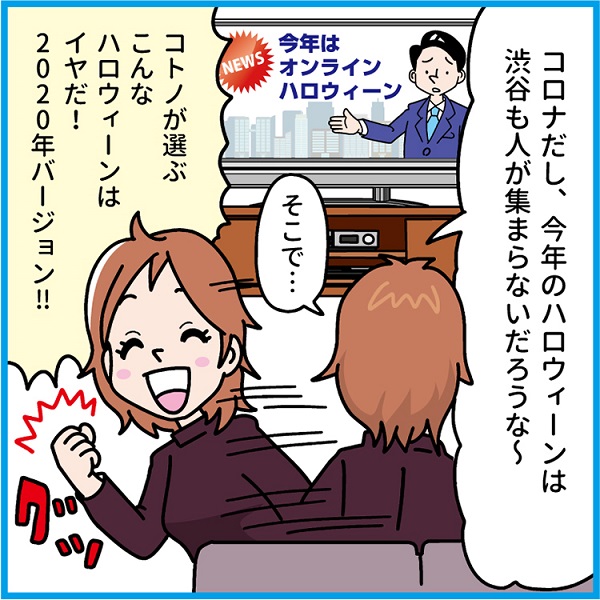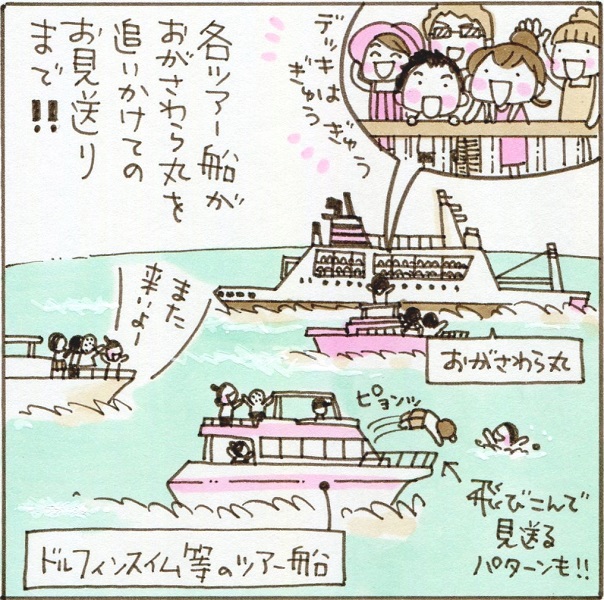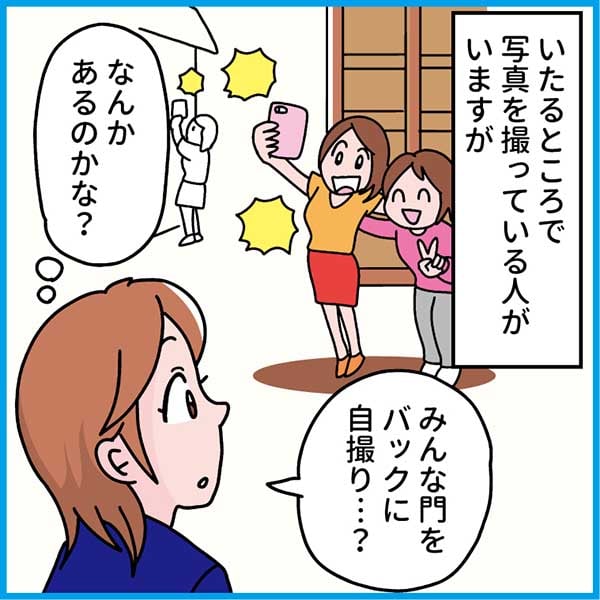「バブル時代」という自覚など、当時ないまま過ごしていた
普段あまりクルマでは移動しないけど、たまに乗ったときに、 四谷四丁目交差点にさしかかると思い出す痛ましい事件があります。
1986(昭和61)年4月、その交差点にあったビルからアイドル歌手・岡田有希子が投身自殺した、あの事件です。
前年に松田聖子が最初の結婚をして 芸能活動を休止していた時期で、同じサンミュージック(当時・新宿区四谷)に所属していた岡田有希子がその穴を埋めるかのようにブレイクしたところでの、突然の悲劇でした。
アイドル評論家・中森明夫氏の『青い秋』(光文社、2019年10月)には、この事件のことを描いた『四谷四丁目交差点』という短編が収録されています。
中森氏は芸能界に近いところにいて、デビュー当時の岡田有希子にも会っていました。そんな思い出と、30年が過ぎても彼女を忘れないファンの光景などを交差させた、美しくも哀しい1編です。
 アイドルのイメージ(画像:写真AC)
アイドルのイメージ(画像:写真AC)
後に「バブル景気」「バブル時代」と呼ばれる1980年代後半ですが、当時はそんな呼ばれ方はしていなかったし、景気がいいとの実感も、その渦中では分からなかったものです。
ただ、華やかで、騒々しく、忙しかったのは確か。
『青い秋』は、その華やかな時代を現在の「私」が回想していく形の私小説集で、8編の短編が収められています。1970~80年代を青春として過ごした世代のひとりとして、懐かしくも、どこか胸の痛む記憶が呼び起こされる、そんな本でした。
地方出身者のための「東京物語」という物語形式
「私小説」は、「自然主義文学」から派生した、自分の身辺に起きたことを、事実を少し加工しつつ書く小説様式です。中森氏はマスコミで仕事をし、アイドル評論家なので芸能界にも近く、彼の「身辺」には有名な芸能人や作家が登場します。
『青い秋』ではその有名人たちが登場しますが、人物名は皆、「宮川りえ」「野口久美子」「篠川実信」など誰のことかすぐに分かる仮名となっていて、これも私小説の常套的手法。「私」も作中では「中野さん」と呼ばれています。
芸能界が舞台になるので、読み方によっては「芸能界暴露小説」と捉えられるかもしれません。しかしこれは紛れもなく「私小説」であり、「青春小説」であり、そして「東京物語」でもある――そう感じたのでした。
 世界の映画監督が選ぶ「最も優れた1本」に選ばれた小津安二郎監督の代表作『東京物語』(1953年、画像:U-NEXT)
世界の映画監督が選ぶ「最も優れた1本」に選ばれた小津安二郎監督の代表作『東京物語』(1953年、画像:U-NEXT)
「東京物語」といえば、最も有名なのは小津安二郎の映画『東京物語』(1953年)でしょう。広島県尾道に住む老夫婦が東京で暮らしている息子や娘たちを訪ねる物語です。
また世代によっては、柴門ふみの漫画『東京ラブストーリー』(1991年)こそが「東京物語」だと言うかもしれません。愛媛出身で東京に出てきた男ふたりと女ひとり、帰国子女によるふたつの三角関係のドラマでした。
『東京ラブストーリー』は鈴木保奈美と織田裕二の主演によりフジテレビの「月9」枠でドラマ化され、高視聴率を獲得した大ヒット作です。これを見るために月曜はみんな早く家へ帰るので、「月曜夜、銀座からOLが消えた」という都市伝説まで生まれたほどでした。
『青い秋』も『東京ラブストーリー』と同じ時代を背景にしていて、どちらも地方から上京してきた者たちを描いているという共通点があります。「東京物語」という物語形式は、「東京で生まれ育った人の物語」ではなく、「地方から東京へ来た人の物語」なのです。
「新宿区歌舞伎町」でなければ、描かれなかった物語
この『青い秋』も1970年代後半に三重県から上京した青年が、東京でさまざまな人に出会っていく物語で、その意味でも「東京物語」ジャンルの王道をゆく小説です。
東京の私立高校に入った「私」が最初に住むのは「東中野のアパート」で、同郷の友人は住むのは「清瀬」(どうでもいいけど、中森明菜が生まれ育った市です)。
フリーライターになってからは「三鷹の風呂なしアパート」に住み、仕事の相手である出版社があるのは都心。「西麻布の薄暗い隠れ家バー」とか「新宿の路地裏」とか、作中の「私」がいる場所が、全て実名で記されていきます。
8編のなかには前述の『四谷四丁目交差点』のほかに『新宿の朝』というタイトルもあって、この新宿というのは歌舞伎町のこと。ちょっと怪しく、怖い世界が描かれます。東京は光り輝く都市であると同時に、闇もまた抱え持つ街であることが表現されています。
 人影のない朝の新宿区歌舞伎町(画像:写真AC)
人影のない朝の新宿区歌舞伎町(画像:写真AC)
人物は仮名なのに地名は実名なのは、この連作が東京以外では成立しない物語だから。「S区のK町」ではなく「新宿の歌舞伎町」としなければ描けない世界が、ここにはあります。
作者・中森明夫の分身である「私」は、テレビ局や大出版社の社員ではなく、フリーライターという立場でマスコミの世界を生き、そこでのさまざまな出来事を描いています。「オタク」という言葉を命名したことでの騒動もあれば、宮沢りえ・後藤久美子を思わせる少女たちとの交流も。
東京そのものが虚構性の高い都市ですが、マスコミはその中でも最も虚構性が高い――というよりも、虚構を生み出す装置です。
そのマスコミの世界は人間関係が薄いのか濃いのか分からず、「仕事」で知り合い「仕事」で付き合うドライな人間関係でありながら、それゆえの熱さもあったりします。それぞれの「個性」をぶつけあう世界だからでしょう。
その人間関係の儚さと脆さと虚構性は、欺瞞がゆえに真実であるという、屈折した世界を示しています。
今も東京にいる彼の、「未完の東京物語」
私が中森氏と知り合ったのは最近ですが、読者としては、彼が世に出た頃からよく読んでいました。彼が書くものが私の関心のある分野のものが多かったからです。
しかし初めて彼の署名のある記事を読んだときは、正直なところ、その内容以前に「中森明菜」をもじったペンネームに、明菜ファンとして不快感を感じました。
この本ではそれが彼が考えたペンネームではなく、勝手に付けられた経緯も描かれています。そうと知っていれば、もっと素直に彼が書いたものを読めたのにと、と思いました。多分、中森氏が自分で明菜をもじって付けたペンネームだと誤解している人も多いはず。その誤解が解ければいいなと思っています。
 茫洋とした虚構性をはらむ街、東京(画像:写真AC)
茫洋とした虚構性をはらむ街、東京(画像:写真AC)
さて、前述のように「東京物語」とは、地方出身者の東京での物語です。
『青い秋』は、東京に出てきた青年が、60歳を前にしてなおも東京にいて、1980~90年代の東京を振り返る物語です。彼はまだ東京にいるのです。
真の「東京物語」になるためには、彼は故郷へ帰らなければならず、帰って東京を思う時に、ようやく彼の「東京物語」は「完結」となります。
もちろん、中森氏には「東京物語」として完結させる義務はなく、「未完の東京物語」であっても、それは何ら問題はありません。
『青い秋』には、1970年代から2010年代までのほぼ半世紀の東京のさまざまな「ところ」の、さまざまな「とき」が凝縮されています。
東京は変わる――だが、ある日を境にして劇的に変わるのではなく、毎日、毎秒、少しずつどこかが変化し、気づくと、大きく変わっている、そんな都市です。
そこに生きる「私」は、定職のない自由業というか自営業で、結婚せず、子供もいません。就職、転職、独立、結婚といった人生の「転機」、区切り、境い目のないままに生きてきた人です。
終わらせることのできない「青春」を抱えて
「結婚式」をすれば、「青春の終わり」を感じ、リストラの肩たたきにあえば「中年の終わり」を悟るのかもしれませんが、そういうタイミングのないまま生きてきた人物。
だから、青春が終わらない、青春を終えられない。
人生の春が終わり、夏も過ぎて秋になっていることは理解しているが、いまも「青い」ままだ――というのが、タイトルの「青い秋」の意味。
私は中森氏と同世代で、同じ時代から出版界にて、似たような人生を歩んできたので、この小説には共感しすぎてしまう。
その意味で、読んでいて、痛い。冬になっても、まだ青いままであることが予感できるだけに、より痛い。
枯れないのはいいことかもしれないけど、成熟できないのもどうだかなあと、自問自答してしまう――そんな、すらすら読めるけど、ずしりと重い小説でした。