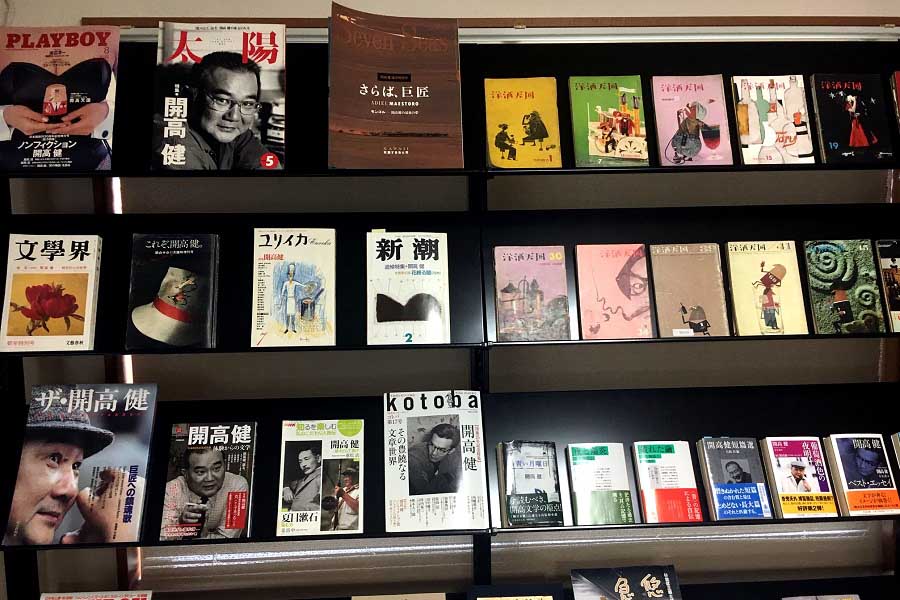THE BOOM『中央線』――日本を代表するニューミュージック路線 杉並区【連載】ベストヒット23区(2)
人にはみな、記憶に残る思い出の曲がそれぞれあるというもの。そんな曲の中で、東京23区にまつわるヒット曲を音楽評論家のスージー鈴木さんが紹介します。音楽界の巨星たちがかつて多く住んでいた 前回取り上げた千代田区の日本武道館から歩いて九段下駅に向かい、東西線の中野行きに乗車。終点の中野駅で中央線に乗り換えて、向かうは高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪、西荻窪――。 というわけで、今回の「ベストヒット23区」は杉並区。実は私、平成初期の20代のころに阿佐ヶ谷に住んでいたことがありまして(地名は杉並区下井草)、思い入れの深い土地でもあります。 都内を走る中央線(画像:写真AC)「杉並」という何となくノーブル(気品ある)な語感、阿佐ヶ谷駅から北に美しく延びるけやき通り(中杉通り)、借りたワンルームマンションの大家さんが話すとても上品な山の手言葉などなど、元区民にとって杉並区は、とっても上品なところだった印象があります。 今回着目するのは、その杉並区のど真ん中を東西一直線に走る中央線です。「ベストヒット杉並区」を「ベストヒット中央線」と改題して、選曲してみたいと思います。 というのは、中央線は、1970年代の「フォーク/ロック = ニューミュージック」の歴史の中で、重要な人物やエリアがひしめく、言わば日本を代表する「ニューミュージック路線」なのです。 まず吉田拓郎が、高円寺駅近くの秀和レジデンスというマンションに住んでいたと言われていて、アルバム『元気です。』(1972年)には『高円寺』という曲まで収録されています。 吉田拓郎のライバルである井上陽水は当時、彼の歌詞をまとめた本『ラインダンス』(1982年)に「中野から三鷹に引っ越した」と書いているので、こちらも中央線沿線住民。中野と三鷹の間にある高円寺を飛び越えたのは、ライバル意識かもしれません。 代表格・友部正人『一本道』の後継曲は……代表格・友部正人『一本道』の後継曲は…… 井上陽水の代表曲の1つ『東へ西へ』では、「満員」「すしずめ」の「電車」が「のびる線路」を走るという表現がありますが、これなど、当時の中央線のことではないかと推測されます。 三鷹を超えて国立まで行けば、そこはRCサクセション・忌野清志郎の聖地。彼が住んでいたという多摩蘭坂(たまらんざか)は、JR国立駅のそば。さらに八王子まで行けば、言わずと知れたユーミン(松任谷由実)の生まれ故郷。八王子の3駅手前、立川から青梅線で1駅のところにある西立川駅の発車メロディは、ユーミンの名曲『雨のステイション』(1975年)。 と、このようにニューミュージック界の巨星たちが、何らかの形で中央線に絡んでくるのですが、1970年代「ベストヒット中央線」の代表格と言えば、友部正人『一本道』(1972年)だと断言できます。舞台は国鉄(現JR)阿佐ケ谷駅。 阿佐ヶ谷駅の外観(画像:写真AC) 歌詞の主人公の男が彼女にフラれた夕方、阿佐ケ谷の駅に立っている。「一本道」とは中央線のこと。主人公は、一本道をまっすぐ走るような中央線が空を飛んで、彼女の胸に突き刺さるさまを妄想する――。 以上、「1970年代ニューミュージック路線」としての「ベストヒット中央線」を見ていきましたが、読者層も考え、この連載では、もう少し手前、1980~1990年代の曲中心でいきたいと思いますので、今回は、この友部正人『一本道』の後継とも言える1曲を「ベストヒット中央線」に認定します。 その名も、THE BOOM『中央線』。 1990年発売のアルバム『JAPANESKA』に収録され、後の1996年にシングルカットされた名曲。矢野顕子のカバーでも有名です。 乗るとよみがえる30年前の甘酢っぱい気持ち乗るとよみがえる30年前の甘酢っぱい気持ち 歌詞はやや抽象的なのですが、野暮ながら意味を読み解けば――僕を待っている彼女に会いに行くために、夜の中央線に乗るのが1番。2番の歌詞では、その彼女が出ていってしまい(逃げた猫を探しに出たまま、という設定がいい)、悲しみの中、僕はまた夜の中央線に乗って、どこかをさまよう――という感じのストーリー。 歌詞では、中央線のどの駅あたりのことを歌っているのかは明示されていません。杉並区かも知れないし、三鷹や国立、八王子かも知れないし、もしかしたら、作者・宮沢和史の出身地である山梨県甲府の「中央本線(中央東線)」のことかも。 ただし、友部正人『一本道』の後継だと考えると、やはりここは杉並区の話と解釈しましょう。以下、元杉並区民の私の独断で、歌詞の舞台を設定します。 時は1990(平成2)年。彼女が住んでいたのは荻窪駅から徒歩10分くらい、地名で言えば杉並区桃井のワンルームマンション、2階建ての2階。8畳一間とユニットバス。フローリングの地べたにソファーベッドと黒いテレビ。強化ガラスを使った黒く細い脚の小さなテーブル。タバコ「キャビン」柄の円筒形金属製のゴミ箱――。 当時の記憶をたどりながら、適当にディテールを書いてみましたが、あれから30年近く経って齢50を超えた今でも、(全身オレンジ色だった当時とは違う、一部だけオレンジの)中央線車両に乗ると、当時の記憶や思い出、ディテールが次々とよみがえってきて、恥ずかしながら、甘酢っぱい気持ちになるのです。 だから、阿佐ケ谷駅から中央線に乗って、THE BOOM『中央線』と友部正人『一本道』をスマホで聴けば、こんな言葉が浮かんできます――。 僕の思い出を乗せて、走り出せ中央線。 そして、一本道の滑走路から、空を飛んで、 あの頃出会った、あの娘やあいつの気持ちに突き刺され。
- 未分類