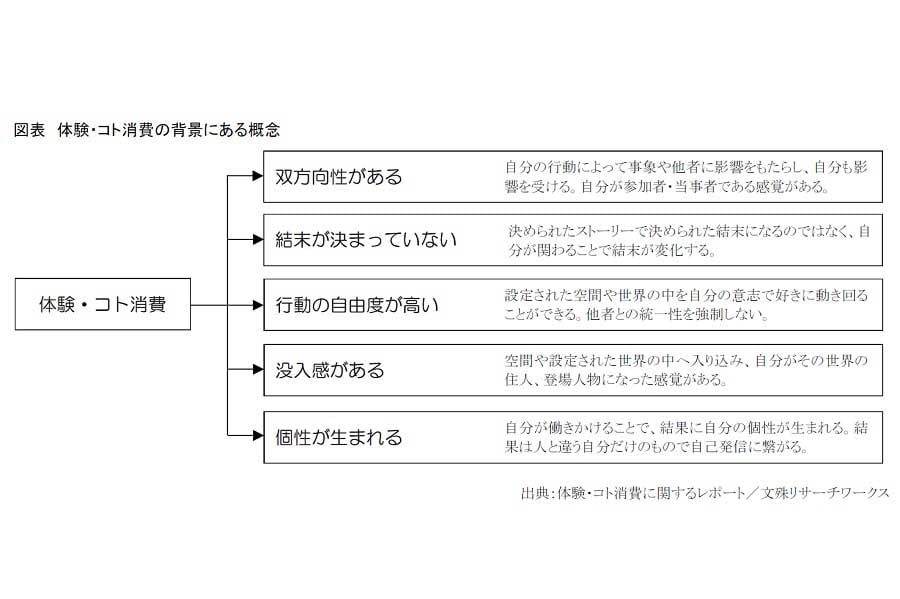赤坂にNY発のベーカリー「THE CITY BAKERY」、併設レストランのランチは焼きたてパン食べ放題!
ベーカリー、レストラン、パン工房の3つを備えた「THE CITY BAKERY STUDIO TOKYO」が赤坂にオープンしました。全国に11店舗構える「THE CITY BAKERY」最大数のラインナップ。併設のレストランでは、工房で焼き上げたパンを多国籍料理とともにたっぷり楽しめる、パン好きには心くすぐられる店です。工房からパンが続々、日本初出店のレストランもオープン ベーカリー、レストラン、パン工房の3つを兼ね備えた THE CITY BAKERY STUDIO TOKYO(ザ シティ ベーカリー スタジオ トーキョー)が、赤坂アークヒルズにグランドオープンしました。 グランドオープンした赤坂アークヒルズ店は、THE CITY BAKERY最大数のパンがラインナップ(画像:フォンス) THE CITY BAKERYは、1990年にニューヨークのユニオンスクエアで開業した米国発祥のベーカリーです。日本には2013年に初上陸。現在、全国に11店舗展開しており(改装休業中含む)、赤坂アークヒルズ店は最大数の品揃えだそうです。 店内から見えるガラス張りの「KOBO(工房)」のなかには、たくさんのパンがところ狭しと並び、思わず手を伸ばしたくなるほど。人気のプレッツェルクロワッサンをはじめ、ニューヨークの味そのままに再現したというパンの数々、旬の素材を使った季節のパン、さらに赤坂アークヒルズ店限定のパンも用意。ニューヨーカーには欠かせないホットチョコレートはじめ、ドリンクメニューも豊富です。 併設のTHE CITY BAKERY日本初出店のレストラン「THE CITY BAKERY BRASSERIE RUBIN(ブラッスリー ルービン)」でも、THE CITY BAKERYのパンが堪能できます。モーニングセット、ランチセット、ディナーメニューとほぼ1日中利用可能です。KOBOで焼き上げたパンが次々とレストランに運ばれてくるのも、当レストランの大きな特長といえるでしょう。 モーニングセットは8種類あり、ヘルシーなサラダセットやTHE CITY BAKERYのパンを使ったフレンチトーストなど、バラエティー豊かです。一例を挙げると、中東の朝食メニュー「シャクシュカ」(1000円)は、サルシッチャ(肉の腸詰)入りのトマトソースに卵を乗せてオーブンで焼き上げます。全粒粉使用の厚切りトースト付きで、プラス200円でドリンクセットにできます。 「マッシュルーム、ほうれん草のスモーブロー」(1300円)は、デンマーク伝統料理のオープンサンド「スモーブロー」をアレンジ。パンの上にマッシュルームクリームソース、ソテーしたほうれん草と舞茸、ポーチドエッグなどを乗せて提供します。 ディナーメニューは多国籍料理が60種類以上ディナーメニューは多国籍料理が60種類以上 ランチセットは16種類と豊富な上、パンの「盛り合わせ」のおかわりが自由です。メニューのひとつ「サブジ(チキン)」(1400円)は、インドで食されている野菜を炒めて煮た「サブジ」をアレンジしたもの。自家製ケバブスパイスをすり込んだチキンをスープ仕立てにした料理です。 ランチメニューの「ごどうふとビーンズのベジサラダ」 1500円。スープとおかわり自由のパンの盛り合わせがセット。ランチセットは、プラス250円で飲み物がつく(画像:フォンス)「ごどうふとビーンズのベジサラダ」(1500円)は、佐賀の郷土料理「呉豆腐(ごどうふ)」と野菜チップスやフルーツを散りばめた、彩りの綺麗なサラダ。スープ付きです。 ディナーメニューは、パンにピッタリなオリエンタルなメニューや、ラムチョップとランプの贅沢2点盛り、旬の白身魚など60種以上の充実のメニューが揃います。カジュアルな集まりから大切な人との会食や記念のディナーまで、さまざまなシーンで利用できることでしょう。バゲット、フォカッチャ、カンパーニュといった人気のパンの盛り合わせが、ひとり200円でおかわり自由です。 店内は、開放感ある心地よい空間が広がります。ニューヨークらしい、さまざまな国の料理を楽しめる上、美味しいパンもたっぷり。パン好きはぜひ一度、訪れてみてください。 ●THE CITY BAKERY(ザ シティ ベーカリー) 赤坂アークヒルズ ・住所:港区赤坂1-12-32 アーク森ビル 2階 ・営業時間:平日・土 7:00〜22:00、日・祝 7:00〜21:00 ・定休日:無休 ・アクセス:南北線「六本木一丁目駅」3番出口から徒歩1分、銀座線「溜池山王駅」13番出口より徒歩1分 ●THE CITY BAKERY BRASSERIE RUBIN(ブラッスリー ルービン) 赤坂アークヒルズ ・営業時間:朝/7:00〜10:00、昼/11:00〜17:00、夜/平日・土曜 17:00〜23:30(L.O.22:30)、日・祝 17:00〜22:00(L.O.21:00) ・定休日:無休 *住所、アクセスは上記に同じ。
- おでかけ
- 赤坂