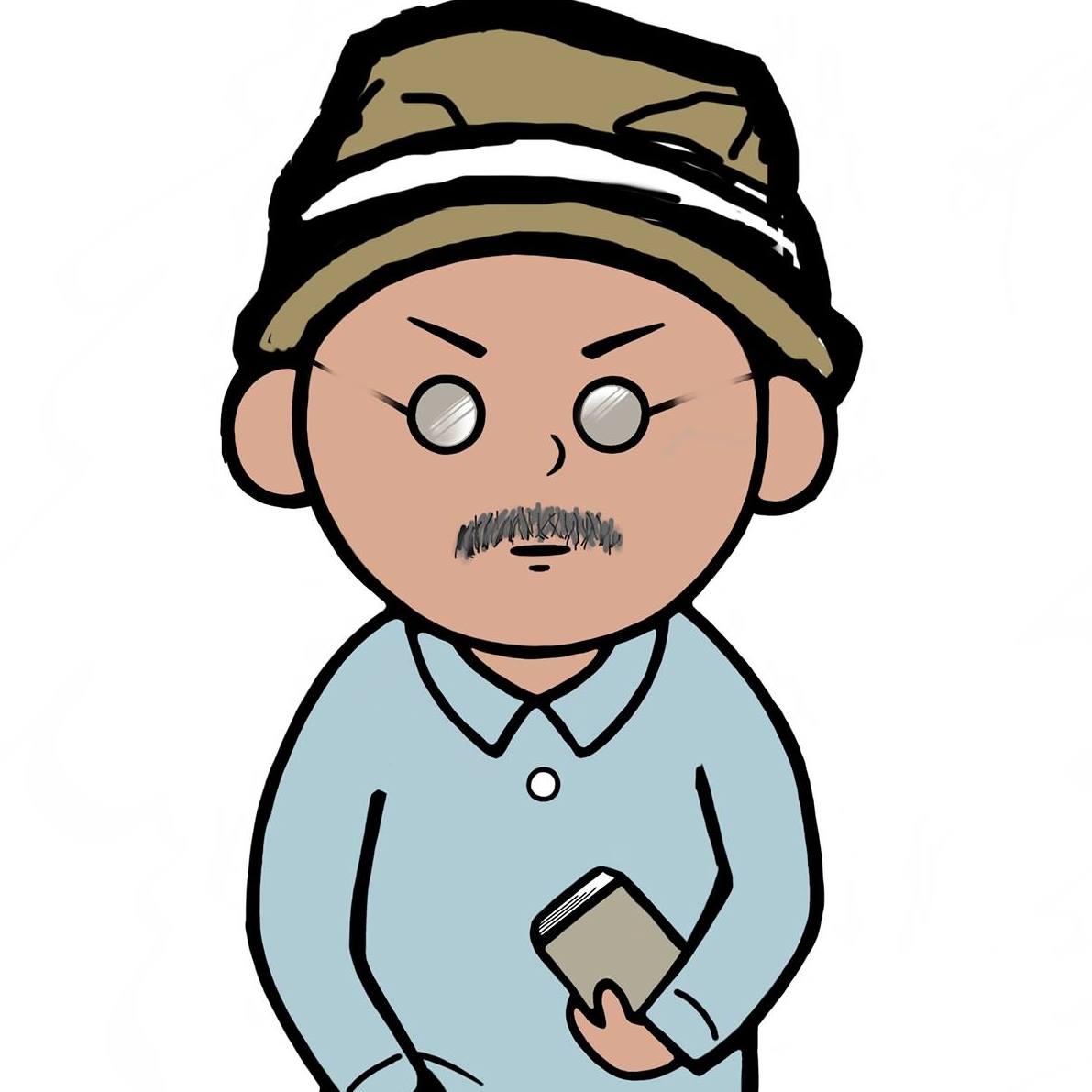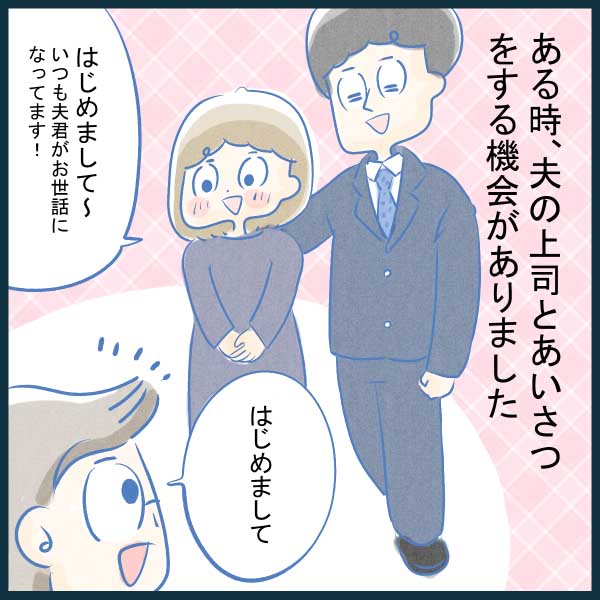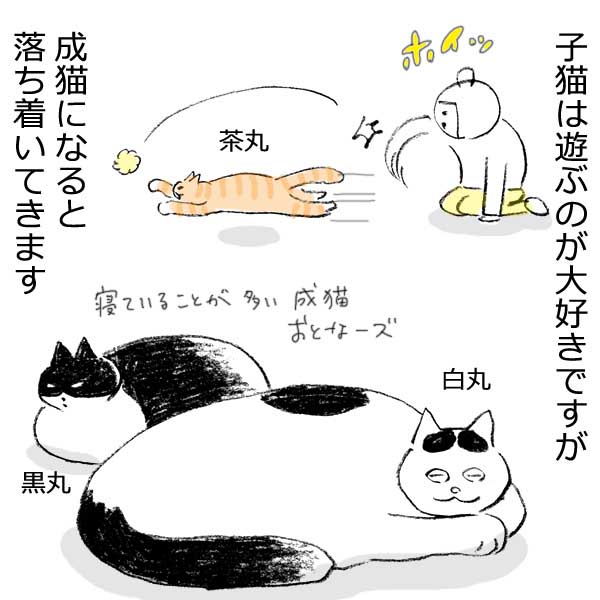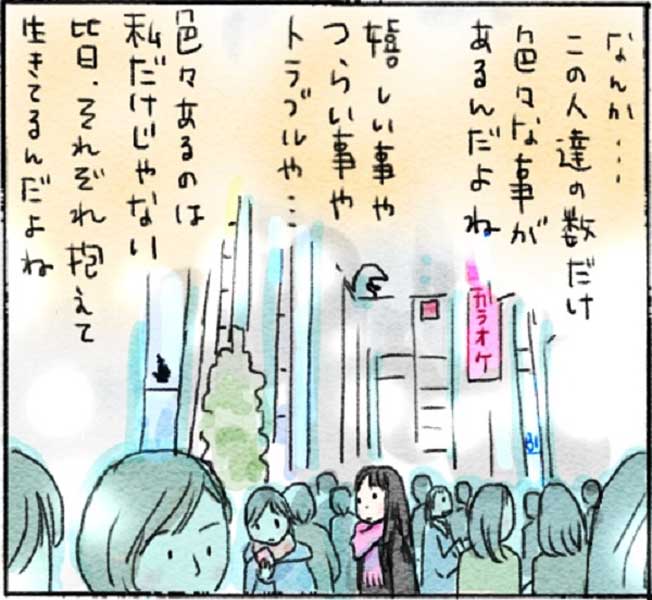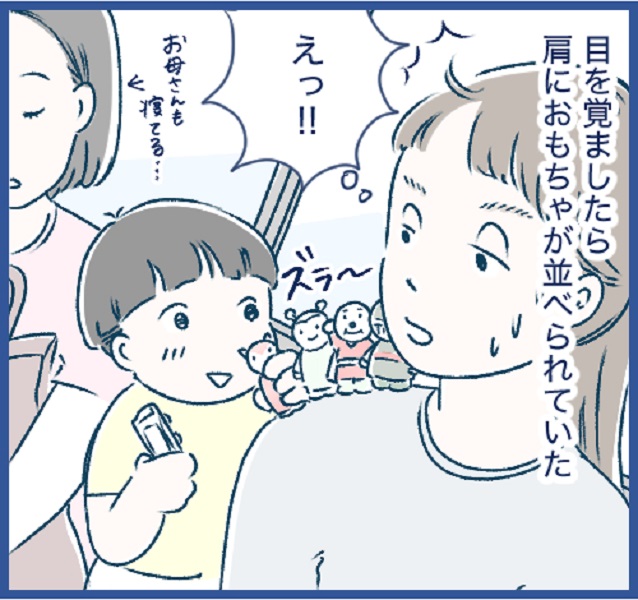食文化も立派な「コンテンツ」
コンビニ以外で、私がいつもおにぎりを購入するのは、自宅そばの「小島米店」です。このお店はもともと米屋でしたが、おにぎりを製造・販売するという事業拡張を行い、現在、練馬区に4店舗を構えています。
お米は富山県産のコシヒカリを使っています。小島米店はテイクアウト専門店ですが、東京はこのような、「米屋がおにぎり店を兼業する」ケースが増えています。おにぎりの生命線は、やはり米にあるからではないでしょうか。
 大きな口を開けてパクッと食らいつきたい(画像:写真AC)
大きな口を開けてパクッと食らいつきたい(画像:写真AC)
この背景には、一種の「おにぎりブーム」があるといっても過言ではありません。日本のソウルフードとしてのおにぎりは、いつの間にか家庭や行楽、運動会などの必需品から、サラリーマンの昼食としての需要も増加していると見ていいでしょう。
もちろん、中食(惣菜や弁当などを買って家で食べること)の役目も果たしているのではないでしょうか。またフランスを始めとして、海外でも徐々におにぎりブームは起きつつあります。
なぜ私がおにぎりについて書いているかというと、それは2017年に『おにぎりと日本人』(洋泉社)を上梓したからです。
当時は「コンテンツツーリズム」の書籍を数冊、書いた後でした。コンテンツツーリズムとは、地域に「コンテンツを通じて醸成された地域固有のイメージ」としての「物語性」「テーマ性」を付加し、その物語性を観光資源として活用することです。
私はふと、「食文化もコンテンツではないか」と考え、それが執筆の発端となりました。つまり料理を作る行為はクリエイティブなものであり、創作物の範疇に充分入るように思えたのです。
東京オリジナルのおにぎりは存在するの?
さて、東京独自のおにぎりというものは存在するのでしょうか。よく、江戸っ子は「親子三代、江戸生まれでなければならない」という話を聞きますが、そうであれば、純粋な江戸っ子の比率は極めて低い数字となるでしょう。
つまり、私が言いたいのは、現在の東京の文化は、流入してきた地方の人々の文化がミックスされたものであり、おにぎりも同様に考えてよいということです。
東京には、あさりの佃煮を使った深川めしをアレンジした「深川おにぎり」のような下町情緒あふれるご当地おにぎりももちろんあります。しかし、総じて「東京のおにぎり」は家庭のおにぎりの場合、出身地の特徴を受け継いでいるものと考えてよいでしょう。
ただ、食文化の古典的な文献である、江戸時代の『貞守謾考(もりさだまんこう)』によると、江戸のおにぎりは「円型」、もしくは「三角型」であり、使う海苔は「焼き海苔」だったとのことです。
関西は「俵型」が当時主流だったらしく、使う海苔も「味付け海苔」を使うことが多いといわれています。また関東では「おむすび」、関西では「おにぎり」と呼ぶ説もあります。
なお、2017年の総務省の家計調査によれば、一世帯当たりの「おにぎり・その他(赤飯、山菜飯)」の消費額の全国平均は4267円ですが、東京都区部は5202円で、第3位となっています。
東京都区部は過去の統計で第1位になったこともあり、一般的に見て全国平均より高い消費額になっています。29歳から49歳までの年代が、それ以降の年代より消費額が大きいのは、やはり昼食、中食で食べる機会が多いからかもしれません。
都内の名店「おにぎり浅草宿六」「ぼんご」「蒲田屋」
以前、浅草にある「おにぎり浅草宿六」(台東区浅草)が、おにぎり店で初めてミシュランの星を獲得したことが話題になりました。この店は1954(昭和29)年創業、東京で最も古いおにぎり店とのこと。まるで寿司屋のように、カウンター越しに目の前でおにぎりを握ってもらえます。
この店は新潟県産のコシヒカリを使っています。現在は三代目の経営ですが、具材は初代のときから変わっていないそうです。価格はコンビニのおにぎりより高価ですが、それでも名店としては決して高くはありません。
 あなたはどのようなおにぎりが好きですか?(画像:写真AC)
あなたはどのようなおにぎりが好きですか?(画像:写真AC)
大塚の「ぼんご」(豊島区北大塚)は1960(昭和35)年の創業。こちらもカウンター越しにおにぎりを握るスタイルです。米は新潟県産コシヒカリを使用、具材は55種類から選べます。価格は「おにぎり浅草宿六」よりも少し庶民的かもしれません。ここのおにぎりはまるで握っていないような、「ふわっと感」に特徴があります。
老舗でいえば十条の「蒲田屋」(北区上十条)が挙げられます。1963(昭和38)年に蒲田で和菓子店として出発。1969年に十条に移転し、そこからおにぎり店へ業態転換した歴史を持っています。テイクアウト専門店ですが、メニューは天むすを中心に40種類以上。価格は110円からとコストパフォーマンスが売りで、もちろん味の方もなかなかのものです。
駅構内やチェーン系も見逃せない
また東京は、JRや私鉄の駅構内でもおにぎり店が目立ちます。JR東京駅を中心に展開する、JR東日本グループの「ほんのり屋」が代表的なところでしょうか。チェーン展開する「おむすび権兵衛(ごんべい)」も私鉄駅構内に複数の店舗を出しています。
コンビニを含めれば、東京はおにぎり店が百花繚乱で、それぞれに具材に工夫を加え、切磋琢磨しているといっても過言ではありません。なかでも地方色豊かな具材に力を入れているところも多いです。
そういえば、JR品川駅構内にある「おむすび百千(ももち)」は47都道府県のおにぎりが楽しめる店です。品川駅のほか、JR東京駅や阿佐ヶ谷駅、都営地下森下駅にあります。『おにぎりと日本人』の執筆時に、47都道府県のおにぎりをすべて購入して、食べた記憶があります。2日がかりでしたが、今となっては笑えるような、懐かしい思い出です。
そういう意味では東京は老舗や米屋、チェーン店、コンビ二などを通して、多様な商品が楽しめる「おにぎりワンダーランド」なのかもしれません。