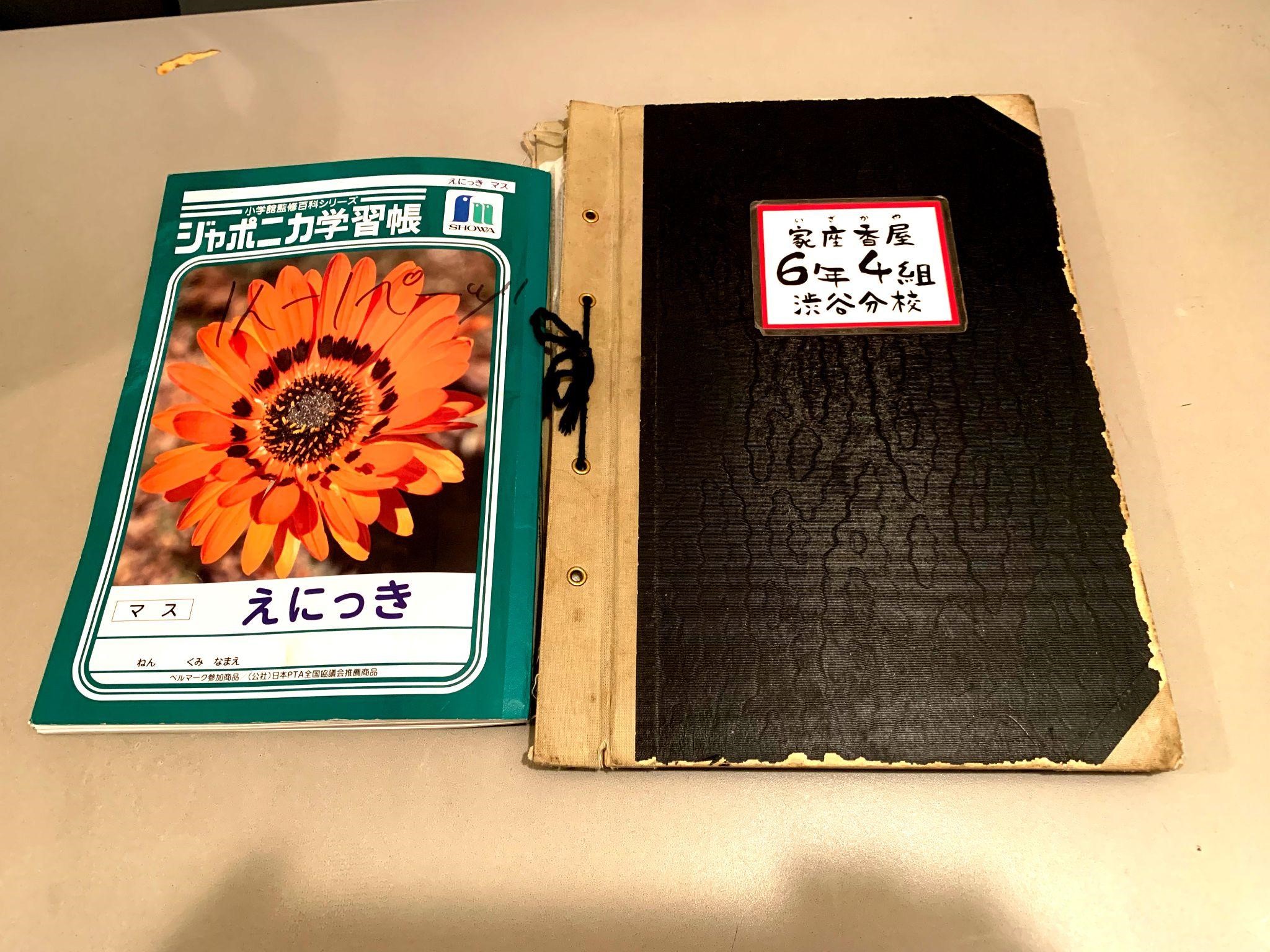東京・晴海に突如出現! 謎の建物「東京鰹節センター」とは何か
事務所っぽい外観 東京23区内で人の少ない地域として、まず思い浮かぶのは湾岸地域です。中でも中央区の晴海かいわいは都心からさほど離れていないにもかかわらず、「3密」を避けられるお勧めのエリアです。 晴海は東京2020オリンピックが延期になったことで、今後の発展がどうなるのか注目されています。2019年には、隈(くま)研吾建築都市設計事務所(港区南青山)がデザイン監修した国産材を用いた「CLT PARK HARUMI」が晴海通り沿いに完成。地域の名所となっていました(9月30日閉館)。 CLTとは「Cross Laminated Timber」の略称で、挽き板を並べた後に繊維方向が直交するよう積層接着した木質系材料のことです。 ちなみにこの施設の跡地は、年末時点ですっかりさら地になっていました。 さて、そんな晴海で年末に散歩を楽しんでいたところ、年越しそばや鰹(かつお)節を売っている店を発見しました。いや、店というより事務所の一角を使って販売しているようなイメージでしょうか。 建物の上を見れば、「東京鰹節センター」と書いてあります。みそ汁や各種の料理の出汁に欠かせない鰹節ですが、御飯にしょうゆと一緒にかけて食べるだけでも格別。そこにマヨネーズを加えた日には、おかずがなくてもご飯が何杯も食べられます。 89の鰹節問屋が集結89の鰹節問屋が集結 ここはそんな鰹節愛好者の集まるビル……ではありません。東京鰹節類卸商業協同組合に加盟している89の鰹節問屋が集まった、日本有数の鰹節のセンターなのです。 中央区晴海3丁目にある東京鰹節センター(画像:(C)Google) センターの敷地内には、同じく中央区の佃にある住吉神社の分社・住吉神社晴海分社(中央区晴海3)があり、ここの石碑には東京鰹節センターのできる経緯と、分社が築かれた経緯が簡潔に記されています。 これによれば、分社はもともと日本橋小舟町の「東京鰹節荷捌所」に祭られており、晴海に移転してきた際に一緒に移したようです。 東京における鰹節業界の歴史 1935(昭和10)年に築地市場が開設されるまで、魚市場は江戸時代から長きにわたり日本橋かいわいにありました。そのため、日本橋には海産物を扱う問屋が数多く集まっていました。 日本橋小舟町には多くの鰹節問屋があり、別名は「鰹河岸」。江戸時代初期の鰹節は高級品で、上納品や貢ぎ物として上流武士の間で使われていましたが、次第に庶民の食材として普及、業界も発展していきました。 明治になると、問屋によって東京鰹節問屋組合(現・東京鰹節類卸商業協同組合)ができ、昭和になると合同入札場も設けられます。この合同入札場は水産加工品メーカーのにんべん(中央区日本橋室町)が土地を購入し、組合に寄付したものでした。 日本橋小舟町(画像:(C)Google) こうした東京の鰹節業界の発展は、江戸から続く鰹節問屋で大番頭まで勤め上げた稲葉美二さんによる『東京鰹節物語』(チクマ秀版社、2001年)で詳細に語られています。筆者と同じく、晴海をぶらぶらしていて「東京鰹節センターとは?」と思った人にはオススメの本です。 一般購入も可一般購入も可 こうして長らく日本橋小舟町を拠点としていた鰹節問屋ですが、1971(昭和46)年に晴海へとやってきました。 東京鰹節センターは単に鰹節問屋が集まっているだけではなく、入札場もある業界では重要な施設です。東京の海産物の入札場といえば大森海苔会館(大田区大森中)が知られていますが、こちらも重要な場所です。 『東京鰹節物語』(画像:チクマ秀版社) とはいえ一般消費者には関係ないのかと思いきや、そうではありません。年越しそばを売っていたお店に聞いたところ、普段から小売りもしているといいます。普段から商品を並べて小売店のように陳列しているわけではありませんが、事務所に声をかけたら売ってくれるそうです。 1971年に建てられたセンターは既に風格のある建物となっていますが、最近では発展に合わせて周辺の土地と一体の再開発計画も進んでいるとのこと。そうなると周囲を歩いているだけで、鰹節の匂いがしてくる現在の姿は見られなくなるかもしれません。散歩するなら、今のうちがオススメです。 なお、筆者は年越しそば(出汁パックとかえし付き)を購入し、不安な年末年始を楽しく過ごせたことはいうまでもありません。
- おでかけ