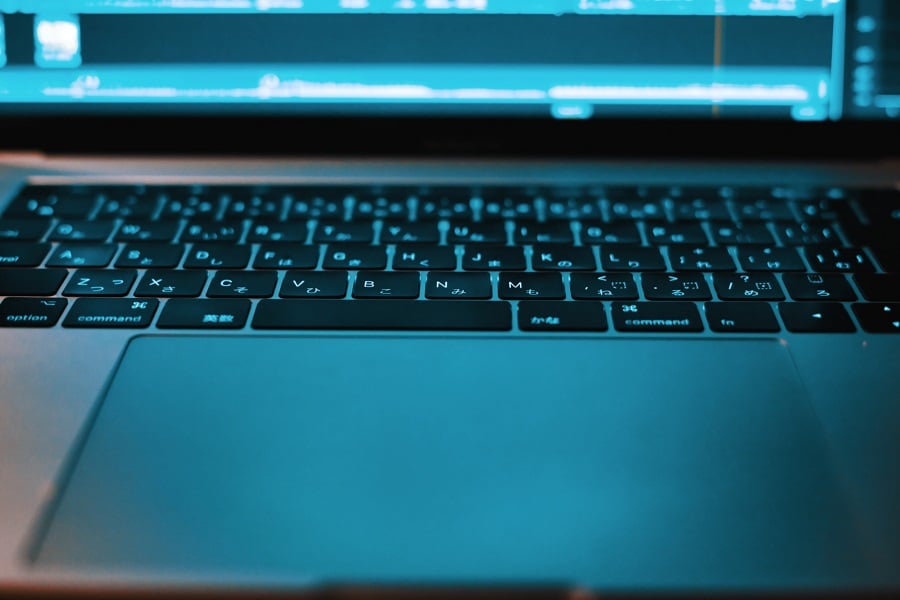コスプレファンも注目? 高輪にある、日本でたったひとつの「物流」専門博物館とは
企業が運営し、自社の活動や技術を紹介する博物館を「企業博物館」と呼びます。全国の博物館や美術家に詳しいライターの浦島茂世さんが、物流博物館の魅力や楽しみ方を紹介します。大人の方がハマる!? 企業博物館が面白い! 東京にはさまざまな博物館がありますが、そのなかには、企業や団体が運営をしている、通称「企業博物館」があることをご存知ですか? この企業博物館、子どもはもちろん、大人もたっぷりたのしめる施設なのです! 巨大な物流ジオラマは圧巻!全てが精密に作られているので、全貌を把握するまでが大変(画像:物流博物館) JR・京浜急行の品川駅から徒歩7分、住宅地のなかにある物流博物館(港区高輪)は、大人もテンションが上がる企業博物館のひとつ。 その名の通り「物流」に関する資料を収集し、研究・展示する博物館です。日本通運株式会社の企業博物館で、利用運送振興会(港区東新橋)が運営しています。 その歴史は長く、もともとは大手町の日本通運本社内に1958(昭和33)年に創設された「通運史料室」が基礎。その後、移転や運営母体の移管などを経て、1998(平成10)年に現在の「物流博物館」になりました。つまり、50年以上もの歴史がある博物館です。 そもそも日本通運は、明治時代に運送事業を行っていた内国通運をはじめ、複数の同業者が合併してできた運送会社。そのため海運、トラック、貨物列車などあらゆる運送手段が大得意です。現在に至るまで日本全国はもとより、世界に広がる物流を担っていました。 博物館には、この日本通運の歴史的資料に加え、江戸時代の飛脚屋の看板や枕、未開梱の昔の荷物、さらには、アマゾンの倉庫で現在バリバリに活躍中のロボットの実物大模型まで、物流に関する資料がたっぷりと並んでいます。 写真資料は約10万点 現在、博物館が収蔵・管理する史料は、文書史料約6000点、美術工芸資料約200点、実物資料約1000点、映像資料約200点、そして写真資料がなんと約10数万点! 写真資料が非常に多いのは、かつて日本通運が社内報の取材のため、各地の営業所を訪れたカメラマンに「できるだけいろいろな写真を撮ってくるように」という指示を出していたため。昭和30年代からの駅舎やトラック、荷さばき場などの写真がたっぷりと撮影されていたのだそうです。 当時はそれほど珍しくない日常の現場風景が記録された写真ばかりでしたが、現在あらためて見てみると、本当に貴重な写真ばかりです。この一部は物流博物館のサイトでも見ることができます。 大人気のコスプレコーナー そんな博物館のなかで、一番の見どころは、「物流の24時間」が分かる、150分の1スケールの動くジオラマ模型。24時間が4分ほどに圧縮され、ガントリークレーンで運ばれるコンテナ、高速道路を走るトラック、貨物を積み込む飛行機など、休みなく動いている様子を眺めることができるのです。 そして、土日になると順番待ちになることもあるという大人気コーナーが「変身キットコーナー」。 日本通運だけでなく、ヤマト運輸や佐川急便、JR貨物にDHLなどなど、さまざまな物流関連会社のユニフォームが勢ぞろい(画像:物流博物館) このコーナーでは日本の主要物流会社のユニフォームを着用できるのです!これは、子どもだけでなく大人にも大人気。 ちなみに、私が個人的に非常に気になったのが、日本通運の通常部門と、美術品輸送専門スタッフとのユニフォームのデザインの違いです。 美術品輸送のユニフォームは、作品を傷つけないよう、余計なポケットなどがありません。さらに、美術品スタッフは、作品に汗が落ちないように、夏でも長袖が義務付けられているのだそうです。 このほかにも、日本通運が昭和20~50年代に企画した映画作品の視聴ができます。昭和35年(1970年)に開催された大阪万博の映像資料などは、当時のファッションや流行なども分かるので見ているだけで楽しくなってきます。 物がどのように運ばれているのか仕組みや歴史を知っておくと、何気なく頼んだ通販の品物も、たくさんの行程を経て我が家にやってきていたことが分かります。 夏休みは、ダンボール工作コーナーなどのイベントも開催されるそう。物流博物館で楽しく学んでみてください。
- おでかけ