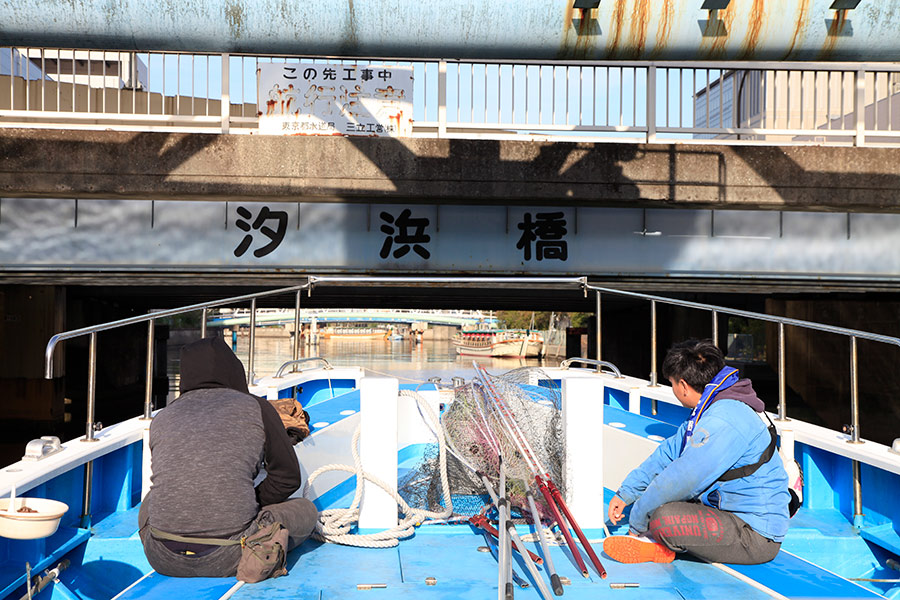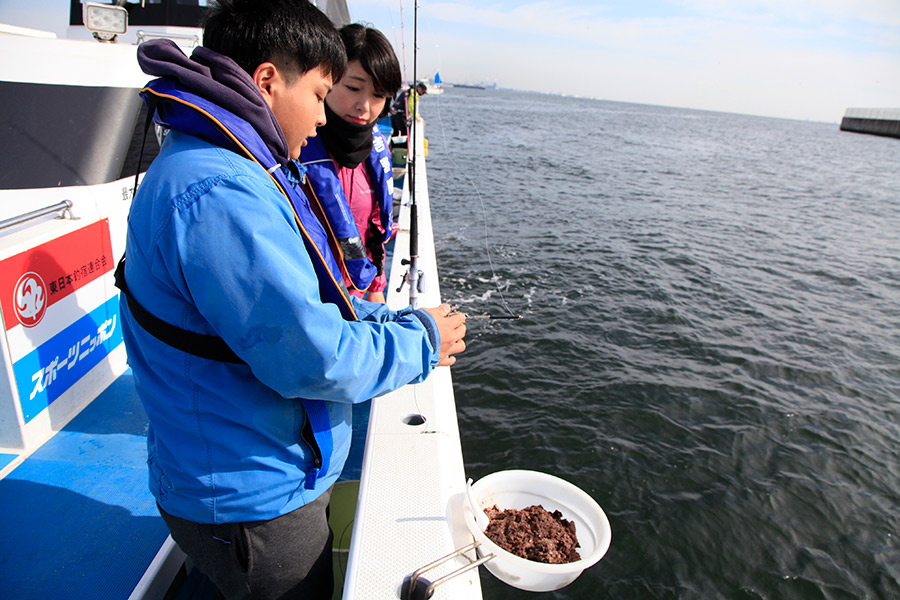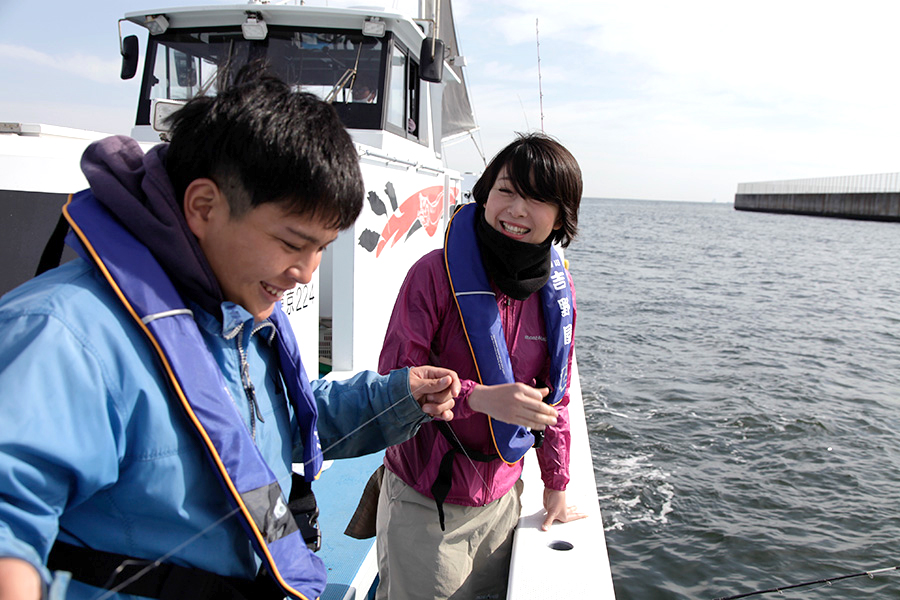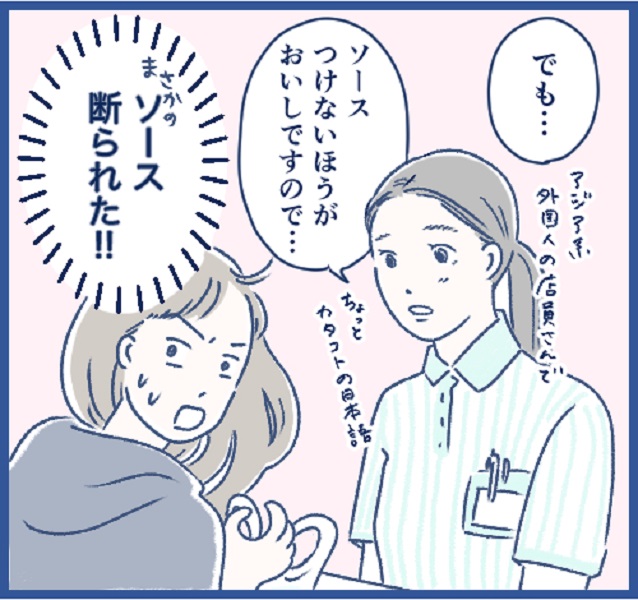5500万人が愛した「葛西臨海水族園」が大ピンチ 老朽化や経営を口実に「都民の財産」を破壊していいのか?
開業のきっかけは都庁の移転問題 2017年に上野動物園(台東区上野公園)で誕生した赤ちゃんパンダ・シャンシャンは、その愛くるしい姿から東京都のみならず日本全国から熱い視線を集め、一般公開が始まると上野動物園のパンダ舎は連日にわたって黒山の人だかりとなりました。 シャンシャンフィーバーに沸く上野動物園は東京都が所管し、東京動物園協会(台東区池之端)に運営が委託されています。同協会が運営を委託されている動物園と水族館は、そのほかに多摩動物園(日野市程久保)、井の頭自然文化園(武蔵野市御殿山)、葛西臨海水族園(江戸川区臨海町)などがあります。このうち、上野動物園と葛西臨海水族園のふたつが東京23区に立地しています。 大きなガラスドームが特徴的な葛西臨海水族園は、世界遺産として知られるインドのタージ・マハルを彷彿とさせるデザイン(画像:小川裕夫) 葛西臨海水族園は、1989(平成元)年に葛西臨海公園内にオープンしています。当時、東京都庁舎は有楽町にあり、老朽化していたことから移転問題が議論されていました。 西新宿に都庁舎が移転することが決まると、東京の東側が廃れてしまうという心配があがり、その対策から墨田区の江戸東京博物館、足立区の東京武道館などが竣工されることになったのです。江戸川区につくられた葛西臨海水族園もその対策のひとつです。 葛西臨海水族園は、その名前が示す通り単なる水族館ではありません。眼前に臨む東京湾、そして広々とした公園と緑とが一体化していることが条件として求められました。その大役として、白羽の矢が立てられたのが建築家の谷口吉生さんです。 谷口さんの父・谷口吉郎は東宮御所や帝国劇場、千鳥ケ淵戦没者墓苑など数々の名建築を設計した「建築界のスーパースター」といえる存在です。息子の吉生さんもニューヨーク近代美術館やGINZA SIX(中央区銀座)を設計した、世界に名を轟かせる大建築家として知られています。 訪日外国人観光客も増加訪日外国人観光客も増加 葛西臨海水族園にはオープン以来、5500万人以上が来園。都民のみならず、千葉県や埼玉県といった近隣県からも多くの来園者を集めています。 赤い目印が葛西臨海水族園(画像:(C)Google) また、最近では葛西臨海公園とセットで水族園を楽しむ訪日外国人観光客が増えており、葛西臨海水族園の訴求力には大きなものがあります。 葛西臨海水族園はペンギンやマグロの展示などで人気を集めていますが、谷口さんが設計したデザイン性も高い評価を受けています。特に、建築関係者や水族館関係者、公園関係者などからは「水族館のお手本」のような存在として語られる存在です。 水族園改築の方針を発表した東京都 しかし、東京都は葛西臨海水族園を改築する方針を発表。2017年12月、有識者による葛西臨海水族園のあり方検討会を発足させました。そして、全5回にわたって議論してきましたが、同委員会には建築に知見を有する専門家がいませんでした。 そうした指摘を受けて、2019年1月に建築の専門家を加えた葛西臨海水族園事業計画検討会が改めて発足しています。 しかし、新たな検討委員会はゼロベースで話が進められたわけではありません。あくまでも、先の検討委員会での議論を踏まえて、そこから話が進められています。 現在の議論では、葛西臨海水族園の隣接区域に新たな建物をつくり、そこに水族館機能を移すとしています。谷口さんが設計した現行の建物について、東京都は今後どのようにするのか明らかにしていません。 1978(昭和53)年3月に発行された地図。カーソル周辺が現在の葛西臨海水族園のある場所(画像:時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕) 建築物には、設計者に著作権が認められています。雨漏りの補修や耐震化といった実用的な改修には、著作権者の許可が不要です。 一方、水族館として使用している建物を別の用途に転用するような文化的改修には、著作権者の許諾が必要になります。所有者である東京都といえども、自己都合で葛西臨海水族園に手を加えることはできないのです。 しかし、それはあくまでも改修における話に過ぎません。仮に老朽化や経営を口実に建物すべてを取り壊す場合、著作権は関係ありません。所有者、つまり東京都の判断だけで工事を進めることができるのです。 水族館の意義、娯楽でなく教育との声も水族館の意義、娯楽でなく教育との声も オープンから30年が経過した葛西臨海水族園は、経年劣化した箇所があちこちにあります。また、昨今は近隣のすみだ水族館をはじめ、各地に水族館がオープンして競合相手も増えています。 葛西臨海水族園の遠景。両サイドに植えられた木々も葛西臨海水族園に必要不可欠なものとして設計されている(画像:小川裕夫) そのため、葛西臨海水族園も大型化・最新化して集客力を強めるべきという意見もあります。しかし、水族館はアミューズメント(= 娯楽施設)ではなく、ミュージアム(= 教育機関)であるという考え方から、集客力やエンターテーメント性を強化する方針に懐疑的な意見もあります。 いずれにしても、都民の財産でもある葛西臨海水族園の議論は広く周知されているとは言い難い現状です。
- 未分類