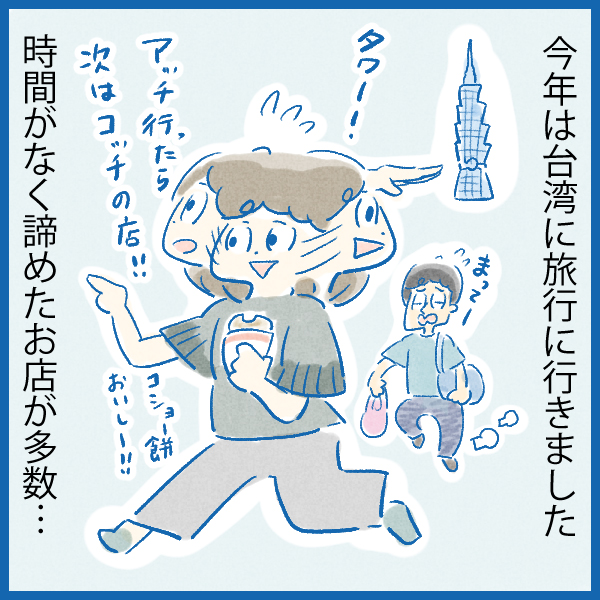FP(ファイナンシャルプランナー)は、昨今の不安定な社会情勢においては、お金に関するプロとして特に需要が高まっています。「FPに関する勉強を始めたい」「世界で活躍できるFPになりたい」と思っている人は、CFPの資格を取得することはおすすめです。
CFPとは、国際CFP組織FPSB(Financial Planning Standards Board)との、ライセンス契約のもと、世界最高レベルのファイナンシャル・プランニング・サービスを提供できる、専門家であることを証明する資格です。
本記事では、CFPの資格の概要や難易度、FP1級との違いについて解説しています。試験の受験資格や受験に必要な費用、合格までに必要な勉強時間についても紹介していますので、今後、CFPの資格にチャレンジしてみてたいと考えている人は、ぜひ参考にしてください。
※本記事はアーバンライフメトロが独自に記事を制作し、スクール紹介にはアフィリエイトプログラムの協力をいただいています。
CFPとはどんな資格?
CFPとは、「Certified Financial Planner」(サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー)の略称で、認定ファイナンシャルプランナーと訳され、国際資格と位置付けられています。現在、世界25の国と地域において、CFP資格が導入されており、FPの頂点として権威を持ちます。
そのため、この資格を有していれば「世界中で通用する金融知識を持っている」とみなされ、顧客からの信頼を獲得できる範囲が広がる可能性も高まります。
実際に、米国などFP認知度の高い国では、CFP資格は特に信頼されるライセンスとして認知されており、公認会計士や弁護士と同じくプロフェッショナルな資格として高く評価されています。
CFPのレベルは、FP1級とほとんど同水準で、全世界に通用します。そのため、海外で仕事をしたい人や、外国人顧客をターゲットにした仕事に就きたいと考えている人には、ピッタリの資格となっています。
CFP資格審査試験について
CFP資格取得にあたっては、当然のことながらCFP資格審査試験に合格する必要があります。この試験は誰でも受けられるものではなく、一定の条件をクリアしている人のみが受けられます。
受験地区は全国16会場に指定されていて、2日間をフルに使って、六 受験地区は全国16会場に指定されていて、2日間をフルに使って、六つの課目をこなしていかなければなりません。ここからは、そんなCFP資格審査試験の概要について見ていきましょう。
試験の受験資格
CFP資格審査試験を受験するためには、次の2つを満たしている必要があります。
- 日本FP協会認定のAFP認定者であること
- 所定の大学院で単位を取得していること
なお、出願後にAFP認定者が一般会員に移行した場合や協会を退会した場合は、受験資格が消失し、これまでのCFP試験の課目合格歴は、すべて失効となりますのでご注意ください。
CFP資格審査試験の日程と内容
CFP資格審査試験は、例年6月と11月の年2回実施されます。試験は6月も11月も2日ずつ、1週間のインターバルをおいて行われます。試験課目は、1日目が「金融資産運用設計」「不動産運用設計」「ライフプランニング・リタイアメントプランニング」の3課目で、2日目が「リスクと保険」、「タックスプランニング」「相続・事業承継」3課目です。試験時間は1課目につき120分です。全ての課目を一度にクリアしなくても大丈夫なのがCFP試験の特徴で、1年のなかで2課目ずつ3回もしくは3課目ずつなど、ご自身の都合に合わせて受験できます。
受験に必要な費用
CFP資格審査試験の受験に必要な費用は、以下の通りです。
| 受験出願科目数 | 1課目 | 2課目 | 3課目 | 4課目 | 5課目 | 6課目 |
|---|
| 受験料(税込) | 5,500円 | 9,900円 | 14,300円 | 18,700円 | 23,100円 | 27,500円 |
1課目のみ受験する場合は5,500円(税込)ですが、同時に2課目以上を受験した場合、1課目毎の値段が2課目目からは4,400円(税込)になります。そのため、6課目全部まとめて受験をしたほうが、1課目ずつ受験するよりも、2課目目から各1,100円も費用を抑えることができます。最大で5,500円分の費用を抑えられるのは魅力的ですよね。
ただし、これはあくまでも、6課目全てを受験して、全課目合格した場合の費用です。6課目全てに申し込みをし、1課目でも落としてしまった場合は、その1課目分の費用5500円を再度払って再受験することになります。
そのため、なるべく費用を抑えたい場合は、受験した課目は全て合格することが重要です。自分のペースをよく知り無理をしすぎず受験を進めていきましょう。
合格後にCFP認定を受けるための手順
合格後にCFP認定を受けるためには、以下1~4の要件を満たす必須となります。
- CFP資格審査試験全6課目に合格
- CFPエントリー研修の受講・修了
- 実務経験申請
- CFP資格登録申請
CFPエントリー研修とは、CFP資格審査試験合格者を対象に、年に2回実施される研修です。この研修は例年、試験合格発表後に実施されており、合格日の10年前から資格認定日までの間に、通算で3年間以上実務経験を積んでいることが、要件となります。実務経験年数が足りなくても実務経験とみなされる業務や実務経験の代わりに受けられる研修もありますので、確認してみましょう。
研修の申し込みは、CFP資格試験全6課目合格後より、Myページの「CFP資格認定手続き」から申請できます。
CFP認定を受けた後の活用方法
CFPの資格を持っていれば、国内外を問わず優秀な金融コンサルタントとして認めてもらえるため、さまざまな仕事に従事できる可能性が限りなく高くなります。特に、グローバル化が進んだ昨今においては、外国人顧客から金融に関する相談を依頼されるケースも少なくありません。そうした場合、CFP資格を所持していることで、十分なスキルを有していることが自動的に証明されるので、顧客からの信頼や評価を勝ち取りやすくなるのです。
CFP試験の難易度・合格率
CFP試験を受験するうえで気になるのが、試験の難易度や合格率だと思います。ここからは、CFP試験の難易度・合格率を分かりやすくリスト形式で説明します。受験すべき順序や合格までに必要な勉強時間についても触れていますので、ぜひ参考にしてください。
難易度と合格率
CFPは、「金融資産運用設計」を筆頭に「不動産運用設計」や「リスクと保険」、「ライフプランニング・リタイアメントプランニング」そして「タックスプランニング」、「相続・事業承継」の6課目すべてに合格しなければ取得することができません。全課目一括受験での合格者は、各回10〜30名ほどで、合格率はおよそ5〜10%です。
これだけを見ると、かなり難しい試験だと思われがちですが、各課目の合格率は平均30%〜40%ほどであり、ひとつひとつの課目の合格率は、そう低いものではありません。難易度としては、行政書士や社労士と同等か少し優しい程度といえるでしょう。
それぞれの課目の実際の合格率は以下の通りです。
| 課目名 | 合格率 |
|---|
| 金融資産運用設計 | 37.0% |
| 不動産運用設計 | 35.4% |
| ライフプランニング・リタイアメントプランニング | 38.3% |
| リスクと保険 | 41.0% |
| タックスプランニング | 37.5% |
| 相続・事業承継 | 35.0% |
受験すべき順序
CFP試験をどの順番で受験していくか迷った際は、前述した合格率を参考に合格しやすそうなものから進めていくのも手ですが、どの課目も合格率にそれほど差があるとはいえません。
そのため、合格できそうなものから進めていくという方法がおすすめです。合格できそうな教科を判断する際には、自身のこれまでの経歴を参考にするのが役立ちます。例えば、金融関係の会社に勤めている人は、、普段見聞きすることの多い言葉や計算などが多い「金融資産運用設計」であれば、その他の課目と比べて、比較的簡単に覚えられるはずです。また、保険関係の会社に勤めている人の場合は、「リスクと保険」の課目が最も取り組みやすいといえます。反対に、ファイナンシャル・プランナーに関する仕事をしたことがない人であれば、言葉の難易度が低い「ライフプランニング・リタイアメントプランニング」から進めると良いでしょう。
テキストや問題集・過去問などを確認しながら、「自分が一番取り組みやすい課目は、どの課目なのか」をはっきりさせ、受験すべき順序を検討してください。
合格までに必要な勉強時間
CFP試験合格までに必要な勉強時間は、約500時間~600時間を要するといわれています。もちろん、人によって個人差があるため、一概にこの時間が必ずしも必要とは言い切れませんが、平均するとこれくらいの時間がかかります。また、各課目ごとにかかる勉強時間は、平均80時間~120時間です。独学で勉強する場合には、さらに勉強時間が必要となるでしょう。試験当日から逆算して、余裕を持った学習スケジュールを計画することが大切です。
CFPとFP1級、どっちを取るのがよい?
CFP試験の受験を検討している人のなかには、「FP1級とCFP試験、どちらを受験する方が良いのだろう?」と悩んでいる人もいるかと思います。ここからは、そういった人のために、FP1級とCFPの違いについて紹介します。
民間資格と国家資格
両者の違いではじめに挙げられるのが、「民間資格」か「国家資格」かという点です。CFP資格は、民間資格であるのに対し、FP1級は、国家資格です。また、FP1級は日本国内限定で有効な資格である一方、CFP資格は、国際的にも通用する資格です。
このように資格の属性で多少違いが見られますが、難易度やランクとしては、おおむね同等となっています。どちらの資格を有している方がベストなのかは、自身の所属している企業や将来的なキャリアプランによって変わりますが、どちらにしても高いスキルを持っているという証明になるのでご安心ください。
継続的な学びの必要性
FP1級は、一度合格すれば、その後は定期的に試験を受けずとも資格を維持することができます。一方、CFPは、資格取得後も単位を取得する必要があるため、継続的に学び続ける必要があります。つまり、CFPはFP1級よりも、「知識を維持し続ける仕組み」が整えられているといえます。
FP1級やCFPに限らず、資格というのは、一度取得してしまうと、その後は学びを止めてしまいやすいものです。その点、CFPでは、資格の維持のために、学び続けなければならないため、知識が衰えてしまう心配がありません。特に、ファイナンシャル・プランナーが携わる金融・不動産、国の制度などは、常に変化を続けます。そのため、CFPの、「生涯をかけて知識を吸収できる体制」という点に魅力を感じられる人は、CFPのほうが適しているといえます。
試験面での違い
CFP試験は、1課目ごとの受験が可能です。加えて1課目ずつの合格率が30%前後と高く、初めて挑戦する人でも、比較的合格しやすい試験となっています。それに対して、FP1級は、一度に全課目分の合格が資格取得の必須条件です。その影響もあり、FP1級試験の学科試験の合格率は、毎回10%前後ほどと低く、一発合格できる人はごく少数であるのが現状です。何年か継続して受験し、やっと合格できたという人は決して珍しくありません。
また、CFP試験に合格できた場合は、FP1級の学科試験が免除となります。このような理由から、両方の資格取得を目指している人は、CFPを先に取得したほうが、効率的に合格につなげられます。
どちらを受けるべきか
どちらも役立つ仕事であり、難易度も同程度ですが、国際的に活躍できる点を鑑みると、CFPの資格取得がおすすめです。また、両方の資格取得を目指している人は、まずCFP試験に挑戦したあと、FP1級を取得すると効率がより良いといえます。
CFP合格のためのおすすめ通信講座3選
| 会社名 | LEC | TAC | FKP研修センター |
|---|
| 画像 |  |  |  |
| 特徴 | 知識を取得する「インプット学習」、実践力を身につける「アウトプット学習」、本試験をシュミレーションする「公開模擬試験」の3ステップ学習で確かな実力を養成 | 経験豊かな実務家、受験指導のプロが揃っている | FP専門校。過去5年分の試験を1冊に収録。過去の試験の約8割を占める過去問題を完全マスター |
| コース/料金 | 2022年11月向け:CFPパック(6課目一括)・通信 118,250円 | cfp1年本科生 web通信講座 174,000円 | 強力合格コース(FRK教材フルセット)1課目 28,000円6課目 166,000円
基本テキストコース(独学でバッチリ合格)1課目 13,500円6課目 79,000円 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
まとめ
今回は、CFPの概要や難易度、FP1級との違いについて、お伝えしてきました。
CFPはFP1級に同等する、認定ファイナンシャルプランナーと訳される国際資格です。CFP資格審査試験を受験するためには、「日本FP協会認定のAFP認定者である」という受験資格を満たしている必要があり、試験は原則として年に2回実施されます。CFPの各課目の合格率は平均30%〜40%程と決して難しくなく、1課目ずつ受験することもできるため、初心者でも十分に合格が狙えます。
また、CFPの資格は、MBAに相当するため、資格を有しているだけでレベルの高いFPとして認定されます。特に、アメリカではCFPはFPの専門家として高い地位付けにあるため、CFPを取得していることで、ビジネスチャンスが広がります。
仕事の幅を拡大したい人や将来的に役立つ資格を取得したい人、ゆくゆくは海外で仕事をしてみたい人は、ぜひCFP試験に挑戦してみてはいかがでしょうか。本記事が少しでも、CFP試験への挑戦を検討している人の参考になれば幸いです。