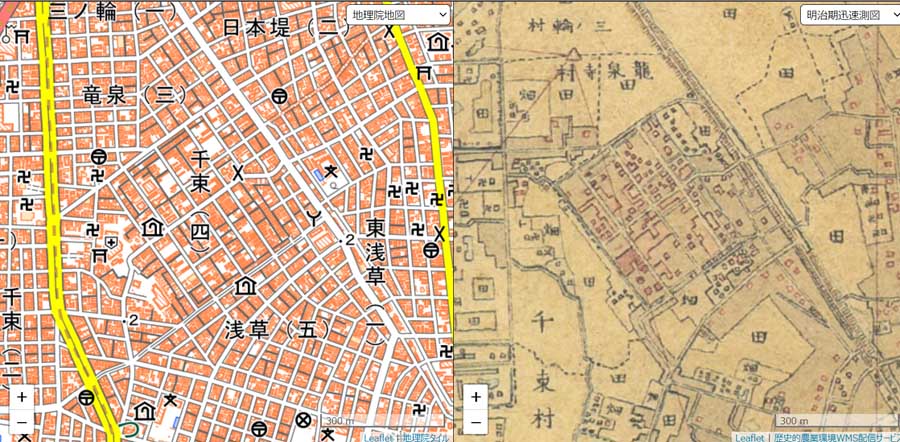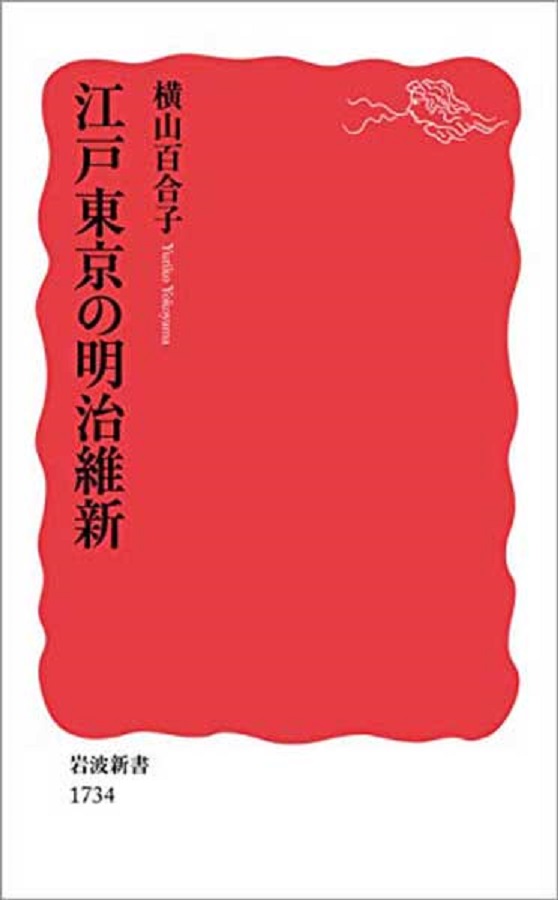小籠包と鯛焼きの「うるわしき化学反応」 戸越銀座商店街を食べ歩く
グルメ漫画家の杏耶さんが、以前から気になっていたという「戸越銀座商店街」で食べ歩きを満喫。イラスト付きでレポートします。友達にススメられた戸越銀座へGO! 東京に越してきて2年、グルメ漫画を描いている漫画家の杏耶(あや)と申します。 いつもは引きこもり気味な私ですが、締め切り明けはその反動なのかフラッと街へ出て食べ歩きをするというのがここ最近のパターンになっています。 そんな話を友人にしたところ、「それならここがおススメだよ」と教えてもらったのが戸越銀座商店街(品川区戸越)。気になってはいたものの、なかなか行けずじまいだったのです。 そして、とある仕事の締め切りを乗り越えた2019年の晩秋、ついに念願を叶えることができました。 やってきました、戸越銀座商店街(画像:杏耶さん制作) 思っていたより自宅の最寄り駅から近い場所にあることが分かったので、財布とスマホ、交通系電子マネー「PASMO」だけ持って家を出ました。初めて降り立った東急池上線・戸越銀座駅(品川区平塚)は、木材の暖かさを感じる駅舎でほっこりにっこり。 そんなこんなで意気込んで、さっそく街歩きスタートです。 全長1.3kmのロングロング商店街全長1.3kmのロングロング商店街 何でも戸越銀座は東京で一番長い商店街なのだそう。そして食べ歩きしたくなるものが、ものすごくたくさんあった、あり過ぎた……。 私事なのですが、食べ歩きをするときはいつも予算を1000円ぐらいに納めるというマイルールを実践しています。 気になるものばかり、「食べ歩きの聖地」(画像:杏耶さん制作) なぜかというと、あんまりたくさん食べ過ぎて、どれがどんな味だったか忘れてしまわないようにするため。それから「買えるのは1000円まで」と決めることで自分なりに食べるメニューを厳選するため。そしてもちろん、食べ過ぎ防止の意味もあります。 それなのに今回は、まんまと1000円以上食べてしまったのです。そんな「犬も歩けばうまいもんに当たる」状態の戸越銀座のなかで、とくにおススメしたいものを4つご紹介します。 もちもち、カリカリ、小籠包!もちもち、カリカリ、小籠包! まずは友人にもおススメされた中華料理店「龍輝(りゅうき)」の焼き小籠包(しょうろんぽう)です。生地はもちもち、焼き目はカリカリ! 中から肉汁たっぷりの熱々スープがじわっとあふれてきて、こりゃたまりません。4個で400円というのも、お値打ち感あります。 それから昭和の雰囲気を残す店構えも魅力的なパン屋さん「ハリマヤ」では、大辛口カレーパン。大辛口という名前ではあるけれど、ほどよい辛さのルーにゴロゴロのお肉とお野菜。スパイスの香りとドーナッツ生地が合う合う! 3つめは「やきとり家竜鳳」のとりもつ。もつの臭みはまったくなくて、甘めのタレとぷりぷりの食感が食欲を爆発させてしまう1本。いやいや、これはビールが欠かせませんね。 そして今回のデザートに選んだのは、「おめで鯛焼き本舗」のつぶあんです。甘過ぎないあんこにカリッモチッとした熱々の生地。あああ、やさしい味。ちなみに私は、鯛焼きはまっぷたつに割って食べる派です。皆さんはいかがですか? このほかにも唐揚げや和菓子、メロンパンやコロッケまで食べてしまいましたが、どれもこれも、とにかく美味。 本当に、これだけたくさん食べても2000円いかないくらいで納まるとは、まさにひと仕事終えた後のお手軽豪遊といったところ。 満腹、満足、ぜいたく気分(画像:杏耶さん制作) 戸越銀座商店街は大きく長い1本道なので、食べ歩きしながら回りやすい造り。これも人気の理由のひとつなのかな、と思いました。 街歩きの最後には、商店街の中にある地域密着型スーパーの「オオゼキ」へ。この街に住む人々の生活の匂いを感じながら、次の日のご飯の材料を買って、満点の日にしたのでした。 暖かくておいしい戸越銀座商店街、何度も通いたくなる街です。
- おでかけ