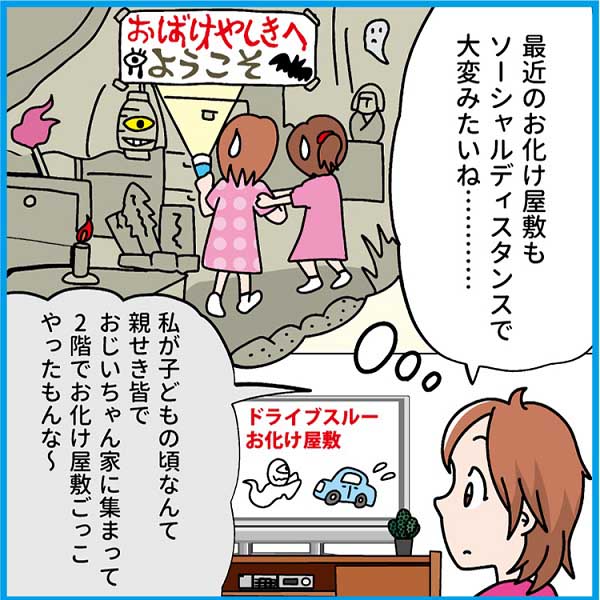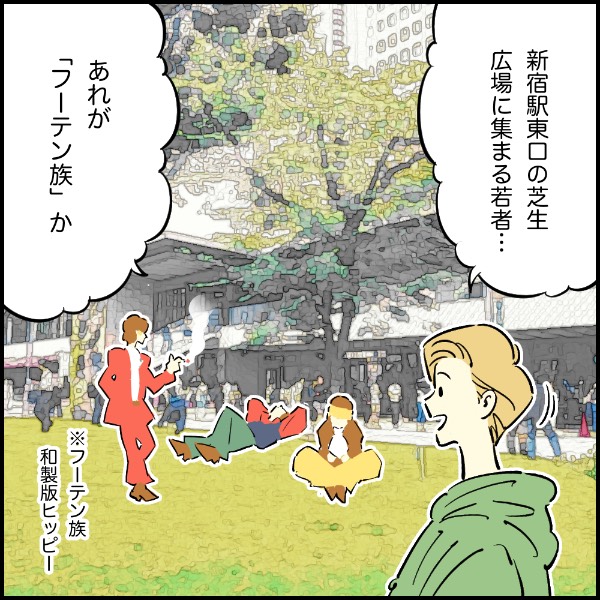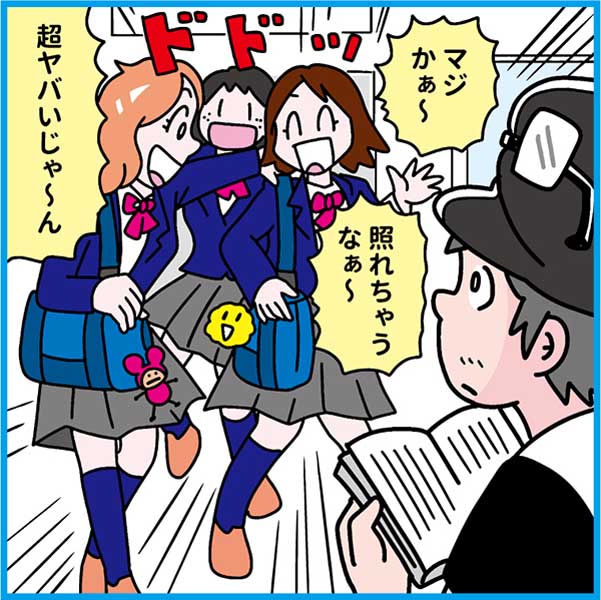「マンハッタン」がもてはやされた時代
下町の雰囲気が今でも残る佃島(中央区)ですが、その北側にはタワーマンションを中心とした近未来的な風景が広がっています。その名は「大川端(おおかわばた)リバーシティ21」(同区佃2)です。
大川端リバーシティ21は、青山や白金に次ぐ「ステータスゾーン」「マンハッタン化されたエリア」として、かつて注目を集めた湾岸エリア再開発の火付け役です。
「ウオーターフロント」という言葉が出てきた当時は、湾岸や隅田川沿いのエリアをニューヨークのマンハッタンに例えて表現することが、ずいぶんとはやっていました。
鈴木都知事の掲げた「マイタウン東京構想」
大川端リバーシティ21のあるエリアは元々、佃島とは別の、石川島と呼ばれる島でした。江戸時代には人足寄場(浮浪人の収容所)があった石川島ですが、明治時代になると海軍省から石川島修船場の跡地を借りた石川島平野造船所(現・IHI)が設立され、隅田川河口の工業地帯として発展していきます。
時代が流れ、石川島平野造船所も東京石川島造船所、石川島重工業、石川島播磨重工業(1960年に播磨造船所と合併)とその名を変えていきました。
 中央区佃にある「大川端リバーシティ21」(画像:写真AC)
中央区佃にある「大川端リバーシティ21」(画像:写真AC)
1979(昭和54)年、同社の東京工場(石川島)が手狭になったことから、三井不動産と日本住宅公団(現・都市再生機構)が買収、大規模再開発の対象となっていきます。この際の指針となったのが、同じ年に当選した鈴木俊一都知事の掲げた「マイタウン東京構想」でした。
当時、東京では人口が郊外に流出しており、ドーナツ化現象が深刻な問題となっていました。これに対して「都心への人口回帰」を念頭に、都心部の再開発が計画されました。そのなかでも、まとまった広い土地が確保できた石川島エリアは熱い注目を浴びたのです。
当時の風景は現在とまったく異なっていました。
現在、大川端リバーシティ21は隅田川を挟んだ対岸の新川と中央大橋でつながっていますが、当時は橋が作られておらず、対岸に渡るには月島から佃大橋を渡らなくてはなりませんでした。
有楽町線の新富町~新木場間開業は1988(昭和63)年ですから、再開発計画の始まった1980年代初頭は「陸の孤島」でした。
家賃「2LDK + 1K」で最高23万4300円
バブル景気による地価高騰が始まり、「これから地下鉄もできる」と大川端リバーシティ21への注目は一段と高まります。なにしろ、完成予定の建物は当時どこにもなかった最高40階建てのタワーマンションだったからです。
なお当時はタワーマンションという言葉は存在せず、超高層住宅と呼ばれていました。タワーマンションという言葉が使われるようになるのは1990年代に入ってからです。
あまりの人気に、本来の目的だった「都心への人口回帰」ではなく投資対象となることが危惧されたため、分譲予定だった住戸を賃貸に切り替えたほどです。それでも家賃は、公団住宅として異例の「2LDK + 1K」で、1か月最高23万4300円となりました。
 渋谷区東にある「コラム南青山」(画像:(C)Google)
渋谷区東にある「コラム南青山」(画像:(C)Google)
この金額は、家賃が発表された1988年時点で史上第2位でした。第1位は1987年に募集された「コラム南青山」(渋谷区東)で、2LDKで24万4500円。公団住宅なのに庶民には手に届かない金額。それでも入居希望者が殺到したといいますから、いかに当時の日本が豊かだったのかがわかります(『読売新聞』1988年1月21日付朝刊)。
応募が殺到したもうひとつの理由
高額家賃にも拘わらず応募が殺到したのは、豊かさだけでなく、遠距離通勤が深刻になっていたからです。当時の地価高騰は著しく、たとえ年末ジャンボ宝くじで一等が当選しても、都心に一戸建てを買えない状況でした。
 遠距離通勤のイメージ(画像:写真AC)
遠距離通勤のイメージ(画像:写真AC)
一戸建てを求める人は東京から遠く離れたところに住まざるを得ず、1日の時間の何割かを自宅と会社の往復に費やしていました。そのような状況ですから、会社に近い都心に住めるなら、共稼ぎをすれば安いと感じる人が多かったのです。
もちろん、バブル景気の時代でも毎月30万円近い家賃を払えたのは限られた人たちです。当時の記事では、事業者側の
「予想入居者は自由業の方や共稼ぎ夫婦、会社で家賃補助をしてくれる人。私たちですか。とてもとても」
という声が記録されています(『読売新聞』1988年6月5日付朝刊)。
別の記事を見ると、月島では1988年8月に地域初のコンビニが開店しています。都心にも拘わらずコンビニがなかったのですから、いかにこのエリアが「都心の田舎」であったかがわかります(『朝日新聞』1988年8月26日付朝刊)。
「カチドキーゼ」なる言葉も誕生
大川端リバーシティ21は2000(平成12)年に完成を迎えますが、その後、周囲で行われていた再開発も相次いで完成を迎えます。2001年には晴海団地を再開発した「晴海アイランドトリトンスクエア」(中央区晴海)が完成。2003年には月島駅前の再開発で「アイ・マークタワー」(同区佃)が完成しています。
 中央区晴海にある「晴海アイランドトリトンスクエア」(画像:写真AC)
中央区晴海にある「晴海アイランドトリトンスクエア」(画像:写真AC)
当時の記事を見ると
・都市を愛するセレブリティをメインターゲットに、高い美意識と機能性のもと開発された
・ゆったり優雅に満喫するワンランク上の都市生活
といったような、とにかく楽しそうな言葉が目立ちます(『宝島』2002年2月20日号)。
とりわけ、晴海アイランドトリトンスクエアは敷地内の商業施設をこだわって作っており、ここで買い物をする近隣女性たちは、最寄りにできた大江戸線勝どき駅にちなんで「カチドキーゼ」と呼ばれました。
そんなキラキラした時代から既に20年あまり。当時生まれた子どもが成人するくらいの現在、当時の勢いはあまり見られません。むしろ庶民的な雰囲気が増しているような気がします。