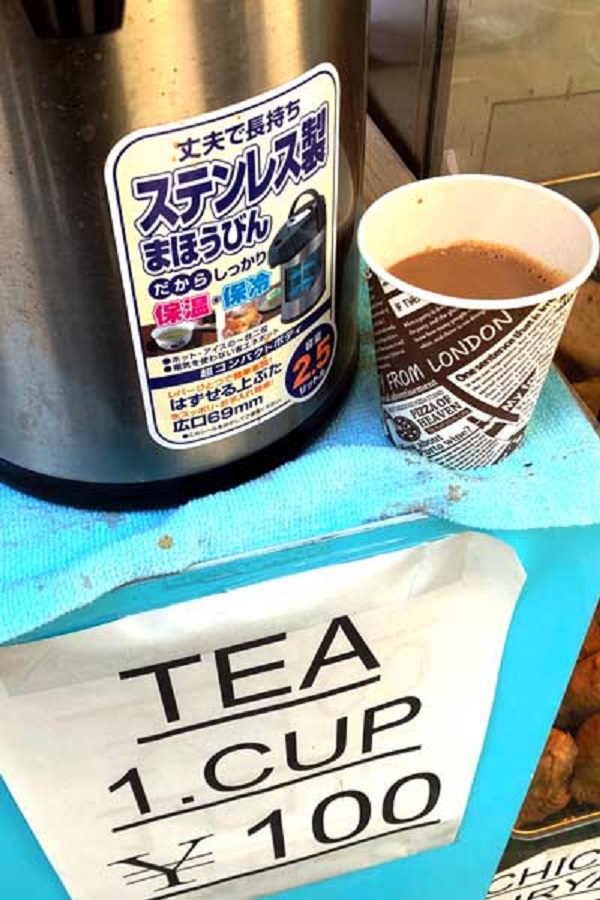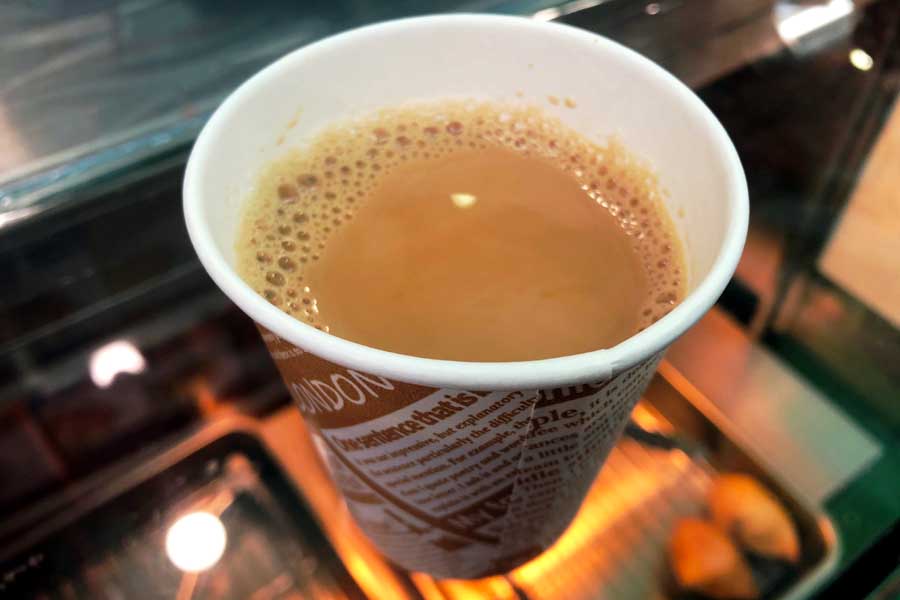旅の達人が教える「ハワイ」の魅力! 池袋で開催の日本最大級「フラ」イベント情報も
誰もが一度はあこがれる「ハワイ」は、昔も今も人気の旅行先。南国リゾートならではのグルメやショッピングなどおすすめ観光スポットに加え、節約テクもご紹介。これまでハワイへ何度も訪れた旅行ジャーナリスト・フォトグラファーのシカマアキさんが、池袋エリアがハワイムードで盛り上がる日本最大級の「フラ」イベントについても解説します。 ●一度行くとその魅力にハマる! 初めての定番ルートを紹介 ハワイは日本人に人気が高い、定番の海外リゾート。その一方で「日本語が通じやすい」「日本人旅行者が多い」「現地の物価が高い」ため、旅の経験が多ければ多いほど、海外旅行の行き先として後回しにされがちです。実は、筆者もその1人でした。 初めて訪れたのは2017年。思わず仕事として行くことになったものの、いざ訪れると1年を通して穏やかな気候、温かく接してくれる現地の人々などハワイの居心地の良さにすっかり魅了されて帰国。その数年後に再びホノルルとハワイ島、さらにまたハワイ島と、数年ごとにリピート中です。 アメリカ・ハワイのワイキキビーチ。奥に見える山がダイヤモンドヘッド(画像:photoAC)【画像】世界有数の絶景スポットにゆったりとした空気、ヘルシーなハワイアンフードと魅力満載!>> ハワイの玄関口は、オアフ島のホノルル。特に、ワイキキビーチがあるエリアは多くのホテルが立ち並び、高級ブランドの店舗が軒を連ねる、日本人旅行者が最も多いエリア。その近くにハワイ最大のショッピングモール「アラモアナセンター」があり、こちらも人気です。 ハワイでは雨上がりに美しい虹が見られる機会も多い(画像:photoAC) ワイキキを拠点とし、ビーチでのんびり過ごすのもよし、ショッピング三昧も楽しめます。さらに、ビーチから見えるダイヤモンドヘッドへ登ったり、フラダンスの現地体験をしたりなども、初めてのハワイでの定番ルートです。 ●オアフ島郊外、離島へ足を伸ばすとさらにハワイの楽しみ広がる ハワイの魅力はワイキキだけにとどまりません。郊外へ足を伸ばすと豊かな自然にあふれ、素朴な田舎街でこそハワイらしい空気を感じることができます。真珠湾の名で知られる「パールハーバー」も、人気観光スポットです。 パールハーバー(真珠湾)で日米の歴史を学ぶのも大事。さまざまなミュージアムが集まるエリア(画像:シカマアキ) 2度目以降のハワイでは、離島もおすすめ。最も大きなハワイ島は「ビッグアイランド」と呼ばれ、活火山があり、夜の星空は絶景。豊かな熱帯雨林やビーチなど自然にあふれています。世界三大コーヒーのひとつ「コナコーヒー」はハワイ島で生産されているので、農園見学もおすすめ。さらにレアな「カウコーヒー」もハワイ島産です。 ハワイを何度も訪れる、その魅力は「居心地の良さ」です。心地よいハワイの風は蒸し暑さがなく、快適。アメリカ本土ほどギスギス感もなく、常にのんびりとした南国リゾートの空気が漂っています。 ハワイ島ワイコロアビーチの夕陽。絶景スポットの1つ(画像:シカマアキ) パンケーキ、アサイーボウル、ロコモコ、ポケ丼、シェイブアイスなど、ハワイの伝統料理からローカルフード、スイーツに至るまで日本人の口に合うグルメも多くあります。なによりフレンドリーなハワイの人々は温かく、のんびりと過ごす生活ぶりを見てリフレッシュすることができるでしょう。 ハワイ島ヒロのマーケットで食べたアサイーボウル。ボリューム満点(画像:シカマアキ)●日本からお得に行く航空券の買い方は? ホテル代の節約テクも 日本からハワイへ向かうには、首都圏では羽田・成田の両空港から直行便があります。全日空(ANA)、日本航空(JAL)、ハワイアン航空などが毎日運航し、行き7時間半程度、帰りは8時間半程度です。ハワイ島へ直行できるJALの成田-コナ線の期間限定運航も。 ハワイアン航空はハワイ・ホノルルを拠点に日本路線などを運航。機内からハワイを体感できる(画像:シカマアキ) 運賃は、年末年始や大型連休時などは高いものの、時期を少しずらすだけで安くなることもあるので、念入りにチェックしましょう。行きはハワイへ早朝に着くため、時差ボケになりやすいので注意。 ハワイで最もネックなのがホテル。初めてのオアフ島ならワイキキ、ハワイ島ならコナがおすすめ。ホテル代は高いですが、1室あたりの価格なので、何名かで一緒に泊まると節約できます。円安と物価高によって外食費も高いため、地元のスーパーマーケットで食材を買い、キッチン付きの部屋で自炊も良いでしょう。 ●日本最大級「フラ」イベントが池袋で開催! フラ一色の3日間 ハワイと言えば「フラダンス」をまず思い浮かべる人も多いでしょう。「フラ」(Hula)とはハワイ語で踊りという意味。ハワイアンフラは、ハワイの伝統的かつ神聖な踊りです。日本ではフラダンスと呼ばれて親しまれています。 「東京フラフェスタ in 池袋 2023」パンフレット(画像引用:豊島区観光協会) 池袋エリアでは、フラダンスの日本最大級のイベント「東京フラフェスタin池袋2023」が7月21日から3日間開催されます。コロナ禍で2020年、2021年は中止。昨年2022年、感染対策を行いながら再開しました。 今回、4会場に147チーム約2300名の出場者が参加予定で、観客は約20万人の見込み。特別ゲストとして、日本における女性ハワイアンバンドの草分け的存在「太田紀美子とザ・バーズ」が前夜祭の池袋西口公園に登場してイベントを盛り上げるほか、各会場ではフラグッズ、フード、ドリンクなどの販売も。 イベント開催の3日間、池袋エリアと大塚エリアがまさに「フラ」一色となります。フラを通し、ハワイを一足先に体験してみてはいかがでしょうか。 ■東京フラフェスタin池袋2023 開催日程:2023年 7月21日(金)~23日(日) 開催場所:【前夜祭(21日)】池袋西口公園野外劇場(GLOBAL RING THEATRE)11:00~19:00頃(14:00頃~本場チーム参加) 【本祭(22日・23日)】 ・池袋西口公園野外劇場(GLOBAL RING THEATRE)11:00~19:00頃、 ・サンシャインシティB1噴水広場11:00~18:00頃 ・中池袋公園11:00~18:00頃 ・大塚駅南口駅前広場「トランパル大塚」15:00~19:00頃 住所:東京都豊島区西池袋1-8-26(池袋西口公園)ほか TEL:03-3981-5849(実行委員会事務局) アクセス:東京メトロ副都心線・丸ノ内線・有楽町線 池袋駅より徒歩1分 JR・東武東上線・西武池袋線池袋駅より徒歩1分 参照:豊島区観光協会公式サイト https://www.kanko-toshima.jp/
- 旅行
- 池袋駅