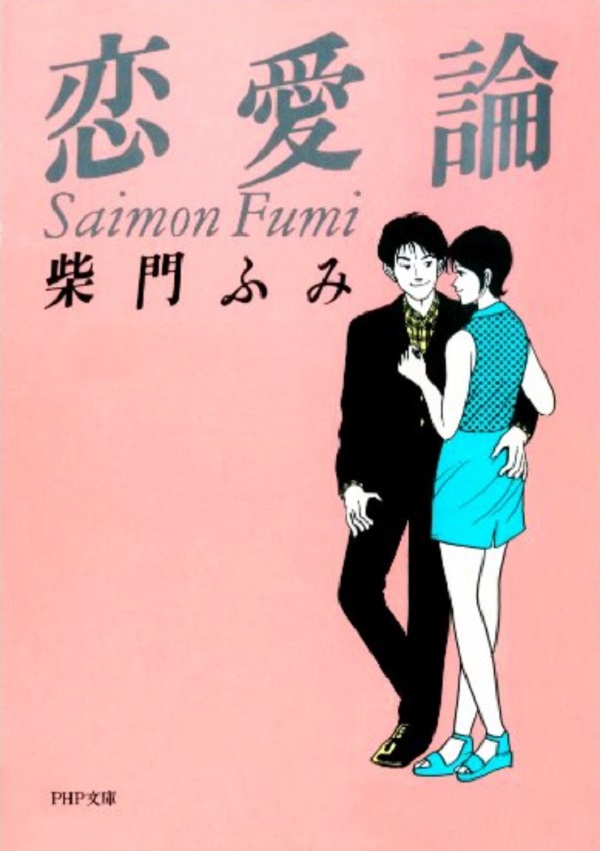文房具なのに食品そっくり! 長年人気の「パロディー商品」、日本人はなぜ好きなのか? 創業70年の老舗メーカーに聞いてみた
すし、カップ酒、お好み焼き 本物そっくりに作られた、いわゆる「パロディー商品」。街のお店でもネット上でも、そういえば見掛けるなあと思ったことはありませんか? 例えば、 ・マグロやイクラ軍艦、エビ、太巻きの形をした、おすし型USBメモリ ・カレーやざるそば、カップ酒など、故人の好物を模したお供え用ロウソク ・たこ焼きやお好み焼きにしか見えない、シュークリームやケーキなどのスイーツ などなど。 ほかにも、お菓子やパンの形をした柔らかい触り心地が魅力のおもちゃ「スクイーズ」は、子どもだけでなく大人にも根強い人気。 2020年5月にはおなじみ液体ノリそっくりの「はちみつアラビックリ!? ヤマト」なる商品が発売されて、予約注文が殺到しました。 のどあめで知られるカンロ(新宿区西新宿)は、人気のお菓子「ピュレグミ」そっくりのトートバッグやクッションを2020年8月に発表、こちらも話題を呼んでいます。 それから、台東区浅草と上野の中間に位置するかっぱ橋道具街に立ち並ぶ「食品サンプル」店。 本来は飲食店などのショーウインドー向けに作られてきた商品ですが、その精巧な作りに魅了される人が後を絶えず、昨今ではすっかり東京の観光地として国内外の来場者を集めるスポットになりました。 浅草に社を構えるパロディー商品の名手 なぜこんなにたくさんのパロディー商品があふれているのか? なぜ日本人はこうしたグッズが好きなのか? その理由が気になり、パロディー商品を作り続ける東京の老舗メーカーに話を聞いてみることにしました。 ※ ※ ※ かっぱ橋道具街からもほど近い場所に社を構える、サカモト(台東区浅草)。 鉛筆の卸商として1950(昭和25)年に創業し、以来さまざまなオリジナル文具などを企画・製造してきた会社です。 消しゴム、ノート、メモ帳、のり、ペンポーチなどバラエティー豊かなアイテムの中で、目を引くのはやはり「パロディー商品」。 どこかで見たことがあるような駄菓子や調味料、一品料理、日用品が、そのまま文房具になっているさまは、眺めているだけで何だか妙に心を浮き立たせます。 雑貨売り場を「食品売り場に」チェンジ雑貨売り場を「食品売り場に」チェンジ 同社広報担当の大竹真美さんによると、同社がこうした商品の販売するようになったのは2001(平成13)年。 当時、哺乳瓶の形をしたペンケースが女子高生らの間で流行しているのを知った社員たちが、同じようなパロディー商品を作ったら受けるのではないかと社内の企画会議で提案。「とんかつソース」型のペンケースを考案し、これがたちまちヒット商品となります。 それを機に、同社の主戦場である雑貨売り場を「『食品売り場』に見立ててみよう」と、現在あるような商品を次々と製造するに至りました。 食品のようでいて、実は文房具。サカモトが考えるパロディー商品の魅力とは?(画像:サカモト)「どこかで見たことがある」ようなシリーズのほか、有名菓子メーカーなどから版権を得た、本物の商品と全く同じデザインの文房具も。 購入者の多くは、ペンやノート、鉛筆などに触れる機会が最も多い小中学生の子どもたちですが、「見た目がカワイイ」「映える!」と注目する20~30代の女性や、「何だか懐かしい」「話のネタになりそう」と手に取る年配の男性も。 どの商品も気になるのですが、一番はお菓子をモチーフにした商品。なぜ魅力的に見えるのでしょう。 「それはやはりお菓子が、誰しも一度ならず2度3度と接したことのあるなじみ深い商品だからかと思います。どんなに不況になったとしてもお菓子売り場は絶対に無くなりませんし、時代を超えて愛され続けてきたロングセラーも数多くある、不動人気のカテゴリーでもありますから」(大竹さん) お菓子は、食べれば無くなってしまう、いわゆる「消えもの」です。 ゆえに、大好きなのに常に手元に置いておくのは難しいもの。それを文房具としていつでも持っていられるとしたら。勉強机や会社のデスク、引き出しの中にそっと忍ばせて、好きなときに取り出して眺めていられたら……。そんな願望を抱く気持ちは、確かに分かるような気がします。 お菓子と同じような理由で、カレーのルーやチーズなども文具も人気なのだそう。 江戸時代から日本人はパロディーが大好き江戸時代から日本人はパロディーが大好き 同社のパロディー商品は初登場から約20年。新商品を発売するたびに必ず反響があり、安定的な人気を誇っています。 「例えばテレビアニメやゲームのキャラは、はやりすたりがある場合もありますが、パロディー商品は非常に手堅く、一過性のブームとは違う手応えを感じるジャンルです」(大竹さん) やはりそれほど「パロディー商品」が国内市場で受ける、ということの証しと言えそうです。 なぜパロディー商品は人気なのか? 大竹さんに聞いてみました。 浅草に立地するサカモト。パロディー商品は20年近く人気を保ち続けているヒットアイテム(画像:(C)Google)「そうですね、小さくてかわいいものって、集めておきたいという心理が働くように思うんです。文房具は安価ですから手を伸ばしやすく、いくつも買い集めたい、コレクションをしたい、という欲求を刺激する要素もあるかと思います」 また3代目社長の坂本雅宣さんは、別の角度からその理由を考えます。 例えば江戸時代にはやった浮世絵や風刺画も、実在の何かを描き写してデフォルメを加えた、いわばパロディー商品の原点。 浮世絵に描かれた歌舞伎役者などはもちろん、有名な名刀を絵に描いて販売した、といった商売の逸話は、現代でも相通じる例をいくつも見つけられそうです。 またそうした作品の特徴は、パロディーの対象に親しみや愛着を込めているところ。海外にはどぎつく手厳しい風刺作品も数多くありますが、日本の場合はどこかおかしみや哀愁を感じさせるものが多い、という点も挙げられるでしょう。 ほかにも箱庭や盆栽などに表れる、雄大な自然を切り取って自分だけの小さな世界として手元に置いておきたい、という思いは、サカモトの商品にもそのまま当てはまりそうなファン心理です。 ※ ※ ※ たとえ理由をうまく説明できなくても、何だか心がときめいて、つい欲しくなってしまうパロディー商品。 これからも日本・東京では数々の商品が生み出されるはず。次はどんなワクワクに出合えるのか今からすでに楽しみになります。
- ライフ