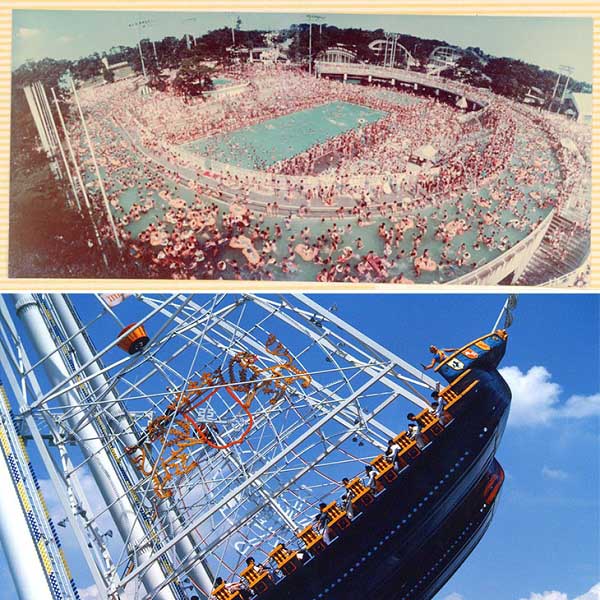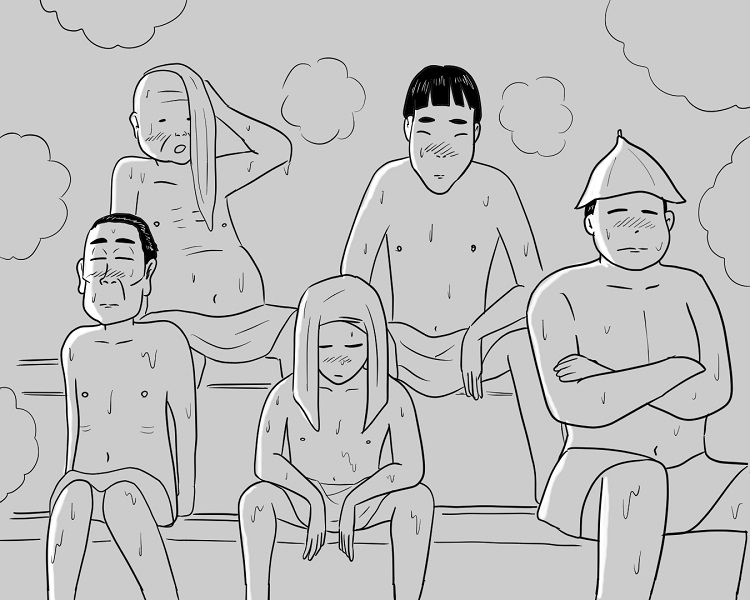【渋谷】デートに女子会に!展望施設「SHIBUYA SKY」できらめく冬景色のかけらを集めよう
宙に浮いているような写真が撮れると人気の展望施設「SHIBUYA SKY」。屋内展望回廊では、12月25日まで幻想的な空間が体験できます。屋上では光と音の特別演出による“ツリー”、ミュージック・バーではスペシャルメニュー、プロの撮影を体験できるプランも登場。今回はエディターの加藤朋美さんが、気になる期間限定イベントをご紹介します。映えまちがいなし!ミラーバルーンの不思議な空間 「渋谷スクランブルスクエア」の14階・45階・46階・屋上に位置する展望施設「SHIBUYA SKY」では、2022年に続き冬の特別イベント「Sparkling View(スパークリングビュー)」を12月25日(月)までの期間限定で開催中です。「渋谷上空からきらめく冬景色」をテーマに、この時期しか見られない特別な冬景色を堪能しましょう! 屋内展望回廊「SKY GALLERY」では、昨年大好評だったミラーバルーンの演出が復活! 日中は澄み渡った冬の青空を、夜にはイルミネーションきらめく都心の夜景を、大小さまざまのミラーバルーンが乱反射することで、多様に変化する不思議で幻想的な空間を体験できます。 回廊には特別な大型映像と環境音楽の演出も(画像提供:渋谷スクランブルスクエア)映え間違いなし、な渋谷上空の特設フォトスポットは一度訪れる価値あり(画像提供:渋谷スクランブルスクエア)【その他の画像】>> 光とシャボン玉による幻想的なクリスマスツリー また、本イベント期間中の19時以降は、SHIBUYA SKYの屋上から渋谷の街に向けて、クリスマスツリーに見立てた光「Sparkling Light Tree」が常時点灯。19時以降の30分おきに、光と音響による特別な演出「スペシャルセレブレーション」が行われます。迫力満点の天に伸びる光に加え、2023年はシャボン玉演出が新登場。渋谷上空229mからの都心の眺望と光の演出、空に舞うシャボン玉で彩る冬の夜空は、渋谷スカイでしか見られないスペシャルな景色。クリスマスデートにもぴったりです! 光とシャボン玉で作られた幻想的なクリスマスツリー(画像提供:渋谷スクランブルスクエア)光と音響による特別な演出「スペシャルセレブレーション」(画像提供:渋谷スクランブルスクエア) また期間中の日中11時~15時には、プロカメラマンによる30分間のプレミアムな撮影プラン「Sparkling View Premium Photo Plan」を実施。外国語も対応OKで、海外からの旅行者にも人気です。 46階ミュージック・バーではスペシャルフードも! さらに、46階「Paradise Lounge(パラダイス ラウンジ)」では期間限定メニューを販売。ホットチョコレートにホイップとマシュマロ、チョコレートソースをトッピングした人気のホットドリンク「マシュマロショコラ」が「Sparkling View」をイメージした限定マグカップ付きで登場します。他にも、ホワイトカクテルやスペシャルサンデーなど、渋谷上空から見渡す渋谷の冬景色とともに特別なドリンク・フードが味わえます。 写真左:クリスマス・メルティサンデー(880円)/写真中央:マシュマロショコラ(限定マグカップ付1,680円※1日限定10杯)/写真右:スノー・ポワール(1,200円)(画像提供:渋谷スクランブルスクエア)14階~45階の移行空間「SKY GATE」、日本最大級の屋上展望空間「SKY STAGE」、46階の屋内展望回廊「SKY GALLERY」の3つのゾーンで構成。渋谷上空229mから広がる360度の景色を眺めるにとどまらず、さまざまな体験を通じて知的好奇心を刺激し、想像力を育む展望施設になっている(画像提供:渋谷スクランブルスクエア)■SHIBUYA SKY 住所:東京都渋谷区渋谷2-24-12(渋谷駅直結・直上) TEL:03-4221-0229 営業時間:10:00~22:30(最終入場21:20) アクセス:JR、東京メトロ副都心線・半蔵門線・銀座線、東急東横線・田園都市線、京王井の頭線「渋谷駅」直結(地下出入り口番号B6) ※SHIBUYA SKY入場チケット、もしくは年間パスポートをお持ちの方は、どなたでも鑑賞可能 https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/sparkling_view
- スポット
- 渋谷駅