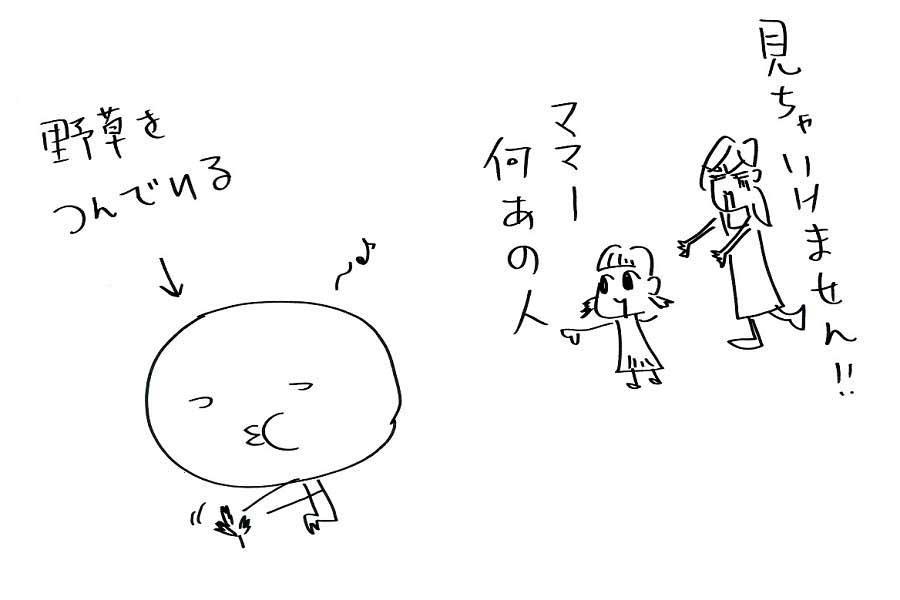歴代最高視聴率は1963年の81.4%
この話題が増えてくると「一年もそろそろ終わりか」と感じるのが、「NHK紅白歌合戦」ではないでしょうか? 2019年で70回という節目を迎える「紅白」。東京との意外に深い関係を探ってみたいと思います。
2017年の紅白歌合戦で「TOKYO GIRL」を歌ったPerfumeのホームページ(画像:アミューズ)
「紅白」の歴代最高視聴率は、1963(昭和38)年に記録された81.4%(ビデオリサーチ調べ、関東地区。以下同じ)です。近年の視聴率はだいたい40%前後なので、いかに驚異的な数字だったかがわかります。
1963年の「紅白」はとても特別なものでした。なぜなら、翌年秋にアジア初となる東京オリンピック開催を控えていたからです。
このオリンピックには、日本人にとって「スポーツの祭典」という以上の意味がありました。それは、敗戦の焼け跡から日本が見事復興を遂げたことを世界に知らしめる絶好の機会だったからです。時は高度経済成長の真っただ中、首都高速道路の開通や東海道新幹線の開業、道路整備やホテルの建設ラッシュなど、オリンピック開催に合わせて東京の風景も一変しました。
そんな時代のなかで、家庭の娯楽の中心になろうとしていたのがテレビでした。ちょうど普及率も8割を超えて「一家に一台」の時代が実現しようとしていた1963年、東京オリンピック開催間近という熱気が加わったのがその年の「紅白」だったのです。
当日の放送でもオリンピック色がふんだんに盛り込まれました。審査員に選手村の責任者が選ばれていただけでなく、オープニングではまだ「寅さん」を演じる前の渥美清が聖火ランナーに扮して登場、東京宝塚劇場の舞台上につくられた聖火台のセットに「点火」する演出がありました。そしてエンディングでは、いまも恒例の「蛍の光」ではなく「東京五輪音頭」が歌手全員で声高らかに歌われました。
「スーパー・シティ」だった1980年の東京
ただ、その頃の出場歌手が歌う曲は、必ずしも明るい未来を謳歌するようなものばかりだったわけではありません。
1963年は、坂本九が「見上げてごらん夜の星を」(作詞:永六輔)を披露しています。ロマンチックなイメージがあるかもしれませんが、元々は集団就職で都会にやってきた若者たちを主人公にしたミュージカルのためにつくられた曲でした。そこには、「ささやかな幸せ」を願う「名もない星」である若者、寂しさをこらえながら都会で懸命に働く若者の姿があります。
同じく永六輔が作詞した「帰ろかな」を歌ったのが、1963年が初出場の北島三郎です。この曲も1965(昭和40)年を皮切りに「紅白」で繰り返し披露されました。詞のなかで、故郷の母親を心配する男性はいっそ結婚して母親を迎えようかと考えます。「やればやれそな東京暮らし」と思案をめぐらせるその姿は、まるで「見上げてごらん夜の星を」とストーリーがつながっているようでもあります。
こうした“東京から故郷を思う”という構図に変化が表れてくるのは、1980(昭和55)年前後のことです。
1978年に初出場した中原理恵の「東京ららばい」は、その兆しともいえる曲です。「午前三時の東京湾(ベイ)」や「午前六時の山の手通り」を舞台に繰り広げられる大人の恋の駆け引きを描いた松本隆の詞は、クールななかにも都会的な哀感を感じさせます。
眠らない夜の六本木通り(画像:写真AC)
そんな“眠らない都市・東京”の誕生を華々しく宣言したのが、ジュリーこと沢田研二の「TOKIO」でした。本物のパラシュートを背負いながら歌ったことでも当時大変な話題になったこの曲は、1980年元日の発売。その年の「紅白」でも歌われました。
このなかで東京は「空を飛ぶ」ような「スーパー・シティ」として描かれています。「欲しいなら 何もかも その手にできるよ A to Z」と詞にあるように、どんな欲望も満たされる消費文化の中心、それが東京という街です。作詞がコピーライターの糸井重里だったのも、大事なポイントでしょう。
そこにはすでにバブルの香りがします。歌のなかに「光の泡」というフレーズが出てくるのも、その印象を強めます。そして実際、1980年代後半バブル景気になると、荻野目洋子の「六本木純情派」やバブルガム・ブラザーズ「WON’T BE LONG」など当時の東京の高揚した気分を反映した楽曲も「紅白」に登場するようになりました。
バブル後に消えた東京ソング、近年復活の兆しも
ただ1990年代初頭のバブル崩壊とともに、大きく世の中の雰囲気は変わりました。良くも悪くも巨大な経済の熱量が失われるのと軌を一にするように、東京を歌った曲も「紅白」のなかであまり目立たなくなりました。
「紅白」で東京ソングがまた目を引くようになったのは、比較的近年のことと言えます。たとえば、最近の「紅白」では、テクノロジーを駆使した演出で“近未来都市・東京”のイメージを見せようとしています。その代表がPerfumeです。
2017年には「TOKYO GIRL」を歌いましたが、このときは渋谷のセルリアンタワー屋上のヘリポートからの中継でした。実写の東京の夜景とVRを最新の技術で重ね合わせ、縦横無尽なカメラワークと光の演出で巧みに近未来感を醸し出していました。
Perfumeが紅白歌合戦で「TOKYO GIRL」を披露したセルリアンタワー(画像:写真AC)
またいうまでもなく、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催決定も大きなことでした。2014年の「紅白」ではその決定を受けてつくられた「東京VICTORY」をサザンオールスターズが披露しました。「東京五輪音頭」も復活し、出場歌手によって何度か歌われています。直接東京に関係するわけではありませんが、2017年にゆずが「栄光の架橋」で初の大トリに抜擢されたのも同じ流れからのことと言えます。
そして再び巡ってきたオリンピック開催前年の2019年の「紅白」。今度はどのような「東京」が表現されるのか、そこに注目して見るのもひとつの楽しみかたではないかと思います。