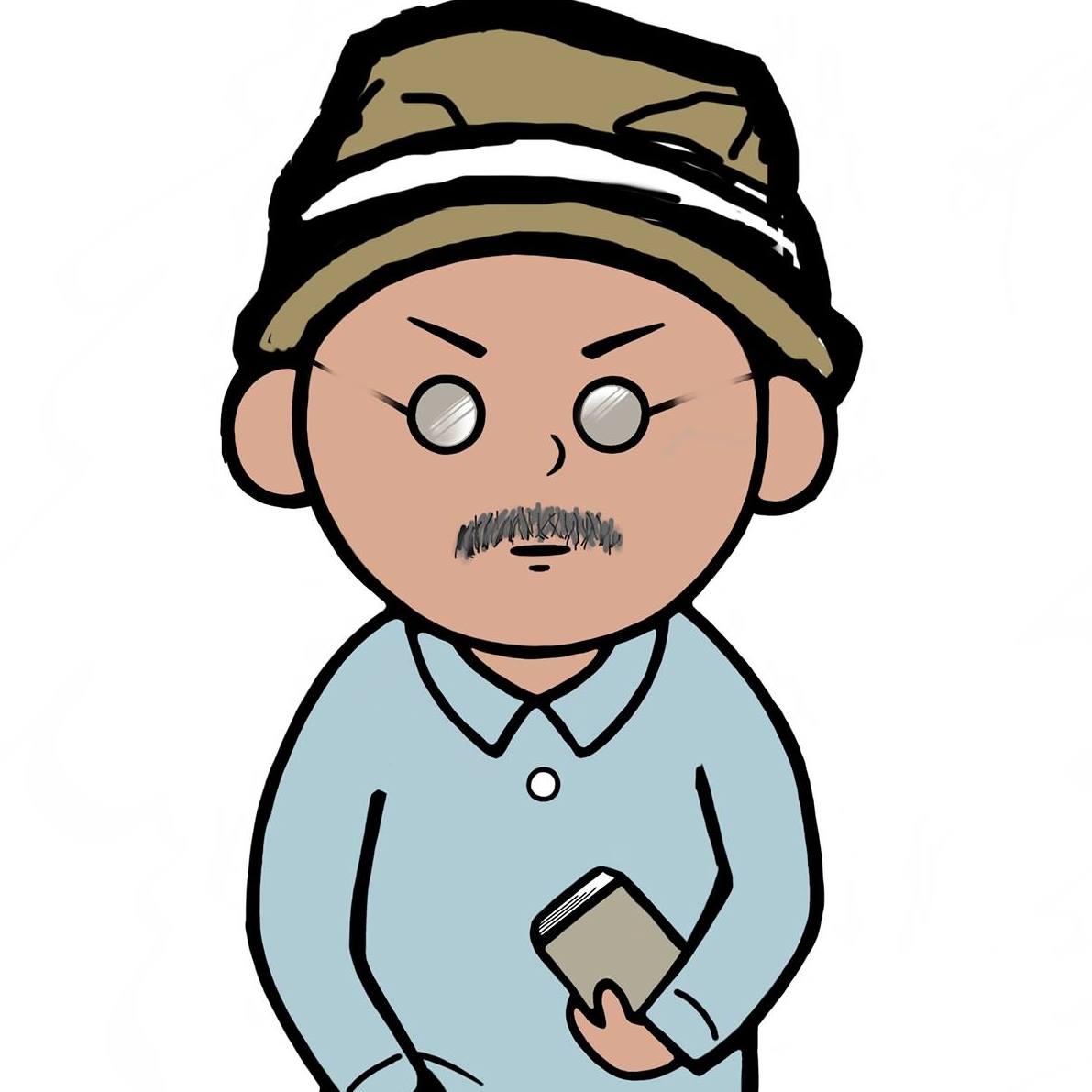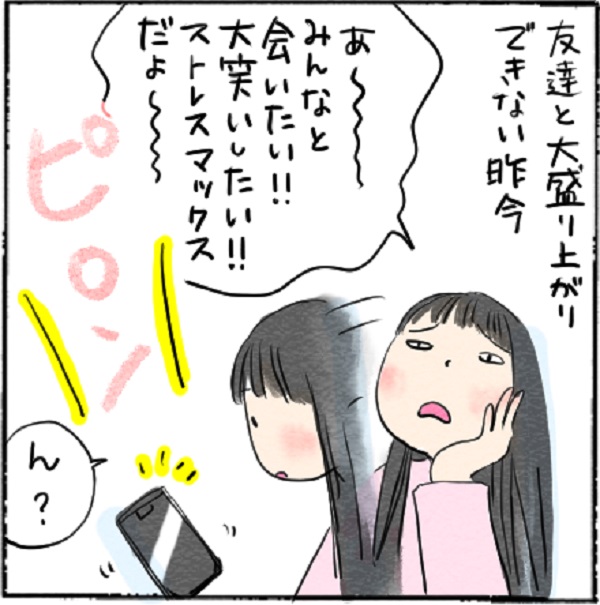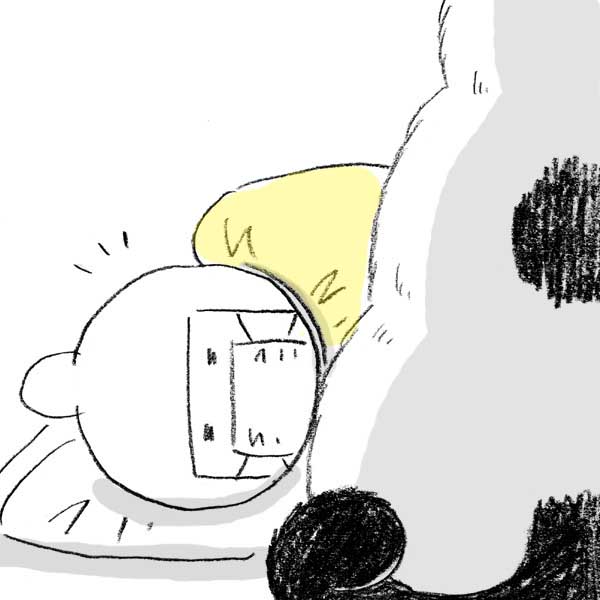「隠れ家」という価値観を広めた世田谷区「三宿」 芸能人御用達も、繁栄は一瞬だった
芸能人のお忍びスポットとして、1990年代中盤から人気を集めた世田谷区の三宿エリアについてルポライターの昼間たかしさんが解説します。「渋谷は人が多くて嫌い」が生んだ 中目黒は、目黒区内でも随一のおしゃれなエリアとして知られています。常に住みたい街の上位に君臨し、2019年にはスターバックスの高級店「スターバックスリザーブロースタリー東京」(目黒区青葉台)がオープンがするなど、話題に事欠きません。 近年は駅周辺の改良工事が進んで街の印象は少しずつ変化しているものの、中目黒の特徴といえば、街のあちこちに洒落たカフェや雑貨屋が点在していること。つまり下町的な雰囲気とおしゃれな雰囲気が融合し、「隠れ家感」があるのです。 三宿の街並みの様子(画像:(C)Google) 中目黒に先行して1990年代中盤から隠れ家的な街として人気を集めたのが、世田谷区の三宿です。今でこそなんとなく知られた土地ですが、かつての三宿は東京に住む人でも地名すら知らないようなエリアでした。自衛隊中央病院(世田谷区池尻)や陸上自衛隊三宿駐屯地(同)以外は目立つような施設はなにもなかったのです。 そんな街におしゃれなイタリア料理店やカフェバーが並ぶようになったのは、渋谷の隆盛が関係しています。バブル景気真っ只中の頃から、渋谷は若者の街として発展を遂げていきました。バブル崩壊後も勢いは留まらず、音楽からファッションまであらゆる渋谷発の文化が注目され、それとともに渋谷には大勢の人が集まるようになりました。 しかし、あまりにも多くの人が集まりすぎました。その結果、どこに行っても行列。話題となる店には、特別感がまったくなくなってしまったのです。そんな不満の受け皿となったのが、渋谷区から適度に離れた地域。そのひとつが自由が丘でした。1990年代半ば以降、自由が丘には高級なセレクトショップの進出が相次ぎ、「渋谷は人が多くて嫌い」と考えるセレブたちが集う街として発展しました。 「ゴミゴミしていない雰囲気で遊べる」「ゴミゴミしていない雰囲気で遊べる」 それに対し、「ゴミゴミしていない雰囲気で遊べる」と脚光を浴びたのが三宿だったのです。中心になったのが国道246号三宿交差点を囲むエリアです。住所では三宿・池尻・太子堂に別れますが、総称して三宿と呼ばれるようになりました。 三宿交差点の様子(画像:ULM編集部) 三宿は最寄り駅の東急田園都市線「池尻大橋駅」「三軒茶屋駅」からも遠く、出掛けるには不便な街。そんなところに店が並ぶようになったのは、絶妙な「渋谷との距離感」でした。鉄道はなくてもタクシーでワンメーターと、「ちょっと、行こうか」と渋谷から移動するにはちょうどいい距離。渋谷の喧噪が一気に消え去るところに、おしゃれな店が並んでいる特別感が好まれたのです。また、当時は表通りに車を停めやすいことも人気を後押ししました。 そんな街ですから、人の目を気にしがちな芸能人も大勢集まることが呼び水に。しかし繁栄は長くは続きませんでした。街に来る人が増えたことで、街の特色だった「隠れ家」的な雰囲気が一気に失われてしまったからです。繁栄は一瞬でした。 インターネット上で情報が溢れる現在、三宿が再び「隠れ家」となるのは到底無理な話ですが、独特の雰囲気はありますし、また「隠れ家」的な店を好む人がいなくなったわけでもありません。むしろ年々多くなり、遠くの街へわざわざ足を運ぶことを趣味とする人もざらです。人々はそれで満足なようです。
- 未分類