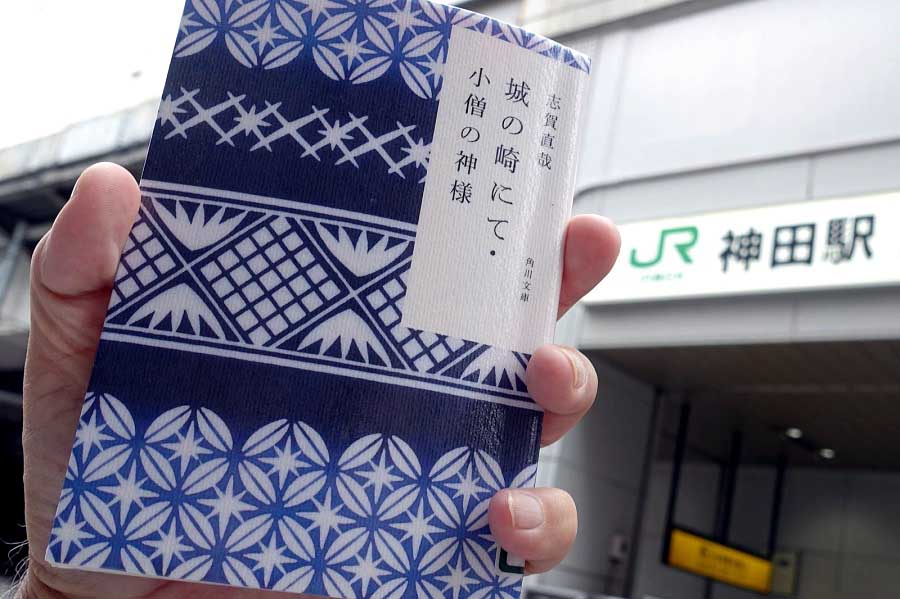そろそろ「ソロキャンプ」デビューしませんか? 手ぶらでOK、インドア&初心者向けの都内スポット4選
コロナ禍で注目を集めた「ソロキャンプ」。自分には関係ない……と思っている初心者&インドア派にこそ、おすすめなスポットが都内にはいくつもあります。インドア派にこそ試してほしい 東京の新型コロナ新規感染者数は1週間以上30人以下を推移しており、東京都のサイトで発表している「都内における繁華街の混雑状況」のデータでは、東京駅丸の内周辺などで前年同時期よりも人口が増えています。 感染者の減少に伴い、通勤や通学、外出を再開した人は少なくないようです。 ただ、“お出かけ解禁”に対してちょっと憂うつな声を上げているのは、もともとインドア派の人たち。 感染拡大防止のため「ステイホーム」に努めてきた期間、堂々とインドア時間を満喫してきたはずですが、そればかりが長く続くと心身の健康に良くない影響を及ぼす恐れもあります。 せっかくの機会、そろそろ外へ出てリフレッシュすることが大切です。 インドア派もぜひ。ソロキャンプの魅力とは(画像:写真AC) 都内でおすすめしたいのは、2020年の「ユーキャン新語・流行語大賞」トップ10にも選ばれた「ソロキャンプ」。アウトドア感がとても高いのに、意外と気軽に行かれてひとりでも十分楽しめる注目のアクティビティーです。 著名人のYouTubeチャンネルで紹介されていることもあり、興味を持っている人も多いはず。インドア派にこそおすすめな、おひとりさまでも楽しめるソロキャンプに最適な都内のスポットをご紹介いたします。 1. 江東区「若洲公園キャンプ場」1. 江東区「若洲公園キャンプ場」 まず紹介するのは「若洲公園キャンプ場」です。 江東区若洲の若洲公園内にあるキャンプ場で、東京ゲートブリッジを臨む立地が東京らしいスポット。日帰りだけでなく宿泊することも可能。場内にはさまざまな設備が整っています。 若洲公園キャンプ場でのテント泊のイメージ(画像:写真AC) かまどは38台、流し台は2台、調理台は2台あり、共同での利用になりますが数に余裕があるため、ストレスなく利用できるでしょう。 キャンプツールは全てレンタルできるため、手ぶらで行っても大丈夫。ソロキャンプ専用のセットもあり、1セット6050円(税込み)で翌朝10時まで使用可能です。 テントや寝袋、調理可能な燃焼器材など、食材以外のキャンプ道具一式がそろっているうえ、初心者でも安心して設営できる軽量なセットになっているのもうれしいポイントです。 公園内の自然燃料で調理も可能ですので、近くのスーパーで好きな食材を調達し、手ぶらでふらっと訪れて、普段とは違う食事を楽しんでみるのはいかがでしょうか。 2. あきる野市「山田大橋キャンプ場」2. あきる野市「山田大橋キャンプ場」 次に紹介するのは「山田大橋キャンプ場」です。 先ほどの若洲公園キャンプとは打って変わって、こちらは多摩の内陸部。あきる野市網代にあるキャンプ場で、山々にほど近い自然豊かな環境が魅力的です。 場内には炊事場はもちろん、トイレなどが完備されているので、初心者でも安心してキャンプを楽しむことができます。 車で乗り込んでキャンプができるオートキャンプ場があり、1区画のスペースが十分にとられているため、ソロキャンプでも他のキャンプ客のことは気になりません。 また、キャンプ場では調理器具を鉄板だけ、まな板だけ、というように1アイテムずつ借りることもできるので、自分が使いたいものだけを選んでレンタルするというソロキャンプならではの気楽な時間を過ごすことができます。 食材は周辺のスーパーで購入でき、バーベキューセットの一式レンタルもあるため、ほぼ手ぶらで行ってもOK。なお、このキャンプ場にはログハウスもあって宿泊することもできます。料金は5500円。 川や森などの豊かな自然の中で宿泊する体験は、都会ではなかなかできません。野鳥の鳴き声を聞きながら、心穏やかに眠りについてみてください。 3. 奥多摩町「氷川キャンプ場」3. 奥多摩町「氷川キャンプ場」 次に紹介するのは「氷川キャンプ場」です。 先ほどの山田大橋キャンプ場よりさらに山深い、奥多摩町氷川にあるキャンプ場。緑が抱かれ、澄んだ空気のなか最高のロケーションでソロキャンプを楽しむことができます。 山々と渓谷に囲まれた氷川キャンプ場(画像:写真AC) 都心から2時間半ほどかかりますが、それに見合うだけの自然を満喫できるはず。 テントでの宿泊はもちろん、ロッジやバンガローもおすすめ。室内にはトイレや冷蔵庫、敷布団などが用意されているので快適に過ごすことができます。団体だけでなくひとりでの利用も可能です。 キャンプ用品に関しては、まな板やトングは200円で借りられるなど初心者でも安心。料金設定が比較的抑えられているのも初心者への心配りを感じます。 テント泊ならひとり1500円。こちらもかなりリーズナブルと言えるでしょう。 近くでカヌーやカヤックも体験できますので、体を動かしてから食事を楽しむのがおすすめ。青い空の下、川遊びをしておいしい焼魚を食べれば、都会での憂うつな出来事もすっきり忘れられるかも? 4. 大田区「城南島海浜公園キャンプ場」4. 大田区「城南島海浜公園キャンプ場」 最後に紹介するのは「城南島海浜公園キャンプ場」です。 こちらは再び都心の23区内、大田区城南島にある城南島海浜公園内のキャンプ場。公園は東京湾をはさんで羽田空港に臨む立地のため、行き交う旅客機を眺めながらキャンプを満喫できるというのが特徴です。 旅客機が見える城南島海浜公園(画像:写真AC) キャンプ場内の「城南島アウトドアセンター」ではキャンプセットを1セット6000円でレンタルできます。さらに、バーベキュー用の肉やドリンクもその場で購入できますので、完全に手ぶらで行けます。 まさに今までアウトドアに触れてこなかったインドア派の人に打ってつけなキャンプ場。場内は広々としているので、ひとりでも周りの目を気にする必要はありません。 バーベキューのプランは、厚切りのお肉2種類と野菜、トルティーヤが付いたアメリカンバーベキュープランと、グレードアップしたお肉、シーフード、焼きそばが加わったボリューム感たっぷりのプレミアムバーベキュープランのふたつ。 開放感のあるベイエリアで海風を感じながら、極上のソロキャンプを楽しんでみませんか? ひとりでも気兼ねなくのんびりとひとりでも気兼ねなくのんびりと インドア派の人があまり外に出ない理由には、「疲れるから」というものがあるのではないでしょうか。 気軽にのんびりソロキャンプ(画像:写真AC) しかし、今回紹介したキャンプ場なら、ひとりでも気兼ねなくリラックスでて、自然の中でのんびりくつろぐだけでもOK。ただ寝そべっているだけでも、自室で過ごすのとは全く違う感覚を味わえるでしょう。 ひとりが好き、まったり過ごしたい、というインドア派にこそ実はおすすめなソロキャンプ。手ぶらで気軽に、一度試してみてはいかがでしょうか。
- おでかけ
- 大森駅
- 奥多摩駅
- 新木場駅
- 武蔵増戸駅