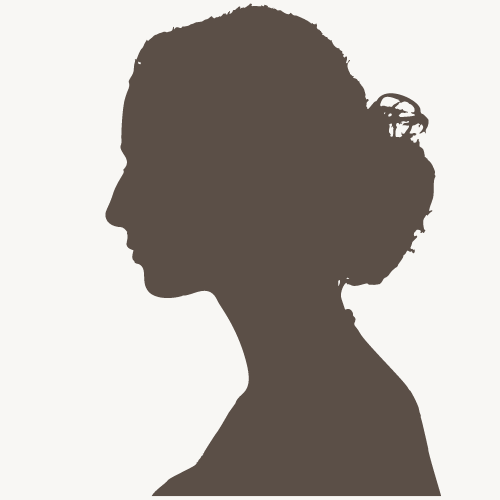クルマ通をうならせた都心No.1ドライブコース! 一度は行きたい「東京ゲートブリッジ」の魅力に迫る
東京都心の移動には何と言っても電車などの公共交通機関が便利。でも、そんな都心において「クルマだからこそ見られる景色」も確かに存在します。ぜひともドライブしてみたいコースについて「のっぴードライブログ」管理人の のっぴー さんが紹介します。レインボーブリッジ以上の魅力? 東京23区というと、都心で賑やかで人が多いイメージが強く、鉄道をはじめとした交通機関もかなり発達している印象が強いのは、皆さんの共通認識ではないでしょうか。 わざわざクルマを運転しなくても目的の場所へ簡単に行くことができるのは、都会ならではの便利さでもあります。 とはいえ、実は東京23区にあって、クルマでのドライブだからこそ楽しめる絶景ポイントというものもいくつか存在します。一番有名なのはやはり、港区芝浦とお台場を結んでいるレインボーブリッジでしょう。 レインボーブリッジは徒歩やゆりかもめなどでもアクセスできますが、ぜひクルマを運転して橋の前後や橋を渡っている途中の景色を楽しんでいただきたいスポットです。 そして、東京23区内にはそんなレインボーブリッジ以上に、ドライブだからこそ楽しめる絶景穴場ポイントがあるのです。 このスポットは、休日ともなると北は青森・南は鹿児島まで、全国あらゆるところへドライブへ行く知人に紹介したところ大変に好評で、それ以来たびたび訪れる常連になっているというお墨つきです。 ベテランのドライバーも思わず同意。東京ゲートブリッジの魅力とは?(画像:写真AC) その名も「東京ゲートブリッジ」(江東区若洲)。今回は、ドライブ通をもうならせる魅力満載の絶景ドライブスポット、東京ゲートブリッジのについて紹介します。 新型コロナウイルス禍でまだまだお出かけには慎重になる時期ですが、気軽なドライブが可能な状況になった際には、ぜひ皆さん自身の運転で東京ゲートブリッジを訪れてみていただければと思います。 走りごたえのある道路設計走りごたえのある道路設計 東京ゲートブリッジは、江東区の新木場近くの若州から、大田区の羽田空港の東側の城南島までの約8kmにおよぶ東京港臨海道路の一部で、東京ゲートブリッジ自体は、全長2618mの橋です。 江東区と大田区の間は、直接的に結んでいる一般道の湾岸道路や高速道路である首都高湾岸線があるため、そちらを利用する人が多く、あえて東京ゲートブリッジのある東京港臨海道路を利用するという人はどちらかといえば少ないでしょう。 ただ、湾岸エリアの道路ということもあり、全区間で片側2車線以上は確保されているほか道路幅も広く設計されているため、クルマを走行するにはとても良い環境が整えられています。 東京ゲートブリッジを渡っている道中も道路の舗装や道幅の確保が十分されていて、しかも他の道路との交差が少ないため信号がほとんどなく、ストレスを感じず快適に運転することができるのも特徴です。 東京ゲートブリッジの魅力その1、走りごたえのある道路設計(画像:のっぴー) それはつまり、運転免許を取得したばかりや長い間運転の経験がない、いわゆる運転初心者にとっても比較的走りやすいコースだと言うこともできます。 東京ゲートブリッジを含む東京港臨海道路は、制限速度が基本的に時速50~60kmに設定されています。道路形状がよく信号が少なく走行しやすいため、速度を出し過ぎてしまう恐れがありますので、スピードメーターをこまめに確認しながら十分に気をつけて走りましょう。 また、この地域一帯が工業地帯ということもあり、大型トラックが多数走行していますので、配慮のある運転を心がけるようにしましょう。 クルマだからこそ楽しめるアクセス方法クルマだからこそ楽しめるアクセス方法 東京ゲートブリッジは、湾岸エリアでも南方に位置するのに加えて、周辺に主だった施設があるわけではありません。これも、クルマでこそ行くべきスポットと筆者が強調したい理由のひとつです。 鉄道の場合、最寄駅が新木場駅でそこからバスで10~15分ほどで若州キャンプ場前に到着してそこから徒歩で30分前後と、乗り換えの回数や最寄のバス停からの距離を考えるとは、他の観光スポットやレジャースポットにくらべると、到着までにかなり労力を使います。 新木場駅から歩いていくことも可能ですが、それでも到着まで片道1時間以上の時間が必要なため、体力に自信がある人でないとなかなか気軽には行かれません。 しかも、これはあくまで新木場駅から東京ゲートブリッジまでのアクセスについてですので、その先の大田区城南島方面まで行こうとするには、鉄道やバスと徒歩の組み合わせでは、途方もない話なのです。 東京ゲートブリッジの魅力その2、クルマだからこそ楽しめるアクセス方法(画像:のっぴー) 一方クルマなら、東京ゲートブリッジ経由で新木場~城南島まで約20分くらいでアクセスできるのに加えて、途中の東京ゲートブリッジでは爽快な走行を楽しむことができるのです。 また、東京港臨海道路の始点と終点の近くには、首都高のインターも設置されているため、東京港臨海道路まで行くためのアクセスも充実しております。 東京都心にあって、クルマだからこそ楽しめるスポットはなかなかないので、そういう観点からも、東京ゲートブリッジはドライブスポットとしてお薦めです。 高層ビルと東京湾の景色のすばらしさ高層ビルと東京湾の景色のすばらしさ 東京ゲートブリッジの最大の魅力は、なんといっても壮大で開放的な景色のすばらしさにあります。東京ではなかなか味わえない景色を見ることができます。 前述の通り東京ゲートブリッジは、立地としては都心部より離れた湾岸エリアの中でも南端の方にあることもあり、主だった商業施設や工業地帯などがほとんどありません。 さらに、橋の周辺はかなり開放的になっており太平洋を見渡せることに加えて、北側に広がるお台場や有明・新木場の高層ビルや工業地帯の街並を眺めることができます。 また、昼間と夜では雰囲気がガラリと変わり、夜になると東京ゲートブリッジ自体がライトアップされるうえ、橋から見える夜景が水面にきれいに映し出されます。 東京ゲートブリッジの魅力その3、高層ビルと東京湾の景色のすばらしさ(画像:のっぴー) しかも、東京ゲートブリッジのライトアップされる色は月ごとに変わるので、一度だけでなく何回訪れても楽しめる工夫が凝らされています。 運転中に飛び込んでくる景色もすばらしく、東京ゲートブリッジの入口から出口まで先の形状がよく見えるので、走行していて気持ちよさが増してきます。 もし時間が許す際は、東京港臨海道路を往復してみてください。内回りと外回りでは景色の見え方に違いがあるので、その違いを楽しむのもなかなか面白いはず。東京港臨海道路自体は、1時間もあれば十分往復できます。 また、東京ゲートブリッジを歩いて景色を楽しみたい人は近隣にある若州公園の駐車場の車を停めることができますので、そちらから歩くのがおすすめです。 ぜひ一度はドライブしてほしい!ぜひ一度はドライブしてほしい! 東京ゲートブリッジは、知る人ぞ知るスポットですが、その魅力は語りつくせないほど満載です。やはり、東京23区にあってなかなか体験できない走行感覚と珍しい景色が見られるのがポイントです。 ぜひ一度はドライブしてみてほしい、東京ゲートブリッジ(画像:のっぴー) 実際、都心の有名な通りに比べると、交通量は少なく人通りもまばらなため、人ごみが苦手でなかなか東京の観光スポットに行けないという人にも特にお薦め。 最近では、羽田空港や城南島方面からだけでなく、お台場・青海・有明方面からの道路が開通して、ますます利便性が高まっています。 2022年は、東京ゲートブリッジが開通して10周年。記念の年を迎える頃には、もっと気軽にお出かけやドライブが楽しめる世の中になっていることを切に願います。
- おでかけ