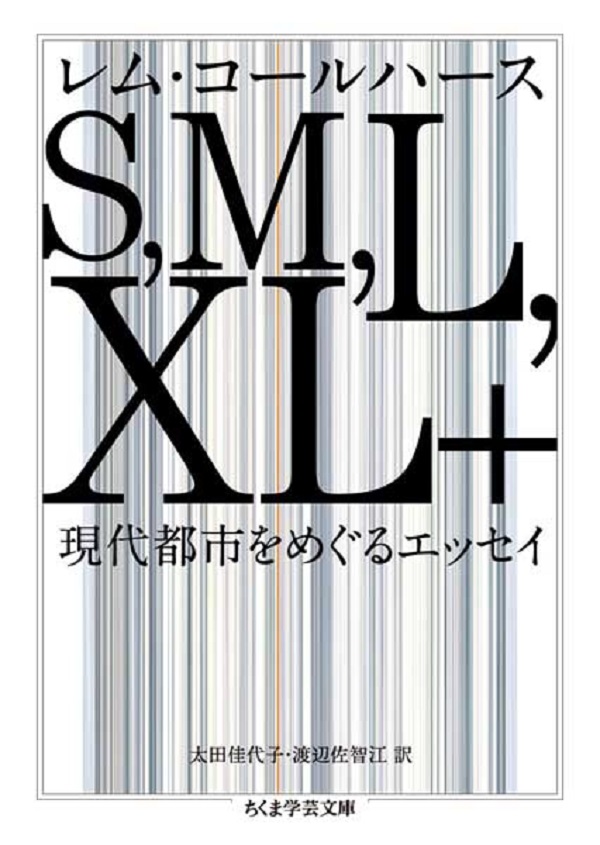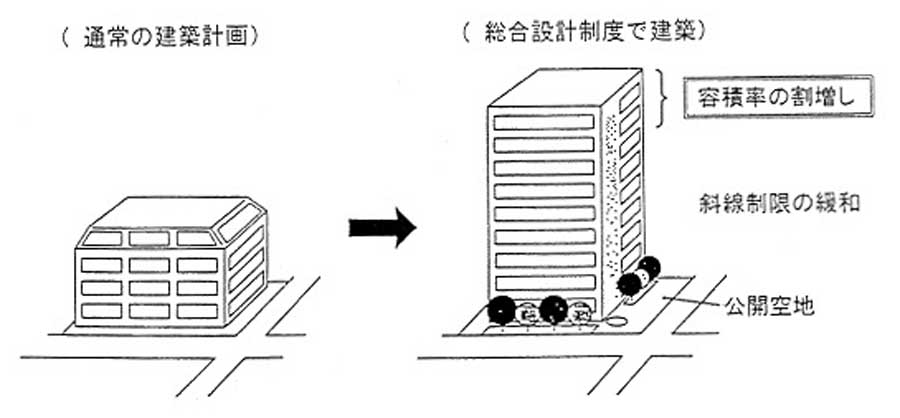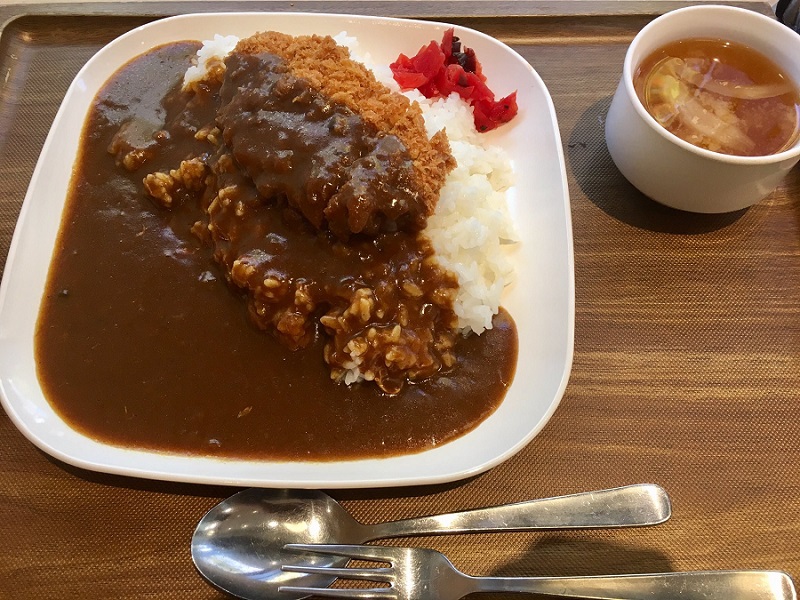クラスター、ソーシャルディスタンス…… カタカナ英語を「何となく」理解する日本人の不思議な言語感覚とは
日常にあふれる英語の不思議 2020年上半期に東京で大はやりした言葉といえば、ソーシャルディスタンス。直訳すれば「社会的距離」あるいは「社会的隔離」という意味です。言わずもがな、新型コロナウイルスの関連で使われるようになった単語です。 ソーシャルディスタンスやクラスターなど、聞き慣れなかったはずの英語が、いつの間にやら日常語に(画像:写真AC) 気がつけば、東京のあちこちで誰もが「ソーシャルディスタンスを保とう」と言っているわけですが、いったいどこから始まった言葉なのでしょう。 調べて見ると3月中旬からネットメディアが使い始めて、テレビや全国紙へと拡大しています。 ここで不思議なことがひとつ。テレビでは比較的早い時期から「ソーシャルディスタンス」という言葉の意味を解説しているのですが、新聞・雑誌ではそうした記事があまり見当たりません。SNSなどを通じて、なんとなく広まっていたという感じです。 このソーシャルディスタンスという言葉を筆頭に、「クラスター(感染者集団)」とか「パンデミック(世界的大流行)」という言葉も、新型コロナウイルス関連の記事では当たり前に使われています。 ここで筆者(昼間たかし。ルポライター)は気づいたのです。日本人はいつの間にか「なんとなく英語を理解する」ようになっていたのか、と。 これはとても不思議なことです。 世界では共通言語として英語が最も普及しています。延期になってしまいましたが、2020年は東京オリンピック・パラリンピックのおもてなしのためにも、東京人の英語力が期待されたました。 でも、日本人の英語力は必ずしも高くはありません。 英語は苦手なはずなのに……英語は苦手なはずなのに…… 多くの研究者によって引用される「EF EPI英語能力指数」によれば、日本はデータのある世界100カ国中の53位という成績。 2011年のデータでは44カ国中14位だったのですが、それから1度も上昇せずに下落を続けています。 これは、日本の英語力が低下しているというよりも、世界で英語の話者が増えてレベルがアップしているにも関わらず、日本が停滞していた結果、次々と順位を追い越されている状況と言えます。 世界的な観光都市となりつつある(今は新型コロナ禍の再生途上ですが)東京を抱えながら、これはあまりにも残念なもの。 しかし、それにも関わらず、日常ではソーシャルディスタンスのような英語が当たり前に使われ、だいたいの人は理解してる――。そんな状況はいつ、どうやって生まれたのでしょうか。 「STAY HOME」も新型コロナ禍でしきりに言われるようになった英語(画像:写真AC) もともと日本で英語の受容が進んだのはバブル景気の頃からでした。 この頃、いっそう進んだ円高を追い風にして洋書やCDなどの価格はグッと下がり、輸入量も増加しました。それに限らず、円高の恩恵によって海外のスポーツや音楽は日本でも取り上げられる機会が増加します。 特に音楽CDの輸入量は1994(平成6)年には前年度比で170億枚以上の増加という驚異的な伸びをしています。 始まりはFMラジオの洋楽から始まりはFMラジオの洋楽から この年に急激な伸びを見せた理由は、それまで数年にわたってテレビや雑誌を通じて海外の音楽が取り上げられることが増えた結果というよりほかありません。 例えば、 東京のFMラジオ放送局J-WAVE(港区六本木)は1988(昭和63)年10月の開局ですが、バイリンガルのDJと洋楽を中心としたアメリカン・スタイルの番組は瞬く間に人気を呼び、老舗の東京FMを抜いて首都圏のFM局ナンバーワンになっています(この後、邦楽を中心とした東京FMとの激しい争いが始まるわけですが、その話題はまたの機会に)。 さらに当時、利用者を増やしていたNHKの衛星第1放送ではNBAバスケットボールとCNNニュースが常に人気の番組となっていました。 そうした番組を最も好んで楽しんでいたのは、当時10代の若者たちだったとされています。 中学校や高校など学校で勉強する英語とは違うスタイルの英語を、感覚として取り入れて楽しむ、そんな若者たちが増えていたのです。 1990年前後、当時の若者たちを夢中にさせたFMラジオ放送(画像:写真AC) そうした若者たちは英語を読めるとか書けるではなく、心地のよい音として感覚で理解していたわけです。 当時、中学校や高校の英語教育ではヒアリングも始まっていましたが、 ペーパーテストでは点数が良くないのにヒアリングだけは抜群という生徒も見られていました。 こうした感覚が進化したものが、「ソーシャルディスタンス」や「クラスター」という言葉を、意味はよく分からないが言わんとすることは分かる、という意識だといえます。 謎のビジネス用語まで増殖中謎のビジネス用語まで増殖中 この「英語は理解できないけど、何となく分かる」感覚は、日本語の新たな進化を生み出します。 従来の外来語とは異なる「日英混交文」と呼ばれるものです。 これは国語学研究者の伊藤雅光氏の造語ですが、『THE有頂天ホテル』(2006年公開の、三谷幸喜監督の映画作品)のように英語をそのまま日本語の中で使う文章スタイルです。 朝日新聞の2006(平成18)年5月2日付の記事では「日英混交文」の増殖が指摘されています。 この時点でも、さらに増加していくだろうと考えられていた「日英混交文」ですが、わずか数年の間に予想以上に進化します。 6年後の2012年12月8日付の『朝日新聞』には「イライラするカタカナ語は?」という記事が掲載されていますが、ここでは「リスペクト」とか「ダイバーシティ」「オルタナティブ」など、意味が分からない言葉が日本語に交じって当たり前に使われていることに、イライラしている人の声を取り上げています。 ビジネスの場面でしばしば登場するカタカナ言葉。よく分からず聞き流してしまう、なんてことも?(画像:写真AC) 実際、2010年代前半には、ビジネスの現場などでも、「トゥギャザーしようぜ」のネタで知られるお笑いタレント・ルー大柴のような英語交じりの日本語を得意げに話す人が増殖し、あ然とする場面も見られました。 今は、それらの妙な英語にもようやく慣れてきたということが、「ソーシャルディスタンス」という言葉をみんなが使っていることからも見て取れます。 でも「スマートシティ」とか「IoT社会」とかが実際どのようなものなのかは、筆者はいまだによく分かっていません。
- ライフ