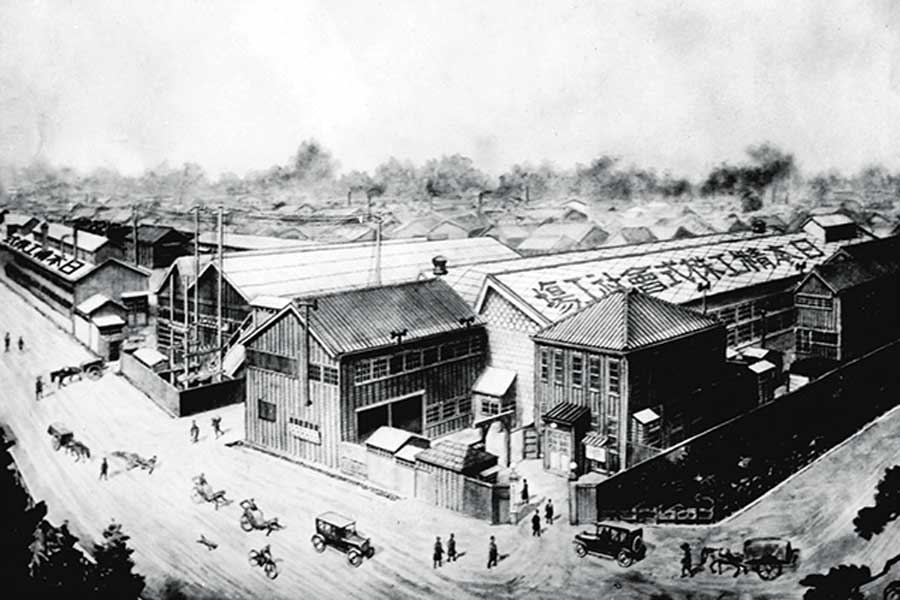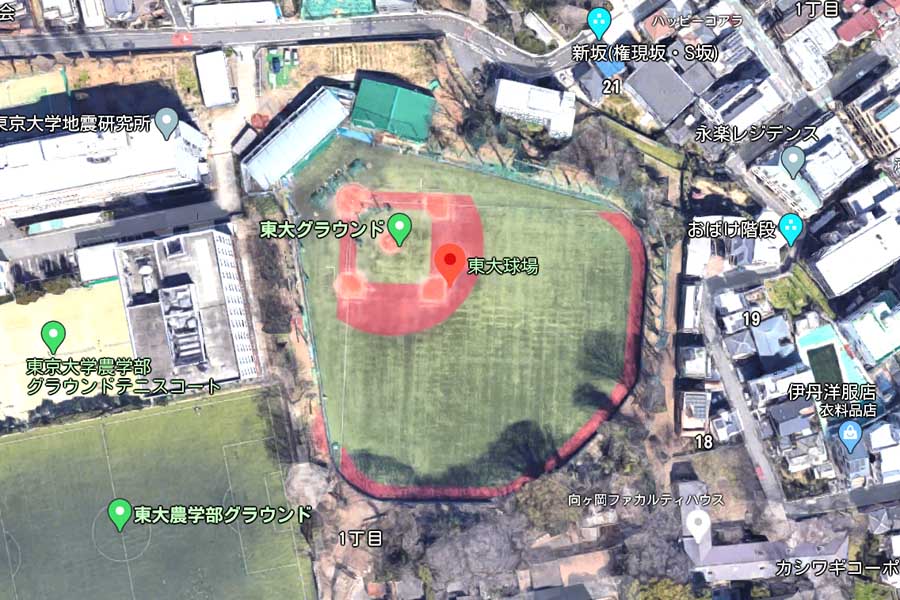過ぎ去る夏の光を追いかけて。アートの秋を先取りする幻想的なプチ・トリップへ【東京・神奈川・栃木】
季節を問わず多彩な色彩やプロジェクションマッピングを使用した光の演出が話題を集めるイルミネーション。今回は、アートの秋を先取りする幻想的な体験ができるおすすめスポットについて、エデュケーショナルライターの日野京子さんが3つご紹介します。 イルミネーションといえば冬をイメージすることが多いですが、現在は季節を問わず多彩な色彩やプロジェクションマッピングを使用した光の演出が話題を集めるようになりました。 技術進化もあり、全国各地で実施されているイルミネーションは場所の個性を活かした展示や演出が見どころの一つです。 今回は、東京都内だけではなく関東近郊で夏の終わりを感じられる、幻想的なおすすめスポットを3つご紹介していきます。 アート作品が体験できる異空間へ(画像:那須スポーツガーデン有限会社リリース)【画像】さまざまな光の演出で体験する異世界への没入体験>> ●光の絵巻も幻想的な「江の島灯籠2023」/~8月31日 首都圏近郊の夏の観光地の代表格である江の島。多くの観光地でにぎわいを見せている同エリアの顔の一つでもある「江島神社」とその周辺では、8月31日(木)まで「江の島灯籠2023」が行われています。 「縁日」は金魚と花火の切り絵をモチーフにしたデザイン(画像:有限会社ベルベッタ・リデザインリリース) イルミネーションは朱色の鳥居と瑞心門にて18時から20時30分の間に実施され、日が沈むのが徐々に早くなる8月下旬は、開始時刻から虫の音を聞きながら幻想的な風景を堪能できます。 新しく追加された「縁日」や「深緑の江島神社」といったデザインの他に、江の島の伝承『江島縁起』を基にした「江の島誕生」「五頭龍」「天女降臨」「天女と五頭龍の出会い」「五頭龍の御加護」の5つのシーンで構成されています。 ライトアップされた石階段「光の導き」(画像:有限会社ベルベッタ・リデザインリリース) また江島神社にある3つの宮のうち、「辺津宮」でも恋愛成就や縁結びを願う特別イルミネーション「天女と縁結び」「縁結びを願う花」が展開されています。去り行く夏を感じながら江島神一帯を美しく照らすイルミネーションを眺めてみてはいかがでしょうか。 恋愛成就の御利益があるとされる辺津宮での「天女と縁結び」(画像:有限会社ベルベッタ・リデザインリリース)●異世界への没入体験「和のあかり×百段階段2023 ~極彩色の百鬼夜行~」/~9月24日 目黒にある「ホテル雅叙園東京」は、1991年の大規模リニューアルの際に、戦前に建てられた木造建築から近代的な施設へとリニューアルしました。その中で、唯一旧館の名残を残すのが東京都指定有形文化財である「百段階段」です。 草丘の間での過去開催の様子。写真中央の作品は異形の生き物を表現した『鞠猫』(造形作家・よねやまりゅう)。今回は七夕飾り作家・櫻井駿氏による作品を展示(画像:ホテル雅叙園東京リリース) 長い階段沿いには宴会などに使用される7部屋が設置され、いずれの部屋も当時の一流画家や職人が携わった豪華絢爛な空間が広がっています。 こうした大正から昭和初期の芸術性の高いレトロさを活かした大人気イベント「和のあかり×百段階段2023 ~極彩色の百鬼夜行~」が、9月24日(日)まで開催中です。 和の空間に亜熱帯の植物を配することで、美しくも恐ろしい異世界へ迷い込んだような没入感を演出。和のあかり×百段階段2023・十畝の間(画像:ホテル雅叙園東京リリース) 百鬼夜行のタイトル通り、暗闇の中に浮かぶ怪しげな雰囲気だけでなくBGMや匂いなど五感を刺激するダイナミックな空間演出で、エリアごとに設定されたストーリーへ迷い込む展示が話題を呼び、入場者数は2万人を突破。 使用されているアート作品はペットボトルを再利用したものもあり、サスティナブルの意識を高める内容にもなっています。 細部まで美しい灯りの意匠。『ほおずきのあかり』(照明作家・弦間康仁)(画像:ホテル雅叙園東京リリース)●アート×グランピング×サウナを楽しめる観光宿泊施設に大変身した元廃校「那須ユートピア美野沢アートヴィレッジ」にて夏の展示/~9月30日 都心から高速道路や新幹線で行ける那須は、温泉やグルメが楽しめる観光地として人気の高いエリアです。那須にはさまざまな体験ができる施設が豊富にそろっていますが、2022年10月、廃校となった小学校をリノベーションした新たな観光宿泊施設「那須ユートピア美野沢アートヴィレッジ」が誕生しました。 自然に囲まれた立地。学校に泊まるというとどこか文化祭のような感覚に陥るかも。カフェもあります(画像:那須スポーツガーデン有限会社リリース) 「那須ユートピア美野沢アートヴィレッジ」では、サウナやグランピング、キャンプで自然と触れ合いながら「クリエイティブリユース」を遊んで学べる観光宿泊施設としてオープン。 本格的なフィンランドサウナ(画像:那須スポーツガーデン有限会社リリース)アートギャラリーには常設で16組のアーティストが手がけた作品が飾られています(画像:那須スポーツガーデン有限会社リリース) 9月30日(土)まではアート集団MIRRORBOWLERによる夏の展示「アマテラス 〜MIRRORBOWLERの魅惑的な世界 〜」が開催中。 「アマテラス」という名の通り、日本神話に登場する天照大神をモチーフにした、神秘的で見る人を包み込むような優しさを感じられる作品が集められています。 広々とした体育館を最大限に利用した光輝く大型のアート作品は必見。那須の自然に囲まれ、アート作品に触れて芸術の秋を先取りしてみるのもいいですね。 体育館一面を照らす光(画像:那須スポーツガーデン有限会社リリース)●夏の終わりのお出かけ うだるような暑い日が続いていますが、日が沈むと秋の虫の音を耳にするようになってきました。 夕暮れ時には秋の気配を感じる季節の狭間の時期です。過ぎ行く夏の光を惜しみながら、アートな小旅行の計画を立ててみてはいかがでしょうか? ■江の島灯籠2023 開催期間:開催中~2023年8月28日(月) 開催場所:江島神社(辺津宮・中津宮・奥津宮)、江の島サムエル・コッキング苑 江の島シーキャンドル、御岩屋道通り、江の島岩屋 住所:神奈川県藤沢市江の島2-3-8(江島神社) TEL:0466-22-4020(江島神社) 点灯時間:18:00~20:30(土日祝21:00まで/雨天・荒天中止) アクセス:小田急線「片瀬江ノ島駅」より徒歩15分 江ノ島電鉄「江ノ島駅」より徒歩20分 湘南モノレール「湘南江の島駅」より徒歩23分 ■和のあかり×百段階段2023 ~極彩色の百鬼夜行~ 開催期間:開催中~2023年9月24日(日) 開催場所:ホテル雅叙園東京 東京都指定有形文化財「百段階段」 住所:東京都目黒区下目黒1-8-1 TEL:03-5434-3140 営業時間:11:00~18:00(最終入館17:30) 入場料:1,500円/学生800円 ※未就学児無料、学生は要学生証呈示 アクセス:JR・東急線・東京メトロ南北線・都営三田線「目黒駅」より徒歩3分 ※詳細は公式サイトをご確認ください ■アマテラス 〜MIRRORBOWLERの魅惑的な世界 〜 開催期間:開催中~2023年9月30日(土) 開催場所:那須ユートピア美野沢アートヴィレッジ 住所:栃木県那須町蓑沢563-4(旧美野沢小学校) TEL:0287-73-5333 営業時間:9:30〜20:00 宿泊チェックイン:15:00〜18:00 入場料:大人1,100円/子ども550円(1ドリンク付き) アクセス:JR「那須塩原駅」より車で約30分 JR「黒磯駅」西口より那須町民バスで43分 東北自動車道 那須ICより車で40分 ※詳細は公式サイトをご確認ください
- スポット
- 栃木
- 目黒駅
- 神奈川