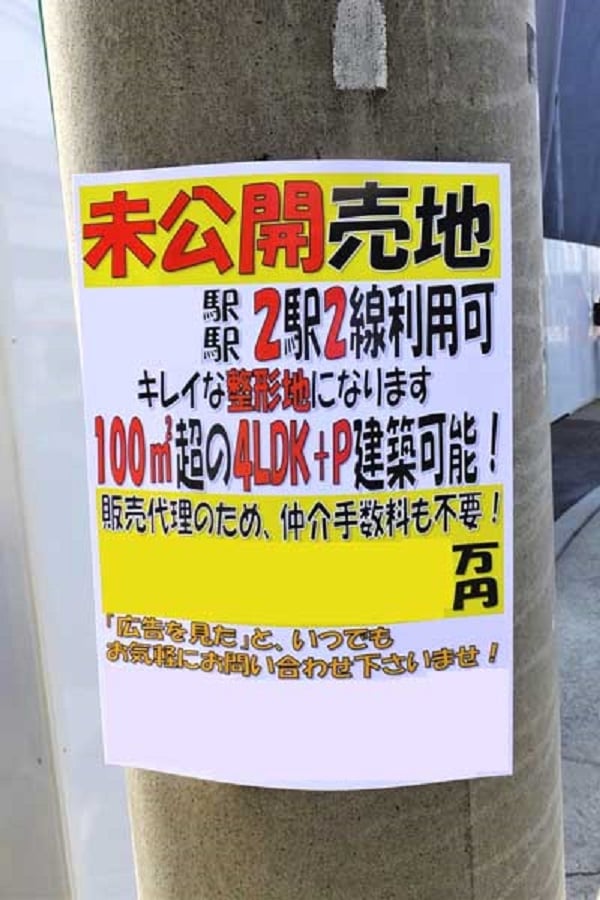中野区「高砂湯」は男湯と女湯をまたぐ富士山の銭湯画が素敵すぎた【連載】TOKYO銭湯ザンブリコ(17)
ソーシャルディスタンスな散歩を満喫したら、街角の銭湯でザンブリコ――。散歩と銭湯巡りをこよなく愛するコラムニストの島本慶さんが、東京の魅力的なコースへとお連れします。第17回は、中野区の中野駅からスタートです。中野ブロードウェイをウロウロ 中野区といえば新宿区・杉並区・練馬区に囲まれていて、まぁそこそこ評判のいい銭湯があり、のぞいて見たいところがけっこうあります。で、まぁどこにしようかと迷いつつJR中野駅へ。 ここに行くとやっぱり歩きたくなるのが、北口側の中野ブロードウェイというアーケードの商店街。最近はどうなってるのかな? なんてキョロキョロウロウロ。 そういえば早稲田通りに出て、新井町の交差点の先に中野寿湯温泉(中野区新井)ってのがありましたなぁ。確かに昔っからある古い造りのお風呂でした。でも私はクルリして駅に戻ります。 北口側に出て、中野通りを丸井を通り越してしばらく行くと、五差路に出ます。 その左手前の道を歩くと、左に中野郵便局と右に中野総合病院があり、さらに行くと左に保健所があってその向かいの路地を右に入ります。 すると緑道があってもうひとつ先の左がいちょう公園。そのもうひとつ先の路地を左に行くと、そこに高砂湯(同区中央)という銭湯が。今回はここに入りましょう。 銭湯絵師・中島盛夫さんの作品? こぢんまりしたいい雰囲気の入り口で、左がコインランドリー。取りあえずげた箱に靴を入れてフロントへ。 静かなオヤジさんがいて、480円を払います。ちなみにサウナはプラス400円。フロント前には6人は座れるソファとテレビが。 中野区中央にある「高砂湯」(画像:島本慶さん制作) 脱衣場で服を脱いで、ロッカーに入れて洗い場へ。おぉっと正面にはナカジマ先生(銭湯絵師の中島盛夫さん)の富士山の絵が。男湯と女湯を富士がまたいでおります。 ん? 何かの媒体に丸山先生(丸山清人さん)の絵って紹介されてたけど、これは明らかにナカジマ先生の絵です。間違って紹介されてたなぁ。まいっか。 さて私はカランを確保して、例によってシャワーで頭をぬらし、備え付けのボディーソープをタオルに塗って体を洗い、リンスインシャンプーで頭も最後に洗ってスッキリ。 それにしてもブルーと白壁が清楚(せいそ)感タップリでいいねぇ。浴槽を見渡すと、サウナと水風呂、電気風呂もあります。それにジェット2本とブクブク湯ねぇ。 おぉっと奥には露天風呂がありますよ。これが白い濁り湯になっていて遠目に見てもいい感じ。 若い人はサウナ目当て?若い人はサウナ目当て? まずはこれにしましょと、奥のドアを開けてなかへ。 2~3人の客がマッタリしております。いいなぁこのぬるま湯。あ~いい気持ち。 アレ? 何かポツポツしてる。そうか小雨が降ってるのか。でも何かそれがいい感じ。見上げると、何やら煙突が。でも半分壊したような短さです。なるほど今は使って無いんだなぁ。なんてかってに想像します。 中野区中央にある「高砂湯」(画像:(C)Google) じゃあお次はジェットで背中と腰を刺激しちゃいます。それにしても年配の常連さんっぽい人が多いっす。 なかには若者もいるけど、大丈夫かみんな。まだ明るいうちから仕事もしないで。あっ私もそうでした(笑)。 そうだよね。若い人はサウナに入りに来てるんだよね。だからオヤジたちみたいに毎日来てわけじゃないからね。 1020mlの冷えた水の入ったペットボトルを持ち込んだりして気合が入ってるもんな。 水風呂の温度は20度 そういえば水風呂だけど、20度はあるみたいで、蛇口から水を出さないでとの表示。 保ってる温度を冷たくしないってことでしょうな。だから普通の客も湯冷ましに入れちゃうみたいですよ。 いやぁいい湯でした。ぬれたタオルをよおく絞って体をフキフキ。脱衣場に出て、乾いたタオルでさらにフキフキ。 中野区中央にある「高砂湯」(画像:島本慶さん制作) ところでここは中野かぁ。やってるかな? まぁ一応飲食街を風に吹かれながらウロチョロしよっと。
- おでかけ
- 中野駅